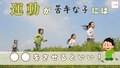お子さんの異変?【クループ症候群 初期症状】見逃さないで!危険な咳と呼吸のサイン
お子さんの急な咳や呼吸の異変に、もしかしてと不安を感じていませんか?
クループ症候群は、乳幼児に多い喉の炎症で、特に夜間に症状が悪化しやすく注意が必要です。
この記事では、特徴的な「犬が吠えるような咳」や声枯れといった初期症状から、すぐに病院へ行くべき危険なサイン、他の病気との見分け方、家庭でのケアまで、お子さんを守るために知っておくべき情報を網羅的に解説します。
早期の気づきと適切な対応が、お子さんの回復を大きく左右する重要な鍵となるからです。
目次[非表示]
- 1.もしかしてクループ症候群?お子さんの咳や呼吸の異変に気づいたら
- 2.クループ症候群とは?お子さんの喉に起こる炎症の正体
- 3.【クループ症候群 初期症状】これが見逃せないサイン
- 3.1.①特徴的な咳「犬が吠えるような咳」や「ケンケン咳」
- 3.2.➁声枯れやかすれ声
- 3.3.➂呼吸の際に聞こえる「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音
- 3.4.④発熱や鼻水など風邪に似た症状
- 3.5.⑤夜間に悪化しやすい理由
- 4.危険なサインを見逃さないで!すぐに病院へ行くべき症状
- 4.1.①呼吸が苦しそう「陥没呼吸」や「喘鳴」
- 4.1.1.・陥没呼吸(かんぼつこきゅう)
- 4.1.2.・喘鳴(ぜんめい)
- 4.2.➁顔色が悪く唇が青い「チアノーゼ」
- 4.3.➂ぐったりして元気がない意識障害の兆候
- 4.4.④水分が取れない脱水症状の危険性
- 5.クループ症候群と間違えやすい病気との見分け方
- 5.1.①気管支喘息との違い
- 5.2.➁急性喉頭蓋炎との違い
- 6.お子さんがクループ症候群と診断されたら 家庭でできるケアと注意点
- 6.1.①加湿と水分補給で喉を潤す
- 6.1.1.・加湿のポイント
- 6.1.2.・水分補給のポイント
- 6.2.➁安静を保ち体力を消耗させない
- 6.3.➂症状が悪化したときの見極め方
- 7.クループ症候群の予防と再発防止のために
- 7.1.①手洗いやうがいなど基本的な感染症対策
- 7.2.➁予防接種で重症化を防ぐ
- 8.まとめ
もしかしてクループ症候群?お子さんの咳や呼吸の異変に気づいたら
お子さんの突然の咳や呼吸の異変に、「これって、もしかして…?」と不安を感じていませんか?
特に夜間、お子さんの咳が「犬の鳴き声のよう」だったり、呼吸が苦しそうだったりすると、親としては心配でたまらないものです。
そのような症状は、もしかしたら「クループ症候群」と呼ばれる病気のサインかもしれません。クループ症候群は、主に乳幼児の喉に炎症が起こり、特徴的な咳や呼吸困難を引き起こす病気です。
お子さんの小さな異変を見逃さず、適切な判断と行動ができるよう、この病気の初期症状から、危険なサイン、そして家庭でできるケアまで、この記事で詳しく解説します。
早期に適切な対応をすることで、お子さんの症状を和らげ、重症化を防ぐことができますので、ぜひ最後までお読みください。
クループ症候群とは?お子さんの喉に起こる炎症の正体
お子さんが急に「ケンケン」という乾いた咳をしたり、息をするたびに「ヒューヒュー」という音が聞こえたりしたら、それはクループ症候群かもしれません。
クループ症候群は、主に乳幼児の喉に起こる炎症性の病気です。
特に、空気の通り道である気道が狭くなることで、特徴的な症状が現れます。
①クループ症候群はどんな病気?原因と特徴
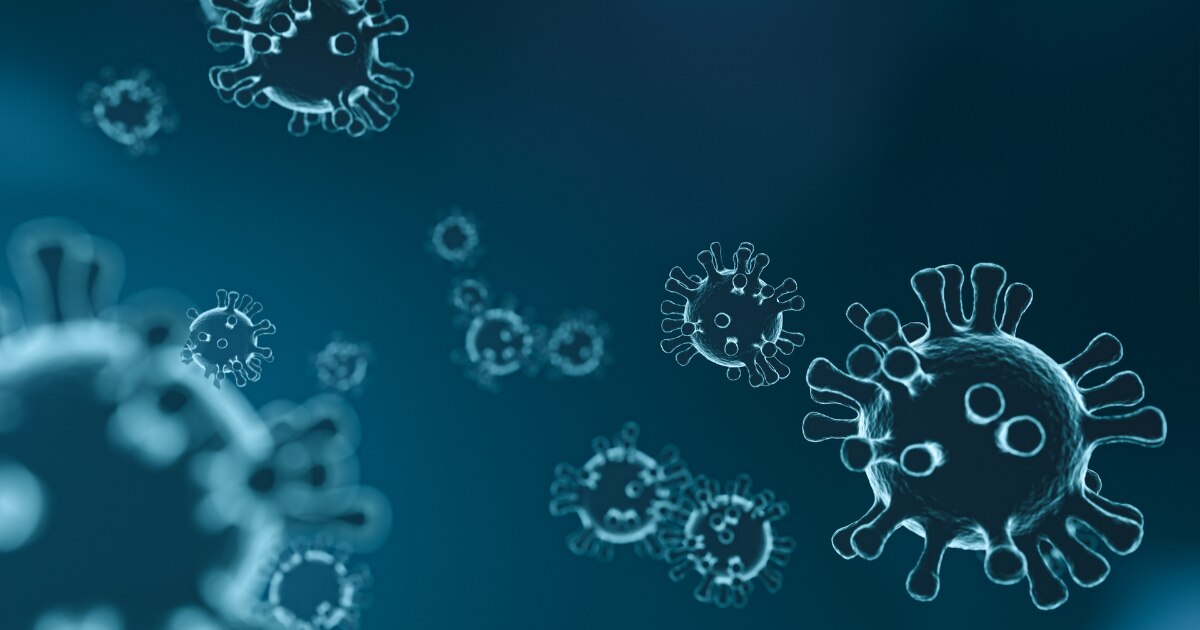
クループ症候群は、医学的には「急性喉頭気管気管支炎」と呼ばれる病気です。
お子さんの喉頭(声帯がある部分)や気管の入り口付近に炎症が起こり、粘膜が腫れることで、気道が狭くなってしまいます。
この気道の狭窄が、クループ症候群特有の症状を引き起こす主な原因です。
この病気の原因のほとんどはウイルス感染です。
特に、以下のウイルスが原因となることが多いとされています。
原因ウイルス | 特徴 |
|---|---|
パラインフルエンザウイルス | クループ症候群の |
RSウイルス | 乳幼児の呼吸器感染症の クループ症候群を |
インフルエンザウイルス | A型、B型ともに 原因となることがあります。 |
アデノウイルス | 呼吸器症状だけでなく、 結膜炎や胃腸炎も |
麻疹ウイルス | 麻疹(はしか)の合併症として クループ症候群が |
稀に細菌感染が原因となることもありますが、ウイルス性クループ症候群が圧倒的に多いです。
喉頭の粘膜が炎症によってむくむ(浮腫)ことで、空気の通り道が狭くなり、吸気時に特徴的な音(吸気性喘鳴)がしたり、声が枯れたり、犬が吠えるような咳が出たりするのが主な特徴です。
➁乳幼児に多い理由と注意が必要な年齢
クループ症候群は、特に乳幼児に多く見られる病気です。
これにはいくつかの理由があります。
まず、乳幼児の気道は大人に比べて非常に狭く、また、喉頭の形が「漏斗状(じょうご型)」であるため、少しの炎症やむくみでも空気の通り道が簡単に塞がれてしまいやすい構造になっています。
大人の場合は気道が広いため、多少炎症があっても症状が出にくいことが多いですが、乳幼児ではそれが命に関わるような呼吸困難につながる可能性もあるのです。
また、乳幼児はまだ免疫システムが十分に発達していないため、さまざまなウイルスに感染しやすく、それがクループ症候群の発症につながりやすいと考えられます。
クループ症候群が最も多く発症するのは、生後3ヶ月から3歳頃までのお子さんです。
特に、1歳前後の乳児に多く見られる傾向があります。
この年齢層のお子さんが特徴的な咳や呼吸の異変を見せたら、クループ症候群を疑い、注意深く観察することが重要です。
学童期以降のお子さんでも発症することはありますが、乳幼児期に比べて重症化するケースは少ないとされています。
【クループ症候群 初期症状】これが見逃せないサイン
お子さんの咳や呼吸に異変を感じたら、それはクループ症候群の初期症状かもしれません。
特に乳幼児の場合、症状の進行が早く、注意が必要です。
ここでは、見逃してはならないクループ症候群の代表的な初期サインを詳しく解説します。
①特徴的な咳「犬が吠えるような咳」や「ケンケン咳」

クループ症候群の最も特徴的で、見逃してはならない初期症状が「犬が吠えるような咳」や「ケンケン咳」です。
これは、喉頭(のどぼとけのあたり)が炎症によって腫れ、空気の通り道が狭くなることで起こる、独特の乾燥した金属音のような咳です。
- 音の特徴: 「オットセイの鳴き声」や「犬が吠えるような」と表現されることが多く、通常の風邪の咳とは明らかに異なります。乾燥した「コンコン」という音や、金属がぶつかるような「ケンケン」という音に聞こえることもあります。
- 発生メカニズム: 喉頭の粘膜が炎症で腫れることで、声帯の動きが制限され、息を吸う際に空気が狭い部分を通過する際に特有の音を発します。
- 出現時期: 特に夜間から明け方にかけて悪化しやすい傾向があり、急に激しい咳が出始めることがあります。
➁声枯れやかすれ声

喉頭の炎症が声帯に及ぶと、声が枯れたり、かすれたりする症状が現れます。
これは、声帯が腫れて正常に振動できなくなるために起こります。
- 声の変化: 通常の声が出しにくくなり、ガラガラ声になったり、ささやき声のようになったりします。
- 咳との関連: 特徴的な咳と同時に、またはその直後に声の変化に気づくことが多いです。
➂呼吸の際に聞こえる「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音

喉頭の腫れがさらに進み、空気の通り道が狭くなると、呼吸をするたびに特徴的な音が聞こえるようになります。
これを「吸気性喘鳴(きゅうきせいぜんめい)」と呼びます。
特に息を吸い込む時(吸気時)に「ヒューヒュー」という高い笛のような音や、「ゼーゼー」という低い音が聞こえるのが特徴です。
これは、狭くなった気道を空気が無理に通ろうとする際に生じる摩擦音です。
お子さんが呼吸をするたびに胸や喉元がへこむ「陥没呼吸」を伴う場合は、呼吸がかなり苦しいサインですので、すぐに医療機関を受診してください。
④発熱や鼻水など風邪に似た症状

クループ症候群は、多くの場合ウイルス感染が原因で発症するため、一般的な風邪に似た症状を伴うことがあります。
初期段階では、これらの症状のためにクループ症候群と気づきにくいこともあります。
症状 | 特徴 |
|---|---|
発熱 | 微熱から38℃以上の |
鼻水・鼻づまり | 透明な鼻水や、 粘り気のある鼻水が |
のどの痛み | 喉の炎症に伴い、 痛みを感じることがあります。 |
倦怠感 | 体がだるく、 元気がなくなることがあります。 |
これらの風邪症状に加えて、前述の「犬が吠えるような咳」や「声枯れ」、そして「呼吸時の異音」が現れた場合は、クループ症候群を強く疑い、注意深く観察する必要があります。
⑤夜間に悪化しやすい理由

クループ症候群の症状、特に咳や呼吸困難は、夜間から明け方にかけて悪化しやすいという特徴があります。
これにはいくつかの理由が考えられます。
- 副交感神経の優位性: 夜間は副交感神経が優位になり、気管支が収縮しやすくなるため、もともと狭くなっている気道がさらに狭くなることがあります。
- 分泌物の貯留: 寝ている間は喉の分泌物(痰など)が排出されにくく、喉に溜まりやすくなります。これにより、気道の閉塞感が増すことがあります。
- 体位の影響: 横になることで、喉の腫れがより顕著に感じられたり、分泌物が気道を刺激しやすくなったりすることがあります。
- 室内の環境: 冬場など、空気が乾燥していると喉の粘膜が乾燥し、炎症が悪化しやすくなります。
夜間に症状が急激に悪化し、お子さんが苦しそうにしている場合は、迷わず医療機関に連絡し、指示を仰ぐようにしてください
危険なサインを見逃さないで!すぐに病院へ行くべき症状

クループ症候群の症状は、時間とともに急激に悪化することがあります。
特に夜間に症状が進行しやすいため、お子さんの様子に異変を感じたら、ためらわずに医療機関を受診することが重要です。
①呼吸が苦しそう「陥没呼吸」や「喘鳴」
お子さんの呼吸が明らかに苦しそうに見える場合、それは非常に危険なサインです。
具体的には、以下の症状に注意してください。
・陥没呼吸(かんぼつこきゅう)
呼吸をするたびに、鎖骨の上のくぼみ(鎖骨上窩)、肋骨の間(肋間)、胸の下(剣状突起部)が大きくへこむ状態を指します。
これは、お子さんが一生懸命呼吸しようとしているのに、空気が十分に肺に入っていないことを示しています。
・喘鳴(ぜんめい)
呼吸をする際に、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった笛のような音や、苦しそうな音が聞こえる状態です。
特に、息を吸い込むときに聞こえる「吸気性喘鳴」は、喉頭の狭窄が進行しているサインであり、クループ症候群では特徴的に見られます。
呼吸のたびに胸やお腹が大きく動くなど、呼吸努力が増している場合も要注意です。
➁顔色が悪く唇が青い「チアノーゼ」

お子さんの顔色が青白い、特に唇や爪の先が青紫色になっている場合は、体内の酸素が不足している状態(チアノーゼ)を示しています。
これは非常に危険なサインであり、一刻も早い医療介入が必要です。
酸素不足は脳や心臓にも影響を及ぼす可能性があるため、直ちに救急車を呼ぶか、緊急で医療機関を受診してください。
➂ぐったりして元気がない意識障害の兆候
いつもと比べてお子さんが明らかにぐったりしている、呼びかけに対する反応が鈍い、うとうとして眠りがち、または意識がはっきりしないように見える場合も、重症化のサインです。
これは、呼吸困難による酸素不足が脳に影響を及ぼしている可能性を示唆しています。
遊びたがらない、好きなものにも興味を示さない、機嫌が悪いといった普段と違う様子にも注意が必要です。
④水分が取れない脱水症状の危険性
喉の痛みや呼吸の苦しさから、お子さんが水分を十分に摂れなくなることがあります。
乳幼児は特に脱水になりやすいため、以下のサインに注意してください。
- おしっこの回数が減る、または全く出ない
- 涙が出ない
- 口の中や唇が乾燥している
- 皮膚の弾力がなく、つまむと元に戻りにくい
- 目のくぼみ
脱水はクループ症候群の症状をさらに悪化させる可能性があるため、水分摂取が困難な場合はすぐに医療機関に相談してください。
これらの危険なサインが見られた場合は、迷わず救急車を呼ぶか、すぐに医療機関を受診してください。
夜間であっても、緊急性の高い症状の場合はためらわないでください。
危険なサイン | 具体的な様子 | すぐに取るべき行動 |
|---|---|---|
呼吸が苦しそう (陥没呼吸、 | 鎖骨上、肋骨間、 胸の下が大きくへこむ。 息を吸うときに 「ヒューヒュー」「ゼーゼー」 と音がする。 | すぐに医療機関を受診。 症状が重ければ 救急車を呼ぶ。 |
顔色が悪く (チアノーゼ) | 唇や爪の先が青紫色になる。 顔色が土気色になる。 | 直ちに救急車を呼ぶ。 |
ぐったりして (意識障害の | 呼びかけへの反応が鈍い。 うとうとして眠りがち。 意識がはっきりしない。 | すぐに医療機関を受診。 状況によっては 救急車を呼ぶ。 |
水分が取れない (脱水症状) | おしっこが出ない、 涙が出ない、 口が乾燥する、 皮膚の弾力がない。 | すぐに医療機関に相談。 |
クループ症候群と間違えやすい病気との見分け方

お子さんの咳や呼吸の症状は、クループ症候群以外にも様々な病気が考えられます。
特に、症状が似ていても、緊急性の高い病気もあるため、正確な鑑別が重要です。
ここでは、クループ症候群と間違えやすい代表的な病気とその見分け方について解説します。
①気管支喘息との違い
気管支喘息も、お子さんに多い呼吸器の病気で、咳や呼吸の音からクループ症候群と混同されることがあります。
しかし、原因や症状の現れ方には明確な違いがあります。
クループ症候群と気管支喘息の主な違いを以下の表にまとめました。
項目 | クループ症候群 | 気管支喘息 |
|---|---|---|
主な原因 | ウイルス感染による 喉頭の炎症 | ・気道の過敏性 ・アレルギー反応 |
主な症状 | 犬が吠えるような咳 (ケンケン咳)、 声枯れ、 吸気性喘鳴 (息を吸う時に | ・ゼーゼー、 という喘鳴 ・乾いた咳 ・痰が絡む咳 |
症状の部位 | 喉頭(のど、声帯付近) | ・気管支 (肺の奥の細い気道) |
発症年齢 | 乳幼児に多い (生後6ヶ月〜 | ・乳幼児から |
緊急性 | 呼吸困難の程度によっては緊急 | ・発作の程度に |
お子さんの呼吸音が「ヒューヒュー」や「ゼーゼー」と聞こえても、それが「息を吸う時」なのか「息を吐く時」なのか、また「咳の音」がどのような特徴を持つのかをよく観察することが、見分けるための重要なポイントになります。
➁急性喉頭蓋炎との違い
急性喉頭蓋炎は、クループ症候群と同じく喉の奥に炎症が起きる病気ですが、極めて緊急性が高く、迅速な対応が必要です。
クループ症候群と症状が似ているように見えても、命に関わる危険性があるため、その違いをしっかり理解しておくことが重要です。
クループ症候群と急性喉頭蓋炎の主な違いは以下の通りです。
項目 | クループ症候群 | 急性喉頭蓋炎 |
|---|---|---|
主な原因 | ウイルス感染 | 細菌感染 (特にインフルエンザ菌b型: Hib) |
症状の進行 | 比較的ゆっくり進行し、 夜間に悪化しやすい | 数時間で急速に悪化し、 窒息の危険性が高い |
特徴的な 症状 | 犬が吠えるような咳、 声枯れ、 吸気性喘鳴 | 高熱、よだれが多い、 唾液を飲み込めない、 声が出せない(無声)、 ぐったりしている、 首を前に突き出すような座り方 |
咳の有無 | 特徴的な咳がある | 咳はほとんど出ない |
緊急性 | 呼吸困難が強い場合は緊急 | 非常に緊急性が高く、 直ちに救急車を呼ぶべき |
特に、「よだれが多い」「唾液を飲み込めない」「声が出ない」「高熱でぐったりしている」といった症状がみられる場合は、急性喉頭蓋炎の可能性が高く、一刻を争う事態です。
すぐに救急車を呼び、医療機関を受診してください。
喉を刺激すると症状が悪化する可能性があるため、無理に口の中を覗き込んだり、食べ物や飲み物を与えたりしないように注意しましょう。
お子さんがクループ症候群と診断されたら 家庭でできるケアと注意点
お子さんがクループ症候群と診断された場合、医師の指示に従いながら、ご家庭での適切なケアが回復を早める上で非常に重要です。
特に、喉の炎症を和らげ、呼吸を楽にするための工夫が求められます。
①加湿と水分補給で喉を潤す
クループ症候群では喉の炎症が咳や呼吸困難を引き起こすため、喉を乾燥させないことが何よりも大切です。
適切な加湿とこまめな水分補給を心がけましょう。
・加湿のポイント

室内の空気が乾燥していると、喉の粘膜がさらに刺激され、咳が悪化しやすくなります。加湿器を使用する、濡れタオルを干すなどして、室内の湿度を50~60%に保つようにしましょう。
特に夜間は症状が悪化しやすい傾向があるため、寝室の加湿は重要です。また、一時的に症状を和らげる方法として、浴室に蒸気を充満させ、お子さんを数分間抱っこして蒸気を吸わせるのも効果的とされています。
ただし、やけどには十分注意してください。
・水分補給のポイント
発熱や咳によって体内の水分が失われやすいため、脱水症状を防ぐためにも、少量ずつ頻回に水分を与えることが大切です。
水分補給は喉の潤いを保ち、痰を柔らかくして出しやすくする効果も期待できます。
推奨される飲み物 | 避けるべき飲み物 |
|---|---|
| × 柑橘系のジュース (喉への刺激が強い) × 炭酸飲料 (咳を誘発しやすい) × 冷たすぎる飲み物 |
➁安静を保ち体力を消耗させない
クループ症候群にかかると、お子さんは咳や呼吸の苦しさで体力を消耗しやすくなります。
十分な安静を保ち、無理に遊ばせたり、興奮させたりしないことが回復には不可欠です。
お子さんが安心して過ごせるよう、静かで落ち着いた環境を整えましょう。激しい運動や遊びは避け、絵本を読んだり、おもちゃで静かに遊ばせたりするなど、体力を温存できる過ごし方を促してください。
また、保護者の方がそばにいて抱っこしたり、優しく声をかけたりすることで、お子さんは精神的に落ち着き、呼吸が楽になることもあります。
➂症状が悪化したときの見極め方

家庭でケアをしていても、クループ症候群の症状が急に悪化することがあります。
少しでも異変を感じたら、ためらわずに医療機関を受診することがお子さんの命を守る上で極めて重要です。
特に、以下の症状が見られた場合は、すぐに病院へ連絡し、指示を仰ぎましょう。
悪化を示すサイン | 取るべき行動 |
|---|---|
|
|
症状は夜間に悪化しやすい傾向があるため、夜間も定期的にお子さんの様子を確認するようにしましょう。
もし、少しでも不安を感じたら、迷わず医療機関に相談してください。
クループ症候群の予防と再発防止のために
お子さんのクループ症候群は、一度経験すると保護者の方にとっては大きな不安が残るものです。
しかし、適切な予防策と日々の注意で、発症リスクを減らし、再発を防ぐことが可能です。
ここでは、お子さんをクループ症候群から守るための具体的な方法をご紹介します。
①手洗いやうがいなど基本的な感染症対策

クループ症候群の多くはウイルス感染が原因であるため、日頃からの感染症対策が非常に重要です。
特に、手洗いやうがいを徹底することは、ウイルスが体内に入るのを防ぐ最も基本的な方法です。
- こまめな手洗い:外出から帰宅した際や食事の前、鼻をかんだ後など、石鹸を使って流水で丁寧に手を洗いましょう。お子さんにも手洗いの習慣を身につけさせてください。
- うがい:うがいは喉の粘膜についたウイルスを洗い流す効果があります。うがいができる年齢のお子さんには、水やうがい薬でのうがいを習慣にさせましょう。
- マスクの着用:家族に風邪症状がある場合や、人混みに出かける際には、お子さんだけでなく、周囲の大人もマスクを着用し、ウイルス感染のリスクを減らしましょう。
- 咳エチケット:咳やくしゃみをする際は、口と鼻をティッシュやハンカチ、腕の内側で覆う「咳エチケット」を徹底し、ウイルスの飛散を防ぎましょう。
- 室内の換気:定期的に窓を開けて室内の空気を入れ替え、ウイルスの滞留を防ぎます。特に冬場は空気が乾燥しやすいため、加湿器などで適切な湿度(50~60%)を保つことも重要です。
- タオルの共有を避ける:家族間でもタオルや食器の共有を避け、感染経路を断ちましょう。
- 免疫力の維持:十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、お子さんの免疫力を高め、ウイルスに対する抵抗力をつけます。規則正しい生活リズムを心がけましょう。
これらの対策は、クループ症候群だけでなく、他の様々な感染症の予防にも繋がります。
➁予防接種で重症化を防ぐ

クループ症候群の原因となるウイルスに対する直接的なワクチンは現在のところありませんが、特定の予防接種を受けることで、クループ症候群の重症化を防いだり、関連する重篤な病気の合併を防ぐことができます。
特に推奨される予防接種は以下の通りです。
予防接種の種類 | 期待される効果 クループ症候群との関連 |
|---|---|
インフルエンザ ワクチン | インフルエンザウイルスも クループ症候群の原因と なることがあります。 インフルエンザワクチンを 接種することで、 インフルエンザの発症を予防し、 万が一感染した場合でも 重症化や合併症 (クループ症候群を含む) のリスクを軽減できます。 毎年流行前に接種することが 推奨されます。 |
Hibワクチン (ヒブワクチン) | インフルエンザ菌b型(Hib)は、 細菌性クループの原因と なることは稀ですが、 急性喉頭蓋炎など、 喉の重篤な炎症を 引き起こす主要な原因菌です。 Hibワクチンは、 これらの重篤な感染症から お子さんを守るために 非常に重要です。 |
肺炎球菌ワクチン | 肺炎球菌も、Hibと同様に、 細菌性クループや 急性喉頭蓋炎といった 重篤な喉の感染症の 原因となることがあります。 肺炎球菌ワクチンを接種することで、 これらの細菌性感染症の予防に繋がります。 |
MRワクチン (麻疹・風疹 混合ワクチン) | 麻疹ウイルスも クループ症候群の原因と なることがあります。 MRワクチンは麻疹と 風疹を予防するための ワクチンであり、 麻疹ウイルスによる クループ症候群の発症リスクを 減らすことができます。 定期接種として定められており、 適切な時期に 接種を完了させることが大切です。 |
これらの予防接種は、お子さんの健康を守る上で非常に有効な手段です。
かかりつけの小児科医と相談し、お子さんの月齢や年齢に合わせた適切な予防接種スケジュールを確認し、忘れずに接種するようにしましょう。
一度クループ症候群を経験したお子さんは、喉の粘膜がデリケートになっている場合があるため、特に感染症対策を徹底し、再発を防ぐ意識を持つことが大切です。
日々の生活の中でできる予防策を実践し、お子さんの健やかな成長をサポートしましょう。
まとめ
クループ症候群は、お子さんの喉に炎症が起こり、特徴的な咳や呼吸困難を引き起こす病気です。
特に「犬が吠えるような咳」や呼吸時の異常音、声枯れといった初期症状を見逃さないことが大切です。
これらのサインに気づいたら、特に呼吸が苦しそう、顔色が悪いなど危険な兆候があれば、迷わず医療機関を受診しましょう。
早期の診断と適切なケアが、お子さんの回復に繋がります。
日頃からの手洗いやうがい、加湿などの予防策も重要です。