
新一年生ママ必見!小学校入学前の準備、いつから何を始める?後悔しないための全知識
新一年生のママさん、小学校入学前の準備はいつから何を始めれば良いのか、不安を感じていませんか?
この記事では、入学準備の全体スケジュールから、必要な持ち物リスト、心の準備、各種手続きまで、後悔しないための全知識を網羅的に解説します。
先輩ママの体験談や「買ってよかったもの」もご紹介。
お子様が自信を持って小学校生活をスタートできるよう、あなたの疑問や不安を解消し、安心して入学を迎えられるようサポートします。
目次[非表示]
- 1.小学校入学前の準備、いつから始めるべき?
- 1.1.小学校入学準備の全体スケジュール
- 1.1.1.①入学の1年前から始めること
- 1.1.2.➁入学の半年前から始めること
- 1.1.3.➂入学の直前から始めること
- 2.小学校入学前の準備物リストと選び方
- 2.1.必須の学用品と文房具
- 2.1.1.①ランドセル選びのポイント
- 2.1.2.➁学習机は必要?後悔しない選び方
- 2.2.通学に必要なもの
- 2.3.体操服や給食着など学校指定品
- 2.4.入学式で必要なもの
- 2.5.名前付けのコツと便利なアイテム
- 3.小学校入学前の心と体の準備
- 3.1.小学校生活に慣れるための心の準備
- 3.1.1.①親子で小学校について話す機会を作る
- 3.1.2.➁小学校のルールや習慣を学ぶ
- 3.2.生活習慣を整える
- 3.2.1.①早寝早起きの習慣化
- 3.2.2.➁自分でできることを増やす練習
- 3.3.就学前健診と予防接種の確認
- 4.小学校入学前の手続きと情報収集
- 4.1.入学説明会で確認すべきこと
- 4.2.学童保育や放課後児童クラブの情報収集
- 4.3.①就学援助制度について知る
- 4.4.➁PTA活動について
- 5.小学校入学準備で後悔しないためのポイント
- 6.まとめ
小学校入学前の準備、いつから始めるべき?

お子さんの小学校入学を控えるママにとって、「いつから何を準備すれば良いの?」という疑問は尽きないものです。
小学校入学準備は、単に学用品を揃えるだけでなく、お子さんの心と体の準備、そして保護者の方の手続きなど、多岐にわたります。
早めに計画を立てて準備を始めることで、直前になって慌てたり、買い忘れがあったりする後悔を避けることができます。
この章では、小学校入学準備をいつから、どのような流れで進めていくべきか、全体像を分かりやすく解説します。
具体的な準備項目については、後続の章で詳しくご紹介します。
小学校入学準備の全体スケジュール

小学校入学準備は、大きく分けて「入学の1年前」「入学の半年前」「入学の直前」の3つの期間に分けて考えると、計画的に進めやすくなります。
それぞれの期間で取り組むべき主な内容を把握し、無理なく準備を進めていきましょう。
時期 | 主な準備内容 | ポイント |
|---|---|---|
入学の1年前 (年長の春~夏頃) | ・情報収集 ・生活習慣の基礎固め ・小学校への興味付 | ゆとりを持って 情報収集を始め、 親子の対話を 増やす時期 |
入学の半年前 (年長の秋~冬頃) | ・就学前健診 ・入学説明会 ・主要な学用品の検討/購入 | 具体的な準備が 本格化する時期。 早めの行動が吉 |
入学の直前 (年長の冬~春休み) | ・学用品の購入/名前付け ・生活リズムの最終調整 ・入学式準備 | 最終確認と 仕上げの時期。 焦らず確実に |
①入学の1年前から始めること

年長さんの春頃から夏頃にかけては、まだ時間的な余裕があるため、焦らずに情報収集と心構えの準備を始めるのに最適な時期です。
- 地域の小学校情報の収集:通学予定の小学校の評判、教育方針、特色などを調べてみましょう。
学校公開や地域のイベントがあれば、親子で参加してみるのも良い経験になります。 - 入学準備に関する情報収集:インターネットや書籍、先輩ママからの情報など、幅広い情報を集め始めましょう。
何から手をつければ良いか分からなくても、全体像を把握するだけでも安心できます。 - 親子で小学校について話す機会を作る:「小学校ってどんなところかな?」「何が楽しみ?」など、ポジティブな会話を増やし、子どもの期待感を高めましょう。不安な気持ちにも寄り添い、話を聞く姿勢が大切です。
- 生活習慣の基礎固め:早寝早起き、規則正しい食事、手洗いうがいなど、基本的な生活習慣の確立を目指します。
入学後にスムーズに学校生活に移行できるよう、少しずつ意識付けを始めましょう。
➁入学の半年前から始めること

年長さんの秋頃から冬頃にかけては、具体的な準備が本格化する時期です。
重要な手続きや大きな買い物が始まりますので、計画的に進めましょう。
- 就学前健診の受診:お住まいの自治体から案内が届いたら、指定された期間内に必ず受診しましょう。子どもの発達状況や健康状態を確認する大切な機会です。気になる点があれば、この機会に相談しておきましょう。
- 入学説明会への参加:多くの小学校で秋から冬にかけて入学説明会が開催されます。学校の教育方針、年間行事、持ち物、PTA活動など、重要な情報が共有されるため、必ず参加しましょう。質問事項を事前にまとめておくと良いでしょう。
- ランドセル選び:この時期からランドセル選びを始める家庭が多いです。人気のモデルは早めに売り切れることもあるため、早めの検討をおすすめします。デザインだけでなく、軽さ、耐久性、背負いやすさ、A4フラットファイル対応かなどを重視して選びましょう。
- 学習机の検討:学習机の購入を考えている場合は、この時期から検討を始めましょう。設置スペースや子どもの成長を考慮し、長く使えるシンプルなデザインを選ぶのがおすすめです。必ずしも入学時に必須ではないため、家庭の方針に合わせて検討しましょう。
- 通学路の確認と練習:親子で実際に通学路を歩いてみましょう。危険な場所がないか、信号の渡り方、交通ルールなどを確認し、安全に通学できるよう練習を始めます。
➂入学の直前から始めること

年長さんの冬休みから春休みにかけては、いよいよ小学校入学が目前に迫る時期です。
最終的な準備と確認を丁寧に進めていきましょう。
- 学用品・文房具の購入と名前付け:入学説明会で指示された学用品や文房具を揃え、一つひとつ丁寧に名前を付けましょう。名前付けは意外と時間がかかる作業なので、余裕を持って取り組むことが大切です。
- 体操服や給食着など学校指定品の準備:学校から指定された体操服や給食着、上履きなどを購入し、名前付けを行います。サイズが合うか、汚れがないかなども確認しておきましょう。
- 生活リズムの最終調整:小学校の登校時間に合わせた起床・就寝時間、食事の時間など、規則正しい生活リズムを確立させます。朝食をしっかり摂る習慣も重要です。
- 自分でできることを増やす練習:着替え、排泄、手洗い、うがい、持ち物の準備、簡単な片付けなど、小学校生活で必要となる基本的な生活スキルを身につける練習をしましょう。自分でできたという経験が子どもの自信につながります。
- 入学式で必要なものの準備:入学式で着用する服、靴、持ち物などを確認し、準備しておきましょう。写真撮影の計画なども立てておくと良いでしょう。
小学校入学前の準備物リストと選び方

小学校入学準備で最も気になるのが「何を、いつまでに、どこで準備すればいいのか」という準備物ではないでしょうか。
ここでは、入学前に揃えるべきアイテムを網羅的にご紹介し、それぞれの選び方や購入のヒントを詳しく解説します。
後悔しないための賢い選び方を知り、安心して入学を迎えましょう。
必須の学用品と文房具
小学校で毎日使う学用品や文房具は、子どもの学習意欲や使いやすさに直結します。
学校からの指定がある場合も多いので、入学説明会で配布される資料を必ず確認してから購入するようにしましょう。
①ランドセル選びのポイント

ランドセルは小学校生活の6年間を共にする大切なパートナーです。
素材、機能、デザインなど、多角的に比較検討して、お子さんにぴったりのものを選びましょう。
- 素材と耐久性:
- 人工皮革(クラリーノなど): 軽くて丈夫、雨にも強く、お手入れが簡単です。カラーバリエーションも豊富で、近年主流となっています。
- 本革(コードバン、牛革): 使い込むほど味が出て、高級感があります。耐久性も高いですが、人工皮革に比べて重く、価格も高めです。
- 重さ: 教科書や副教材、給食袋など、毎日たくさんの荷物を入れて通学するため、本体が軽いものを選ぶと、子どもの負担が軽減されます。試着して、実際に背負わせてみることが重要です。
- 容量とサイズ: A4フラットファイルが折れずにすっぽり入るサイズが主流です。
最近はタブレット端末の持ち運びも考慮された、大容量モデルも増えています。 - 機能性:
- 背負いやすさ: 肩ベルトの立ち上がり方(背カン)、背あての形状など、フィット感を重視しましょう。
「フィットちゃん」「天使のはね」など、各メーカー独自の工夫があります。 - 安全性: 夜道での安全を確保するため、反射材が使われているか確認しましょう。
防犯ブザーを取り付けられる金具があるかもポイントです。 - 防犯・防水性: 防水加工が施されているか、鍵の開閉が簡単か(ワンタッチロックなど)も確認しましょう。
- デザインと色: お子さんの好みを尊重しつつ、6年間飽きずに使えるシンプルなデザインや色を選ぶのも一案です。高学年になっても違和感なく使えるかを考慮しましょう。
- 保証とアフターサービス: 6年間保証が付いているか、修理時の対応はどうなるかなど、購入前に確認しておくと安心です。
- 購入時期: 人気のモデルは夏頃から売り切れ始めることがあります。早くても入学の1年前、遅くとも年内には購入を検討し始めるのがおすすめです。
➁学習机は必要?後悔しない選び方

学習机は子どもの学習スペースとして検討されますが、最近ではリビング学習を選ぶ家庭も増えています。
子どもの性格や家庭環境に合わせて、必要性を検討しましょう。
- 学習机の必要性:
- メリット: 自分の学習スペースを持つことで、学習習慣が身につきやすく、集中力を高める効果が期待できます。教科書や文房具を整理整頓する習慣も養われます。
- デメリット: 部屋のスペースを取る、高価である、リビング学習の方が親の目が届きやすいという意見もあります。
- 後悔しない選び方:
- サイズと配置: 部屋の広さに合わせて適切なサイズを選びましょう。将来的にレイアウト変更が可能か、他の家具との兼ね合いも考慮します。
- 機能性: 引き出しの数、本の収納スペース、コンセントの有無など、必要な機能を洗い出しましょう。成長に合わせて高さ調節ができるタイプも人気です。
- デザインと素材: 長く使えるシンプルなデザインや、部屋の雰囲気に合う素材を選びましょう。
- 安全性: 角が丸い、引き出しが抜け落ちないなどの安全対策が施されているか確認しましょう。
- リビング学習の場合: 専用の机を置かない場合でも、リビングに子どもの学習スペースを確保し、集中できる環境を整えることが大切です。コンパクトなワゴンや収納付きの椅子などを活用するのも良いでしょう。
その他、小学校で使う主な学用品と文房具は以下の通りです。
学校からの指定がなければ、お子さんが使いやすいシンプルなものを選びましょう。
カテゴリ | 主な準備物 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
筆記用具 | 筆箱 鉛筆(Bまたは2B)、 赤鉛筆 消しゴム 定規、鉛筆削り | 学校指定の 有無を必ず確認。 シンプルで使いやすいもの。 鉛筆は数本多めに用意。 |
色塗り 造形 | 色鉛筆、クレヨン、 絵の具セット (筆/パレット/水入れ) 粘土 (粘土板/油粘土ケース) | 学校指定品や 推奨品があることが多い。 名前付けを忘れずに。 |
切る 貼る | はさみ (安全キャップ付き) のり (スティックのり/液体のり) セロハンテープ | 子どもが 安全に使えるもの。 はさみは利き手に 合ったものを選ぶ。 |
その他 | 連絡帳 自由帳 下敷き | 学校から 配布されることが多いが、 念のため確認。 |
通学に必要なもの
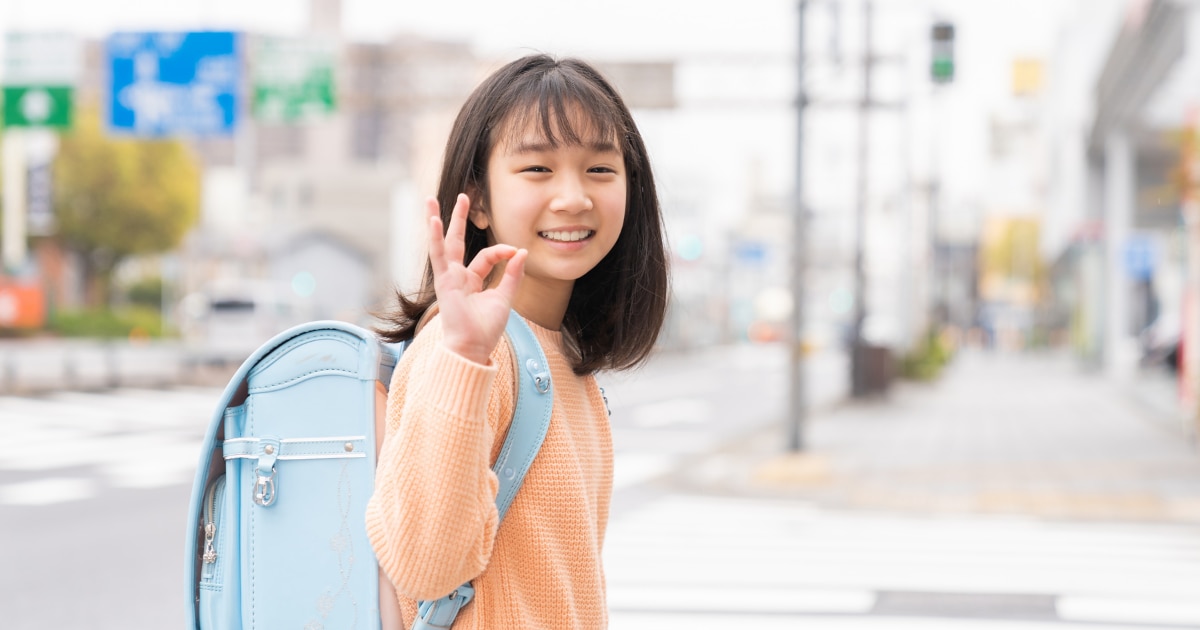
毎日安全に、そして快適に通学するために必要なアイテムもリストアップしておきましょう。
- 上履き・上履き入れ: 学校指定の素材や色がある場合が多いです。少し大きめを選び、成長を見越して予備を用意すると安心です。上履き入れはランドセルに付けられるタイプや、手提げタイプがあります。
- 手提げ袋(レッスンバッグ): 体操服や図工の作品、鍵盤ハーモニカなどを持ち運ぶ際に使用します。A4サイズがすっぽり入るものを選びましょう。丈夫な素材で、持ち手がしっかりしているものがおすすめです。
- 防災頭巾・防災頭巾カバー: 多くの小学校で必須となっています。普段は椅子の座布団や背もたれとして使えるカバーとセットで購入するのが一般的です。学校の椅子のサイズに合うか確認しましょう。
- 雨具:
- 傘: 視界を遮らない透明窓付きや、反射材付きのものが安全です。子どもが自分で開閉しやすいものを選びましょう。
- レインコート: ランドセルを背負ったまま着られるタイプや、フードに透明な部分があるものがおすすめです。
- 防犯ブザー: 万が一の際に備え、子どもがすぐに使える場所に装着させましょう。電池残量も定期的に確認することが大切です。
体操服や給食着など学校指定品
学校生活で使う衣類は、学校によってデザインや購入方法が異なります。
入学説明会で案内される指定販売店や購入方法を必ず確認しましょう。
- 体操服: 半袖シャツ、ハーフパンツ、長ズボンなどが一般的です。少し大きめのサイズを選び、洗い替え用に複数枚用意すると便利です。記名場所も確認しておきましょう。
- 給食着: 白衣、帽子、マスクがセットになっていることが多いです。こちらも洗い替え用を準備しておくと安心です。
- 赤白帽: 体育の授業や運動会などで使用します。学年で同じものを購入する場合が多いです。
- 水着(夏): プール学習が始まる前に準備します。学校指定がある場合もあれば、自由な場合もあります。
これらの衣類は、子どもの成長が早いため、毎年サイズ確認が必要になります。
特に体操服は、頻繁に洗濯するため、丈夫な素材を選ぶと良いでしょう。
入学式で必要なもの

入学式は小学校生活の始まりを祝う大切な日です。
当日に慌てないよう、必要なものを事前に準備しておきましょう。
- お子さんの服装:
- 男の子:スーツ、ブレザー+シャツ+パンツ、またはセットアップ。
- 女の子:ワンピース、アンサンブル、スーツ、またはセットアップ。
- 清潔感があり、動きやすいものを選びましょう。靴や靴下、ヘアアクセサリーなども忘れずに。
- 保護者の服装:
- 母親:セレモニースーツ、ワンピース、セットアップなど。落ち着いた色合いで、上品な印象のものが一般的です。コサージュやアクセサリーで華やかさをプラスするのも良いでしょう。
- 父親:ダーク系のスーツが基本です。
- 室内履き(スリッパ)も忘れずに持参しましょう。
- 持ち物リスト:
- 学校からの案内書類、筆記用具: 受付で提出する書類や、説明会でメモを取るために必要です。
- カメラ・ビデオカメラ: お子さんの晴れ姿を記録するために忘れずに。充電やSDカードの確認もしておきましょう。
- サブバッグ: 持ち帰る書類や配布物が多い場合があるので、A4ファイルが入る大きめのサブバッグがあると便利です。
- その他: ハンカチ、ティッシュ、飲み物など、一般的なお出かけグッズも準備しましょう。
名前付けのコツと便利なアイテム

小学校の持ち物は、鉛筆一本から体操服まで、全てに名前を付ける必要があります。
膨大な量になるので、効率的に進めるためのコツと便利なアイテムを活用しましょう。
- 名前付けの基本:
- 「全てのものに」「見やすい場所に」「はっきりと」記名する。
- 学年が上がっても使えるものは、学年が分かるように工夫する(例:学年部分をシールにする)。
- 紛失した際に返却されやすいよう、クラス名や名前の読み方も書くと親切です。
- 名前付けのコツ:
- 計画的に、少しずつ進める: 一度にやろうとすると大変なので、購入した物から順に、早めに名前付けを始めましょう。
- 素材に合わせて方法を選ぶ: 布製品、プラスチック、金属など、素材によって最適な名前付け方法を選びます。
- お子さんと一緒に: 自分の持ち物という意識を持たせるため、一緒に名前付けをするのも良い経験になります。
- 便利な名前付けアイテム:
アイテム名 | 特徴 | 活用シーン |
|---|---|---|
お名前 スタンプ セット | サイズ違いの スタンプとインクが セットに。 ポンと押すだけ で簡単。 | 算数セットの細かなパーツ ※プラスチック、 布・紙など 幅広い素材に。 特にに大活躍。 |
フロッキー ネーム | アイロンで 簡単に接着できる 立体的な 名前シール。 | 伸縮性のある布製品 ※体操服、靴下 下着など。 洗濯にも強い。 |
アイロン 接着ネーム シール | アイロンで 貼り付ける 布用シール。 デザインも豊富。 | 布製品全般 ※体操服、給食着 レッスンバッグなど。 |
タグ用 お名前 シール | 衣類のタグに 貼り付けるシール。 アイロン不要で手軽。 | 洗濯する布製品 ※洋服、タオル ハンカチなど。 |
油性ペン | 手軽に名前を書ける 定番アイテム。 | 表面が滑らかなもの ※鉛筆、消しゴム、定規 プラスチック製品など。 |
お名前ペン (布用) | 布ににじみにくく、 洗濯しても 落ちにくいペン。 | 布製品 ※体操服、給食着 靴下など。 |
小学校入学前の心と体の準備

小学校入学は、お子さんにとって大きな環境の変化です。
新しい生活への期待とともに、少なからず不安も抱えています。この時期に、心と体の両面からしっかりと準備をすることで、お子さんはスムーズに小学校生活に溶け込み、自信を持って新生活をスタートできるでしょう。
親御さんも安心して見守れるよう、具体的な準備を進めていきましょう。
小学校生活に慣れるための心の準備
小学校は幼稚園や保育園とは異なり、集団生活のルールや学習の機会が増えます。
お子さんが安心して学校生活を送るためには、事前に心の準備を整えることが大切です。
①親子で小学校について話す機会を作る

お子さんの小学校への期待や不安を共有し、前向きな気持ちを育むために、親子で小学校について話す時間を作りましょう。
無理に質問攻めにするのではなく、日常の会話の中で自然に触れることがポイントです。
- 小学校の楽しいイメージを伝える:新しい友達ができること、色々なことを学べること、休み時間に遊べることなど、ポジティブな側面を具体的に話してあげましょう。
- 不安な気持ちを受け止める:「一人で大丈夫かな?」「勉強が難しいかも」といったお子さんの不安な気持ちに耳を傾け、「そうだね、最初はドキドキするかもしれないね」と共感し、安心できる言葉をかけてあげましょう。
- 絵本や動画を活用する:小学校生活をテーマにした絵本を読み聞かせたり、小学校の様子がわかる動画を一緒に見たりするのも効果的です。視覚的にイメージを掴むことで、より具体的に学校生活を想像できるようになります。
- 通学路を一緒に歩く:入学前に何度か一緒に通学路を歩き、学校の建物や周辺の様子を見せることで、物理的な不安を軽減できます。
➁小学校のルールや習慣を学ぶ
小学校には、集団生活を送る上で守るべきルールや習慣がたくさんあります。
これらを事前に少しずつ知っておくことで、お子さんは戸惑うことなく学校生活に慣れていけます。
- 基本的な生活習慣とマナー:
- 「おはようございます」「ありがとうございます」など、基本的な挨拶の練習。
- 「座って話を聞く」「順番を守る」といった集団行動のルール。
- 物の貸し借りや片付け、整理整頓の習慣。
- 学校生活の具体的な場面:
- 授業中は静かにすること。
- 給食の準備や片付けの仕方。
- 休み時間の過ごし方。
- トイレの使い方。
- 情報収集の方法:
- 入学説明会で配布される資料をよく読む。
- 学校のウェブサイトや広報誌を確認する。
- 近所の小学生や先輩ママから話を聞く。
家庭でできる具体的な練習としては、以下のようなものが挙げられます。
小学校の ルール・習慣 | 家庭での練習例 |
|---|---|
時間を見て 行動する | 「〇時になったらおもちゃを片付けようね」 「〇時になったらお風呂に入ろうね」 など、時間を意識した声かけ |
先生や友達 への挨拶 | 家庭で家族への挨拶を習慣化する。 「おはよう」「ありがとう」「ごめんなさい」 などを自然に言えるようにする |
着替えや 身支度 | 自分で服を選び、着替え、 脱いだ服をたたむ練習。 靴を揃える習慣 |
話を聞く姿勢 | 絵本の読み聞かせや家族会議などで、 相手の目を見て話を聞く練習 |
片付け 整理整頓 | 使ったものを元の場所に戻す習慣。 自分の持ち物を管理する練習 |
生活習慣を整える
 小学校生活は、幼稚園や保育園よりも活動時間が長く、学習時間も増えます。
小学校生活は、幼稚園や保育園よりも活動時間が長く、学習時間も増えます。
規則正しい生活習慣を身につけることは、お子さんの健康維持と学習への集中力向上に不可欠です。
①早寝早起きの習慣化
小学校入学を機に、生活リズムを小学校の時間割に合わせる準備を始めましょう。
特に、早寝早起きの習慣は、お子さんの心身の健康と学習効率に大きく影響します。
- 就寝・起床時間を固定する:小学校の登校時間に間に合うよう、逆算して起床時間を決め、そこから就寝時間を設定します。
休日もできるだけ同じ時間に起きるように心がけましょう。 - 寝る前のルーティンを作る:お風呂、歯磨き、絵本の読み聞かせなど、毎日同じ流れで寝る準備をすることで、お子さんの体は「もうすぐ寝る時間だ」と認識し、スムーズに入眠できるようになります。
- 朝食をしっかり摂る習慣:朝食は脳のエネルギー源です。
早起きして、しっかり朝食を摂ることで、午前中の集中力が高まります。 - 日中の活動量を増やす:日中に体を動かして適度に疲れることで、夜ぐっすり眠れるようになります。公園で遊んだり、散歩に出かけたりする機会を増やしましょう。
➁自分でできることを増やす練習

小学校では、自分の身の回りのことを自分でこなす機会が増えます。
入学前に、基本的な身の回りのことができるように練習しておくことで、お子さんは自信を持って学校生活を送れるようになります。
- 着替えや身支度:自分で服を着替える、ボタンを留める、靴を履く、髪を整えるなど。
- 手洗い・うがい・排泄:正しい手洗いの方法を身につける、うがいをする、トイレに一人で行けるようにする。
- 持ち物の準備・管理:自分の持ち物を整理する、忘れ物がないか確認する、ランドセルに教科書や学用品を出し入れする。
- 簡単な家事の手伝い:食卓の準備や片付け、自分の部屋の簡単な整理整頓など、家庭での役割を持たせることで、責任感や自立心が育まれます。
これらの練習は、焦らず、お子さんのペースに合わせて進めることが大切です。
「自分でできた!」という成功体験をたくさん積ませてあげることが、自己肯定感を高め、自信に繋がります。
就学前健診と予防接種の確認

小学校入学前には、お子さんの健康状態を確認し、集団生活で感染症から身を守るための準備も欠かせません。
- 就学前健診の受診:
- 目的:小学校入学を控えたお子さんの心身の発達状況や健康状態を確認し、必要に応じて就学に関する助言を行うための健診です。
- 時期と内容:入学前年の秋頃に、お住まいの自治体から通知が届きます。内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科の診察のほか、視力・聴力検査、発達検査などが行われます。
- 活用:健診の結果、気になる点が見つかった場合は、学校や専門機関と連携し、入学後のサポート体制について相談する良い機会となります。
- 予防接種の確認と完了:
- 重要性:小学校は多くの子どもたちが集まる場所であり、感染症が広がりやすい環境です。
予防接種を完了しておくことで、お子さん自身だけでなく、周囲の子どもたちへの感染リスクも低減できます。 - 確認すべきワクチン:麻しん風しん混合(MR)、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)、日本脳炎、ポリオ(不活化ポリオワクチン)、ジフテリア・百日せき・破傷風(DPT)など、接種状況を母子手帳で確認しましょう。
- 接種漏れがないか確認:かかりつけの小児科医に相談し、小学校入学までに必要な予防接種がすべて完了しているか確認し、未接種のものがあれば早めに接種を済ませましょう。
就学前健診や予防接種は、お子さんが安心して小学校生活を送るための大切なステップです。
通知を見逃さず、計画的に進めるようにしましょう。
小学校入学前の手続きと情報収集
小学校入学は、お子さんだけでなく保護者にとっても大きな節目です。
スムーズなスタートを切るためには、入学前の各種手続きや情報収集が非常に重要になります。
ここでは、見落としがちな手続きや、知っておくべき情報について詳しく解説します。
入学説明会で確認すべきこと

入学説明会は、入学を控えたお子さんの保護者を対象に、学校生活の概要や必要な準備について説明が行われる大切な機会です。
学校の雰囲気や教育方針を知る貴重な場でもありますので、積極的に参加し、疑問点はその場で解消しましょう。
多くの場合、入学前年の秋から冬にかけて開催されます。
説明会で確認すべき主な項目を以下にまとめました。
事前に質問事項をリストアップしていくと、より効率的に情報を得られます。
項目 | 確認内容 |
|---|---|
入学式に ついて | 日時、場所、持ち物、服装、 保護者の参加人数制限など |
学校生活の 基本 | 始業・終業時間、 給食の有無、 アレルギー対応、 登下校のルール (通学路、集団登校の有無)、 緊急時の連絡方法、 欠席・遅刻・早退の連絡方法 |
学習に ついて | 授業時間、 宿題の量、 評価方法、 家庭学習のサポート方法、 使用する教科書・教材について |
持ち物 学用品 | 指定の学用品 (体操服、給食着、上履きなど) の購入方法、 ランドセルや 学習机に関する推奨事項、 持ち込み禁止品 |
年間行事 | 遠足、運動会、授業参観、 個人面談などの 年間スケジュール |
保健 安全 | 保健室の利用方法、 健康診断、 予防接種の確認、 災害時の対応 |
PTA 保護者会 | PTA活動の概要、 加入の有無、 役員選出について、 保護者会の開催頻度 |
その他 | 学校からの連絡方法 (プリント、アプリ、WEBサイトなど)、 就学援助制度、 学童保育との連携、 個別相談の機会 |
学童保育や放課後児童クラブの情報収集

共働き家庭や日中保護者が不在になる家庭にとって、小学校入学後の放課後の居場所確保は重要な課題です。
多くの自治体では、小学校の敷地内や近隣に「学童保育」や「放課後児童クラブ」が設置されています。
利用を検討している場合は、早めの情報収集と申し込みが不可欠です。
情報収集のポイントと確認すべき項目は以下の通りです。
- 情報収集の方法:
- お住まいの市区町村の広報誌やウェブサイト
- 教育委員会や子育て支援課
- 小学校の入学説明会
- 地域の児童館や子育て支援センター
- すでに利用している保護者からの口コミ
- 確認すべき項目:
- 開所時間: 平日、土曜日、長期休暇中の開所時間、延長保育の有無。
- 利用条件: 保護者の就労状況、所得制限の有無など。
- 費用: 月額利用料、おやつ代、教材費などの費用体系。
- 定員と待機児童の状況: 特に都市部では待機児童が多い傾向にあるため、早めの確認が必要です。
- 活動内容: 遊び、宿題支援、イベントなど、どのような活動が行われているか。
- 指導員の体制: 指導員の人数や資格、子どもとの関わり方。
- 場所と送迎: 学校内にあるか、学校からの距離、送迎の有無。
- 申し込み時期と方法: 例年、入学前年の秋から冬にかけて募集が始まり、締め切りが早いため注意が必要です。
- 見学や説明会の有無: 実際に施設を見て、雰囲気を知る機会があるか。
多くの学童保育は定員制であり、申し込み時期を逃すと利用できない可能性もあります。
必ず最新の情報を確認し、計画的に準備を進めましょう。
①就学援助制度について知る

小学校への入学は、学用品の購入や給食費など、さまざまな費用がかかります。
経済的な理由で就学が困難な家庭に対しては、国や地方自治体による「就学援助制度」が設けられています。
この制度は、経済的な不安を抱えることなく、子どもが安心して学校生活を送るための大切な支援です。
就学援助制度の主な内容と確認事項は以下の通りです。
- 制度の目的: 経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行うことで、義務教育の円滑な実施を支援します。
- 対象者: 生活保護を受けている世帯、またはそれに準ずる程度に経済的に困窮していると認められる世帯が対象となります。所得基準は各市町村によって異なります。
- 援助の内容:
- 学用品費: 教科書以外の学用品の購入費用。
- 給食費: 給食にかかる費用。
- 新入学児童生徒学用品費等: 新入学時に必要な学用品や通学用品の購入費用(入学前または入学後早期に支給される場合が多い)。
- 修学旅行費、校外活動費、体育実技用具費、医療費(学校保健安全法に基づく健康診断で治療が必要とされたもの)などが含まれる場合もあります。
- 申請時期: 入学前年の秋頃から入学後すぐの期間に申請を受け付けていることが多いです。年度途中でも申請できる場合があります。
- 申請窓口: お住まいの市区町村の教育委員会、または入学予定の小学校。
- 必要書類: 所得証明書、住民票、保護者の身分証明書など、自治体によって異なります。
- 重要性: 制度の利用は子どもの学習環境を整える上で非常に有効です。
対象となる可能性がある場合は、遠慮なく自治体や学校に相談し、詳細を確認しましょう。
➁PTA活動について
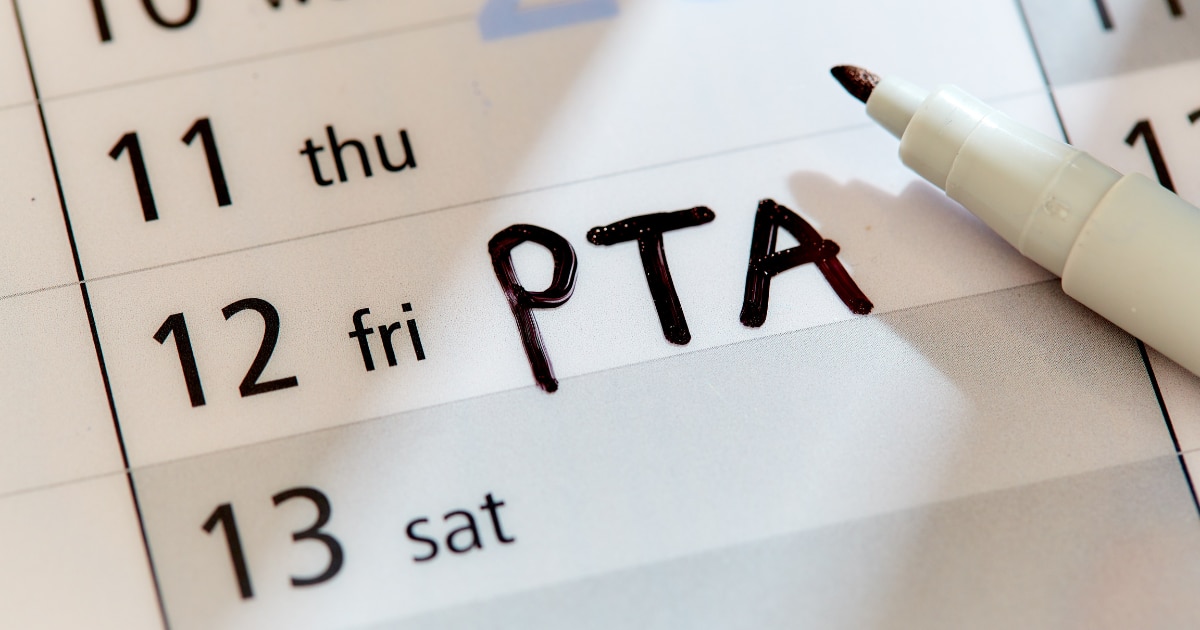
PTA(Parent-Teacher Association)は、保護者と教職員が協力し、子どもの健全な成長と学校教育の充実を目的として活動する任意団体です。
小学校入学を機に、PTA活動への参加を検討する保護者も多いでしょう。
PTAの役割や活動内容を事前に把握しておくことは、学校生活への理解を深める上で役立ちます。
PTA活動に関する主な情報と確認すべき点は以下の通りです。
- PTAの役割と目的:
- 学校行事への協力(運動会、文化祭、遠足など)
- 登下校時の見守りや交通安全活動
- 学校施設の環境整備や清掃活動
- 広報誌の発行やウェブサイト運営
- 保護者間の交流促進や情報交換の場作り
- 学校と地域社会との連携強化
- 教育に関する研修会や講演会の開催
- 加入の任意性: PTAへの加入は原則として任意です。しかし、多くの小学校では、入学時にPTA加入の案内があり、特に申し出がなければ自動的に加入となるケースもあります。
ご自身の意思を確認し、不明な点は学校や先輩保護者に問い合わせましょう。 - 活動への参加:
- 役員活動: 会長、副会長、書記、会計などの役員や、各委員会の委員を務めることがあります。任期や活動内容は学校によって異なります。
- ボランティア活動: 行事の手伝いや地域活動への参加など、役員以外でも様々な形で協力する機会があります。
- メリットと懸念:
- メリット: 学校の様子を詳しく知ることができる、他の保護者や先生方との交流が深まる、子どもの学校生活をより身近に感じられる、子どもの教育環境改善に貢献できる。
- 懸念: 活動時間や負担、人間関係など。近年では、PTA活動の見直しや負担軽減の取り組みが進められている学校も増えています。
- 情報収集のポイント:
- 入学説明会でPTAの活動内容や役員選出について説明があるか確認する。
- 学校のウェブサイトやPTAの広報誌で活動状況を調べる。
- すでにその学校に通っている先輩保護者から、実際の活動状況や雰囲気について話を聞く。
PTA活動は、子どもの学校生活をより豊かにするための重要な役割を担っています。ご自身のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で関わり方を検討してみましょう。
小学校入学準備で後悔しないためのポイント
①先輩ママの体験談から学ぶ

小学校入学準備は、初めての経験で戸惑うことも多いものです。
そんな時、先輩ママたちの体験談は非常に貴重な情報源となります。
実際に経験したからこそわかる「やっておけばよかったこと」や「これは必要なかった」といった生の声は、あなたの準備をより効率的で後悔のないものにする手助けとなるでしょう。
情報収集の際は、SNSのコミュニティ、地域の情報交換会、子育てブログなどを活用してみましょう。
ただし、すべての情報に鵜呑みにせず、ご自身の家庭の状況や子どもの性格に合わせて取捨選択することが大切です。
例えば、特定の学習教材が良いと聞いても、お子さんに合うかどうかは実際に試してみないとわかりません。
周りの意見に流されすぎず、本当に必要なもの、お子さんが楽しく取り組めるものを選ぶ視点を持つことが、後悔しない準備の第一歩です。
➁入学準備で「買ってよかったもの」「いらなかったもの」
入学準備では、様々な学用品や通学グッズの購入が必要になります。
しかし、中には「結局使わなかった」「もっと安価なものでよかった」と後悔するアイテムも少なくありません。
ここでは、先輩ママたちの声をもとに、「買ってよかったもの」と「いらなかったもの」の具体例をまとめました。購入前にぜひ参考にしてください。
カテゴリ | 買ってよかったもの | 理由・ポイント |
|---|---|---|
名前付け 関連 | お名前シール スタンプ | 膨大な数の持ち物への名前付け作業を 大幅に効率化できます。 特に洗濯に強いタイプや、 算数セット用の細かいシールは重宝します。 |
学用品 収納 | 学用品収納 ラックワゴン | ランドセルや教科書、 体操服などをまとめて置く場所があると、 子どもが自分で準備しやすくなり、 忘れ物防止にも繋がります。 |
生活習慣 | 子ども用の 目覚まし時計 | 自分で時間を意識し、 早寝早起きの習慣を 身につけるきっかけになります。 シンプルなデザインで、 文字盤が見やすいものがおすすめです。 |
通学関連 | 反射材付きの 防犯ブザー | 通学時の安全対策として必須。 ランドセルに簡単に取り付けられ、 いざという時に使いやすいものを選びましょう。 |
学習関連 | シンプルな 学習タイマー | 集中して学習する時間を意識させ、 時間の管理能力を養うのに役立ちます。 ゲーム感覚で使えるものがおすすめです。 |
カテゴリ | いらなかったもの | 理由・ポイント |
|---|---|---|
文房具 | 高価な キャラクター文具 | 学校によっては キャラクターものの使用が 禁止されている場合があります。 また、飽きやすい、失くしやすい といった声も聞かれます。 シンプルなものや、 学校指定のものが無難です。 |
学習机 | 小学校入学時に 購入した学習机 | 低学年のうちはリビング学習が 中心になる家庭も多く、 専用の学習机は あまり使われないことがあります。 必要になってから 購入を検討しても遅くありません。 |
衣類 | 入学式用の特別な フォーマル服 | 入学式以外に すぐにサイズアウト してしまうことがあります。 普段使いもできる 兄弟姉妹のお下がりで 十分という声も多いです。 |
通学関連 | 多機能すぎる ランドセルカバー | シンプルな防水機能のもので 十分な場合が多いです。 多機能なものはかさばったり、 子どもが扱いにくかったり することがあります。 |
上記のリストはあくまで一例です。
購入前に学校からの配布物や説明会で必要なものをしっかり確認し、本当に家庭に合うもの、子どもが使いやすいものを選ぶように心がけましょう。
フリマアプリやリサイクルショップで状態の良いものを探したり、お下がりを活用したりするのも賢い選択です。
➂焦らない!無理なく進める準備のコツ
小学校入学準備は多岐にわたり、つい焦ってしまいがちです。
しかし、完璧を目指しすぎると親子ともに疲弊してしまう可能性があります。
無理なく、着実に準備を進めるためのコツをいくつかご紹介します。
- 早めに全体像を把握する:入学の1年前から準備の項目をリストアップし、大まかなスケジュールを立てておくと、直前になって慌てずに済みます。
- 家族で分担する:準備はママ一人で抱え込まず、パパや祖父母など、家族みんなで協力しましょう。名前付けや買い物など、できることを分担するだけで負担は大きく軽減されます。
- 優先順位をつける:全ての準備を同時に完璧に進めるのは困難です。まずは学校から指定された必須アイテムの準備や、生活習慣の確立など、優先度の高いものから着手しましょう。
- 「完璧主義」を手放す:多少の不備があっても、入学後に対応できることはたくさんあります。
子どもが楽しく小学校生活をスタートできるよう、おおらかな気持ちで準備を進めることが大切です。 - 休息をしっかり取る:準備期間中も、親子でリラックスできる時間を作りましょう。心身ともに健康な状態で入学を迎えられるよう、無理のないペースを心がけてください。
④小学校入学前の不安を解消する方法
新しい環境への変化は、子どもだけでなく保護者にとっても不安がつきものです。
特に小学校入学は、子どもの成長の大きな節目であり、様々な心配事が頭をよぎるかもしれません。
ここでは、入学前の不安を解消し、親子で安心して新生活を迎えられるための方法を提案します。
- 親子で小学校について具体的に話す:漠然とした不安は、具体的にイメージすることで軽減されます。
「どんな先生がいるのかな?」「どんなお友達ができるかな?」「給食ってどんな感じかな?」など、ポジティブな内容を中心に話し合い、期待感を高めましょう。 - 小学校や通学路に慣れる機会を作る:可能であれば、小学校の校庭で遊んでみたり、通学路を一緒に歩いてみたりする機会を作りましょう。
実際に足を運ぶことで、環境への慣れや安心感が生まれます。 - 絵本や動画を活用する:「がっこうへいこう」「いちねんせい」など、小学校生活を描いた絵本を読み聞かせたり、小学校の紹介動画を見たりするのも有効です。具体的なイメージを持つことで、不安が和らぎます。
- 地域の情報交換会に参加する:同じ小学校に入学する保護者との交流は、情報共有だけでなく、不安を分かち合い、共感を得る上で非常に役立ちます。地域のコミュニティセンターや子育て支援センターなどで開催されるイベントに参加してみましょう。
- 先生や学校に相談する:入学説明会や個別の面談などで、気になることや不安なことがあれば遠慮なく質問しましょう。学校側も子どものスムーズな適応を望んでいます。具体的なアドバイスやサポートが得られることもあります。
- 「できること」に目を向ける:子どもがまだできないことばかりに目を向けるのではなく、「もうこんなことができるようになったね!」と成長を認め、自信を持たせることが大切です。
その自信が、新しい環境へ飛び込む勇気につながります。
まとめ
 小学校入学は、お子さんにとってもご家族にとっても大きな節目です。
小学校入学は、お子さんにとってもご家族にとっても大きな節目です。
この記事では、いつから何を準備すべきか、必要なものリスト、心と体の準備、そして手続きまで、多岐にわたる情報をお届けしました。
完璧を目指すよりも、お子さんのペースに合わせて、一つひとつ着実に準備を進めることが大切です。
特に、名前付けや生活習慣の確立は、入学後のスムーズなスタートに直結するため、早めに取り組むことをおすすめします。
不安なことは一人で抱え込まず、学校や地域の情報、先輩ママの体験談を参考に、親子で楽しみながら準備を進めましょう。
この情報が、新一年生ママの皆様の不安を解消し、希望に満ちた小学校生活の第一歩となることを願っています。





