
「子どもにお菓子、適量は?」を解決!食育につながるおやつ習慣
「子どもにお菓子、どのくらいあげていいの?」
と悩む親御さんは多いのではないでしょうか。
この記事では、子どもの成長段階に応じたお菓子の「適量」と正しい与え方を徹底解説します。
お菓子が果たす役割から、与えすぎが招くリスク、さらには栄養を考慮した選び方や食育につながるおやつ習慣のコツまで網羅。
お菓子との賢い付き合い方を身につけ、お子さんの健やかな成長をサポートするおやつ習慣を築きましょう。
目次[非表示]
子どもにお菓子 適量はなぜ大切なのか
子どもの健やかな成長において、お菓子との付き合い方は非常に重要です。
単なる楽しみとしてだけではなく、その与え方一つで、子どもの心身の発達や食習慣に大きな影響を与えるからです。
お菓子の適量を知り、適切なタイミングで与えることは、子どもの健康を守り、豊かな食生活を育むための第一歩と言えるでしょう。
①おやつが果たす役割とは?

おやつは、子どもにとって単なる嗜好品ではありません。
特に成長期の子どもは大人に比べて胃が小さく、一度に多くの食事を摂ることが難しい場合があります。
そのため、おやつは食事で摂りきれないエネルギーや栄養素を補う「補食」としての役割を担っています。
また、おやつは心のリフレッシュや気分転換にもつながります。
遊びや勉強の合間に食べることで、集中力を高めたり、親子や友達とのコミュニケーションの機会となったりすることもあります。
ただし、これらの役割が適切に果たされるのは、あくまで適量を守り、バランスを考えたおやつ選びをした場合です。
➁お菓子の与えすぎが招くリスク
 お菓子は子どもの楽しみの一つですが、与えすぎると様々な健康リスクを招く可能性があります。
お菓子は子どもの楽しみの一つですが、与えすぎると様々な健康リスクを招く可能性があります。
特に、糖分や脂質の多いお菓子は、子どもの成長に悪影響を及ぼしかねません。
リスクの種類 | 具体的な影響 |
|---|---|
虫歯 | 歯のエナメル質が溶ける |
肥満 | 生活習慣病のリスク |
栄養偏り | 食事への意欲低下 |
味覚形成 | 濃い味を好む |
血糖値変動 | 集中力低下 |
これらのリスクの中でも、特に注意したいのは、子どもの成長に必要な栄養素が不足し、食事への意欲も低下してしまうことです。
お菓子でお腹がいっぱいになり、肝心な食事を摂らなくなることで、鉄分やカルシウムなどの重要な栄養素が不足し、発育に影響が出ることもあります。
また、肥満は将来の生活習慣病につながる可能性も否定できません。
甘い味に慣れてしまうと、素材本来の味を感じにくくなり、味覚の形成にも悪影響を及ぼすことがあります。
子どもの年齢別 お菓子の適量と与え方
①乳幼児期 0歳から1歳半頃のお菓子
 この時期のおやつは、離乳食では補いきれない栄養を補給する「補食」としての役割が主です。
この時期のおやつは、離乳食では補いきれない栄養を補給する「補食」としての役割が主です。
まだ消化機能が未熟なため、量よりも質を重視し、食事に影響が出ないよう少量に留めることが大切です。
具体的な目安と注意点は以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
適量 | 1日1回程度 |
少量 | |
種類 | 赤ちゃんせんべい |
ボーロ | |
プレーンヨーグルト | |
バナナ | |
与え方 | 手づかみ食べの練習に |
食事に響かない時間に | |
注意点 | 砂糖・塩分なし |
アレルギーに配慮 | |
のどに詰まらせない |
赤ちゃん用のお菓子を選ぶ際は、原材料をよく確認し、余計な添加物やアレルゲンが含まれていないか注意しましょう。
➁幼児期 1歳半から3歳頃のお菓子
 活発に動き回るこの時期は、エネルギー消費も増えます。
活発に動き回るこの時期は、エネルギー消費も増えます。
おやつは3食で不足しがちな栄養を補うだけでなく、活動に必要なエネルギー源としても重要です。
食事のリズムを崩さないよう、時間と量を決めて与えることがポイントです。
具体的な目安と注意点は以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
適量 | 1日1~2回程度 |
食事の1/4程度 | |
種類 | おにぎり |
ふかし芋 | |
チーズ | |
果物 | |
野菜スティック | |
与え方 | 時間を決める |
食べ過ぎに注意 | |
注意点 | 虫歯予防 |
食事への影響 |
市販のお菓子を与える場合は、パッケージに記載された対象年齢や目安量を参考にし、少量に留めるようにしましょう。
➂学童期 3歳以降のお菓子

学童期になると、さらに活動量が増え、成長のために多くのエネルギーと栄養が必要です。
おやつは、不足しがちな栄養を補い、気分転換にもなる大切な時間です。
ただし、自己判断で食べ過ぎてしまうリスクもあるため、家庭でのルール作りが重要になります。
具体的な目安と注意点は以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
適量 | 1日1~2回程度 |
総摂取カロリーの10~15% | |
種類 | おにぎり |
サンドイッチ | |
果物 | |
乳製品 | |
少量スナック菓子 | |
与え方 | 時間を決める |
量を決める | |
自分で選ばせる | |
注意点 | 肥満・虫歯予防 |
偏食を避ける | |
メディアの影響 |
この時期は、子ども自身が食べたいものを主張し始めるため、「なぜこのお菓子は適量なのか」「どうして食べ過ぎてはいけないのか」を一緒に考える機会として、食育につなげましょう。
子どもに選んであげたいお菓子の種類
子どもに与えるお菓子は、単なる嗜好品ではなく、成長をサポートする「補食」としての役割も持ちます。
賢くお菓子を選び、食育につなげましょう。
①栄養を補うおやつの選び方
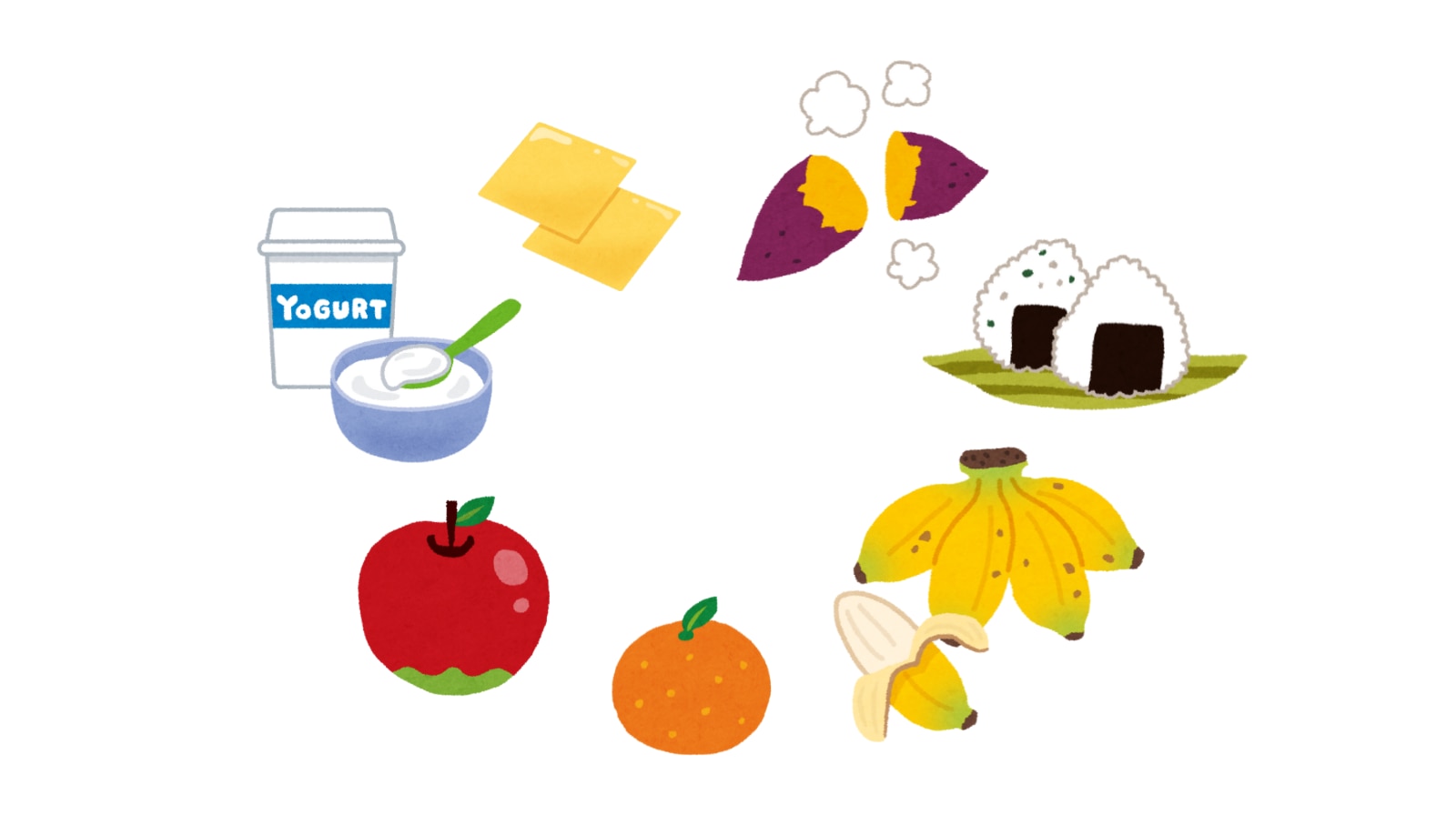 子どものおやつは、食事で不足しがちな栄養素を補う大切な機会です。
子どものおやつは、食事で不足しがちな栄養素を補う大切な機会です。
特にカルシウムやビタミン、食物繊維などが不足しやすい傾向にあります。
これらを意識的に補える食材を選ぶことが重要です。
おやつの種類 | 期待する栄養 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|---|
乳製品 | カルシウム、タンパク質 | ヨーグルト、チーズ | 砂糖不使用が理想 |
果物 | ビタミン、食物繊維 | バナナ、りんご、みかん | 季節のものを適量 |
芋類、穀物 | 炭水化物、エネルギー | ふかし芋、おにぎり | 味付けは薄めに |
これらのおやつは、素材の味を活かし、加工が少ないものを選ぶことで、余計な糖分や塩分を控えることができます。
➁市販のお菓子を選ぶ際のポイント

市販のお菓子は手軽ですが、選び方を間違えると糖分や添加物の過剰摂取につながりかねません。以下のポイントを参考に、賢く選びましょう。
チェック項目 | 確認ポイント | 選ぶ理由 |
|---|---|---|
原材料表示 | シンプルな材料 | 余計な添加物減 |
栄養成分表示 | 糖分、塩分控えめ | 肥満、生活習慣病予防 |
形状・固さ | 年齢に合わせる | 誤嚥リスク回避 |
個包装 | 小分け包装 | 量の管理が容易 |
アレルギー表示 | 特定原材料確認 | 安全な選択 |
特に「砂糖不使用」や「低糖質」と記載された商品や、米菓、せんべい、ビスケット類でも、油分や塩分が控えめなものを選ぶと良いでしょう。
子どもの成長段階に合わせた固さや形状も、安全面から非常に重要です。
➂手作りお菓子で食育を深める

手作りお菓子は、材料を自分で選べるため、砂糖や油の量を調整しやすく、子どもの健康に配慮したおやつを提供できます。
また、親子で一緒に作る過程そのものが、貴重な食育の機会となります。
手作りのメリット | 具体例 | 食育効果 |
|---|---|---|
材料の調整 | 砂糖、油を減らす | 健康的な味覚育む |
親子で体験 | 一緒に作る | 食への関心高まる |
旬の食材 | 季節の果物使う | 自然の恵み学ぶ |
蒸しパン、クッキー、ゼリー、プリンなどは、比較的簡単に作れる手作りお菓子の代表例です。
一緒に材料を混ぜたり、型抜きをしたりする体験は、「食べ物への感謝」や「作る楽しさ」を育み、子どもの五感を刺激します。
季節の果物を取り入れることで、旬の味や自然の恵みを感じる機会にもなります。
お菓子を食育につなげるおやつ習慣のコツ
①おやつの時間と場所を決める
 子どもにお菓子を与える際は、時間と場所を明確に決めることが、食育の第一歩となります。
子どもにお菓子を与える際は、時間と場所を明確に決めることが、食育の第一歩となります。
これにより、だらだら食べを防ぎ、次の食事への影響を最小限に抑えられます。
具体的には、以下の点を参考に習慣化しましょう。
項目 | ポイント |
|---|---|
時間 | 食事の2~3時間後 |
場所 | 食卓など |
ルール | 食べ終わったら片付ける |
毎日同じ時間に、決まった場所で食べることで、子どもは「おやつは特別な時間」と認識し、食事とのメリハリをつけやすくなります。
➁「お菓子は別腹」にしない考え方
 大人にとっては「お菓子は別腹」という感覚があるかもしれませんが、子どものおやつは「食事の一部」と捉えることが重要です。
大人にとっては「お菓子は別腹」という感覚があるかもしれませんが、子どものおやつは「食事の一部」と捉えることが重要です。
これは、おやつが単なる嗜好品ではなく、不足しがちな栄養を補う役割も持つためです。
おやつを与える際は、食事で摂りきれなかった栄養素(例:カルシウム、食物繊維)を意識して選ぶようにしましょう。
また、おやつを食べすぎると食事に響くことを伝え、食事全体で栄養バランスを考える習慣を育むことが食育につながります。
➂おやつを通じた親子のコミュニケーション
 おやつの時間は、子どもとの大切なコミュニケーションの機会でもあります。
おやつの時間は、子どもとの大切なコミュニケーションの機会でもあります。
単に与えるだけでなく、一緒に準備したり、選び方を教えたりすることで、食への関心や感謝の気持ちを育むことができます。
- 一緒に選ぶ:スーパーで「今日のおやつは何にする?」と一緒に考え、栄養面や添加物の有無を話す。
- 一緒に作る:簡単なおやつ(例:フルーツヨーグルト、おにぎり)を一緒に作り、食の楽しさを共有する。
- 会話を楽しむ:おやつを食べながら、今日の出来事や感想を話し合う。
このような親子の関わりを通じて、子どもは食に関する知識や判断力を自然と身につけ、健全な食習慣を築いていくことができます。
子どもがお菓子をせがむ時の対処法
子どもがお菓子をせがむ場面は、多くの家庭で日常的に起こります。
この時、どのように対応するかが、子どもの食習慣や食育に大きく影響します。
感情的に叱るのではなく、冷静かつ一貫した対応を心がけましょう。
①食事への影響を避ける声かけのヒント
 子どもがお菓子をせがむ時、最も重要なのは、その後の食事に影響が出ないようにすることです。
子どもがお菓子をせがむ時、最も重要なのは、その後の食事に影響が出ないようにすることです。
食事を大切にする習慣を育むためにも、適切な声かけが重要になります。
声かけ例 | ポイント |
|---|---|
「今はおやつの 時間じゃないよ」 | 明確に伝える |
「ご飯の前だから お腹を空かせよう」 | 理由を伝える |
「食後に食べようね」 | 約束する |
「おやつは〇〇に しようね」 | 時間を伝える |
「ご飯を食べてから もっと美味しくなるよ」 | 食事を促す |
これらの声かけを通じて、子どもは「お菓子には適切な時間がある」というルールを学び、食事の重要性を理解しやすくなります。
曖昧な返事をせず、親が一貫した態度で接することが大切です。
➁お菓子以外の楽しみを見つける工夫
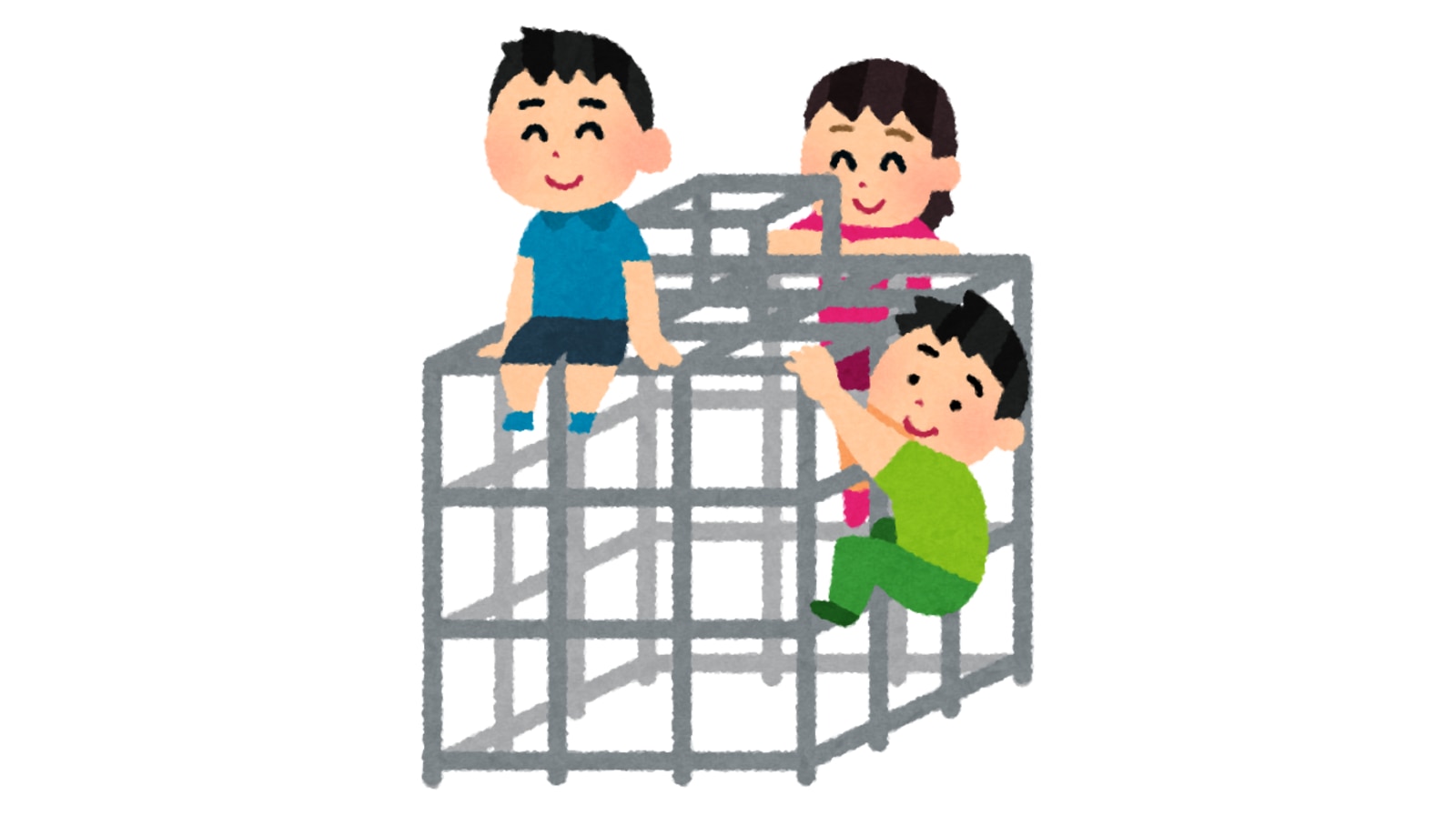 子どもがお菓子をせがむ背景には、退屈や寂しさ、あるいは単に「何かしたい」という気持ちが隠れていることがあります。
子どもがお菓子をせがむ背景には、退屈や寂しさ、あるいは単に「何かしたい」という気持ちが隠れていることがあります。
お菓子以外の魅力的な選択肢を提示することで、子どもの気持ちを上手に切り替えることができます。
具体的な工夫としては、以下のようなものがあります。
- 体を動かす遊び:公園に行く、室内で体を動かす遊びをする。
- 知的好奇心を刺激する遊び:絵本の読み聞かせ、ブロックやパズル、お絵描きなど。
- お手伝い:簡単な家事(洗濯物をたたむ、野菜を洗うなど)を一緒に楽しむ。
- スキンシップ:抱っこしたり、一緒に歌を歌ったり、親子の触れ合いの時間を増やす。
- 気分転換:窓の外を眺める、違う部屋に移動するなど、環境を変える。
これらの工夫を通じて、子どもはお菓子がなくても楽しい時間を過ごせることを知り、感情のコントロールを学ぶきっかけにもなります。
親子のコミュニケーションを深める良い機会と捉えましょう。
まとめ
子どもにとってお菓子は楽しみの一つであり、時には気分転換やエネルギー補給の役割も果たします。
しかし、与えすぎは健康リスクにつながるため、「適量」を知り、年齢に合わせた与え方をすることが何よりも大切です。
本記事でご紹介したように、栄養を考慮したお菓子の選び方や、おやつを食育の機会と捉える習慣は、子どもの健やかな成長を促します。
親子のコミュニケーションを深めながら、無理なく健康的で楽しいおやつ習慣を築き、子どもたちが心身ともに豊かに育つようサポートしていきましょう。





