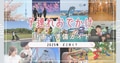その夜泣き、いつまで続く?放置はNG?考えられる原因とスムーズな卒業方法
終わりが見えない夜泣きに、心身ともに疲れ果てていませんか。
赤ちゃんの夜泣きは個人差が大きいものの、一般的に生後6ヶ月から1歳半頃にピークを迎え、2歳頃には落ち着くことが多いです。
この記事では、夜泣きの原因や放置せず安心感を与えるべき理由を解説。
さらに、今すぐできる対処法から夜泣き卒業を早める生活習慣、専門の相談先まで網羅的にご紹介します。
辛い夜を乗り越えるための具体的なヒントがきっと見つかります。
目次[非表示]
- 1.夜泣きはいつまで続く?一般的な時期とピーク
- 1.1.①夜泣きが始まる時期の目安は生後3ヶ月頃から
- 1.2.➁夜泣きのピークは生後6ヶ月から1歳半頃
- 1.3.➂多くの赤ちゃんは2歳頃までに夜泣きが落ち着く
- 1.4.④ただし個人差が大きいことも忘れないで
- 2.なぜなくの?月齢別に考えられる夜泣きの原因
- 2.1.①新生児から生後3ヶ月頃の主な原因
- 2.2.➁生後4ヶ月から生後8ヶ月頃の主な原因
- 2.3.➂生後9ヶ月以降の主な原因
- 2.4.④身体的な不快感が原因の場合
- 2.4.1.①お腹がすいた、喉が渇いた
- 2.4.2.➁おむつが濡れて気持ち悪い
- 2.4.3.➂暑い、寒いなど室温が不快
- 2.4.4.④鼻づまりや体の痛み
- 2.5.⑤精神的な要因が原因の場合
- 2.5.1.①昼間の刺激が強すぎた
- 2.5.2.➁ママやパパと離れるのが不安(分離不安)
- 2.5.3.➂怖い夢を見た
- 2.6.⑥生活リズムや睡眠サイクルが原因の場合
- 2.6.1.①睡眠サイクルが未熟で浅い眠りが多い
- 2.6.2.➁生活リズムが乱れている
- 3.夜泣きは放置しても大丈夫?知っておきたいこと
- 4.今すぐできる夜泣きがおさまらない時の対処法
- 4.1.①まずは不快な原因がないかチェックする
- 4.2.➁抱っこやトントンで安心させる
- 4.3.➂部屋の電気を一度つけて気分転換
- 4.4.④ホワイトノイズや子守唄を聴かせる
- 4.5.⑤水分補給や授乳を試す
- 5.夜泣き卒業へ スムーズに終わらせるための生活習慣
- 5.1.①朝は決まった時間に起こし日光を浴びる
- 5.2.➁日中は適度に体を動かして遊ばせる
- 5.3.➂お昼寝の時間と長さを調整する
- 5.4.④寝る前の入眠儀式(ねんねルーティン)を確立する
- 5.4.1.入眠儀式の例
- 5.5.⑤ねんねトレーニング(ネントレ)を検討する
- 6.もう限界…夜泣きで辛い時の相談先リスト
- 6.1.①かかりつけの小児科
- 6.2.➁地域の保健センターや保健師
- 6.3.➂子育て支援センターや児童館
- 6.4.④家族やパートナーと悩みを共有する
- 6.4.1.役割分担の具体例
- 7.まとめ
夜泣きはいつまで続く?一般的な時期とピーク

毎晩のように続く赤ちゃんの夜泣き。
「一体いつまで続くの…?」と、終わりが見えない不安と寝不足で心身ともに疲れ果ててしまうママやパパは少なくありません。
しかし、夜泣きには一般的な時期やピークがあり、終わりは必ずやってきます。
まずは夜泣きの全体像を把握して、少しだけ先の見通しを立ててみましょう。
ここでは、夜泣きがいつから始まり、いつ頃ピークを迎え、いつになったら落ち着くのか、一般的な目安を解説します。
ただし、これからお伝えする時期はあくまでも目安であり、すべての赤ちゃんに当てはまるわけではないことを心に留めておいてください。
①夜泣きが始まる時期の目安は生後3ヶ月頃から

個人差はありますが、本格的な夜泣きは生後3ヶ月頃から始まる赤ちゃんが多いと言われています。新生児期も夜中に泣くことは頻繁にありますが、その多くはお腹がすいた、おむつが気持ち悪いといった生理的な欲求によるものです。
生後3ヶ月頃になると、少しずつ昼と夜の区別がつき始め、睡眠リズムが変化してくる過程で、理由がはっきりしない「夜泣き」が起こりやすくなります。
この時期は、赤ちゃんの心と体が大きく成長する第一歩のサインともいえるでしょう。
➁夜泣きのピークは生後6ヶ月から1歳半頃

多くのパパやママが最も大変だと感じる夜泣きのピークは、生後6ヶ月から1歳半頃に訪れることが多いです。
この時期は、赤ちゃんの心と体の発達が著しく、夜泣きの原因も複雑に絡み合ってきます。
- 記憶力の発達:日中に体験した楽しかったことや怖かったこと、興奮したことなどを夢に見やすくなります。
- 分離不安:ママやパパがいないことに気づいて不安で泣き出します。後追いが始まる時期と重なることもあります。
- 体の発達:寝返り、おすわり、ハイハイ、つかまり立ちなど、次々と新しいことができるようになることで脳が興奮状態になり、夜中に目が覚めやすくなります。
- 歯の生え始め:歯が生える時のむずがゆさや不快感(歯ぐずり)で眠りが浅くなることがあります。
このように、様々な要因が重なるため、夜泣きの回数が増えたり、一度泣き出すと激しくなったりする傾向があります。
➂多くの赤ちゃんは2歳頃までに夜泣きが落ち着く

終わりが見えないように感じる夜泣きですが、多くの赤ちゃんは1歳半から2歳頃までには自然と落ち着いてきます。
もちろん、それよりも早く終わる子もいれば、もう少し続く子もいます。
この時期になると、次のような理由で夜泣きが減っていきます。
- 睡眠サイクルの成熟:浅い眠りと深い眠りのサイクルが安定し、大人に近い睡眠パターンになってきます。
- 体内時計の確立:生活リズムが整い、夜は眠るものだという習慣が身につきます。
- コミュニケーション能力の発達:言葉で自分の気持ちを少しずつ伝えられるようになり、泣く以外の方法で不安や要求を表現できるようになります。
「あと少しで楽になるかもしれない」という見通しを持つことが、つらい時期を乗り越えるための助けになります。
④ただし個人差が大きいことも忘れないで

これまでご紹介した時期は、あくまでも一般的なデータに基づいた目安です。
赤ちゃんの夜泣きには非常に大きな個人差があり、すべての赤ちゃんがこのパターンに当てはまるわけではありません。
生まれた時からほとんど夜泣きをしない子もいれば、3歳を過ぎても続く子もいます。
赤ちゃんの気質や感受性の強さ、発達のペース、その日の出来事、家庭環境など、様々な要因が影響します。
大切なのは、他の赤ちゃんと比べて「うちの子は遅いかも…」と焦ったり、自分を責めたりしないことです。
目の前にいる我が子の個性と発達のペースを尊重し、寄り添ってあげることが何よりも重要です。
時期 | 状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|
生後3ヶ月頃〜 | 開始期 | 睡眠リズムの変化に伴い、 理由のわからない 夜泣きが始まる。 |
生後6ヶ月 〜1歳半頃 | ピーク期 | 心身の発達が著しく、 分離不安や日中の刺激など、 様々な要因が重なり 夜泣きが激しくなりやすい。 |
1歳半 〜2歳頃 | 落ち着く時期 | 睡眠サイクルが安定し、 生活リズムが整うことで、 多くの場合は自然と 夜泣きが減っていく。 |
全体を通して | 注意点 | 時期や程度には大きな個人差がある。 他の子と比べず、 その子のペースを 見守ることが大切。 |
なぜなくの?月齢別に考えられる夜泣きの原因
赤ちゃんの夜泣きの原因は一つではありません。
多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合っています。
赤ちゃんの心と体がめまぐるしく成長する過程で起こる、自然な現象の一つと捉えることが大切です。
ここでは、夜泣きの主な原因を「月齢別」「身体的」「精神的」「生活的」な側面に分けて詳しく解説します。
①新生児から生後3ヶ月頃の主な原因

この時期の赤ちゃんが夜中に泣くのは、まだ昼夜の区別がついておらず、睡眠リズムが確立されていないためです。
一般的に「夜泣き」と呼ばれるものとは少し異なりますが、夜間に泣いて起きる主な原因は、以下のような生理的な欲求がほとんどです。
- お腹がすいた
- おむつが濡れて気持ち悪い
- 暑い・寒いといった室温の不快感
- げっぷが出なくて苦しい
- モロー反射(大きな音などに驚いて手足を広げる原始反射)で起きてしまう
この時期は、赤ちゃんが発するサインに丁寧に応え、不快を取り除いてあげることが最も重要です。
まずは、お腹が空いていないか、おむつは汚れていないかなどを確認しましょう。
➁生後4ヶ月から生後8ヶ月頃の主な原因

いわゆる「夜泣き」が本格的に始まるのがこの時期です。
多くのママやパパを悩ませる原因は、赤ちゃんの急激な発達と深く関係しています。
- 睡眠退行(4ヶ月の壁):赤ちゃんの睡眠サイクルが、新生児期の「浅い眠り」と「深い眠り」の2相から、大人と同じようにレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返すパターンに変化する時期です。この睡眠構造の変化にうまく適応できず、眠りが浅くなったタイミングで目を覚ましやすくなります。これは成長の証ですが、一時的に夜中に何度も起きる原因となります。
- 心と体の発達:寝返りやお座りなど、できることが増えることで日中の活動が活発になります。その興奮が冷めやらぬまま夜を迎え、脳が覚醒してしまって泣き出すことがあります。
- 歯ぐずり:歯が生え始める際の歯茎のむずがゆさや痛みで、夜中に目を覚ましてぐずることがあります。
➂生後9ヶ月以降の主な原因

知能や感情がさらに発達し、夜泣きの原因もより複雑になってきます。
身体的な不快感よりも、精神的な要因が大きく影響するようになります。
- 分離不安:ママやパパといった特定の養育者との愛着関係が深まることで、「寝ている間にママがいない」と気づき、強い不安から泣き出すことがあります。後追いが始まるのと同じメカニズムで、これも愛着が順調に形成されている証拠です。
- 記憶力の発達:日中に体験した楽しかったことや、逆に怖かったことなどを記憶できるようになります。その記憶が夢となって現れ、驚いたり怖がったりして泣いてしまうことがあります。
- 自己主張の芽生え:「もっと遊びたい」「まだ寝たくない」といった自我が芽生え、自分の思い通りにならないことへの抵抗として泣くこともあります。
④身体的な不快感が原因の場合

月齢にかかわらず、赤ちゃんが泣く最も基本的な理由は身体的な不快感です。
夜泣きが始まったら、まずは以下の点を確認してみましょう。
①お腹がすいた、喉が渇いた
特に低月齢のうちは消化器官が未熟で、一度にたくさんの量を飲めません。
そのため、夜間でもお腹が空いて目を覚ますことは頻繁にあります。
また、空調や発汗によって喉が渇いている可能性も考えられます。
➁おむつが濡れて気持ち悪い
おしっこやうんちでおむつが濡れている不快感は、赤ちゃんにとって大きなストレスです。
肌が敏感な赤ちゃんの場合、おむつかぶれの痛みで泣いていることもあります。
➂暑い、寒いなど室温が不快
赤ちゃんは体温調節機能が未熟です。
大人が快適だと感じる室温でも、赤ちゃんにとっては暑すぎたり、寒すぎたりすることがあります。
汗をかいていないか、手足が冷たくなりすぎていないかなどをチェックし、衣類や寝具で調整しましょう。
④鼻づまりや体の痛み
風邪による鼻づまりで呼吸がしづらかったり、中耳炎で耳が痛かったり、便秘でお腹が張っていたりと、病気や体調不良が隠れている可能性もあります。
普段と泣き方が違う、ぐったりしているなど、気になる様子があれば早めに小児科を受診しましょう。
また、服のタグが肌に当たってチクチクするなど、些細なことが原因の場合もあります。
⑤精神的な要因が原因の場合

赤ちゃんの心は日々成長しており、その過程で生まれる不安や興奮が夜泣きにつながることがあります。
①昼間の刺激が強すぎた
初めての場所へのお出かけや、大勢の人に会った日など、日中に強い刺激を受けると脳が興奮状態になります。
その興奮が夜になっても静まらず、寝ている途中で脳が覚醒してしまい、泣き出すことがあります。
➁ママやパパと離れるのが不安(分離不安)
前述の通り、生後8ヶ月頃から顕著になることが多いです。
眠りが浅くなったタイミングでふと目を覚ました時、隣にいるはずのママやパパの姿が見えないと、強い不安を感じて泣き出してしまいます。
これは赤ちゃんがママやパパを「安全基地」として認識している大切な発達の証です。
➂怖い夢を見た
記憶力が発達してくると、大人と同じように夢を見るようになります。
夢の内容はコントロールできないため、怖い夢を見てパニックになり、泣き叫んで起きることがあります。
⑥生活リズムや睡眠サイクルが原因の場合

毎日の生活習慣が、夜の睡眠に大きく影響します。
①睡眠サイクルが未熟で浅い眠りが多い
赤ちゃんの睡眠は、大人とは異なる特徴を持っています。
特に睡眠サイクルが短く、浅い眠り(レム睡眠)の割合が多いため、物音やわずかな環境の変化で目を覚ましやすいのです。
サイクルとサイクルの合間でうまく次の眠りに入れず、泣いてしまうことがよくあります。
大人の場合 | 赤ちゃんの場合 | |
|---|---|---|
1サイクルの長さ | 約90分 | 約40分~60分 |
浅い眠りの割合 | 約20% | 約50% |
特徴 | 深い眠りから始まり、サイクルが安定している。 | 浅い眠りから始まり、サイクルが短く途中で目覚めやすい。 |
➁生活リズムが乱れている
朝起きる時間や夜寝る時間、お昼寝のタイミングが日によってバラバラだと、体内時計が乱れてしまいます。
特にお昼寝が長すぎたり、夕方遅くに寝てしまったりすると、夜になってもなかなか眠れず、睡眠の質が低下して夜泣きの原因になります。
夜泣きは放置しても大丈夫?知っておきたいこと
毎晩続く夜泣きに、「このまま泣き止むまで放っておいてもいいの?」と疑問に思う保護者の方は少なくありません。
赤ちゃんの心と体の発達、そして安全を守るために知っておきたい「放置」に関する考え方と、注意すべきサインについて解説します。
①基本的には放置せず安心感を与える対応を

結論から言うと、夜泣きの原因がわからない場合でも、放置はせず、まずは赤ちゃんの訴えに耳を傾け、安心感を与えることが基本です。
赤ちゃんは言葉で不快や不安を伝えられないため、「泣く」ことでコミュニケーションをとっています。
そのサインを無視し続けると、赤ちゃんは「自分の要求は受け入れてもらえない」と感じ、健全な愛着形成に影響が出る可能性も指摘されています。
海外では「クライイング・イット・アウト(Cry It Out)」のように、あえて泣かせたままにしておくトレーニング方法も存在します。
しかし、これは専門家の指導のもとで月齢や状況を慎重に判断して行うべきものであり、自己流で安易に試すのは推奨されません。
特に、日本の集合住宅のような住環境では、近隣への配慮も必要となります。
まずは、おむつが濡れていないか、お腹が空いていないか、部屋が暑すぎたり寒すぎたりしないかを確認しましょう。
身体的な不快がない場合は、抱っこや背中を優しくトントンするなどして、「パパやママはちゃんとそばにいるよ」というメッセージを伝え、赤ちゃんを安心させてあげることが大切です。
この安心感が、赤ちゃんの情緒の安定と、いずれ夜泣きを卒業していくための土台となります。
➁こんな夜泣きは要注意 病院受診を検討するサイン
ほとんどの夜泣きは成長過程の一時的なものですが、中には病気や体の不調が隠れているケースもあります。
「いつもの夜泣きと違う」と感じたら、注意深く様子を観察し、必要であれば医療機関の受診を検討しましょう。
以下に、受診を考えるべきサインをまとめました。
注意すべき サイン | 考えられる原因や 病気の例 | 具体的な症状や状況 |
|---|---|---|
いつもと違う 激しい泣き方 | ・中耳炎 ・腸重積 ・鼠径ヘルニア嵌頓 (かんとん)など | ・火が付いたように 突然泣き出す。 ・何をしても泣き止まない。 ・甲高い声で泣く。 ・うめき声をあげる。 ・泣きと不機嫌を繰り返す。 |
発熱や嘔吐、 下痢を伴う | ・ウイルス ・細菌感染症 ・胃腸炎など | ・38度以上の熱がある。 ・繰り返し吐く。 ・水のような便が続く。 ・ぐったりして 水分が摂れない。 |
呼吸の異常 | ・RSウイルス感染症 ・気管支炎 ・喘息様気管支炎など | ・呼吸時にゼーゼー ヒューヒューという音がする。 ・肩で息をする。 ・息が苦しそうで 顔色や唇の色が悪い。 |
ぐったりして 元気がない | ・脱水症 ・その他重篤な病気 | ・泣く力もなくぐったりしている ・呼びかけへの反応が鈍い ・おしっこの量が極端に少ない |
体を触ると 嫌がる | ・骨折 ・脱臼 ・打撲など | ・特定の腕や脚に触れると激しく泣く、 ・おむつ替えや着替えの際に 特定の箇所を痛がる様子を見せる。 |
これらのサインが見られる場合は、夜泣きではなく、病気のサインである可能性が高いです。
いつもと様子が違う、保護者の直感で「何かがおかしい」と感じた場合は、ためらわずに小児科を受診してください。
夜間や休日で判断に迷う場合は、子ども医療電話相談事業(#8000)に電話して、看護師や医師からアドバイスをもらうこともできます。
今すぐできる夜泣きがおさまらない時の対処法

けたたましく泣き叫ぶ赤ちゃんの声で真夜中に起こされ、何をしても泣き止んでくれない…。
そんな状況では、パパもママも途方に暮れてしまいますよね。
しかし、そんな時こそ冷静になることが大切です。ここでは、どうしてもうまくいかない夜に試せる、即効性のある対処法を具体的にご紹介します。
一つずつ試して、赤ちゃんが落ち着くポイントを探してみましょう。
①まずは不快な原因がないかチェックする

赤ちゃんが泣くのには、必ず何かしらの理由があります。
特に、言葉で不快感を伝えられない赤ちゃんにとって、泣くことは唯一のコミュニケーション手段です。
まずは、赤ちゃんが身体的に不快に感じていないか、以下の項目を冷静にチェックして、原因を取り除いてあげましょう。
チェック項目 | 確認のポイントと具体的な対処法 |
|---|---|
お腹がすいた、 喉が渇いた | 前回の授乳やミルクから 時間が空いていませんか? 口をパクパクさせたり、 指をしゃぶったりする仕草は 空腹のサインかもしれません。 まずは授乳やミルク、 月齢によっては 白湯や麦茶を 少し飲ませてあげましょう。 |
おむつが濡れて 気持ち悪い | おむつを触って、濡れていたり、 うんちをしていたりしないか確認します。 特に夏場は少しの尿でも 蒸れて不快に感じやすいです。 新しいおむつに替えて、 おしりを清潔にしてあげましょう。 |
暑い、寒いなど 室温が不快 | 赤ちゃんの背中や 首筋に手を入れて、 汗ばんでいないか、 逆に冷たくなっていないか を確認します。 汗をかいているなら服を 一枚脱がせる、 冷たいならスリーパーを 着せるなど調整しましょう。 快適な室温は 夏場で25〜27℃、 冬場で20〜23℃が目安です。 |
鼻づまりや 体の痛み | フガフガと苦しそうな 呼吸音がしないか、 熱っぽくないか、 体を触って嫌がる場所は ないかなどを確認します。 鼻が詰まっているようであれば、 鼻吸い器で吸ってあげる と楽になります。 普段と違う激しい泣き方や、 発熱など他の症状がある場合は、 病気の可能性も考えられます。 |
➁抱っこやトントンで安心させる

身体的な不快感を取り除いても泣き止まない場合、精神的な不安が原因かもしれません。
そんな時は、ママやパパのぬくもりや匂いが、赤ちゃんにとって何よりの安心材料になります。
まずは優しく抱きしめてあげましょう。
縦抱きや横抱き、コアラ抱っこなど、赤ちゃんが落ち着く抱き方を探してみてください。
おくるみで体を包んであげると、ママのお腹の中にいた時のような安心感を得られることもあります。
抱っこしながら、背中や胸を心臓の鼓動に近い一定のリズムで優しくトントンしてあげたり、「の」の字を描くようにお腹をさすってあげたりするのも効果的です。
➂部屋の電気を一度つけて気分転換

何をしても泣き止まず、親子ともに興奮状態になってしまった時の「奥の手」です。
一度、部屋の電気を点けてみましょう。ただし、煌々とした天井の明かりではなく、間接照明や常夜灯などの優しい光がおすすめです。
暗闇の中でぐずり続けていた赤ちゃんが、少し明るくなることでハッと我に返り、気分が変わることがあります。
目的はあくまで気分転換なので、完全に覚醒させて遊び始めるのはNGです。
少し落ち着いたら、「ねんねの時間だよ」と優しく声をかけ、再び部屋を暗くして寝かしつけを再開しましょう。
一度リセットすることで、かえってスムーズに寝直せる場合があります。
④ホワイトノイズや子守唄を聴かせる

聴覚に働きかける方法も有効です。
単調でリズミカルな音は、赤ちゃんの興奮を鎮め、眠りの世界へといざなう助けになります。
「ザーザー」「ゴー」といったホワイトノイズは、赤ちゃんがママのお腹の中で聞いていた血流の音に似ているため、安心すると言われています。
テレビの砂嵐の音、換気扇や空気清浄機の音、ビニール袋をくしゃくしゃにする音などが代表的です。
最近では、スマートフォンアプリや専用のぬいぐるみ、プロジェクターなどでも手軽に再生できます。
また、ママやパパの優しい声で歌う子守唄も、赤ちゃんをリラックスさせる効果が抜群です。
上手い下手は関係ありません。
穏やかで優しい声で、ゆっくりと歌ってあげることが大切です。
⑤水分補給や授乳を試す

最初のチェック項目でも挙げましたが、喉の渇きや空腹は夜泣きの大きな原因の一つです。
特に夏場や暖房の効いた冬の部屋では、赤ちゃんも喉が渇きやすくなります。
まずは白湯や麦茶などで水分補給を試してみましょう。
それでも泣き止まない場合は、授乳やミルクを試します。
お腹が満たされることで安心して、すぐに眠ってくれることも少なくありません。
ただし、毎回授乳で寝かしつけると「おっぱいがないと眠れない」という癖がつき、かえって夜中に起きる原因になる可能性もあります。
あくまで他の方法を試した上での選択肢の一つとして考え、少し飲んだら口から離すなど、眠るための「きっかけ」として上手に活用しましょう。
夜泣き卒業へ スムーズに終わらせるための生活習慣
毎晩繰り返される夜泣き。
その場しのぎの対応も大切ですが、夜泣きを根本から改善し、スムーズな卒業を目指すには、毎日の生活習慣を見直すことが非常に重要です。
赤ちゃんの体内時計を整え、質の高い睡眠へと導くための5つの習慣をご紹介します。
①朝は決まった時間に起こし日光を浴びる

夜泣き卒業への第一歩は、朝の過ごし方から始まります。
毎朝同じ時間にカーテンを開けて太陽の光を浴びせることで、赤ちゃんの体内時計がリセットされ、生活リズムが整いやすくなります。
人間の体は、朝日を浴びることで「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌が活発になります。
このセロトニンは、夜になると「睡眠ホルモン」であるメラトニンに変化する性質があります。
つまり、朝しっかりセロトニンを分泌させておくことが、夜の深い眠りにつながるのです。
雨や曇りの日でも、窓際で外の光を感じるだけで効果があります。
毎日7時までには起こすなど、家庭でのルールを決めて、まずは2週間続けてみましょう。
赤ちゃんの「朝」と「夜」の区別がつきやすくなります。
➁日中は適度に体を動かして遊ばせる

日中の過ごし方も、夜の睡眠に大きく影響します。
月齢に合わせた遊びを取り入れ、適度に体を動かすことで、心地よい疲労感が得られ、夜にぐっすりと眠りやすくなります。
ただし、疲れさせすぎは、かえって興奮して寝付けなくなる原因にもなります。
特に、夕方以降に激しい遊びをするのは避け、静かな活動に切り替えるのがポイントです。
赤ちゃんの様子を見ながら、無理のない範囲で活動量を調整しましょう。
月齢 | おすすめの遊び |
|---|---|
生後3ヶ月 ~5ヶ月頃 | 手足の運動 (ベビーマッサージ)、 寝返りの練習、 音の出るおもちゃで遊ぶ |
生後6ヶ月 ~11ヶ月頃 | ずりばいやハイハイ、 おすわりでのボール遊び、 公園での外気浴 |
1歳以降 | つかまり立ちやあんよの練習、 公園の遊具(安全なもの)、 手遊び歌 |
➂お昼寝の時間と長さを調整する

「夜にしっかり寝てほしいから」とお昼寝を極端に短くするのは逆効果です。
赤ちゃんにとってお昼寝は、心と体の成長に欠かせない大切な時間。しかし、お昼寝が長すぎたり、遅い時間になったりすると、夜の睡眠に影響が出てしまいます。
お昼寝は15時までには切り上げるようにし、夕寝は避けるのが理想です。
月齢ごとのお昼寝の合計時間や回数の目安を参考に、お子さんに合ったリズムを見つけてあげましょう。
月齢 | お昼寝の 合計時間(目安) | 回数 (目安) |
|---|---|---|
生後4ヶ月 ~6ヶ月 | 3~4時間 | 2~3回 |
生後7ヶ月 ~1歳頃 | 2~3時間 | 2回 |
1歳 ~2歳頃 | 1~2.5時間 | 1~2回 |
お昼寝から起こすときは、急にではなく、優しく声をかけたり、部屋を少しずつ明るくしたりして、穏やかに目覚めさせてあげるとご機嫌で起きられます。
④寝る前の入眠儀式(ねんねルーティン)を確立する

入眠儀式(ねんねルーティン)とは、「これをしたら、ねんねの時間」という毎日決まった寝る前の習慣のことです。これを繰り返すことで、赤ちゃんは「もうすぐ寝る時間だ」と心の準備ができ、安心して眠りにつきやすくなります。
大切なのは、毎日同じ時間帯に、同じ順番で、静かに行うことです。興奮させるようなテレビや激しい遊びは避け、リラックスできる内容を組み合わせましょう。
入眠儀式の例
- お風呂に入る
- パジャマに着替える
- 歯磨きをする
- 寝室へ移動し、照明を暗くする
- 絵本を1冊読む
- 静かな子守唄を歌う or オルゴールを聴く
- 「おやすみ」の挨拶をして布団に入る
すべての工程を15~30分程度で行うのがおすすめです。
家族みんなで協力し、一貫したルーティンを続けることが成功の鍵です。
⑤ねんねトレーニング(ネントレ)を検討する

様々な生活習慣を試しても夜泣きが改善しない場合、「ねんねトレーニング(ネントレ)」を検討するのも一つの方法です。
ネントレとは、赤ちゃんがママやパパの助けなしに、自力で眠りにつく力を育むための練習のことです。
ネントレには、泣いてもすぐには抱き上げず、少しずつ見守る時間を延ばしていく方法(ファーバーメソッドなど)や、抱き癖をつけないようにする子育て法(トレイシー・ホッグ式)など、様々な考え方があります。
ただし、ネントレは赤ちゃんの月齢や発達、性格、そしてご家庭の方針によって向き不向きがあります。始める前には、必ず以下の点を確認してください。
- 赤ちゃんの体調が良い時に行う
- 生後6ヶ月以降を目安に検討する
- パートナーや家族と方針を話し合い、協力を得る
- 途中でうまくいかなくても、親や自分自身を責めない
「泣かせ続けるのは可哀想」と感じるかもしれませんが、ネントレの目的は、赤ちゃんが質の良い睡眠を自分でとれるようにサポートすることです。
無理のない範囲で、情報収集をしながら試してみてはいかがでしょうか。
もう限界…夜泣きで辛い時の相談先リスト

毎晩続く夜泣きに、心も体も疲れ果てて「もう限界…」と感じてしまうのは、決してあなただけではありません。
睡眠不足が続くと、冷静な判断が難しくなったり、精神的に追い詰められたりすることもあります。
大切なのは、一人ですべてを抱え込まないことです。
専門家や身近な人に頼ることは、赤ちゃんとあなた自身を守るための重要なステップです。
ここでは、具体的な相談先をリストアップしました。
利用しやすい窓口から、ぜひ連絡してみてください。
①かかりつけの小児科

まず検討したいのが、いつもお世話になっているかかりつけの小児科医です。
夜泣きが激しい背景に、中耳炎や皮膚のかゆみ、便秘など、何らかの病気や身体的な不調が隠れている可能性もゼロではありません。
一度専門家に診てもらうことで、医学的な問題がないかを確認でき、大きな安心材料になります。
受診する際は、いつから夜泣きが始まったか、一晩に何回くらい泣くか、どんな泣き方をするか、試した対処法などをメモしておくと、医師に状況が伝わりやすくなります。
生活習慣の改善アドバイスや、場合によっては夜泣きに効果のある漢方薬(甘麦大棗湯など)を処方してくれることもあります。
➁地域の保健センターや保健師

各市区町村に設置されている保健センターは、子育てに関する悩みを無料で相談できる心強い味方です。
専門知識を持った保健師が常駐しており、電話相談や面談、家庭訪問などを通じて、それぞれの家庭状況に合わせた具体的なアドバイスをしてくれます。
「夜泣きが辛くて眠れない」「育児に自信がなくなってきた」といった気持ちを正直に話してみましょう。
保健師は赤ちゃんの成長・発達の専門家であると同時に、お母さん自身の心と体の健康についても親身に相談に乗ってくれます。
乳幼児健診の機会を待たずとも、いつでも連絡して大丈夫です。
お住まいの「市区町村名+保健センター」で検索すれば、すぐに連絡先が見つかります。
➂子育て支援センターや児童館

お住まいの地域にある子育て支援センターや児童館も、有効な相談先の一つです。
これらの施設には保育士などの専門スタッフが常駐していることが多く、日中の開館時間内であれば気軽に育児の悩みを相談できます。
何よりのメリットは、同じように子育てに奮闘する他の保護者と出会えることです。
「うちも夜泣きがひどくて…」と話してみると、共感してもらえたり、他の家庭での乗り越え方を聞けたりして、気持ちが楽になることも少なくありません。
家に赤ちゃんと二人きりでいると孤独を感じがちですが、外に出て人と話すだけでも良い気分転換になります。
④家族やパートナーと悩みを共有する

最も身近な存在である家族、特にパートナーとの連携は不可欠です。
夜泣きの対応は、決して母親だけの役割ではありません。
「辛い」「眠い」「助けてほしい」という気持ちを正直に伝え、どうすれば負担を分担できるか具体的に話し合いましょう。
ママ一人が夜泣きの対応をすべて背負う必要はありません。
パパや他の家族も一緒に乗り越えるチームです。
具体的な役割分担を決めておくと、お互いに協力しやすくなります。
役割分担の具体例
分担方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
曜日で分担 | 月・水・金はママ、 火・木・土はパパ、 日曜は体力のある方が 担当するなど、 曜日ごとに夜泣き対応の 主担当を決める。 | 「今夜は休める」 という見通しが立つため、 精神的な負担が軽減される。 まとまった睡眠を 確保しやすい。 |
時間で分担 | 夜中の0時まではママ、 0時以降は パパが担当するなど、 時間帯で区切って交代する。 | お互いに数時間ずつの 連続した睡眠時間を 確保できる。 |
役割で分担 | 赤ちゃんが泣いたら、 一人が抱っこであやし、 もう一人がミルクの準備や おむつ替えを するなど、作業を分担する。 | 一人あたりの作業量が 減り、対応がスムーズになる。 チームで乗り越えている 感覚が強まる。 |
パートナーに「どうせ言っても分かってくれない」と諦める前に、まずは今のあなたの状況と気持ちを伝えてみてください。
具体的な協力体制を築くことが、この辛い時期を乗り越えるための大きな力となります。
まとめ
赤ちゃんの夜泣きがいつまで続くのか、終わりが見えず不安になりますよね。
夜泣きは生後6ヶ月から1歳半頃にピークを迎え、
多くは2歳頃までに落ち着きますが、
個人差が大きいものです。
原因は空腹や室温などの不快感から、生活リズムの乱れまで様々です。
まずは原因を探り、抱っこなどで安心させてあげましょう。
日中の過ごし方や寝る前の習慣を見直すことも卒業への近道です。
一人で抱え込まず、辛い時は専門家や家族に相談してください。