
赤ちゃんがパクパク!先輩ママが教える本当に使える離乳食初期の簡単レシピ集
初めての離乳食、何から作ればいい?
忙しくて大変…と悩むママ・パパへ。
この記事では、先輩ママが実践して「赤ちゃんがパクパク食べた!」とっておきの簡単レシピを食材別にご紹介します。
基本の進め方から冷凍保存のコツ、よくある悩みまで、離乳食初期のすべてをこの記事1本に凝縮。
離乳食作りが驚くほど楽になり、赤ちゃんの「おいしい!」という笑顔がもっと増えること間違いなしです。
目次[非表示]
- 1.離乳食初期の悩みは「簡単レシピ」で解決!
- 2.まずは基本から 離乳食初期(ゴックン期)の進め方
- 3.【主食編】基本の10倍がゆ 簡単な作り方
- 3.1.お鍋でコトコト作る基本のレシピ
- 3.1.1.材料(作りやすい分量)
- 3.1.2.作り方
- 3.2.炊飯器で大人用ご飯と一度に作る時短レシピ
- 3.3.電子レンジで少量から作れるお手軽レシピ
- 4.【野菜編】初めてでも安心 離乳食初期の簡単レシピ
- 4.1.にんじんペーストの甘みを引き出すレシピ
- 4.2.かぼちゃペーストは電子レンジでさらに簡単に
- 4.3.ほうれん草ペーストのアク抜きと調理のコツ
- 4.4.じゃがいもペーストをなめらかに仕上げるレシピ
- 4.5.トマトペーストの湯むきと種の取り方
- 5.【タンパク質編】慣れてきたら挑戦したい簡単レシピ
- 6.忙しいママパパの味方 もっと楽になる離乳食の時短テクニック
- 6.1.週末にまとめて作り置き 冷凍保存(フリージング)のコツ
- 6.2.製氷皿やフリーザーバッグの賢い活用術
- 6.3.ブレンダーや調理セットで下ごしらえを楽に
- 6.4.市販のベビーフードを上手に取り入れる方法
- 7.先輩ママが回答 離乳食初期のよくあるお悩みQ&A
- 7.1.赤ちゃんが離乳食を食べてくれないときはどうする?
- 7.2.味付けは必要?昆布だしの簡単な作り方と使い方
- 7.2.1.一番簡単!水出し昆布だしの作り方
- 7.2.2.昆布だしの使い方
- 7.3.調理に使うお水は水道水でも大丈夫?
- 7.4.旅行や外出時の離乳食はどうしたらいい?
- 7.4.1.外出時にベビーフードを選ぶポイント
- 7.4.2.外出時の持ち物リスト(離乳食編)
- 8.まとめ
離乳食初期の悩みは「簡単レシピ」で解決!

「初めての離乳食、何から始めたらいいの?」
「毎日忙しいのに、裏ごしとか手間がかかりそう…」
「せっかく作っても赤ちゃんが食べてくれなかったらどうしよう?」
生後5ヶ月、6ヶ月ごろから始まる離乳食初期(ゴックン期)。
赤ちゃんの成長は嬉しいけれど、たくさんの不安や疑問が押し寄せてきますよね。
特に、毎日の献立を考え、慣れない調理をこなすのは本当に大変です。
でも、安心してください。
離乳食作りは、もっとシンプルで、もっと楽にできるんです。
この記事では、実際にたくさんの先輩ママたちが実践してきた「本当に使える」簡単レシピと、離乳食作りが驚くほど楽になるコツだけを厳選してご紹介します。
この記事を読めば、肩の力を抜いて、赤ちゃんと一緒に離乳食の時間を楽しめるようになりますよ。
この記事でわかる離乳食初期のすべて
この記事一本で、離乳食初期(ゴックン期)の基本から応用まで、ママ・パパが知りたい情報を網羅的に理解できます。
具体的なレシピだけでなく、スムーズに進めるための知識や時短の工夫まで、しっかりサポートします。
カテゴリ | この記事でわかること |
|---|---|
基本の進め方 | 離乳食を始めるサイン、 1日のスケジュール、 食材の量や固さの目安、 アレルギーの注意点など、 安全に進めるための 基礎知識がわかります。 |
食材別の 簡単レシピ | 主食(10倍がゆ)、 野菜、タンパク質 (豆腐・しらす・白身魚)の 基本レシピを網羅。 電子レンジや炊飯器を 使った時短調理法も 詳しく解説します。 |
時短テクニック | 週末の作り置きに 役立つ冷凍保存 (フリージング)のコツや、 ブレンダーなどの 便利グッズ活用法、 市販のベビーフードを 上手に取り入れる方法が わかります。 |
よくある お悩み解決 | 「赤ちゃんが食べてくれない」 「味付けはどうする?」 「旅行の時は?」など、 先輩ママたちが経験した リアルな悩みとその解決策 がわかります。 |
先輩ママが実践した離乳食作りを楽にするコツ

離乳食作りを毎日続けるのは、想像以上に根気がいるもの。
ここでは、少しでもママ・パパの負担を軽くするために、先輩たちが実践してきた「頑張りすぎない」ためのコツをご紹介します。
完璧を目指さず、上手に手を抜くことが、楽しく続ける秘訣です。
コツ | 具体的な方法 |
|---|---|
完璧を 目指さない | 「一口でも食べたら100点満点」 と考えましょう。 赤ちゃんの機嫌や体調によって 食べむらがあるのは当たり前。 ママ・パパが笑顔でいることが 一番の栄養です。 |
調理器具に 頼る | ブレンダーや ハンドミキサーがあれば、 面倒な裏ごしが一瞬で終わります。 少量なら、すり鉢とすりこぎが セットになった 離乳食調理セットも便利です。 |
大人の食事から 取り分ける | 味噌汁やスープを作るとき、 味付け前に野菜 (大根、にんじんなど)を 取り出して潰せば、 簡単に一品が完成。 わざわざ赤ちゃんのためだけ に調理する手間が省けます。 |
作り置きで 平日を楽に | 時間のある週末に まとめて調理し、 製氷皿などで小分け冷凍 (フリージング)しておきましょう。 平日は電子レンジで解凍する だけで、すぐにご飯の準備ができます。 |
ベビーフードを 賢く使う | 疲れた日や時間がない日は、 市販のベビーフードに頼ってOK。 手作りの10倍がゆに ベビーフードの 野菜ペーストをかけるなど、 上手に組み合わせることで、 栄養バランスも手間も両立できます。 |
まずは基本から 離乳食初期(ゴックン期)の進め方
離乳食初期は、生後5ヶ月〜6ヶ月頃の赤ちゃんが母乳やミルク以外の食べ物に初めて出会う大切な時期。
「ゴックン期」とも呼ばれ、食べ物を飲み込む練習をするのが主な目的です。
初めてのことばかりで戸惑うかもしれませんが、赤ちゃんのペースに合わせて焦らず、食べる楽しさを伝える気持ちで進めていきましょう。
この章では、離乳食初期の基本的な進め方について、わかりやすく解説します。
いつから始める?赤ちゃんの離乳食開始サイン

離乳食を始めるタイミングは、月齢だけでなく赤ちゃんの成長・発達のサインを見極めることが重要です。
厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」でも、生後5〜6ヶ月頃が適当とされています。
次のようなサインが見られたら、離乳食開始を検討してみましょう。
- 首のすわりがしっかりして、寝返りができる。
- 支えてあげると5秒以上お座りできる。
- 大人が食事している様子に興味を示し、よだれを出すなど食べたそうな素振りを見せる。
- スプーンなどを口に入れても、舌で強く押し出すこと(哺乳反射)が減ってくる。
※これらのサインはあくまで目安です。
すべてのサインが揃わなくても、赤ちゃんの体調や機嫌が良い日に、まずは1さじから始めてみましょう。
もし判断に迷う場合は、乳幼児健診などでかかりつけの医師や保健師、栄養士に相談するのもおすすめです。
1日のスケジュールと離乳食の量の目安

離乳食初期は、1日1回食からスタートします。
授乳のリズムを崩さないように、毎日なるべく決まった時間にあげるのがポイントです。
アレルギー反応が出た場合に備えて、病院の開いている平日の午前中が安心して試せるでしょう。
例えば、午前10時頃の授乳の前に離乳食を与え、その後は赤ちゃんが欲しがるだけ母乳やミルクをあげます。
離乳食を開始してからの1ヶ月間の、食材別の量の目安は以下の通りです。
赤ちゃんの食欲や体調には個人差があるため、下記の表はあくまで参考として、お子さんのペースに合わせて調整してください。
時期 | 穀類(10倍がゆ) | 野菜・果物 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
1週目 (開始1〜7日) | まずは小さじ1から。 慣れてきたら 少しずつ増やす。 | まだ与えない。 | まだ与えない。 |
2週目 (開始8〜14日) | 小さじ3程度まで 増やす。 | お米に慣れたら、 すりつぶした野菜 (にんじん、かぼちゃなど)を 小さじ1から試す。 | まだ与えない。 |
3週目 (開始15〜21日) | 小さじ4程度 (約20g)。 | 小さじ2〜3程度 (約10〜15g)。 | 野菜に慣れたら、 すりつぶした豆腐を 小さじ1から試す。 |
4週目 (開始22日目以降) | 大さじ1〜2程度 (約15〜30g)。 | 大さじ1程度 (約15g)。 | 豆腐なら大さじ1.5 (約25g)、 白身魚なら 小さじ2 (約10g)程度。 |
新しい食材を試すときは、必ず小さじ1杯から始めましょう。
嫌がる様子を見せたら無理強いせず、日を改めて挑戦することが大切です。
食材の固さの目安はなめらかなポタージュ状

ゴックン期の赤ちゃんは、まだ舌を上手に使って食べ物をすりつぶすことができません。
そのため、食材は裏ごししたり、ブレンダーにかけたりして、なめらかなペースト状にする必要があります。
固さの目安は、スプーンを傾けるとトロトロと流れ落ちるポタージュスープや、プレーンヨーグルトくらいをイメージしてください。
粒が残っていると赤ちゃんがうまく飲み込めず、むせてしまう原因になるので注意が必要です。
最初は水分を多めにしてサラサラの状態から始め、慣れてきたら少しずつ水分を減らして固さを調整していきましょう。
アレルギーで注意したい食材と安全な進め方

離乳食を進める上で、食物アレルギーは多くのママ・パパが心配する点です。
特にアレルギー表示義務のある「特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)」や、それに準ずる食材を初めて与える際は注意が必要です。
離乳食初期に関係が深いのは、主に卵、小麦、乳製品などです。
アレルギーのリスクを最小限に抑え、安全に離乳食を進めるためのポイントは以下の通りです。
- 初めて食べる食材は、必ず1日1種類、小さじ1杯から試す。
- 万が一症状が出たときにすぐ受診できるよう、かかりつけの小児科が開いている平日の午前中に試す。
- 食べさせた後は、口の周りや皮膚に発疹が出ていないか、機嫌は悪くないかなど、赤ちゃんの様子をよく観察する。
- 新しい食材を試すときは、加熱が不十分だとアレルギー反応が出やすくなることがあるため、必ず中心部までしっかりと火を通す。
例えば、卵はアレルギーが出やすい食材の代表格ですが、栄養価も高いため適切な時期に始めたいものです。
卵を試す際は、必ず固ゆでした卵の「卵黄」の中心部分を耳かき1杯程度のごく少量から始め、様子を見ながら少しずつ量を増やしていきます。
自己判断で特定の食材を避けたり、開始を遅らせたりするのではなく、心配なことがあれば必ずかかりつけの医師に相談してから進めるようにしましょう。
【主食編】基本の10倍がゆ 簡単な作り方

離乳食のスタートは、主食となる「お粥」から。
ゴックン期の赤ちゃんが飲み込みやすいよう、お米1に対して水10の割合で作る「10倍がゆ」が基本です。
なめらかでトロトロのポタージュ状に仕上げるのがポイント。
ここでは、ご家庭の状況に合わせて選べる3つの簡単な作り方をご紹介します。
どの方法も、赤ちゃんがお米の自然な甘みを感じられるように、愛情を込めて作りましょう。
お鍋でコトコト作る基本のレシピ

時間がある時にぜひ試してほしいのが、お鍋でじっくり作る方法です。
手間をかけた分、お米の甘みと風味が最大限に引き出され、赤ちゃんも喜んでくれるはず。
焦げ付かないように時々かき混ぜながら、赤ちゃんの最初の食事を丁寧に作ってみましょう。
材料(作りやすい分量)
食材 | 分量 |
|---|---|
お米(生米) | 大さじ2(約30g) |
水 | 300ml |
作り方
- お米を研ぎ、たっぷりの水(分量外)に30分以上浸しておきます。しっかり吸水させることで、ふっくらと炊き上がります。
- 浸水させたお米と分量の水を小鍋に入れ、中火にかけます。
- 沸騰したら弱火にし、吹きこぼれないように蓋を少しずらして、30〜40分ほどコトコト煮込みます。
- お米がやわらかく膨らんだら火を止め、蓋をしたまま10分ほど蒸らします。
- 熱いうちにすり鉢とすりこぎでなめらかになるまですりつぶすか、裏ごし器でこします。ブレンダーやハンドブレンダーを使っても簡単です。
- 赤ちゃんの食べやすさに合わせて、お湯(分量外)を加えてポタージュ状にのばして完成です。
炊飯器で大人用ご飯と一度に作る時短レシピ

毎日の離乳食作りは大変。
そんな時に大活躍するのが炊飯器を使った時短テクニックです。
大人用のご飯を炊くのと同時に10倍がゆが作れるので、火加減を見る手間もなく、忙しいママパパの強い味方になります。
洗い物が少なく済むのも嬉しいポイントです。
材料(1〜2食分)
食材 | 分量 |
|---|---|
お米(生米) | 大さじ1 |
水 | 150ml |
作り方
- 湯呑みやマグカップなどの小さめの耐熱容器に、研いだお米と分量の水を入れます。
- 大人用のお米をセットした炊飯釜の真ん中に、1の耐熱容器を置きます。
- そのまま炊飯器のスイッチを入れ、通常通り炊飯します。
- 炊き上がったら耐熱容器を取り出し、熱いうちにすりつぶしたり裏ごししたりして、なめらかにします。炊飯器から取り出す際は非常に熱いので、やけどに十分注意してください。
電子レンジで少量から作れるお手軽レシピ

「少しだけ作りたい」「ストックが切れてしまった」という時に便利なのが、電子レンジを使ったレシピです。
炊いたご飯から作るので、あっという間に1食分が完成する手軽さが魅力。
食べムラがある時期にも、無駄なく作れて安心です。
材料(1食分)
食材 | 分量 |
|---|---|
炊いたご飯 | 大さじ1 |
水 | 大さじ5 |
作り方
- 深めの耐熱容器に炊いたご飯と水を入れ、ご飯を軽くほぐします。
- ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で2分〜2分30秒ほど加熱します。
- 加熱後、ラップをしたまま5〜10分蒸らします。蒸らすことで、ご飯が水分を吸ってよりやわらかくなります。
- スプーンの背などでなめらかになるまでつぶし、食べやすい固さに調整したら完成です。加熱すると吹きこぼれやすいので、必ず深さのある容器を使いましょう。
【野菜編】初めてでも安心 離乳食初期の簡単レシピ
おかゆに慣れてきたら、いよいよビタミンやミネラルが豊富な野菜に挑戦です。
離乳食初期は、アレルギーの心配が少なく、甘みがあって赤ちゃんが食べやすい野菜から始めるのが基本。
最初は1種類ずつ、1さじからゆっくりと進めていきましょう。ここでは、先輩ママたちが実際に作って「赤ちゃんがよく食べた!」と評判の、簡単でおいしい野菜ペーストのレシピをご紹介します。
調理を始める前に、初期に使いやすい野菜の調理ポイントを一覧で確認しておきましょう。
野菜 | 調理法 | 調理時間の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
にんじん | 鍋・電子レンジ | 15〜20分 | じっくり加熱すると甘みが増す。 皮のすぐ下に栄養が多いので 厚むきしない。 |
かぼちゃ | 鍋・電子レンジ | 10〜15分 | 電子レンジ調理が時短でおすすめ。 甘みが強く赤ちゃんに人気。 |
ほうれん草 | 鍋 | 約10分 | アクが強いので必ず下茹でし、 水にさらす。 葉先の柔らかい部分のみ使う。 |
じゃがいも | 鍋・電子レンジ | 15〜20分 | 必ず芽を取り除く。 熱いうちに潰さないと 粘りが出てしまうので注意。 |
トマト | 鍋 | 約10分 | 必ず湯むきして種を取り除く。 加熱すると酸味が和らぐ。 |
にんじんペーストの甘みを引き出すレシピ

β-カロテンが豊富で、彩りもきれいな「にんじん」。加熱すると自然な甘みが出るので、初めての野菜にぴったりです。
材料
- にんじん:輪切り2〜3枚(約20g)
- 水または昆布だし:大さじ2〜3
作り方
- にんじんは皮を薄くむき、5mm程度の輪切り、またはいちょう切りにします。
- 小鍋ににんじんと、かぶるくらいの水(分量外)を入れ、中火にかけます。
- 沸騰したら弱火にし、竹串がスッと通るくらい柔らかくなるまで15分ほど茹でます。
- ザルにあげて水気を切り、温かいうちに裏ごし器やブレンダーでなめらかなペースト状にします。
- 水や昆布だしを少しずつ加え、ヨーグルトくらいのなめらかさになるようにのばして完成です。
調理のポイント
にんじんは電子レンジでも調理可能です。耐熱容器ににんじんと水(大さじ1)を入れ、ふんわりとラップをして600Wで2〜3分加熱してください。少量のお水でじっくり蒸し煮にすると、甘みが凝縮されてよりおいしくなります。
かぼちゃペーストは電子レンジでさらに簡単に

ビタミン類が豊富で甘みが強いかぼちゃは、赤ちゃんに大人気の食材です。電子レンジを使えば、皮むきも調理も驚くほど簡単になります。
材料
- かぼちゃ:2cm角を2〜3個(約20g)
- 水または昆布だし:大さじ1〜2
作り方
- かぼちゃは種とワタを取り除きます。皮は加熱後にむくので、この時点ではそのままでOKです。
- 耐熱皿にかぼちゃを並べ、水(大さじ1/2程度・分量外)を振りかけ、ふんわりとラップをします。
- 電子レンジ(600W)で1分30秒〜2分、柔らかくなるまで加熱します。
- 熱いうちにスプーンで皮から実をこそげ取り、裏ごしします。
- 水や昆布だしを加えて、ポタージュ状にのばしたら出来上がりです。
調理のポイント
かぼちゃの皮は硬くてむきにくいですが、加熱してからだとスプーンで簡単に実を取り出せます。
皮ごと加熱することで、栄養やうま味も逃しにくくなるので一石二鳥です。
ほうれん草ペーストのアク抜きと調理のコツ

鉄分やビタミンが豊富なほうれん草。
アク(シュウ酸)が強いので、赤ちゃんに与える際は下処理がとても重要です。必ずアク抜きをしてから調理しましょう。
材料
- ほうれん草の葉先:3〜4枚
- 水または昆布だし:大さじ1〜2
作り方
- ほうれん草はよく洗い、繊維が少なく柔らかい葉先の部分だけを使います。
- 鍋にたっぷりのお湯を沸かし、ほうれん草の葉先を入れて1〜2分、くたっとするまで茹でます。
- 冷水にとり、水気をしっかり絞ります。この工程でアクが抜けます。
- 細かく刻んでから、すり鉢で丁寧につぶすか、ブレンダーにかけます。
- 水や昆布だしでのばし、なめらかに仕上げます。
調理のポイント
ほうれん草の茎は繊維が多く、初期の赤ちゃんには食べにくいため使いません。
アク抜きを丁寧に行うことが、赤ちゃんの腎臓への負担を減らし、えぐみをなくしておいしく食べてもらうための最大のコツです。
じゃがいもペーストをなめらかに仕上げるレシピ

炭水化物が多く、エネルギー源になるじゃがいも。おかゆに混ぜたり、他の野菜と混ぜたりとアレンジしやすい便利な食材です。
材料
- じゃがいも:1/4個(約30g)
- 水または昆布だし:大さじ2〜3
作り方
- じゃがいもは皮をむき、芽があれば必ず深くえぐり取ります。
- 1cm角に切り、変色を防ぐためにサッと水にさらします。
- 小鍋にじゃがいもと、かぶるくらいの水(分量外)を入れ、柔らかくなるまで15分ほど茹でます。
- 熱いうちにザルにあげ、フォークやマッシャーで潰してから裏ごしします。
- 水や昆布だしを少しずつ加え、なめらかな状態にのばします。
調理のポイント
じゃがいもは、冷めてから潰すと粘りが出てしまい、食感が悪くなります。
必ず熱いうちに手早く調理するのが、なめらかでおいしいペーストを作る秘訣です。
だしでのばすと風味もアップします。
トマトペーストの湯むきと種の取り方

リコピンが豊富なトマト。酸味があるため、他の野菜に慣れてきた頃に試すのがおすすめです。
皮と種は消化に悪いので、必ず取り除きましょう。
材料
- トマト:1/8個(約20g)
作り方
- トマトはよく洗い、ヘタと反対側に浅く十字の切り込みを入れます。
- フォークに刺して直火で炙るか、熱湯に10〜20秒くぐらせ、すぐに冷水にとると皮がするりとむけます(湯むき)。
- 横半分に切り、スプーンなどを使ってゼリー状の種をきれいに取り除きます。
- 果肉部分を細かく刻み、小鍋に入れて弱火で2〜3分加熱し、酸味を飛ばします。
- 裏ごし器でこして、なめらかにしたら完成です。水分が多いため、のばすための水分は不要な場合が多いです。
調理のポイント
トマトはアレルギー表示推奨品目に含まれるため、初めて与える際は少量からにし、赤ちゃんの様子をよく観察しましょう。
加熱することで酸味がまろやかになり、甘みが増して食べやすくなります。
【タンパク質編】慣れてきたら挑戦したい簡単レシピ
お米や野菜に慣れてきたら、次はタンパク質に挑戦してみましょう。
タンパク質は赤ちゃんの体を作る大切な栄養素ですが、アレルギーの原因になりやすい食材でもあります。
豆腐→白身魚→卵黄の順番で、赤ちゃんの様子を見ながら少量ずつ慎重に進めるのが基本です。
ここでは、離乳食初期におすすめの「豆腐」「しらす」「白身魚(たい)」の簡単レシピをご紹介します。
タンパク質を始める時期や量の目安は以下の通りです。必ず加熱したものを、まずはひとさじから始めましょう。
食材 | 開始時期の目安 | 1回あたりの目安量 |
|---|---|---|
豆腐 | 離乳食開始 1ヶ月ごろから | 25g程度まで |
しらす | 豆腐に 慣れたころ | 5g程度まで |
白身魚 (たい・かれい等) | しらすに 慣れたころ | 10g程度まで |
※上記はあくまで目安です。赤ちゃんの食欲や体調に合わせて調整してください。
なめらか豆腐ペーストの作り方
 豆腐は植物性タンパク質が豊富で、調理も簡単なため最初のタンパク質として最適です。なめらかにしやすい絹ごし豆腐を使いましょう。
豆腐は植物性タンパク質が豊富で、調理も簡単なため最初のタンパク質として最適です。なめらかにしやすい絹ごし豆腐を使いましょう。
材料
- 絹ごし豆腐:大さじ1(約15g)
- お湯または野菜スープ:小さじ1〜
作り方
- 豆腐を耐熱容器に入れ、かぶるくらいの水を加えて電子レンジ(600W)で30秒〜1分ほど加熱します。お鍋で茹でてもOKです。雑菌の繁殖を防ぐため、必ず加熱調理をしてください。
- 加熱した豆腐の水分を軽く切り、裏ごし器や目の細かいザルでなめらかにすりつぶします。すり鉢を使っても構いません。
- お湯や野菜スープを少しずつ加えながら、赤ちゃんが飲み込みやすいポタージュ状のなめらかさになるまで混ぜ合わせたら完成です。
調理のポイント
豆腐は水分が多いので、冷凍すると食感が変わりやすい食材です。都度調理するのがおすすめですが、もし冷凍する場合は、すりつぶしてなめらかにした状態で製氷皿などに入れて冷凍し、解凍時に再度加熱して水分を調整してください。
しらすの塩抜きと簡単ペーストレシピ

しらすは骨ごと食べられるのでカルシウムも補給できる便利な食材です。ただし塩分が多いため、赤ちゃんにあげる前には必ず塩抜きをしましょう。
材料
- しらす干し:小さじ1(約5g)
- お湯:適量
作り方
- 茶こしなどにしらすを入れ、たっぷりの熱湯を回しかけます。または、小鍋にお湯を沸かし、しらすを入れて1〜2分茹でてザルにあげます。この塩抜き作業は、赤ちゃんの腎臓への負担を減らすために非常に重要です。
- 塩抜きしたしらすをすり鉢に入れ、なめらかになるまで丁寧にすりつぶします。少量の場合は、まな板の上で包丁で細かく刻んでから、さらにスプーンの背などで潰しても作れます。
- お湯を少量加えてのばし、ペースト状にしたら完成です。
調理のポイント
塩抜き後にすりつぶしたものを、1食分ずつラップに包んだり製氷皿に入れたりして冷凍保存しておくと、使いたい時にすぐに使えて便利です。釜揚げしらすよりも、よく乾燥している「しらす干し」の方が日持ちしやすく、塩抜きもしやすいのでおすすめです。
白身魚(たい)の骨と皮の取り方と調理法

白身魚は脂肪が少なく消化しやすいため、魚の第一歩としておすすめです。中でも「たい」はアレルギーが出にくく、クセもないため人気です。骨がないお刺身用のサクを使うと調理が格段に楽になります。
材料
- たい(刺身用):1切れ(約10g)
- お湯または昆布だし:小さじ1〜
作り方
- たいを耐熱皿に乗せて水を少量ふりかけ、ふんわりとラップをして電子レンジ(600W)で20〜30秒、白くなるまで加熱します。お鍋で茹でる場合は、沸騰したお湯で火が通るまで茹でてください。
- 加熱したたいの粗熱が取れたら、皮や血合い、骨が残っていないか指で触って念入りに確認しながら、身をほぐします。小さな骨が残っていることがあるので、細心の注意を払いましょう。
- すり鉢でなめらかにすりつぶします。繊維が残りやすいので、丁寧に行いましょう。
- お湯や昆布だしを加えて、ヨーグルトくらいの固さにのばしたら完成です。
調理のポイント
白身魚は加熱するとパサパサしがちで、赤ちゃんが飲みにくいことがあります。その場合は、水溶き片栗粉を少量加えてとろみをつけてあげると、口当たりが良くなり食べやすくなります。たいの他に、かれい、ひらめ、たらなども離乳食初期から使えますが、たらはアレルギーが出やすい魚なので、他の魚に慣れてから慎重に試しましょう。
忙しいママパパの味方 もっと楽になる離乳食の時短テクニック

毎日の離乳食作り、本当にお疲れ様です。
特に仕事や家事、上の子のお世話などで忙しいと、一から手作りするのは大きな負担になりますよね。
しかし、少しの工夫で離乳食作りは驚くほど楽になります。
この章では、先輩ママたちが実践している「作り置き」や「便利グッズの活用」など、今すぐ使える離乳食の時短テクニックを余すところなくご紹介します。
週末にまとめて作り置き 冷凍保存(フリージング)のコツ
離乳食初期の時短テクニックとして最も効果的なのが、週末など時間のあるときにまとめて作って冷凍しておく「フリージング」です。一度に数日分を用意しておくことで、平日の調理時間を大幅に短縮できます。
フリージングを成功させるには、いくつかの大切なコツがあります。
まず、食材は新鮮なうちに調理し、加熱後はしっかり粗熱をとってから冷凍庫に入れること。
熱いまま冷凍すると、他の冷凍食品を傷めたり、霜の原因になったりします。
また、衛生面を考慮し、解凍後の再冷凍は絶対に避けましょう。
冷凍した離乳食は、作った日付と食材名を必ずラベルに記録し、1週間を目安に使い切るのが基本です。
解凍する際は、食中毒のリスクを避けるため自然解凍はせず、電子レンジや小鍋で必ず中心部までしっかりと再加熱してください。
このひと手間が、赤ちゃんの安全を守ります。
製氷皿やフリーザーバッグの賢い活用術

フリージングには、100円ショップなどでも手に入る身近なアイテムが活躍します。
特に「製氷皿」と「フリーザーバッグ」は、離乳食初期のママ・パパの必須アイテムと言えるでしょう。
それぞれの特徴を理解し、上手に使い分けるのがポイントです。
ペースト状にしたおかゆや野菜は、蓋付きの製氷皿に入れて冷凍するのがおすすめです。
1ブロックあたりの量が決まっているので、赤ちゃんの食べる量に合わせて解凍しやすく便利です。
完全に凍ったら、製氷皿から取り出して食材ごとにフリーザーバッグにまとめておくと、冷凍庫の省スペースになり、製氷皿を繰り返し使えます。
それぞれのアイテムの使い分けを以下の表にまとめました。
アイテム名 | 特徴と活用術 | おすすめの食材 |
|---|---|---|
製氷皿 (蓋付き推奨) | 1食分の量を計りやすく、 少量ずつ小分けするのに 最適です。 凍ったブロックは フリーザーバッグに 移し替えると効率的です。 | 10倍がゆ、 野菜ペースト (にんじん、かぼちゃ等)、 だし汁 |
フリーザーバッグ | 冷凍したキューブの保存や、 食材を薄く平らに伸ばして 冷凍するのに便利。 使いたい分だけ 手で折って使えます。 | 冷凍キューブの保管、 ペースト状にした しらすや白身魚 |
離乳食専用 冷凍トレー | 様々な容量のサイズがあり、 1食分に合わせた 小分けが可能です。 シリコン製など、凍った後も 取り出しやすい工夫が されています。 | すべての 離乳食初期の食材 |
ブレンダーや調理セットで下ごしらえを楽に

離乳食初期の最大の難関ともいえる「すりつぶし」や「裏ごし」。
この作業を楽にしてくれるのが、ハンドブレンダーや離乳食用の調理セットです。
手作業に比べて時間と労力を劇的に削減でき、仕上がりもよりなめらかになります。
ハンドブレンダーは、鍋やカップの中で直接「つぶす」「混ぜる」が数秒で完了し、なめらかさも自由自在に調整できる優れものです。
ポタージュ状にするのが一瞬で終わるため、まとめて作り置きする際に大活躍します。
洗い物が少ないのも嬉しいポイントです。
一方、離乳食調理セットは、「すり鉢」「裏ごし器」「果汁しぼり器」「おろし器」などがコンパクトにまとまっています。
電子レンジに対応しているものも多く、少量だけ作りたいときに非常に便利です。
ブレンダーを導入するほどではないけれど、下ごしらえを少しでも楽にしたい、という方におすすめです。
市販のベビーフードを上手に取り入れる方法
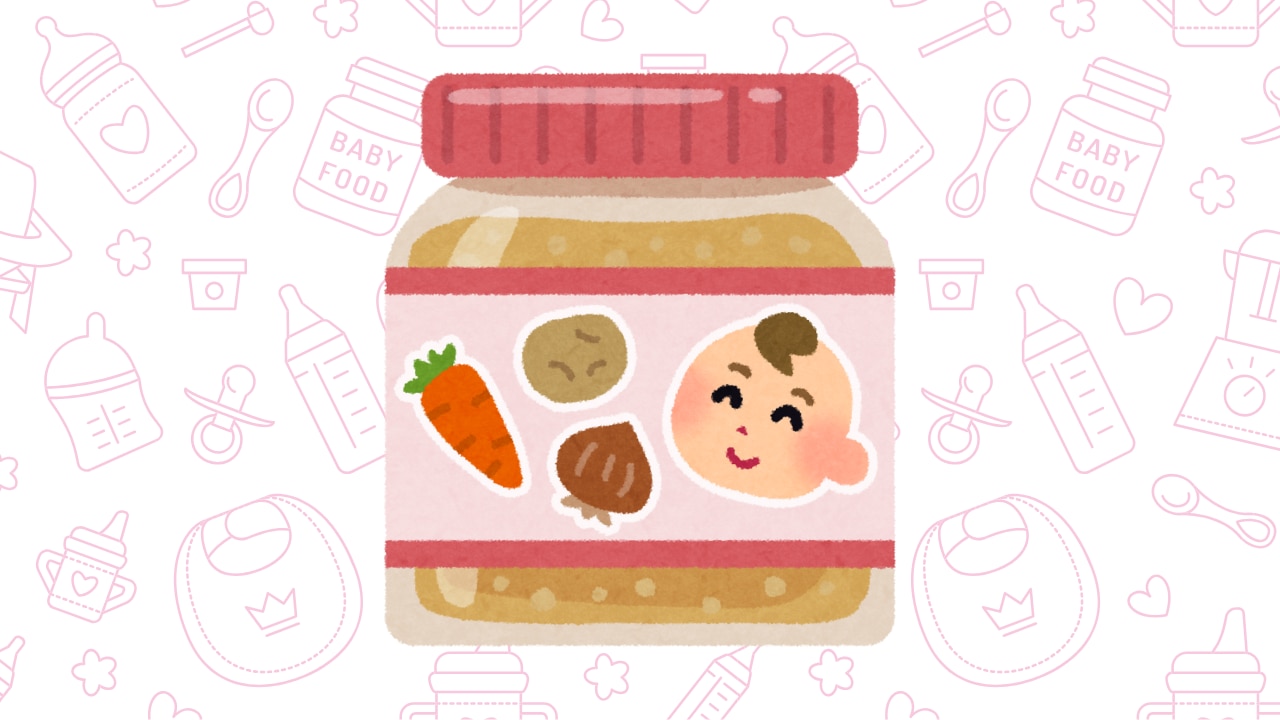
「ベビーフードを使うのは手抜きでは?」と罪悪感を感じる必要は全くありません。
現在のベビーフードは栄養バランスや安全性に非常に優れており、忙しいママ・パパの力強い味方です。
むしろ、すべて手作りと気負わずにベビーフードを上手に活用し、心の余裕を持つことは、赤ちゃんにとってもプラスになります。
ベビーフードは、疲れている日や時間がない日のメインディッシュにするだけでなく、「ちょい足し」に使うのも賢い方法です。
例えば、手作りのおかゆに市販のかぼちゃペーストを加えたり、豆腐にフリーズドライの白身魚を混ぜたりするだけで、手軽に栄養と味のバリエーションがアップします。
また、レバーや家庭では調理しにくい食材を手軽に試せるのも大きなメリットです。
味付けや食材の固さの参考にもなるため、まずはベビーフードで試してみて、赤ちゃんが気に入ったら手作りに挑戦するというステップも良いでしょう。
外出時や災害時のストックとしても役立つため、いくつか常備しておくと安心です。
先輩ママが回答 離乳食初期のよくあるお悩みQ&A
離乳食作りには、レシピ以外にもさまざまな疑問や不安がつきものです。
ここでは、多くのママやパパが抱える離乳食初期の代表的なお悩みに、先輩ママたちがQ&A形式でお答えします。
ひとりで抱え込まず、ここで解決のヒントを見つけてくださいね。
赤ちゃんが離乳食を食べてくれないときはどうする?

離乳食を始めたばかりの赤ちゃんが、なかなか食べてくれないのは「離乳食あるある」です。
焦ったり、落ち込んだりする必要はまったくありません。
まずは、「そういう時期もある」と大らかな気持ちで構えることが一番の解決策です。
その上で、考えられる原因と対策を試してみましょう。
赤ちゃんが食べてくれないとき、いくつかの理由が考えられます。
無理強いはせず、赤ちゃんの様子をよく観察して原因を探ってみましょう。
考えられる原因 | ママ・パパができる対策 |
|---|---|
お腹が空いていない | 授乳やミルクの直後ではありませんか? 生活リズムを見直し、 空腹になりやすい時間帯に 離乳食を試してみましょう。 授乳の1時間~1時間半前などが目安です。 |
眠い・機嫌が悪い | 眠かったり、疲れていたりすると 食べることに集中できません。 お昼寝の後など、赤ちゃんの機嫌が 良いタイミングを選んでみましょう。 |
食感や温度が 好みでない | ペーストが固すぎたり、 ザラザラしていたりしませんか? お湯やだしでのばして、 よりなめらかにしてみましょう。 また、人肌くらいの温かさが基本ですが、 少し冷たい方が好きな子もいます。 温度を変えてみるのも一つの手です。 |
スプーンが嫌 | 金属製のスプーンの感触が 苦手な赤ちゃんもいます。 シリコン製や木製など、 素材の違うスプーンを試してみましょう。 ママの指先に少量つけて、 口元に運んであげるのも 効果的な場合があります。 |
体調が いつもと違う | 便秘や下痢、 鼻づまり、 熱っぽいなど、 体調が優れないのかもしれません。 食欲がないだけでなく、 他に変わった様子がないか 全身をチェックし、 心配な場合は かかりつけの小児科に相談しましょう。 |
大切なのは、食事の時間を「楽しいもの」だと赤ちゃんに感じてもらうことです。
ママやパパが笑顔で「おいしいね」と声をかけながら、リラックスした雰囲気を作ってあげてください。
1日くらい食べなくても大丈夫。
長い目で見て、赤ちゃんのペースに合わせてゆっくり進めていきましょう。
味付けは必要?昆布だしの簡単な作り方と使い方

結論から言うと、離乳食初期(ゴックン期)には、基本的に調味料による味付けは不要です。
この時期の目的は、食べ物を飲み込む練習をすることと、食材そのものの味を知ってもらうこと。
塩分や糖分は、まだ発達が未熟な赤ちゃんの腎臓に負担をかけてしまう可能性があります。
ただし、どうしても食が進まないときや、風味をプラスしたいときに役立つのが「だし」です。
特に昆布だしは、うま味成分が豊富で香りも穏やかなので、離乳食初期にぴったりです。
一番簡単!水出し昆布だしの作り方
- 清潔なポットやボトルに、水500mlと昆布5g(5cm角程度)を入れます。昆布の表面の汚れが気になる場合は、固く絞った濡れ布巾でさっと拭きます。(白い粉はうま味成分なので洗い流さないでください)
- 蓋をして冷蔵庫に入れ、6時間~一晩置けば完成です。
これなら、前の晩に仕込んでおくだけなのでとっても簡単。作っただしは冷蔵庫で2~3日保存可能です。製氷皿で小分けに冷凍しておけば、使いたい分だけ解凍できてさらに便利です。
昆布だしの使い方
- 10倍がゆを作る際の水の代わりに使う
- 野菜ペーストをのばすときに使う
- 豆腐や白身魚を煮るときに使う
このように、水の代わりにだしを使うだけで、ぐっと風味が増して赤ちゃんの食欲を刺激してくれることがあります。
野菜を煮て作る「野菜スープ(野菜だし)」もおすすめです。
にんじんや玉ねぎ、かぶなどの野菜くずを水から煮るだけで、やさしい甘みのスープが作れますよ。
調理に使うお水は水道水でも大丈夫?

離乳食に使う水について、悩む方も多いかもしれません。
日本の水道水は世界的に見ても水質基準が厳しく、非常に安全です。
そのため、必ず一度しっかりと沸騰させた「湯冷まし」であれば、離乳食の調理に問題なく使用できます。
浄水器を通した水を使う場合も、念のため一度煮沸するとより安心です。
一方で、ミネラルウォーターを使いたい場合は注意が必要です。
ミネラルウォーターには「軟水」と「硬水」があり、赤ちゃんにはミネラル分の少ない「軟水」を選んでください。
マグネシウムやカルシウムが多く含まれる「硬水」は、赤ちゃんの未熟な腎臓や消化器官に負担をかける恐れがあるため、離乳食には不向きです。
水の種類 | 離乳食への使用 | 注意点 |
|---|---|---|
水道水 | ◎ (推奨) | 必ず一度沸騰させて 冷ました「湯冷まし」を 使用する。 |
浄水器の水 | ○ | 水道水と同様、 一度沸騰させてから 使用するとより安心。 |
ミネラルウォーター (軟水) | ○ | 加熱殺菌済みのベビー用や、 硬度が60mg/L以下 のものを選ぶ。 |
ミネラルウォーター (硬水) | × (不向き) | 赤ちゃんの体に 負担をかける可能性が あるため避ける。 |
ペットボトルのラベルに記載されている「硬度」を確認し、「軟水」と書かれたものを選ぶようにしましょう。
旅行や外出時の離乳食はどうしたらいい?

赤ちゃんとのお出かけは楽しみな反面、離乳食をどうするかは悩みの種ですよね。
衛生面や手軽さを考えると、外出時や旅行の際は、市販のベビーフードを上手に活用するのが最もおすすめです。
最近のベビーフードは種類が豊富で、安全性も高く、栄養バランスも考えられています。特に、カップやパウチに入っていて、温めずにそのまま食べさせられるタイプは非常に便利です。
外出時にベビーフードを選ぶポイント
- 月齢に合っているか:パッケージの対象月齢を確認しましょう。
- アレルギー食材の確認:原材料表示を必ずチェックし、まだ試していない食材が入っていないものを選びます。
- 容器のタイプ:スプーン付きのカップタイプなら、食器がなくてもその場で食べさせられます。パウチタイプはかさばらず、持ち運びに便利です。
もし手作りの離乳食を持っていく場合は、食中毒を防ぐために衛生管理を徹底する必要があります。調理した離乳食は十分に冷ましてから冷凍し、当日は保冷剤を入れた保冷バッグで持ち運びましょう。
そして、食べる直前に電子レンジなどで再加熱できる施設がある場合に限定するのが安全です。常温での長時間の持ち歩きは絶対に避けてください。
外出時の持ち物リスト(離乳食編)
- 市販のベビーフード
- 使い慣れたスプーン(使い捨てタイプも便利)
- 食事用エプロン
- ウェットティッシュ、ティッシュ
- 汚れたものを入れるビニール袋
- 飲み物(湯冷ましや麦茶を入れたマグ)
外出先では、いつもと環境が違うことで赤ちゃんが離乳食に集中できないこともあります。
そんなときは無理強いせず、授乳やミルクで対応するなど、柔軟に考えましょう。
ママとパパが安心して楽しめるように、便利なアイテムを賢く利用してくださいね。
まとめ
離乳食初期の簡単なレシピと、作り方を楽にするコツをご紹介しました。
基本の10倍がゆから野菜、タンパク質のレシピは、電子レンジや炊飯器を活用すれば驚くほど簡単です。
また、週末の作り置き冷凍や市販のベビーフードを上手に取り入れることで、忙しい毎日でも心に余裕が生まれます。
完璧を目指さず、赤ちゃんのペースに合わせて、親子で食事の時間を楽しむことが何より大切です。
この記事が、あなたの離乳食スタートの不安を解消する一助となれば幸いです。





