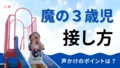離乳食を食べないのはなぜ?先輩ママ100人に聞いた「遊び食べ・むら食い」克服法
赤ちゃんが離乳食を食べてくれないと「うちの子だけ?」と不安や焦りを感じますよね。
この記事では、先輩ママ100人への調査結果をもとに、月齢別の食べない原因から「遊び食べ」「むら食い」の具体的な克服法まで徹底解説します。
調理の工夫や栄養の考え方、やってはいけないNG対応も紹介。
食べない理由と対処法がわかり、ママのイライラや心配が軽くなるヒントがきっと見つかります。
目次[非表示]
- 1.離乳食を食べないのは多くのママが通る道
- 2.【月齢別】赤ちゃんが離乳食を食べない原因
- 2.1.×離乳食初期(5ヶ月から6ヶ月)に食べない
- 2.1.1.主な原因
- 2.2.×離乳食中期(7ヶ月から8ヶ月)に食べない
- 2.2.1.主な原因
- 2.3.×離乳食後期(9ヶ月から11ヶ月)に食べない
- 2.3.1.主な原因
- 2.4.×離乳食完了期(1歳から1歳6ヶ月)に食べない
- 2.4.1.主な原因
- 3.先輩ママ100人に調査 離乳食を食べない理由トップ5
- 3.1.1位 食べることより楽しい「遊び食べ」
- 3.2.2位 気分で食べたり食べなかったりする「むら食い」
- 3.3.3位 眠い・機嫌が悪いなど気分や体調の問題
- 3.4.4位 食材の味や食感が好みではない
- 3.5.5位 ミルクや母乳でお腹がいっぱい
- 4.【悩み別】離乳食を食べないときの先輩ママ実践の克服法
- 4.1.①「遊び食べ」が始まったときの対処法
- 4.1.1.〇食事の時間を15分から20分で区切る
- 4.1.2.〇食事に集中できる環境を整える
- 4.1.3.〇手づかみ食べメニューを積極的に導入する
- 4.2.➁「むら食い」にイライラしないための対処法
- 4.2.1.〇一食くらい食べなくても大丈夫と割り切る
- 4.2.2.〇生活リズムを整えてお腹を空かせる
- 4.2.3.〇調理法や味付けを変えてマンネリを防ぐ
- 4.3.➂口を開けない・べーっと出すときの対処法
- 4.3.1.〇食材の固さや大きさを月齢に合わせて見直す
- 4.3.2.〇スプーンや食器を赤ちゃんが好きなものに変える
- 4.3.3.〇大人が美味しそうに食べる姿を見せる
- 5.離乳食を食べないときに試したい調理のひと工夫
- 5.1.①だしや野菜スープで風味を変える
- 5.2.➁調理形態を変えて食感に変化をつける
- 5.3.➂市販のベビーフードや調味料を上手に活用する
- 5.3.1.ベビーフードの「ちょい足し」活用術
- 5.3.2.便利な赤ちゃん用調味料
- 6.逆効果かも 離乳食を食べないときに避けたいNG対応
- 6.1.×無理やり口に運ぶ
- 6.2.×食事中に叱ったりイライラした態度を見せたりする
- 6.3.×テレビや動画を見せながら食べさせる
- 6.4.×他の赤ちゃんと比べる
- 7.離乳食を食べないときの栄養は大丈夫?ミルクや母乳の考え方
- 8.こんなときは専門家へ相談 病院受診の目安
- 8.1.①体重が増えない・減っている
- 8.2.➂嘔吐や下痢など体調不良のサインがある
- 8.3.④水分も受け付けない
- 9.まとめ
離乳食を食べないのは多くのママが通る道

せっかく時間をかけて作った離乳食を、赤ちゃんが食べてくれない。
スプーンを口に運んでもプイッと横を向いたり、べーっと出してしまったり…。
ときにはお皿をひっくり返して遊び始めてしまうことも。
そんな我が子の姿に、
「どうして食べてくれないの?」
「栄養は足りているのかな?」
と不安になったり、ついイライラしてしまったりするのは、あなただけではありません。
実は、離乳食を食べないという悩みは、ほとんどのママが一度は経験する「育児あるある」なのです。
当サイトが実施したアンケートでも、多くの先輩ママが同じ悩みを抱えていたことがわかります。
①育児に関する悩みアンケート(n=100)
順位 | 育児の悩み | 回答割合 |
|---|---|---|
1位 | 睡眠・寝かしつけ | 85% |
2位 | 食事・離乳食 | 82% |
3位 | イヤイヤ期・ぐずり | 76% |
4位 | 発熱・体調不良 | 68% |
5位 | 成長・発達の不安 | 65% |
このように、「赤ちゃんの食事」は睡眠の悩みに次いで多くのママを悩ませています。
頑張って作ったものを食べてくれないと、ママ自身の頑張りを否定されたように感じて、悲しくなってしまいますよね。
しかし、赤ちゃんが離乳食を食べないのには、月齢や成長段階に応じた様々な理由があります。
例えば、こんなことで悩んでいませんか?
- 食べ物で遊び始めてしまう「遊び食べ」
- 昨日まで食べていたものを急に嫌がる「むら食い」
- そもそもスプーンを嫌がって口を開けない
- 食材の好き嫌いが激しい「偏食」
- 母乳やミルクばかり欲しがる
これらの行動は、赤ちゃんの自我が芽生えたり、好奇心が旺盛になったりしている成長の証でもあります。
大切なのは、その原因を理解し、赤ちゃんのペースに合わせて根気強く向き合っていくことです。
この記事では、「離乳食を食べない」という大きな悩みを解決するために、月齢別の原因から先輩ママ100人が実践した具体的な克服法、調理のひと工夫、そしてやってはいけないNG対応まで、網羅的に解説していきます。
一人で抱え込まず、この記事を参考に、少し肩の力を抜いて離乳食の時間を乗り越えていきましょう。
【月齢別】赤ちゃんが離乳食を食べない原因
離乳食を食べない原因は、赤ちゃんの成長段階によって大きく異なります。
ゴックン期、モグモグ期、カミカミ期、パクパク期と、それぞれのステージでつまずきやすいポイントがあります。
まずは赤ちゃんの月齢ごとの特徴を理解し、なぜ食べてくれないのか原因を探っていきましょう。
×離乳食初期(5ヶ月から6ヶ月)に食べない

離乳食をスタートしたばかりの初期は、赤ちゃんにとって何もかもが初めての体験です。食べないからといって焦る必要はありません。この時期は、母乳やミルク以外の味やスプーンの感触に慣れるための「練習期間」と捉えましょう。
項目 | 内容 |
|---|---|
食べ方 | 唇を閉じて、食べ物を「ごっくん」と飲み込む練習 |
食事回数 | 1日1回 |
固さの目安 | なめらかなポタージュ状 |
主な原因
舌で押し出してしまう(舌突出反射)
生まれたときから備わっている、固形物を舌で口の外に押し出す反射がまだ残っている場合があります。これは成長ととも自然に消えていきますが、残っているうちはうまく飲み込めません。
スプーンに慣れていない
今までおっぱい・哺乳瓶しか知らなかった赤ちゃんにとって、金属やプラスチックのスプーンは異物です。その感触を嫌がって口を閉ざしてしまうことがあります。
味や食感への戸惑い
おかゆや野菜ペーストなど、母乳やミルクとは全く違う味や舌触りにびっくりして、受け付けないことがあります。
お腹が空いていない・眠い
離乳食の時間が授乳直後だったり、お昼寝の時間と重なったりすると、お腹がいっぱいであったり眠かったりして、食べる意欲がわきません。
×離乳食中期(7ヶ月から8ヶ月)に食べない
1日2回食に進み、食べられる食材の種類も増えてくる時期です。
しかし、食事量や食べ方にムラが出始め、ママやパパが悩み始めるのもこの頃。
味覚が発達し、食べ物の好き嫌いが出始めるサインかもしれません。
項目 | 内容 |
|---|---|
食べ方 | 舌と上あごで食べ物を「もぐもぐ」とつぶす練習 |
食事回数 | 1日2回 |
固さの目安 | 舌でつぶせる豆腐くらいの固さ |
主な原因
食感のミスマッチ
ペースト状から少し形のあるものにステップアップするため、粒々した食感やザラザラした舌触りが苦手で、ベーっと出してしまうことがあります。逆に、軟らかすぎて物足りなさを感じている可能性もあります。
味に飽きてきた
いつも同じようなだしの味付けだと、赤ちゃんも飽きてしまいます。味覚が発達してくるため、風味の変化を求めるようになります。
周りのものへの好奇心
おすわりが安定し、周りがよく見えるようになると、食事以外のものに興味が移りがちです。おもちゃやテレビなど、気になるものがあると食事に集中できなくなります。
体調の変化
歯が生え始める時期でもあり、歯ぐずり(歯が生えるときの不快感)で機嫌が悪く、食欲が落ちることがあります。また、便秘気味でお腹が張っているのかもしれません。
×離乳食後期(9ヶ月から11ヶ月)に食べない
1日3回食になり、いよいよ大人と同じリズムに近づいてきます。手づかみ食べも始まり、赤ちゃんの「自分で食べたい」という意欲が育つ大切な時期です。
しかし、「遊び食べ」や自我の芽生えによる「イヤイヤ」に悩まされることが増えてきます。
項目 | 内容 |
|---|---|
食べ方 | 歯ぐきで食べ物を「かみかみ」とつぶす練習 |
食事回数 | 1日3回 |
固さの目安 | 歯ぐきでつぶせるバナナくらいの固さ |
主な原因
「遊び食べ」が始まった
食べ物を手でこねたり、お皿をひっくり返したり、スプーンを投げたり…。
これは食べ物への好奇心や、手先の機能が発達してきた証拠です。
食べることが目的ではなく、食べ物で遊ぶことが楽しくなってしまっています。
自我が芽生え、自己主張が始まる
「自分でスプーンを持ちたい」「ママに食べさせられるのは嫌」といった自己主張が出てきます。
思い通りにならないと、口を固く閉ざして抵抗することがあります。
固さや大きさが合っていない
カミカミの練習期ですが、うまく噛みつぶせない固さや大きさだと、飲み込めずに口から出してしまいます。
逆に軟らかすぎると丸飲みしてしまい、噛む練習になりません。
メニューのマンネリ化
3回食になるとレパートリーに悩み、同じようなメニューが続きがちです。
赤ちゃんも味や見た目の変化を求めるようになり、マンネリ化するとそっぽを向いてしまうことがあります。
×離乳食完了期(1歳から1歳6ヶ月)に食べない

ほとんどの栄養を母乳やミルクではなく食事から摂るようになる大切な時期です。
食べられるものも増え、幼児食への移行期間に入ります。
一方で、「むら食い」が激しくなったり、食べ物の好みがはっきりしてきたりと、新たな悩みが出てきやすい時期でもあります。
項目 | 内容 |
|---|---|
食べ方 | ・前歯でかじり取り、 奥の歯ぐきでつぶして 「ぱくぱく」食べる |
食事回数 | ・1日3回+おやつ(1〜2回) |
固さの目安 | ・歯ぐきで噛める 肉団子くらいの固さ。 |
主な原因
「むら食い」が本格化する
昨日はたくさん食べたのに今日はほとんど食べない、ご飯は嫌がるけどパンは食べるなど、気分や日によって食べる量や内容が大きく変わります。これは子どもの成長過程でよく見られる現象です。
味付けへのこだわり
大人の食事に興味を持ち始め、薄味の離乳食では物足りなく感じることがあります。
かといって、大人と同じ濃い味付けは内臓に負担がかかるため注意が必要です。
おやつや水分の摂りすぎ
食事の前にジュースやお菓子などを与えると、それだけでお腹が満たされてしまい、肝心の食事を食べなくなってしまいます。
おやつの時間と量を決めることが大切です。
卒乳・断乳による精神的な影響
この時期に卒乳・断乳をする場合、心のよりどころだったおっぱいがなくなることで精神的に不安定になり、一時的に食欲が落ちることがあります。
先輩ママ100人に調査 離乳食を食べない理由トップ5
「うちの子だけ、どうして離乳食を食べてくれないの…」と悩んでいませんか?その悩み、実は多くのママが経験しています。
今回、1歳6ヶ月までのお子さんを持つ先輩ママ100人にアンケート調査を実施したところ、離乳食を食べない理由には共通点があることがわかりました。
ここでは、その結果をランキング形式でご紹介します。原因がわかれば、きっと気持ちが少し楽になりますよ。
1位 食べることより楽しい「遊び食べ」

堂々の1位は、多くのママが頭を悩ませる「遊び食べ」でした。
これは、食べ物への好奇心や手先の機能が発達してきた成長の証でもあります。
しかし、毎食となるとママも疲れてしまいますよね。
具体的には、以下のような行動が見られます。
- スプーンやお皿をカチカチ鳴らして遊ぶ
- 食べ物を手でこねたり、握りつぶしたりする
- お皿から食べ物をわざと落とす、投げる
- 口に入れたものをべーっと出す
これらは、赤ちゃんにとって食べ物が
「どんな感触かな?」
「落としたらどうなるかな?」
という探求の対象になっているサインです。
「食事は食べるもの」と教えたいママの気持ちとは裏腹に、赤ちゃんの世界は発見で満ち溢れています。
この時期の悩みは、赤ちゃんの健やかな発達の裏返しでもあるのです。
2位 気分で食べたり食べなかったりする「むら食い」

次に多かったのが、日によって食べる量が極端に違う「むら食い」です。
「昨日は完食したのに、今日は一口も食べない…」といった状況に、一喜一憂してしまうママは少なくありません。
この「むら食い」は、赤ちゃんの自我が芽生え、「食べたい」「食べたくない」という意思表示ができるようになった証拠でもあります。
また、その日の活動量によってお腹の空き具合が変わるのも自然なこと。
公園でたくさん遊んだ日と、お家で静かに過ごした日とでは、必要なエネルギー量も食欲も違って当然です。
栄養が足りているか心配になりますが、「1日」ではなく「1週間」単位で栄養バランスを考えるなど、少し長い目で見守る姿勢がママの心の負担を軽くしてくれます。
3位 眠い・機嫌が悪いなど気分や体調の問題

大人でも眠い時や疲れている時に食欲がなくなるように、赤ちゃんも気分や体調に食欲が大きく左右されます。
特に言葉で伝えられない赤ちゃんにとっては、食事を拒否することが唯一のサインである場合もあります。
先輩ママたちからは、以下のような状況で食べなくなったという声が多く聞かれました。
原因 | 赤ちゃんの様子 |
|---|---|
眠気 | ・食事中にぐずりだす ・目をこする ・あくびをする |
歯ぐずり | ・歯茎がむずがゆく ・口にスプーンが 入るのを嫌がる ・よだれが多い |
体調不良 | ・鼻水や咳が出る ・熱っぽい ・便秘や下痢をしている |
疲れ | ・外出後など刺激が多くて 疲れている時に 食欲が落ちる |
食事の時間だからと無理強いする前に、まずは赤ちゃんのコンディションをチェックすることが大切です。
生活リズムを見直したり、食事の時間を少しずらしたりするだけで、あっさり食べてくれることもあります。
4位 食材の味や食感が好みではない

離乳食が進むにつれて、赤ちゃんの味覚や食感の好みもはっきりしてきます。
今まで食べていたものを急に嫌がるようになるのは、味覚が発達し、より繊細な味や食感の違いがわかるようになったからかもしれません。
特に、以下のような味や食感は赤ちゃんに敬遠されがちです。
- 味:野菜の苦味(ピーマン、ほうれん草など)、果物の酸味(トマト、柑橘類など)
- 食感:パサパサするもの(鶏むね肉、パンなど)、ベタベタするもの(納豆など)、舌触りが悪いもの(野菜の繊維など)
「この食材は嫌いなんだ」と決めつけてしまう前に、調理法を少し変えてみましょう。
例えば、パサつくお肉にはとろみをつけたり、酸っぱいトマトは加熱して甘みを引き出したりするだけで、喜んで食べてくれる可能性があります。
赤ちゃんの「好き嫌い」の裏には、食べやすくしてほしいというサインが隠れているのかもしれません。
5位 ミルクや母乳でお腹がいっぱい

特に離乳食の初期から中期にかけて多いのが、離乳食の前にお腹が満たされてしまっているケースです。
この時期の赤ちゃんにとって、ミルクや母乳はまだメインの栄養源であり、安心材料でもあります。
そのため、離乳食の直前に授乳してしまうと、満腹で食べる意欲が湧かなくなってしまいます。
赤ちゃんはまだ胃が小さく、一度にたくさんの量を飲むことも食べることもできません。食事から栄養を摂る練習をするためには、お腹が空いているタイミングで離乳食を与えることが重要です。授乳と食事の間隔を少し空けるなど、生活リズムを調整することで解決することが多い原因です。空腹は最大のスパイス、というわけですね。
【悩み別】離乳食を食べないときの先輩ママ実践の克服法
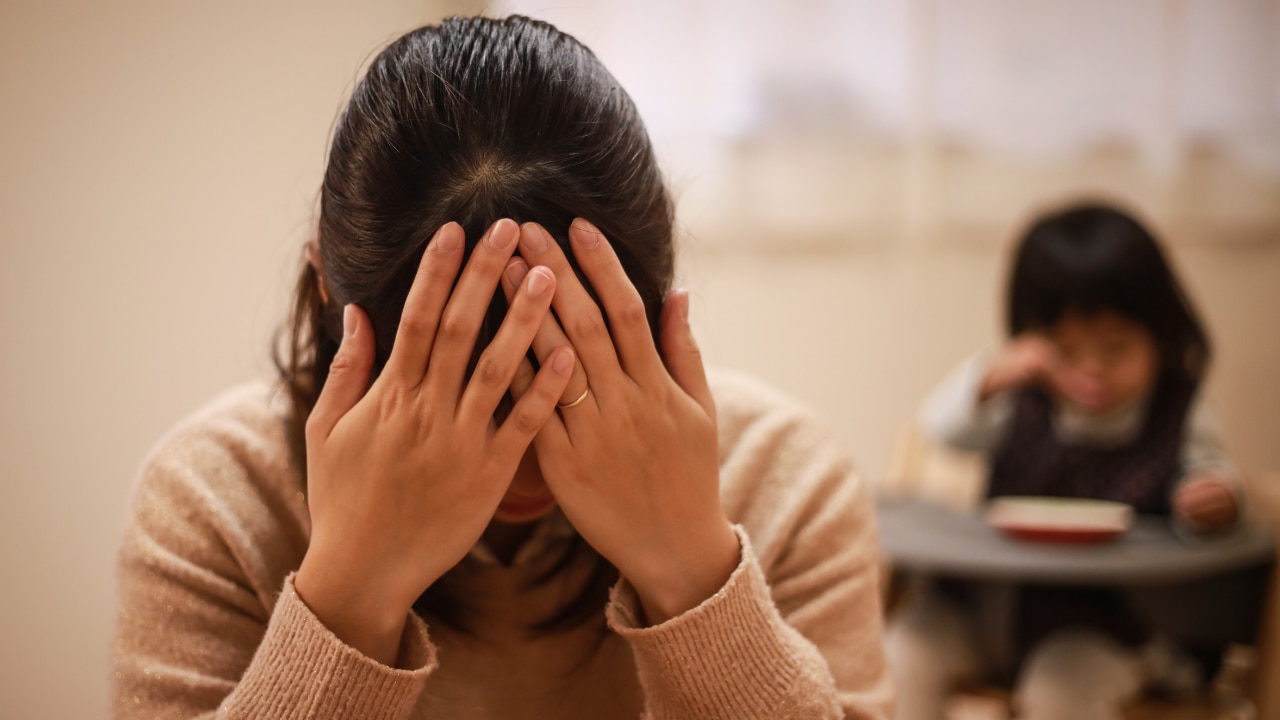
アンケートで挙がった「遊び食べ」や「むら食い」といったお悩みは、多くのママが経験するものです。
しかし、毎日続くと「どうして食べてくれないの?」と不安になったり、イライラしてしまったりしますよね。
ここでは、先輩ママたちが実際に試して効果があった具体的な対処法を、お悩みの種類別に詳しくご紹介します。
赤ちゃんの個性に合わせて、できそうなことから試してみてください。
①「遊び食べ」が始まったときの対処法

食べ物をぐちゃぐちゃにしたり、スプーンを投げたりする「遊び食べ」。
これは、食べ物そのものや手を使うことに興味が出てきた成長の証でもあります。
とはいえ、食事のたびに後片付けが大変だったり、ちゃんと食べていないことが心配になったりするものです。
遊び食べが始まったときは、食事と遊びのメリハリをつけることを意識してみましょう。
〇食事の時間を15分から20分で区切る

赤ちゃんの集中力は長く続きません。
食事時間が長引くと、飽きてしまい遊び食べに繋がりやすくなります。
先輩ママからは「タイマーをセットして時間を可視化する」「『あと一口でごちそうさましようね』と終わりを予告する」といった声が多く聞かれました。
時間が来たら、たとえ残していても「ごちそうさま」と一度食事を切り上げる勇気も大切です。
これを繰り返すことで、赤ちゃんも「この時間内に食べるんだ」と理解するようになります。
〇食事に集中できる環境を整える

赤ちゃんの周りにテレビやおもちゃなど、興味を引くものがあると食事への集中が途切れてしまいます。
食事の前には、まず環境を整えることから始めましょう。
- テレビや動画は消す
- おもちゃは片付ける
- スマートフォンは食卓に置かない
- 食事用のベビーチェアに座らせる
「ここはご飯を食べるところ」と赤ちゃんが認識できるような、静かで落ち着いた環境を作ることが、遊び食べを防ぐ第一歩です。
食事の時間は、赤ちゃんと向き合う大切なコミュニケーションの時間と捉えましょう。
〇手づかみ食べメニューを積極的に導入する

「自分で食べたい」という意欲の表れが、遊び食べにつながることもあります。
その意欲を食事に向けてあげるために、手づかみ食べメニューを取り入れるのが非常に効果的です。
自分で持って口に運ぶという一連の動作が、赤ちゃんの満足感や食べる楽しさを育みます。
汚れることを前提に、床に新聞紙やビニールシートを敷いたり、袖までカバーできる食事用エプロンを活用したりすれば、ママの片付けのストレスも軽減できます。最初はうまく口に運べなくても、温かく見守ってあげましょう。
月齢 | メニュー例 | ポイント |
|---|---|---|
中期 (7〜8ヶ月頃) | やわらかく茹でた 野菜スティック (にんじん、大根など)、 食パンの耳をとった パンがゆを丸めたもの | 歯ぐきでつぶせる固さが目安。 赤ちゃんが握りやすい太さや 大きさに調整します。 |
後期 (9〜11ヶ月頃) | おやき、 軟飯のおにぎり、 バナナ、 鶏ささみや豆腐のハンバーグ | 前歯でかじり取り、 歯ぐきでつぶせるメニューを。 食材の種類を増やして 栄養バランスもアップ。 |
完了期 (1歳〜1歳6ヶ月頃) | ミニおにぎり、 フレンチトースト、 蒸しパン、 ブロッコリーなど | 少し歯ごたえのあるものもOK。 フォークやスプーンの練習と 並行して取り入れます。 |
➁「むら食い」にイライラしないための対処法
「昨日は完食したのに、今日は一口も食べない」「朝は食べたけど昼は拒否」など、日や時間帯によって食べる量が大きく変わる「むら食い」。
赤ちゃんの気分や体調に左右されることが多く、ママにとっては献立の立て方や栄養面で悩みの種になりがちです。
むら食いには、ママの気持ちの持ち方と生活習慣の見直しが鍵になります。
〇一食くらい食べなくても大丈夫と割り切る
栄養バランスを考えると毎食しっかり食べてほしいと思うのが親心ですが、赤ちゃんも大人と同じように「今はお腹が空いていない」という日もあります。
一食単位で一喜一憂せず、1日や数日、長い目で見れば1週間単位で栄養が摂れていれば大丈夫、と大きく構えることが大切です。
ママが「食べさせなきゃ」と必死になると、その緊張感が赤ちゃんに伝わり、かえって食事の時間が苦痛になってしまうことも。
食べないときは早めに切り上げて、次の食事や授乳で調整しましょう。
〇生活リズムを整えてお腹を空かせる

決まった時間に食事が来ると、体も自然と食事モードになります。朝起きる時間、お昼寝の時間、夜寝る時間をなるべく一定にして、生活リズムを整えましょう。
また、日中に公園で外気浴をしたり、お家の中で体を動かす遊びを取り入れたりして、しっかりエネルギーを消費させることも大切です。
「お腹が空く」という感覚を赤ちゃんが覚えることで、食事への意欲が湧いてきます。
食事の直前におやつやジュース、牛乳などを与えすぎないように注意することもポイントです。
〇調理法や味付けを変えてマンネリを防ぐ

いつも同じようなメニューだと、赤ちゃんも飽きてしまうことがあります。
好きな食材でも、調理法や味付けに少し変化をつけるだけで、また食べてくれるようになるケースは少なくありません。
マンネリを防ぐひと工夫が、赤ちゃんの食への好奇心を再び刺激します。
例えば、にんじんなら「すりおろしてポタージュにする」「細かく刻んでご飯に混ぜる」「スティック状にして煮る」など、形態を変えるだけでも食感が変わります。
味付けも、いつもの和風だしだけでなく、野菜スープやトマトソース、少量の牛乳や豆乳で風味を変えてみるのもおすすめです。
➂口を開けない・べーっと出すときの対処法
スプーンを近づけても頑なに口を閉じたり、口に入れたものをべーっと出してしまったり。
これは単なる「イヤ!」という意思表示だけでなく、「うまく飲み込めない」「口の中が不快」といった赤ちゃんからのサインかもしれません。
原因を探り、それに合わせた対処を試してみましょう。
〇食材の固さや大きさを月齢に合わせて見直す

離乳食をべーっと出す最も多い原因の一つが、食材の形態が赤ちゃんの咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)の発達段階に合っていないことです。
固すぎたり、大きすぎたりすると、うまくモグモグ・ゴックンができずに口から出してしまいます。
逆に、月齢が進んでいるのにいつまでもペースト状だと、食感のなさに飽きてしまうことも。
月齢の目安を参考にしつつ、一番大切なのは実際のお子さんの口の動きをよく観察することです。
その子に合った固さや大きさに調整してあげましょう。
月齢 | 固さの目安 | 大きさの目安 |
|---|---|---|
初期 (5〜6ヶ月) | なめらかな ポタージュ状 | ー |
中期 (7〜8ヶ月) | 舌でつぶせる 豆腐くらい | 2〜3mm角の みじん切り |
後期 (9〜11ヶ月) | 歯ぐきでつぶせる バナナくらい | 5〜8mm角の 粗みじん切り |
完了期 (1歳〜1歳6ヶ月) | 歯ぐきで噛める 肉団子くらい | 1cm角くらい |
〇スプーンや食器を赤ちゃんが好きなものに変える

毎日使うスプーンや食器が、実は食べない原因になっている可能性もあります。
スプーンの金属の感触が嫌だったり、口の大きさに対してスプーンが大きすぎたりすることもあります。
シリコン製や木製など素材を変えたり、先端が浅く食べ物が残りづらい形状のものを選んだりすると、すんなり食べてくれることがあります。
また、好きなキャラクターや動物が描かれた食器に変えるだけで、食事への関心が高まることも。
道具を変えるという簡単な工夫で、赤ちゃんの気持ちが切り替わるかもしれません。
〇大人が美味しそうに食べる姿を見せる

赤ちゃんは周りの大人の真似をするのが大好きです。
ママやパパが「おいしいね!」「もぐもぐ、上手だね」と笑顔で声をかけながら、楽しそうに食事をする姿を見せることは、何よりの食育になります。
「食べること=楽しい時間」というポジティブなイメージを赤ちゃんに持たせることが重要です。
できるだけ家族で食卓を囲み、赤ちゃんと同じ食材(薄味にしたもの)を食べて「〇〇ちゃんと同じだね、おいしいよ」と見せてあげるのも効果的。
食事の時間を、親子の楽しいコミュニケーションの場にしていきましょう。
離乳食を食べないときに試したい調理のひと工夫
毎日同じようなメニューが続くと、赤ちゃんも味や食感に飽きてしまうことがあります。
特に中期以降は味覚が発達し、好き嫌いが出てくる時期。
そんなときは、ほんの少し調理に工夫を加えるだけで、驚くほど食が進むことがあります。
ここでは、先輩ママたちが実践してきた「食べない」を「食べる!」に変える調理のアイデアをご紹介します。
①だしや野菜スープで風味を変える

離乳食の基本は素材の味を活かすことですが、いつも同じ味ではマンネリになりがちです。
そんなときは、うま味成分が豊富な「だし」や野菜の自然な甘みが溶け込んだ「野菜スープ」を活用してみましょう。
塩分を使わずに風味を豊かにし、赤ちゃんの食欲を優しく刺激します。
おかゆに混ぜたり、ペースト状の野菜をのばしたり、煮物に使ったりと活用方法は無限大。
昆布だしは初期から、かつおだしは香りが立つので中期以降におすすめです。
また、にんじんや玉ねぎ、キャベツなどを煮込んで作る野菜スープ(ベジブロス)は、野菜の栄養も摂れる万能選手です。
種類 | おすすめの時期 | 特徴と使い方 |
|---|---|---|
昆布だし | 離乳食初期 (5〜6ヶ月頃)から | クセがなく、 うま味の基本となる グルタミン酸が豊富。 おかゆや野菜ペーストなど、 何にでも合わせやすい。 |
野菜スープ | 離乳食初期 (5〜6ヶ月頃)から | 野菜の自然な甘みと香りが特徴。 にんじん、玉ねぎ、かぶなど、 赤ちゃんが食べ慣れた 野菜を使うのがおすすめ。 |
かつおだし | 離乳食中期 (7〜8ヶ月頃)から | 豊かな香りが食欲をそそる。 魚に慣れてきた中期以降に。 うどんや煮物に使うと 本格的な味わいになる。 |
鶏がらスープ | 離乳食後期 (9〜11ヶ月頃)から | コクがあり、満足感がアップする。 中華風のおかゆやスープに。 脂肪分を取り除いてから 使うのがポイント。 |
だしやスープは手作りが理想ですが、忙しいときは市販の赤ちゃん用だしパックや粉末だしを上手に使うのも良いでしょう。
無添加で食塩不使用のものを選ぶと安心です。
➁調理形態を変えて食感に変化をつける

「昨日まで食べていたのに、急にべーっと出すようになった」という場合、もしかしたらその食材の食感に飽きてしまったのかもしれません。
同じ食材でも、調理形態を変えるだけで赤ちゃんにとっては全く新しい食べ物に感じられます。
例えば、いつもペースト状にしている野菜を少し形が残るくらいに刻んでみたり、茹でるだけでなく焼いたり蒸したりして食感に変化をつけてみましょう。
「噛む」「舌でつぶす」といった口の発達を促す練習にもなります。
特に後期からは、手づかみ食べメニューがおすすめです。
野菜スティックやおやき、小さなおにぎりなど、自分で持って食べる楽しさが食への興味を引き出します。
食材 | いつもの調理法 | 変化をつけるアイデア |
|---|---|---|
にんじん 大根 | ペースト状 みじん切り | 柔らかく茹でて スティック状にする。 すりおろしておやきや パンケーキに混ぜ込む。 |
じゃがいも さつまいも | マッシュポテト | 小さく角切りにして スープに入れる。 マッシュしたものに 片栗粉を混ぜてお餅風にす。 細切りにして焼く。 |
豆腐 | 豆腐ペースト | 水切りして焼いて 豆腐ステーキにする。 ひき肉と混ぜて 豆腐ハンバーグにする。 |
鶏ささみ | ほぐしてとろみをつける | 細かく刻んでつくねにする。 ひき肉にして そぼろあんかけにする。 |
「いつもと違う」という新鮮さが、赤ちゃんの「食べてみたい!」という好奇心を刺激します。
月齢に合わせて、少しずつステップアップしていきましょう。
➂市販のベビーフードや調味料を上手に活用する
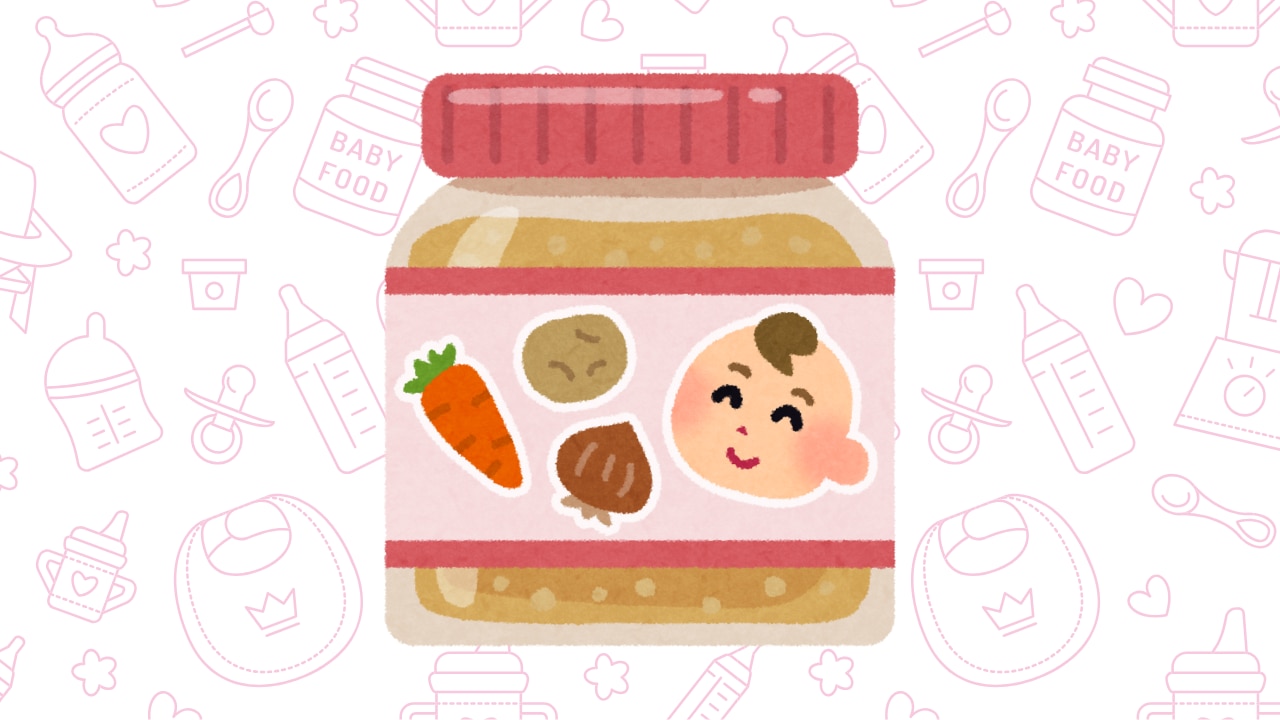
「離乳食は手作りでなければ」と頑張りすぎていませんか?
ときには市販のベビーフードや調味料に頼ることも、ママやパパの心と時間の余裕を生み出す大切な工夫です。
手作りではなかなか出せない味付けやメニューを手軽に取り入れられるため、マンネリ打破の強い味方になります。
最近のベビーフードは、月齢に合わせた栄養バランスやアレルギーにも配慮されており、品質も向上しています。すべてを置き換えるのではなく、手作りに「ちょい足し」するだけでも、味のバリエーションがぐっと広がります。
ベビーフードの「ちょい足し」活用術
- 手作りのおかゆに、市販のレトルトパウチ(ミートソース風、ホワイトソース風など)を少量かける。
- 茹でた野菜やうどんに、フリーズドライのレバーや白身魚などを和える。
- 手作りのハンバーグや煮物に、赤ちゃん用のコンソメやトマトソースで風味付けする。
便利な赤ちゃん用調味料
和光堂、ピジョン、キユーピーなど、各社から赤ちゃん向けの調味料が販売されています。
これらを活用すれば、味付けの失敗も少なく、手軽にプロの味に近づけることができます。
- 粉末・液体だし:お湯に溶かすだけ、かけるだけで手軽にだしの風味がプラスできます。
- ホワイトソース・ミートソース:野菜と和えたり、ごはんにかけたりするだけで洋風メニューが完成します。
- 赤ちゃん用コンソメ・野菜だし:スープやポトフの味付けに便利です。
- 赤ちゃん用ケチャップ・ソース:後期以降、オムレツやハンバーグの味付けのアクセントになります。
市販品を使うことに罪悪感を感じる必要は全くありません。
ママやパパが笑顔で食卓を囲むことが、赤ちゃんにとって一番の栄養になります。
上手に活用して、親子で食事の時間を楽しみましょう。
逆効果かも 離乳食を食べないときに避けたいNG対応
赤ちゃんが離乳食を食べてくれないと、ママやパパは「栄養は足りているかな?」「どうして食べてくれないの?」と不安や焦りを感じてしまいますよね。
そんな気持ちから、ついやってしまいがちな行動が、実は赤ちゃんの「食べる意欲」をさらに削いでしまう逆効果になっているかもしれません。
ここでは、先輩ママたちが「あの時やらなければよかった…」と後悔しがちなNG対応について、その理由とともに詳しく解説します。
×無理やり口に運ぶ
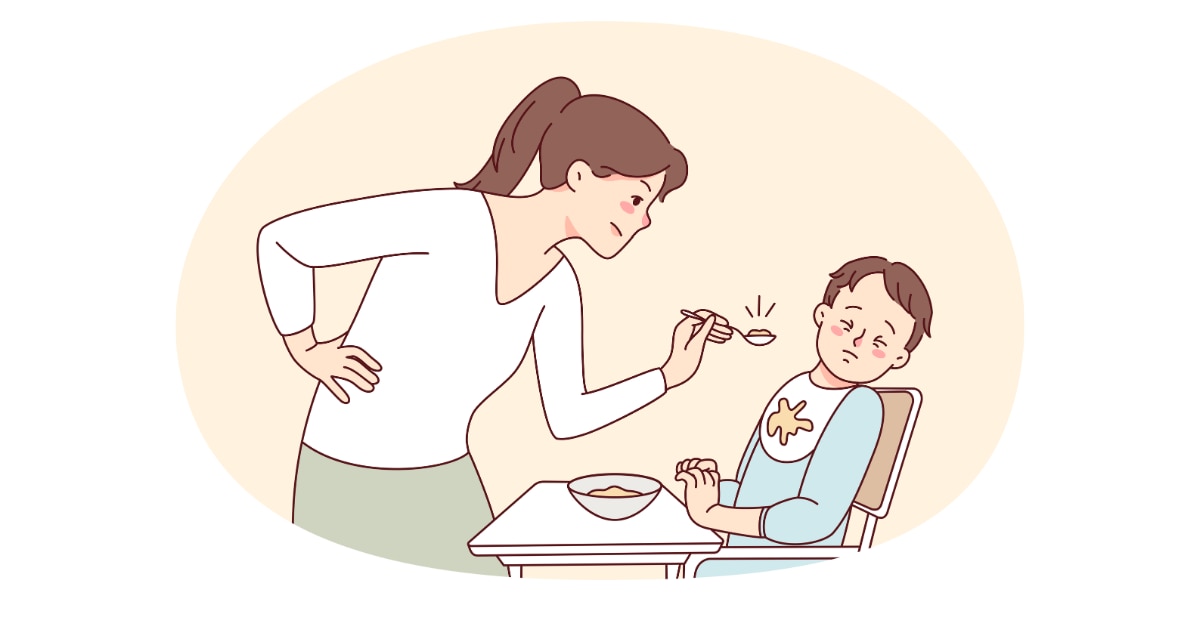 口を固く閉ざしたり、顔を背けたりする赤ちゃんに対して、スプーンを無理やり口に押し込むのは絶対に避けましょう。
口を固く閉ざしたり、顔を背けたりする赤ちゃんに対して、スプーンを無理やり口に押し込むのは絶対に避けましょう。
赤ちゃんにとって、食事の時間が「怖い」「苦しい」といったネガティブな体験として記憶されてしまいます。
赤ちゃんが口を開けないのは、「お腹がいっぱい」「今は食べたい気分じゃない」「この味や食感が苦手」といった、赤ちゃんからの意思表示(サイン)です。
そのサインを無視して無理強いを続けると、食事の時間そのものに強い拒否感を示すようになり、食べない悩みがさらに深刻化する可能性があります。
泣いているときに食べさせるのも同様です。
一度食事を中断し、赤ちゃんの気持ちが落ち着くのを待つ勇気も必要です。食事は楽しいものだと赤ちゃんが感じられることを最優先に考えましょう。
×食事中に叱ったりイライラした態度を見せたりする
食べ物を手でぐちゃぐちゃにする「遊び食べ」や、ベーっと吐き出してしまう姿を見ると、つい「どうして!」「やめて!」と声を荒らげたくなってしまうかもしれません。
しかし、食事中に叱られたり、大人がイライラした態度を見せたりすると、赤ちゃんは敏感にその場の空気を感じ取ります。
赤ちゃんにとって、大好きなママやパパが怒っている状況は非常に大きなストレスです。
「食べないと怒られる」「食事の時間は楽しくない」と学習してしまい、食事がプレッシャーになってしまいます。
その結果、ますます口を開かなくなったり、食事の椅子に座ること自体を嫌がったりする悪循環に陥ることも少なくありません。
たとえ食べてくれなくても、まずは「一口でも食べられたら花丸!」という気持ちで、笑顔で接することを心がけましょう。
×テレビや動画を見せながら食べさせる

テレビやスマートフォンで動画を見せると、赤ちゃんが夢中になっている隙に食事が進むため、つい頼ってしまいがちです。
しかし、「ながら食べ」は、赤ちゃんの健やかな食習慣の形成を妨げるさまざまなデメリットがあります。
動画に意識が向いていると、赤ちゃんは「自分が何を食べているのか」「どんな味がするのか」をほとんど認識できません。
食べ物への興味や関心が育たず、食事の楽しさを学ぶ機会を失ってしまいます。
また、「動画がないと食べない」という癖がつきやすく、外食時や保育園などで困る原因にもなります。
食事は五感を使って楽しむ大切な時間です。
テレビや動画は消して、食事そのものに集中できる環境を整えましょう。
デメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
×味覚や食への興味が 育たない | 無意識に口を動かしているだけで、 食材の味や食感、 香りなどを楽しむ経験ができない。 |
×満腹感を 感じにくい | 食べることに集中していないため、 脳が満腹のサインを認識しにくく、 過食につながる可能性がある。 |
×悪い食習慣が 身につく | 「動画がないと食べない」 という癖がつき、 自発的に食べる意欲が 育ちにくくなる。 |
×コミュニケーションの 機会損失 | 「おいしいね」「にんじんだよ」といった、 食事中の親子の 大切なコミュニケーションが 減ってしまう。 |
×他の赤ちゃんと比べる
SNSや子育て支援センターなどで、同じ月齢の赤ちゃんがパクパク食べている様子を見ると、「どうしてうちの子は…」と焦りを感じてしまうのは自然なことです。
しかし、赤ちゃんの成長や発達のペースは千差万別。食べる量や好み、離乳食の進み具合にも大きな個人差があります。
比べるべきは「他の子」ではなく「過去のわが子」です。
「昨日より一口多く食べられた」「苦手な食材に口をつけられた」など、ほんの小さな成長を見つけて褒めてあげましょう。
他人との比較は、ママやパパ自身を不必要に追い詰めるだけでなく、その焦りが赤ちゃんにも伝わってしまいます。
「うちの子はうちの子のペースで大丈夫」と、どっしり構えることが、結果的に赤ちゃんの食べる意欲を引き出す近道になります。
離乳食を食べないときの栄養は大丈夫?ミルクや母乳の考え方
離乳食を思うように食べてくれないと、「このままで栄養は足りているの?」「成長に影響はない?」と心配になりますよね。
しかし、焦る必要はありません。
特に離乳食の初期から中期にかけては、栄養の大部分をまだ母乳や育児用ミルクから摂取しています。
離乳食の主な目的は、食べ物を飲み込む練習や、様々な味や食感に慣れることです。
まずは赤ちゃんのペースを大切にしながら、食事と授乳のバランスを理解していきましょう。
①月齢ごとの食事と授乳のバランス目安

離乳食の進み具合によって、食事から摂る栄養と母乳・ミルクから摂る栄養の割合は変化していきます。
月齢ごとの目安を知っておくと、心の余裕にも繋がります。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、赤ちゃんの食欲や成長には個人差があることを忘れないでください。
離乳食の時期 (月齢) | 食事の回数 | 食事からの 栄養割合 (目安) | 授乳(母乳・ミルク)の役割と ポイント |
|---|---|---|---|
初期 (5~6ヶ月頃) | 1回 | 約10~20% | 栄養の中心。 離乳食のあとに、 赤ちゃんが欲しがるだけ与えます。 授乳リズムは 今まで通りで問題ありません。 |
中期 (7~8ヶ月頃) | 2回 | 約30~40% | 引き続き栄養の主役。 離乳食のあとにもしっかり与え、 1日3回程度の授乳リズムを意識すると 生活リズムが整いやすくなります。 |
後期 (9~11ヶ月頃) | 3回 | 約60~70% | 栄養の中心が 食事へと移行してきます。 食後の授乳は欲しがる場合にあげ、 量は少しずつ減っていきます。 食間の授乳は 1日2回程度が目安です。 |
完了期 (12~18ヶ月頃) | 3回+補食1~2回 | 約75%以上 | 栄養のほとんどを 食事から摂るようになります。 授乳は食事に影響しない範囲で、 子どもの心の安定のためにも 活用できます。 牛乳を飲ませることも可能です。 |
表を見てわかるように、離乳食完了期になるまでは、母乳やミルクも大切な栄養源です。
食べないからといって、すぐに栄養不足になるわけではありません。
一食食べなくても、1日や2~3日のトータルで栄養が摂れていれば大丈夫と、少し長い目で見てあげましょう。
➁フォローアップミルクはいつから必要か?

離乳食が進む9ヶ月頃になると、「フォローアップミルク」という言葉を耳にする機会が増えます。
育児用ミルク(乳児用調整乳)が母乳の代替品として栄養を補うものであるのに対し、フォローアップミルクは、離乳食だけでは不足しがちな鉄分やカルシウム、ビタミンなどを補うための補助的な飲み物です。
そのため、フォローアップミルクは必ずしもすべての赤ちゃんに必要なものではありません。
3回の離乳食が順調に進み、肉や魚、野菜などをバランス良く食べられている場合は、無理に与える必要はないとされています。
牛乳が飲めるようになれば、牛乳で栄養を補うこともできます。
フォローアップミルクの活用を検討すると良いのは、以下のようなケースです。
- 離乳食の進みが遅く、食べる量が少ない
- 食べムラが激しく、鉄分が不足しがち(特にレバーや赤身魚などが苦手)
- 牛乳アレルギーがあり、牛乳が飲めない
- 体重の増え方が気になる
もしフォローアップミルクを使うか迷った場合は、自己判断で切り替えるのではなく、かかりつけの小児科医や地域の保健師、管理栄養士に相談してみるのがおすすめです。
赤ちゃんの成長や食事の状況に合わせて、適切なアドバイスをもらえます。
こんなときは専門家へ相談 病院受診の目安
離乳食を食べない日が続くと、「もしかしてどこか悪いのかな?」と心配になりますよね。
ほとんどの場合は赤ちゃんの気分や成長過程によるものですが、中には病気のサインが隠れていることもあります。
ママやパパだけで抱え込まず、気になることがあれば専門家に相談することが大切です。
ここでは、小児科などの医療機関を受診すべき目安について具体的に解説します。
①体重が増えない・減っている

赤ちゃんの成長を測るうえで、体重はとても大切な指標です。毎日体重計に乗せる必要はありませんが、母子健康手帳にある「身体発育曲線(成長曲線)」を使って、定期的にチェックする習慣をつけましょう。
チェックするポイントは、成長曲線のカーブに沿って、その子なりのペースで体重が増えているかどうかです。
一時的に横ばいになることはあっても、体重が明らかに減少していたり、長期間にわたって成長曲線の帯から大きく外れていたりする場合は、かかりつけの小児科医に相談しましょう。
たとえ食べむらがあっても、元気で機嫌が良く、体重が順調に増えていれば、過度に心配する必要はありません。
➂嘔吐や下痢など体調不良のサインがある

「離乳食を食べない」という症状に加えて、他に気になる症状がある場合は注意が必要です。
単なる食欲不振ではなく、何らかの病気が原因かもしれません。
特に、特定の食材を食べた後に、じんましんや発疹、嘔吐、咳などの症状が出る場合は、食物アレルギーの可能性も考えられます。
自己判断でその食材を完全に除去するのではなく、必ず医師の診断を仰ぎましょう。
その際は、いつ、何を、どれくらい食べて、どのような症状が出たかをメモしておくと診察がスムーズです。
その他、以下のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診してください。
- 発熱している
- 嘔吐や下痢を繰り返す
- 咳や鼻水がひどい
- 顔色が悪く、ぐったりしている
- いつもと比べて明らかに機嫌が悪い
④水分も受け付けない

食事を食べないこと以上に緊急性が高いのが、水分を摂れない状態です。
赤ちゃんは体内の水分量が多く、大人よりも脱水症状に陥りやすいため、特に注意が必要です。
離乳食だけでなく、母乳やミルク、白湯なども受け付けず、ぐったりしている様子が見られたら、すぐに病院へ行きましょう。
脱水症状が疑われるサインは以下の通りです。
一つでも当てはまる場合は、夜間や休日であっても救急外来の受診を検討してください。
チェック項目 | 脱水が疑われるサイン |
|---|---|
おしっこ | 半日以上出ていない。 または回数が普段より極端に少ない。 色が濃い。 |
口・唇 | 口の中や舌が乾いている。 唇がカサカサになっている。 |
涙 | 泣いているのに涙が出ていない。 または量が少ない。 |
肌 | 肌にハリがなく、 お腹の皮膚をつまんで離しても、 なかなかもとに戻らない。 |
様子 | ぐったりして元気がない。 あやしても反応が鈍い。 目が落ちくぼんでいる。 |
赤ちゃんの「食べない」というサインの裏には、様々な理由が隠されています。
不安なときは一人で悩まず、かかりつけの小児科医や地域の保健師、栄養士など、信頼できる専門家に相談して、安心して離乳食を進めていきましょう。
まとめ

赤ちゃんが離乳食を食べない理由は、遊び食べや気分、好みなど様々で、多くの親子が経験する成長過程の一環です。
無理強いはせず、食事環境を整えたり、調理法を工夫したりと、赤ちゃんの興味を引くことが大切です。
何より保護者が「一食くらい大丈夫」と大らかに構え、食事の時間を楽しいものにしましょう。
この記事で紹介した先輩ママのアイデアを参考に、焦らず赤ちゃんのペースに合わせて進めてくださいね。