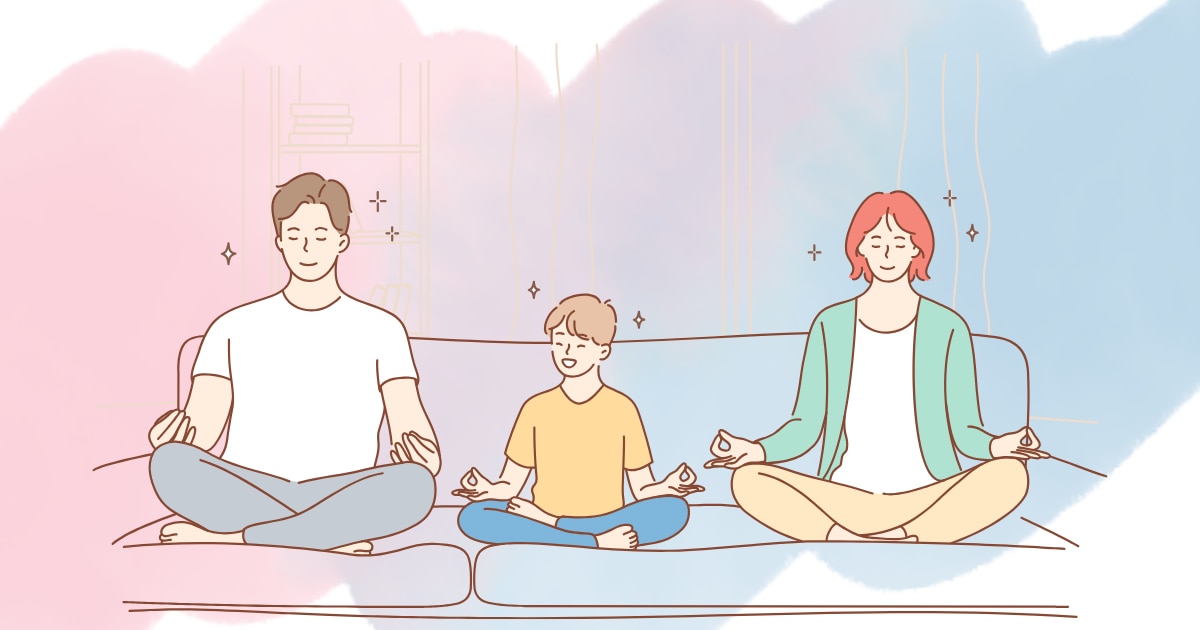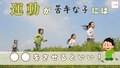ゲームばかりの子どもが運動好きに!親が実践できる意外な秘訣で運動不足解消
お子さんがゲームばかりで運動不足が心配ではありませんか?
この記事では、なぜ子どもがゲームに夢中になるのか、そして運動不足が心身に与える深刻な影響を解説します。
さらに、運動嫌いな子を運動好きに変えるための、親が実践できる意外な秘訣を具体的にご紹介。
強制するのではなく、運動を「遊び」に変えたり、親子で楽しんだりすることで、子どもが自ら体を動かすようになるヒントが満載です。
スクリーンタイムとの賢い付き合い方もわかるので、もう運動不足に悩むことはありません。
目次[非表示]
- 1.ゲームばかりの子どもが増加中?運動不足の深刻な影響
- 2.運動嫌いな子どもを運動好きに変える親の心構え
- 3.【親が実践できる意外な秘訣①】 運動を「遊び」に変える工夫
- 3.1.①ゲーム要素を取り入れた運動遊びのアイデア
- 3.1.1.宝探しゲームで全身運動
- 3.1.2.アスレチックごっこで体幹を鍛える
- 3.2.➁競争ではなく「協力」で楽しむ運動
- 4.【親が実践できる意外な秘訣➁】 ゲームと運動のバランスを見つける方法
- 4.1.①スクリーンタイムのルール作りと運動時間の設定
- 4.2.➁ゲームの休憩時間にできる簡単運動
- 4.2.1.ストレッチや軽い体操で体をほぐす
- 4.2.2.縄跳びやボール遊びでリフレッシュ
- 5.【親が実践できる意外な秘訣3】 親子で楽しむ運動で子どもも運動好きに
- 5.1.①親が楽しむ姿を見せることの重要性
- 5.2.➁家の中でもできる親子運動の具体例
- 5.2.1.室内アスレチックで運動不足解消
- 5.2.2.ダンスやヨガでリラックス運動
- 5.3.➂公園や広場で楽しめる外遊びの提案
- 6.運動習慣を無理なく続けるためのヒント
- 6.1.①子どもの「好き」を見つけるサポート
- 6.2.➁継続のためのご褒美や目標設定
- 6.3.周囲の環境を味方につける方法
- 7.まとめ
ゲームばかりの子どもが増加中?運動不足の深刻な影響

現代の子どもたちの生活は、デジタルデバイスの普及とともに大きく変化しています。
特にスマートフォンやタブレット、家庭用ゲーム機の進化により、ゲームに夢中になる子どもが増加の一途をたどっています。
それに伴い、外で体を動かす機会が減り、運動不足が深刻な社会問題となっています。
①なぜ子どもはゲームに夢中になるのか?

子どもたちがゲームに夢中になるのには、いくつかの理由があります。
ゲームは、単なる娯楽以上の魅力を持っているからです。
- 即座の達成感と報酬:ゲームは、目標を達成したり、敵を倒したりするたびに、即座に視覚的・聴覚的な報酬を与えます。この即時的なフィードバックが、子どもの脳の報酬系を刺激し、「もっとやりたい」という欲求を生み出します。
- 手軽さと没入感:いつでもどこでも手軽に始められ、一度始めるとその世界観に深く没入できる点が、子どもたちを強く惹きつけます。現実世界での制約が少なく、自分の思い通りに操作できる自由度も魅力の一つです。
- 仲間とのつながり:オンラインゲームでは、友達と一緒にプレイしたり、遠く離れた人ともコミュニケーションを取ったりできます。共通の趣味を持つ仲間との交流は、子どもの社会性を育む一方で、ゲームを続ける強い動機となります。
- 現代社会の環境変化:公園で遊ぶ機会の減少や、塾や習い事による多忙なスケジュールも、子どもたちが手軽に楽しめるゲームに流れやすい要因となっています。
➁運動不足が子どもの心と体に与える悪影響

ゲームに夢中になるあまり運動の機会が減少すると、子どもの心身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
運動は単に体を動かすだけでなく、子どもの成長と発達に不可欠な要素だからです。
影響の種類 | 具体的な悪影響 |
|---|---|
身体的影響 |
|
精神的・ 心理的影響 |
|
このように、子どもの運動不足は、単に「体がなまける」だけでなく、心と体の健全な成長を阻害し、将来の健康にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
親がこの現状を深く理解し、適切な対策を講じることが重要です。
運動嫌いな子どもを運動好きに変える親の心構え
ゲームばかりで体を動かす機会が少ない子どもを運動好きに変えるには、まず親の接し方や考え方を見直すことが重要です。
無理強いするのではなく、子どもの内なる意欲を引き出すための心構えについて解説します。
①強制は逆効果!子どもの「やりたい」を引き出す視点

子どもに「運動しなさい!」と命令しても、反発を招くだけで逆効果になりがちです。
大切なのは、子どもが自ら「やりたい」と感じるような環境やきっかけを作ること。
親が主導するのではなく、子どもの自主性を尊重する視点を持つことが、運動への意欲を引き出す第一歩となります。
まずは、子どもの興味関心を探りましょう。
どんな遊びが好きか、どんなキャラクターに夢中か、どんな場所に行くと楽しそうかなど、日頃から観察し、会話の中からヒントを見つけることが重要です。
そして、いくつかの選択肢を提示し、子ども自身に選ばせることで、「やらされている」という感覚ではなく、「自分で選んだ」という主体的な気持ちで運動に取り組めるようになります。
避けるべき声かけ (NG例) | 試したい声かけ (OK例) |
|---|---|
×「ゲームばかり してないで、 外で遊びなさい!」 | 〇「今日は公園に行くのと、 お家で体を動かすの、 どっちがいい?」 |
×「毎日30分は 運動しなさい!」 | 〇「これとこれ、 どっちの運動なら やってみたい?」 |
×「早く縄跳び しなさい!」 | 〇「〇〇ちゃん (キャラクター名)みたいに、 かっこよく走れるかな?」 |
×「こんな運動も できないの?」 | 〇「これ、ママ(パパ)と一緒に やってみない?」 |
➁完璧を目指さない!小さな成功体験を積み重ねる大切さ

運動習慣を身につけさせる上で、最初から高い目標を設定したり、完璧を求めたりすることは避けるべきです。
重要なのは、どんなに小さなことでも「できた!」という成功体験を積み重ねさせること。
これにより、子どもは「自分にもできる」という自信を持ち、次のステップへ進む意欲が湧いてきます。
例えば、最初は「縄跳びを3回跳べた」「公園まで歩けた」といった、ごく簡単な目標から始めましょう。
そして、目標を達成したら、結果だけでなく、その過程での努力や頑張りを具体的に褒めてあげることが大切です。
失敗しても、「次はこうしてみようか」と一緒に考え、励ますことで、挑戦することへの抵抗感を減らすことができます。
NGな声かけ・態度 | OKな声かけ・態度 |
|---|---|
×「たったこれだけ? もっとできるでしょ!」 | 〇「わぁ、すごい! 前より遠くまで 走れるようになったね!」 |
×「なんでそんなことも できないの?」 | 〇「惜しかったね! でも、最後まで 諦めずに頑張ったのが 素晴らしいよ!」 |
×「どうせ 続かないんでしょ?」 | 〇「ちょっとずつでも 毎日体を動かしているの、 本当に偉いね!」 |
×結果ばかりに注目し、 できていない点を 指摘する | 〇努力の過程や、 以前と比較して 成長した点を 具体的に褒める |
【親が実践できる意外な秘訣①】 運動を「遊び」に変える工夫

「運動しなさい」と口で言っても、ゲームに夢中の子どもにはなかなか響きません。
そこで重要なのが、運動を子どもが自ら「楽しい」と感じる「遊び」に変える工夫です。
ゲームが持つ「ワクワク感」や「達成感」といった要素を現実の運動に取り入れることで、子どもは自然と体を動かすようになります。
運動は「やらされるもの」ではなく、「楽しい時間」であると認識させることが、運動習慣の第一歩となります。
①ゲーム要素を取り入れた運動遊びのアイデア
ゲーム好きの子どもにとって、ミッションやレベルアップ、アイテム収集といった要素は非常に魅力的です。
これらの要素を運動に取り入れることで、子どもは遊び感覚で体を動かし、運動不足の解消につながります。
宝探しゲームで全身運動
 宝探しゲームは、子どもの探求心を刺激しながら全身を効率的に動かせる優れた運動遊びです。
宝探しゲームは、子どもの探求心を刺激しながら全身を効率的に動かせる優れた運動遊びです。
家の中や庭、公園など、場所を選ばずに実践できます。
事前に「宝の地図」を作成し、そこに隠された「宝物」(おもちゃやちょっとしたお菓子、メッセージなど)を探すミッションを与えましょう。
地図には、宝の場所だけでなく、特定の運動を促す指示を盛り込むのがポイントです。
運動の指示例 | 期待できる効果 |
|---|---|
「〇〇まで走る」➡ | 〇持久力 ○瞬発力 |
「階段を〇段 カエル跳びで上る」➡ | 〇脚力 ○体幹 |
「片足立ちで 〇秒キープ」➡ | 〇バランス感覚 ○集中力 |
「〇〇の下を ハイハイでくぐる」➡ | 〇全身運動 ○柔軟性 |
「〇〇をジャンプして 乗り越える」➡ | 〇跳躍力 ○脚力 |
宝探しを通して、子どもは走る、跳ぶ、かがむ、登る、くぐるなど、多様な動きを自然と行い、全身運動を促進します。
宝を見つけた時の達成感は、次の運動へのモチベーションにもつながるでしょう。
難易度を調整することで、飽きずに長く楽しめます。
アスレチックごっこで体幹を鍛える

家の中にあるクッションや椅子、布団、段ボールなどを活用して、オリジナルのアスレチックコースを作る「アスレチックごっこ」もおすすめです。
公園の遊具をアスレチックに見立てて遊ぶのも良いでしょう。
体幹を鍛え、バランス感覚や運動能力を高めるのに非常に効果的です。
例えば、以下のようなコース設定が考えられます。
- クッションを並べて「不安定な橋」に見立て、落ちないように渡る。
- 椅子を障害物に見立て、乗り越えたり、くぐったりする。
- 布団や毛布をトンネルのようにして、四つん這いで進む。
- 平均台に見立てた板の上をバランスを取りながら歩く。
- 壁に貼った的にボールを当てる、など。
それぞれのセクションに「〇秒以内にクリア」「〇回ジャンプしてから次へ」といったミッションを加えることで、さらにゲーム性を高めることができます。
親が一緒に挑戦したり、タイムを計って記録更新を目指したりすると、子どもの競争心や挑戦意欲も刺激され、遊びながら自然と体幹が鍛えられ、運動能力が向上します。
安全には十分に配慮し、見守りながら行いましょう。
➁競争ではなく「協力」で楽しむ運動

運動と聞くと、つい競争をイメージしがちですが、すべての競争が子どもにとって良い刺激になるとは限りません。
特に競争が苦手な子どもや、失敗を恐れてしまう子どもには、「協力」をテーマにした運動遊びが非常に効果的です。
みんなで力を合わせることで得られる達成感は、競争とは異なる喜びや充実感をもたらします。
具体的なアイデアとしては、以下のようなものがあります。
- 親子二人三脚:親と子どもが足を結び、協力してゴールを目指します。呼吸を合わせることで、協調性が育まれます。
- ボール運びリレー:複数の親子や子どもたちでチームを作り、大きなボールを落とさないように協力して運ぶリレー。速さよりも、いかに協力してボールを繋ぐかに焦点を当てます。
- 協力鬼ごっこ:鬼が複数人いて、協力してターゲットを捕まえる、あるいは逃げる側が協力して鬼から逃げ切るなど、チームプレイを意識した鬼ごっこ。
- 共同での障害物クリア:親子で協力して、大きな段ボールを運んだり、複雑な障害物を乗り越えたりするミッション。
これらの遊びは、子どもが「自分だけが頑張る」のではなく、「みんなで成功する」という喜びを体験できます。
失敗しても責められることがなく、お互いを励まし合うことで、運動への苦手意識を克服し、ポジティブな気持ちで体を動かす習慣を育むことができます。
また、コミュニケーション能力や協調性も自然と養われるでしょう。
【親が実践できる意外な秘訣➁】 ゲームと運動のバランスを見つける方法
ゲームに夢中な子どもにとって、いきなりゲーム時間をゼロにするのは現実的ではありません。
大切なのは、ゲームを完全に禁止するのではなく、ゲームと運動の間に健康的なバランスを見つけることです。
ここでは、親が実践できる具体的な方法を提案します。
①スクリーンタイムのルール作りと運動時間の設定

子どもが自ら運動する習慣を身につけるためには、ゲーム時間の管理が不可欠です。
しかし、一方的にルールを押し付けるのではなく、子どもと一緒に話し合い、納得できる形でルールを設定することが成功の鍵となります。
親子で協力して、デジタルデバイスとの健康的な付き合い方を見つけましょう。
ルール設定の ポイント | 具体的な実践例 |
|---|---|
子どもと 一緒に決める | なぜゲームばかりではいけないのか、 運動がなぜ大切なのかを、 子どもの目線に合わせて 丁寧に説明します。 その上で、 「一日〇時間まで」 「宿題が終わってから」など、 子どもが納得できる時間や ルールを話し合い、 合意形成を目指しましょう。 |
時間を 可視化する | キッチンタイマーやアプリ、 ホワイトボードなどを活用して、 ゲーム時間と 運動時間を明確にします。 視覚的に「あと〇分」や 「今日は〇分運動した」と わかるようにすることで、 子ども自身が時間を 意識しやすくなります。 |
運動時間を 先に設定する | 「ゲームをする前に30分外で遊ぶ」 「〇時になったら 家族でストレッチの時間」など、 運動を優先する習慣をつけます。 ゲームが始まる前に 体を動かすことで、 自然と運動が 生活の一部になります。 |
小さな目標から 始める | 最初から完璧を 目指す必要はありません。 「今日は10分だけ外で遊ぶ」 「ゲームの合間に簡単なストレッチをする」など、 無理のない範囲で 小さな目標を設定し、 達成感を積み重ねることが重要です。 |
ルールを 守れたら 褒める | 設定したルールを守れたら、 「よくできたね!」 「約束を守れてすごい!」 と具体的に褒めましょう。 場合によっては、 少しゲーム時間を延長したり、 子どもの好きなことをする時間を 設けたりするなど、 小さなご褒美を 用意するのも効果的です。 |
これらのルールは一度決めたら終わりではなく、子どもの成長や状況に合わせて柔軟に見直すことも大切です。
親子で定期的に話し合い、より良いバランスを探していくプロセス自体が、子どもの自己管理能力を育むことにも繋がります。
➁ゲームの休憩時間にできる簡単運動
長時間ゲームに集中していると、子どもは同じ姿勢で座りっぱなしになりがちです。
これは集中力の低下や体の凝り、血行不良を引き起こすだけでなく、将来的な健康問題にも繋がりかねません。
ゲームの合間に意識的に体を動かす時間を取り入れることで、心身のリフレッシュと健康維持を図りましょう。
ストレッチや軽い体操で体をほぐす

ゲームの休憩時間にできる最も手軽な運動の一つが、ストレッチや軽い体操です。
座ったままやその場でできる簡単な動きを取り入れることで、固まった体をほぐし、血行を促進し、集中力を再び高めることができます。
運動名 | 方法とポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
伸びの運動 | 椅子に座ったまま、 または立ち上がって、 両手を組み天井に 向かってゆっくりと伸ばします。 背中を丸めず、全身を大きく 伸ばすことを意識しましょう。 | 全身の血行促進、 リフレッシュ、 集中力アップ、 姿勢改善 |
首回し 肩回し | ゆっくりと首を左右に回したり、 肩を大きく前後に回したりします。 特に猫背になりがちな姿勢を改善し、 肩こりや目の疲れを 和らげるのに効果的です。 | 首・肩の凝り解消、 血行促進、 リラックス効果 |
足首回し | 座ったまま、片足ずつ足首を ゆっくりと大きく回します。 足のむくみや冷えの改善にも繋がり、 長時間の座りっぱなしに よる疲労を軽減します。 | 足の疲労回復、 血行促進、 むくみ改善 |
軽いスクワット | 椅子から立ち上がるように、 膝を軽く曲げて腰を落とします。 太ももの筋肉を意識して、 無理のない範囲で数回繰り返します。 | 下半身の 血行促進、 筋力維持、 代謝アップ |
これらの運動は、それぞれ1分程度でも効果があります。
ゲームのロード時間や、休憩に入るタイミングなど、短い時間を見つけて習慣化することが大切です。
親子で一緒にやってみるのも良いでしょう。
縄跳びやボール遊びでリフレッシュ

よりアクティブに体を動かしたい場合は、縄跳びや簡単なボール遊びもおすすめです。
これらは短時間で心肺機能を高め、気分転換にもなります。
外に出るのが難しい場合は、室内用の柔らかいボールや、スペースをあまり取らない縄跳び(エア縄跳びなど)を活用するのも良いでしょう。
- 縄跳び縄跳びは、全身運動として非常に効果的です。短時間で心拍数を上げ、心肺機能を鍛えることができます。連続跳びや駆け足跳び、片足跳びなど、様々な跳び方に挑戦することで、飽きずに続けられます。目標回数を決めて挑戦するのも良いでしょう。
- ボール遊び壁当てやドリブル練習、キャッチボールなど、ボールを使った遊びは、瞬発力や協調性、集中力を養います。公園や庭がなくても、室内用の柔らかいボールを使えば、家具を傷つける心配なく安全に楽しめます。親子で簡単なパス交換をするだけでも、良い運動になります。
これらの運動も、ゲームの合間の休憩時間に「ちょっとだけ外で縄跳びしようか」「ボールで壁打ちしてみない?」と誘ってみるのがポイントです。
無理強いせず、あくまで「リフレッシュ」や「気分転換」として提案することで、子どもも受け入れやすくなります。
【親が実践できる意外な秘訣3】 親子で楽しむ運動で子どもも運動好きに
子どもが運動を好きになる最も効果的な方法の一つは、親自身が運動を楽しむ姿を見せ、一緒に体を動かすことです。
親が運動を「楽しいもの」として捉え、積極的に実践することで、子どもも自然と運動に興味を持ち、前向きに取り組むようになります。
親子で一緒に運動することは、子どもの運動能力向上だけでなく、親子のコミュニケーションを深め、絆を育む貴重な時間にもなります。
①親が楽しむ姿を見せることの重要性

子どもは親の背中を見て育ちます。
親が運動を義務としてではなく、心から楽しんでいる姿を見せることは、子どもにとって何よりのモチベーションとなります。
例えば、親がリビングでストレッチをしているのを見たり、公園で楽しそうに走っている姿を見たりすることで、子どもは「運動って楽しそう」「私もやってみたい」と感じるようになります。
強制するのではなく、親が運動を生活の一部として自然に楽しむ姿勢を示すことが、子どもの運動習慣形成への第一歩です。
また、親子で一緒に体を動かすことで、子どもは「一人でやるのはつまらない」と感じる運動も、「親と一緒なら楽しい」と感じるようになります。
親が子どものレベルに合わせて遊び方を工夫し、時には負けてあげるなど、子どもが成功体験を積み重ねられるようにサポートすることも大切です。
これにより、子どもは運動に対する苦手意識を克服し、自信を持って体を動かせるようになります。
➁家の中でもできる親子運動の具体例
天候に左右されず、手軽に始められるのが家の中での親子運動です。
特別な道具がなくても、工夫次第で全身を使った楽しい運動ができます。
運動を「遊び」として捉えることで、子どもは抵抗なく体を動かすことに夢中になるでしょう。
室内アスレチックで運動不足解消

家の中にあるクッションや座布団、毛布、段ボールなどを活用して、オリジナルのアスレチックコースを作りましょう。
障害物を乗り越えたり、くぐったり、バランスを取りながら進んだりする遊びは、子どもの全身運動になり、体幹やバランス感覚を養うのに最適です。
- クッションジャンプ:床にクッションを並べ、その上をジャンプして進みます。
- トンネルくぐり:椅子と毛布でトンネルを作り、ハイハイや腹ばいでくぐり抜けます。
- 一本橋渡り:タオルやひもを床に置き、その上を落ちないようにゆっくり歩きます。
- 障害物競争:上記の要素を組み合わせ、スタートからゴールまでのタイムを競うなど、ゲーム性を持たせるとさらに盛り上がります。
安全には十分に配慮し、家具にぶつからないようスペースを確保しましょう。
親も一緒に挑戦することで、子どもの笑顔がさらに増えるはずです。
ダンスやヨガでリラックス運動

音楽に合わせて体を動かすダンスや、呼吸とポーズで心身を整えるヨガも、室内で手軽にできる親子運動です。
運動が苦手な子どもでも、楽しみながら体を動かすことができます。
- 親子ダンス:子どもの好きなアニメの主題歌や童謡、J-POPなど、ノリの良い音楽をかけて自由に踊りましょう。YouTubeなどには、親子で楽しめるダンス動画もたくさんあります。振り付けを真似するだけでなく、オリジナルのダンスを創作するのも楽しいです。リズム感や表現力を育むだけでなく、全身運動にもなります。
- 親子ヨガ:子ども向けの簡単なヨガポーズを取り入れてみましょう。「犬のポーズ」「猫のポーズ」「木のポーズ」など、動物や自然をモチーフにしたポーズは、子どもにも親しみやすいです。深い呼吸を意識しながら、ゆっくりと体を伸ばすことで、柔軟性が向上し、集中力も養われます。親子で一緒にリラックスできる時間にもなります。
どちらも、運動後の爽快感や達成感を親子で共有することで、運動に対するポジティブな感情を育むことができます。
➂公園や広場で楽しめる外遊びの提案

外に出て体を動かすことは、運動能力の向上だけでなく、太陽の光を浴びることで心身のリフレッシュにも繋がります。
公園や広場は、子どもがのびのびと体を動かすのに最適な場所です。
ここでは、親子で一緒に楽しめる外遊びのアイデアを提案します。
遊び | 期待できる効果 | 準備物 (簡単なもの) |
|---|---|---|
鬼ごっこ かくれんぼ | ・全身運動 ・瞬発力 ・持久力 ・状況判断能力 ・戦略的思考 | 不要 |
縄跳び | ・全身運動 ・リズム感 ・跳躍力 ・持久力 ・集中力 | 縄跳び |
ボール遊び (キャッチボール、 ドッジボール) | ・投げる ・捕る能力、 ・目と手の協調性 ・空間認識能力 | 柔らかいボール |
シャボン玉遊び | ・体を動かすきっかけ ・リラックス効果 ・創造性 | シャボン玉液 吹き棒 |
公園の遊具遊び | ・全身運動 ・バランス感覚 ・筋力 ・柔軟性 ・冒険心 | 不要 |
これらの外遊びは、子どもが自然の中で五感を使い、のびのびと体を動かす絶好の機会です。
親も童心に帰って一緒に楽しむことで、子どもの運動に対するハードルを下げ、運動を「楽しい体験」として記憶させることができます。
運動習慣を無理なく続けるためのヒント
子どもの運動習慣を定着させるためには、一過性の取り組みで終わらせず、日々の生活に自然と溶け込ませることが重要です。
ここでは、無理なく運動を続けられるよう、親ができる具体的なサポート方法をご紹介します。
①子どもの「好き」を見つけるサポート

子どもが自ら運動に取り組むようになるためには、何よりも「楽しい」「好き」という気持ちが大切です。
親が一方的に運動を押し付けるのではなく、子どもの興味や関心に寄り添い、その「好き」を見つける手助けをしましょう。
- 多様な運動を体験させる: 球技、水泳、ダンス、武道、体操など、様々な種類の運動を経験する機会を提供しましょう。子ども自身が「これなら続けられそう」「もっとやってみたい」と感じるものが見つかるかもしれません。
- 興味の芽を逃さない: 子どもがテレビや漫画で特定のスポーツに興味を示したり、公園で特定の遊具に夢中になったりしたら、それは「好き」のサインかもしれません。その興味を深掘りできるような声かけや、体験の機会を与えてみましょう。
- 運動以外の「好き」から繋げる: ゲームやアニメのキャラクターになりきって体を動かす、好きな音楽に合わせて踊るなど、子どもの既存の「好き」と運動を結びつけることで、運動への抵抗感を減らすことができます。
- 結果よりもプロセスを褒める: 上手くできたかどうかだけでなく、「挑戦したこと」「楽しんでいる姿」「頑張ったこと」を具体的に褒めることで、子どもの自己肯定感を高め、運動への意欲を維持させます。
➁継続のためのご褒美や目標設定

運動を習慣化するためには、モチベーションを維持する仕組みも有効です。
ただし、ご褒美は物を与えるだけでなく、達成感や次のステップにつながるものにすることが大切です。
また、目標設定は子どものレベルに合わせ、小さく具体的なものから始めましょう。
項目 | 具体的な方法 | ポイント |
|---|---|---|
ご褒美 |
|
|
目標設定 |
|
|
ご褒美や目標設定は、あくまで運動を始めるきっかけや継続のサポートであり、最終的には運動そのものの楽しさや、体が動くことの心地よさを子ども自身が感じられるようになることが理想です。
周囲の環境を味方につける方法

子どもの運動習慣は、家庭内だけでなく、周囲の環境によっても大きく左右されます。
運動しやすい環境を整え、周囲の人々や地域のリソースを積極的に活用しましょう。
- 家庭内の環境整備:
- リビングにバランスボールやストレッチマットを置くなど、いつでも手軽に体を動かせるスペースを作る。
- 縄跳び、ボール、フリスビーなど、すぐに使える運動グッズを手の届く場所に置いておく。
- テレビを見ながらできる簡単なストレッチや体操を家族で実践する。
- 地域のリソースを活用:
- 近くの公園の遊具を積極的に利用する。
- 地域のスポーツクラブ、体操教室、スイミングスクールなどの情報を集め、子どもの興味に合うものがあれば体験させてみる。
- 自治体が開催する親子向けのスポーツイベントやレクリエーションに参加する。
- 仲間との繋がりを促進:
- 友達と一緒に遊ぶ約束をする際に、公園や広場で体を動かす遊びを提案するよう促す。
- 習い事や地域の活動を通じて、一緒に運動できる仲間を見つけるサポートをする。
- 親自身が、子どもの友達の親と協力し、合同で外遊びの機会を作ることも有効です。
- 親自身がロールモデルに:
- 親が楽しそうに運動する姿を見せることは、子どもにとって何よりの刺激になります。一緒に散歩する、自転車に乗る、公園で遊ぶなど、親子で体を動かす時間を増やすことが大切です。
- 「運動は楽しいもの」「体を動かすことは気持ちいい」というポジティブなメッセージを日頃から伝えるように心がけましょう。
まとめ
ゲームに夢中な子どもが増える現代において、運動不足は心身の成長に大きな影響を与えかねません。
しかし、強制するのではなく、運動を「遊び」として捉え、親自身が楽しみながら子どもを巻き込むことが、運動嫌いを克服する鍵となります。
宝探しやアスレチックごっこ、室内でのダンスなど、ゲーム要素を取り入れたり、親子で協力する運動は効果的です。
スクリーンタイムのルールを設け、休憩時間に軽い運動を取り入れることも大切。
親が楽しむ姿を見せ、小さな成功体験を積み重ね、子どもの「好き」を見つけるサポートをすることで、無理なく運動習慣を継続させ、子どもの健やかな成長を促しましょう。