
子育てと仕事の両立に疲れたワーママ必見!家族も自分も笑顔になる時間の使い方
子育てと仕事の両立に疲れを感じているワーママのあなたへ。
その疲労は、時間不足だけでなく「完璧主義」や「頼れない」環境が原因かもしれません。
この記事では、家族も自分も笑顔で過ごせるようになるため、具体的な時間管理術、夫や外部サービスとの連携術、そして何よりも大切なセルフケアの方法を詳しく解説します。
もう無理しなくて大丈夫。
あなたらしい「笑顔の両立」を見つける道筋が、きっと見つかります。
目次[非表示]
- 1.子育てと仕事の両立に疲れたあなたへ まずは共感から
- 2.なぜ子育てと仕事の両立で疲れてしまうのか? 原因を深掘り
- 3.家族も自分も笑顔になる時間の使い方 時間管理術の基本
- 3.1.〇タスクを見える化する時間管理術
- 3.1.1.①見える化で家事と育児の負担を明確に
- 3.1.2.➁一日のタイムスケジュールを見直す
- 3.2.〇「やらないこと」を決める勇気 子育てと仕事の優先順位
- 3.3.〇スキマ時間を有効活用するワザ
- 4.子育てと仕事の両立を楽にする 家族や外部との連携術
- 4.1.〇夫やパートナーと協力 子育てと家事の分担を見直す
- 4.1.1.①役割分担を話し合う具体的な方法
- 4.1.2.➁「ありがとう」を伝え合う習慣
- 4.2.〇頼れるものは頼る 外部サービスを賢く利用する
- 4.2.1.①家事代行や宅配サービスで時短を叶える
- 4.2.2.➁保育園や学童 病児保育を上手に活用する
- 4.3.〇実家や友人との関係を良好に保つコツ
- 5.子育てと仕事の両立で疲れた心を癒やす セルフケアの重要性
- 5.1.〇短時間でもOK ワーママのリフレッシュ術
- 5.1.1.①心のゆとりを取り戻すマインドフルネス
- 5.1.2.➁質の良い睡眠を確保する工夫
- 5.2.➂「まあいっか」の精神で自分を許す
- 5.3.④自分を褒める習慣で自己肯定感を高める
- 6.子育てと仕事の両立はマラソン 長期的な視点を持つ
- 7.まとめ
子育てと仕事の両立に疲れたあなたへ まずは共感から
仕事も子育ても、毎日本当にお疲れ様です。
朝から晩まで、仕事に家事に育児にと、休む間もなく走り続けていることと思います。
「子育てと仕事の両立に疲れた」そう検索して、このページにたどり着いたあなたは、きっと今、心身ともに限界に近い状態なのではないでしょうか。
その気持ち、痛いほどよく分かります。
「もう無理」、「全てを投げ出したい」そう感じるのは、あなたがそれだけ真剣に、そして一生懸命に子育てと仕事に向き合ってきた証拠です。
決して、あなたが弱いわけではありません。
あなたは、本当に素晴らしい頑張り屋さんです。
①頑張り屋さんのワーママが抱える悩みとは?

頑張り屋さんのワーママだからこそ、抱え込んでしまう悩みや苦しみがあります。
多くのワーママが共通して感じている、具体的な悩みをいくつかご紹介しましょう。
悩みの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
時間的制約 による疲弊 | 仕事の締め切りに追われながら、 保育園のお迎え時間や子どもの 習い事の時間に常に気を配る日々。 帰宅すれば、休む間もなく 夕食の準備、入浴、寝かしつけと、 自分のための時間は一秒たりともない と感じているかもしれません。 週末も、平日にできなかった 家事や子どもの行事などで埋まり、 心から休まる暇がないと 感じることも少なくありません。 |
精神的・心理的 プレッシャー | 「仕事では成果を出さなければ」 「子育てでは完璧な母親でいたい」 といったプレッシャーが、 常に心にのしかかっている のではないでしょうか。 子どもが熱を出せば仕事に 穴を開けてしまう罪悪感、 仕事が忙しくて子どもと ゆっくり向き合えないこと への自責の念など、 常に板挟みになっている ような感覚に陥りがちです。 |
肉体的疲労と 睡眠不足 | 朝早く起きて家族の準備をし、 夜は子どもが寝てから ようやく家事が終わる。 慢性的な睡眠不足に陥り、 常に体がだるい、 頭が重いといった状態が 続いているかもしれません。 風邪をひいても休む暇もなく、 無理をしてしまい、 体調を崩しやすくなっている と感じることもあるでしょう。 |
孤独感と孤立 | 誰にも本音を打ち明けられず、 一人で悩みを抱え込んでいる と感じていませんか? 夫やパートナーに相談しても 理解してもらえなかったり、 職場の同僚や友人には 弱音を吐きづらかったりして、 孤立感を深めてしまうこともあります。 「みんなはもっとうまくやっているのに」と、 自分だけが苦しんでいるように 感じてしまうこともあるでしょう。 |
これらの悩みは、決してあなただけのものではありません。
多くのワーママが、多かれ少なかれ同じような感情を抱えながら、毎日を必死に過ごしています。
➁「もう限界」そう感じるのはあなただけじゃない
「もう無理」、「全てを放り出してしまいたい」と感じる時、あなたはきっと「自分はダメな母親だ」「仕事も子育ても中途半端だ」と、自分を責めてしまっているかもしれません。
しかし、どうか安心してください。そのように感じるのは、あなただけではありません。
むしろ、「限界」と感じるほど頑張ってきたからこそ、そのサインが出ているのです。
子育てと仕事の両立は、まるでマラソンのように長く、時に過酷な道のりです。
疲労困憊の状態では、心も体も悲鳴を上げて当然です。
あなたは決して一人ではありません。
多くのワーママが、あなたの抱える感情に共感し、理解を示しています。
この章では、まずそのことを心から知っていただきたいと思います。
なぜ子育てと仕事の両立で疲れてしまうのか? 原因を深掘り

子育てと仕事の両立で「疲れた」と感じるのは、単に時間がないからだけではありません。
ワーママが抱える疲労の根源には、物理的な要因だけでなく、精神的な負担や周囲の環境など、複雑な要素が絡み合っています。
ここでは、あなたが疲れを感じる具体的な原因を深掘りし、その正体を明らかにしていきます。
①時間がないだけじゃない ワーママの心と体の疲労の正体

「時間がない」と感じることはもちろん大きな要因ですが、ワーママの疲労はそれだけにとどまりません。
常に複数のタスクを同時にこなし、脳も心も休まる暇がない状態が、見えない疲労として蓄積されていきます。
例えば、仕事中も子どものことが気になり、家に帰れば家事と育児が山積みに。
物理的な労働時間だけでなく、「常に思考が働き続けている」状態が、脳と心を疲弊させているのです。
これは「名もなき家事」や「見えない家事」と呼ばれる、献立を考える、子どもの持ち物を準備する、学校からの連絡に対応するといった、具体的に時間として計上されにくいけれど、精神的な負担が大きいタスクにも言えます。
疲労の種類 | 具体的な状態・例 |
|---|---|
身体的疲労 | 慢性的な睡眠不足、 休日の寝だめでも 回復しないだるさ、 肩こりや頭痛などの 身体症状、 風邪をひきやすいなど 免疫力の低下。 |
精神的疲労 | 常に気が張っている状態、 マルチタスクによる 思考のオーバーロード、 自分の時間がない ことによるストレス、 リフレッシュ不足、 イライラしやすくなる、 集中力の低下、無気力感。 |
こうした疲労が重なることで、「自分だけが頑張っている」という孤独感や、罪悪感を抱えやすくなり、さらに精神的な負担が増大する悪循環に陥ることも少なくありません。
➁「完璧主義」がワーママを追い詰める
多くのワーママは、真面目で責任感が強く、「ちゃんとしなければ」という意識が高い傾向にあります。しかし、この完璧主義が、かえって自分自身を追い詰める原因となることがあります。
仕事では成果を出し、家では完璧な家事をこなし、子どもには愛情をたっぷり注ぐ理想の母親でいたい。
そうした「こうあるべき」という理想像や、周囲からの評価を気にするあまり、自分に過度なプレッシャーをかけてしまうのです。
例えば、部屋が散らかっていると落ち着かない、手抜き料理は許せない、子どもの教育には手を抜きたくない、といった考えは、一つ一つは素晴らしいことですが、すべてを完璧にこなそうとすると、膨大な時間とエネルギーが必要になります。その結果、「もっと頑張らなければ」と自分を追い込み、心身ともに疲弊してしまうのです。
完璧主義は、自分だけでなく、周囲にも高い水準を求めてしまいがちです。パートナーの家事のやり方に不満を感じたり、子どもが期待通りに動かないことにイライラしたりと、人間関係にも影響を及ぼすことがあります。
➂頼れない 環境やパートナーとの関係性
 子育てと仕事の両立において、周囲のサポートを得られるかどうかは、疲労度を大きく左右する要因です。
子育てと仕事の両立において、周囲のサポートを得られるかどうかは、疲労度を大きく左右する要因です。
特に、パートナーとの関係性や、実家・地域社会からの支援が得にくい環境にある場合、ワーママの負担は一層増大します。
夫やパートナーが家事・育児に非協力的であったり、役割分担が明確でなかったりすると、すべての負担がワーママに集中する「ワンオペ育児」の状態に陥りがちです。
コミュニケーション不足や価値観の違いから、疲れていることを理解してもらえない、あるいは協力を求めにくいと感じるケースも少なくありません。
また、実家が遠方で気軽に頼れない、あるいは親が高齢で頼ることが難しい、友人や知人も忙しく助けを求めにくいといった環境も、ワーママを孤立させ、疲労感を増幅させます。
会社での理解や制度の不十分さも、両立を困難にする一因です。
「人に頼るのは申し訳ない」「自分でやった方が早い」といった考えから、助けを求めることをためらってしまうことも、疲労が蓄積する大きな原因となります。
物理的なサポートだけでなく、精神的な支えが得られない状況も、ワーママの心を深く傷つけ、疲弊させてしまうのです。
家族も自分も笑顔になる時間の使い方 時間管理術の基本
子育てと仕事の両立に疲れているワーママにとって、時間の使い方を見直すことは、心にゆとりを取り戻し、家族との時間をより豊かにするための第一歩です。
完璧な時間管理を目指すのではなく、まずは「できること」から始めてみましょう。
〇タスクを見える化する時間管理術

「時間がない」と感じる原因の一つに、自分が抱えているタスクの全体像が見えていないことがあります。
まずは、漠然とした不安を解消するために、タスクを具体的に「見える化」することから始めましょう。
①見える化で家事と育児の負担を明確に
日々こなしている家事や育児のタスクは、意識しないうちに増えていき、「名もなき家事」として認識されていないものも少なくありません。
まずは、どんな小さなことでも、全て書き出してみることから始めましょう。
例えば、以下のようなタスクをリストアップします。
カテゴリー | タスク例 |
|---|---|
家事 | 洗濯、食器洗い、掃除機かけ、 トイレ掃除、お風呂掃除、 ゴミ出し、献立考案、買い物、 食事の準備、片付け、 布団干し、アイロンがけ、 郵便物の確認、日用品の補充 |
育児 | 子どもの送迎(保育園・学童)、 着替え、食事介助、おむつ替え、 寝かしつけ、遊び相手、宿題の確認、 連絡帳記入、習い事の準備、 病院受診、予防接種、 学校・園行事の参加準備 |
自分ごと | 身支度、通勤、仕事、休憩、 睡眠、食事、リフレッシュ、通院 |
これらのタスクを書き出すことで、「これだけ多くのことをこなしているんだ」という自身の頑張りを客観的に認識できます。
同時に、無意識のうちに抱え込んでいた負担が明確になり、「どこを減らせるか」「誰かに頼めるか」を考えるきっかけにもなります。
➁一日のタイムスケジュールを見直す

タスクの見える化ができたら、次はそのタスクが「いつ」「どのくらい」時間を使っているのかを把握するために、一日、または一週間のタイムスケジュールを書き出してみましょう。
理想のスケジュールではなく、まずは現状のリアルな時間の使い方を記録することが重要です。
朝起きてから夜寝るまで、仕事の時間、通勤時間、食事の時間、家事の時間、育児の時間、そして「なんとなく過ごしている時間」も含めて、具体的に書き込んでみてください。
書き出すことで、無意識に費やしている時間や、逆に有効活用できる時間帯が見えてきます。
例えば、朝の準備に予想以上に時間がかかっている、夕食後の片付けに手間取っている、といった具体的な課題を発見できるでしょう。
現状を把握した上で、「本当にその時間にそのタスクが必要か」、「もっと効率的な方法はないか」を検討し、理想のスケジュールに近づけるための改善点を見つけ出していきます。
〇「やらないこと」を決める勇気 子育てと仕事の優先順位

全てのタスクを完璧にこなそうとすることは、ワーママを疲弊させる大きな原因です。
「やらないこと」を決める勇気を持つことは、時間管理において非常に重要です。
書き出したタスクリストを前に、以下の視点で優先順位を付けてみましょう。
- 重要度と緊急度で分類する:
- 重要かつ緊急なこと:すぐに取り組むべき最優先事項(例:子どもの体調不良、仕事の締め切り)
- 重要だが緊急ではないこと:長期的な視点で取り組むべきこと(例:子どもの成長を促す遊び、自己啓発)
- 緊急だが重要ではないこと:他人でもできること、手放せること(例:完璧な部屋の片付け、毎日手の込んだ料理)
- 緊急でも重要でもないこと:やめても問題ないこと(例:SNSの無駄な閲覧、不要な情報収集)
- 「完璧主義」を手放す:「〇〇でなければならない」という思い込みが、自分を追い詰めていることがあります。
- 例えば、「毎日手作りの夕食でなければならない」「家は常にピカピカでなければならない」といった考えは、少し緩めても大丈夫です。
- 「まあいっか」の精神で、7割、8割の出来栄えでもOKと割り切ることで、心の負担が大きく軽減されます。
- 「やらないことリスト」を作る:あえて「やらないこと」をリストアップし、意識的に手放しましょう。例えば、「毎日の床拭きは週に2回にする」「作り置きは無理せず週末だけにする」「子どものおもちゃは完全に片付かなくても寝る前まででOKとする」など、具体的に決めることで、精神的な余裕が生まれます。
〇スキマ時間を有効活用するワザ

ワーママにとって、まとまった時間を確保するのは至難の業です。
そこで重要になるのが、一日の中に散らばる「スキマ時間」をいかに有効活用するかです。
ほんの数分でも、積み重ねれば大きな時間になります。
具体的なスキマ時間の活用例を挙げます。
スキマ時間 | 有効活用例 |
|---|---|
電車・バス での移動中 | メール返信、献立考案、 今日やるタスクの確認、 読書(電子書籍)、 オーディオブックで情報収集 |
子どもが 遊んでいる間 (短時間) | 洗濯物をたたむ、 食器を食洗機に入れる、 保育園の連絡帳記入、 翌日の持ち物準備 |
食事の準備中 (煮込み時間など) | シンク周りの片付け、 翌日のお弁当の下準備、 子どもの宿題チェック |
待ち時間 (病院、銀行など) | スマホで情報収集、 To Doリストの見直し、 家計簿アプリの入力、 短い瞑想 |
朝の身支度中 (数分) | 今日のスケジュールを 頭の中でシミュレーション、 簡単なストレッチ |
スキマ時間でできるタスクは、「短時間で完結するもの」、「移動しながらできるもの」、「思考をあまり必要としないもの」が適しています。
事前に「このスキマ時間にはこれをやる」と決めておくことで、無駄なく時間を使えるようになります。
ただし、全てのスキマ時間を埋めようとすると、かえって疲れてしまうこともあります。
時にはあえて何もしない時間として、ぼーっとしたり、好きな音楽を聴いたりするのも、大切なリフレッシュになります。
自分にとって心地よいバランスを見つけることが重要です。
子育てと仕事の両立を楽にする 家族や外部との連携術
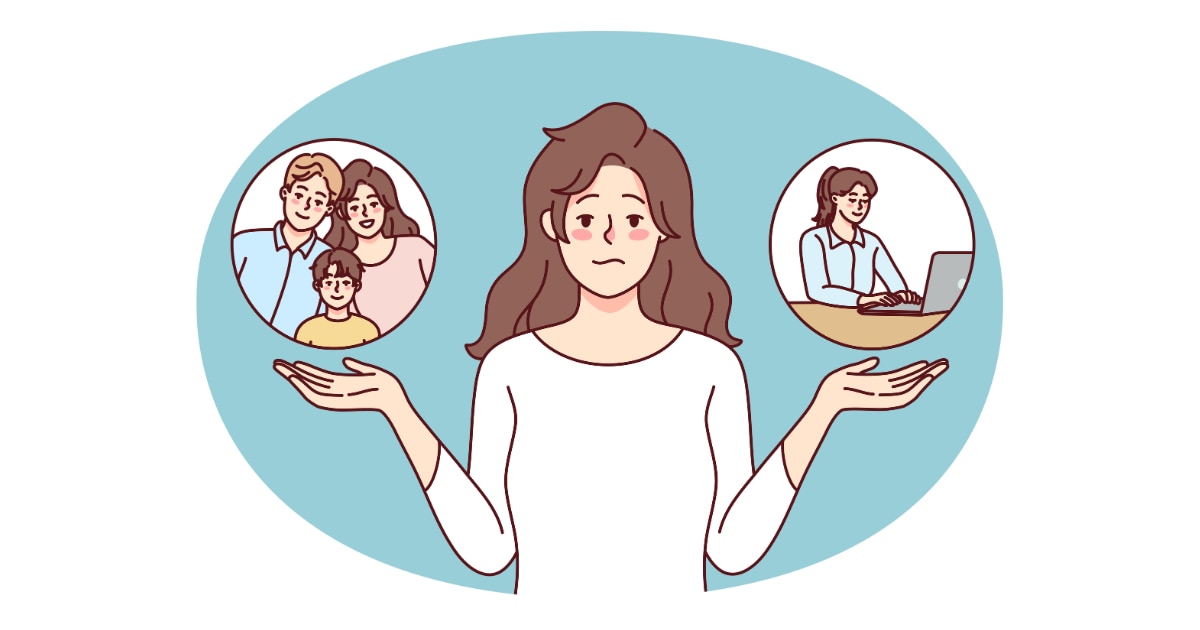
子育てと仕事の両立で疲弊している時、すべてを一人で抱え込む必要はありません。
むしろ、家族や外部の力を上手に借りることが、心と体のゆとりを取り戻し、持続可能な両立を実現するための鍵となります。
この章では、周囲との連携を強化し、あなたの負担を軽減するための具体的な方法をご紹介します。
〇夫やパートナーと協力 子育てと家事の分担を見直す
子育てと家事の負担が一方に偏っていると、疲労は蓄積する一方です。
夫やパートナーとの協力体制を築くことは、両立の疲労を軽減する上で最も重要なステップの一つと言えるでしょう。
①役割分担を話し合う具体的な方法
家事や育児の分担を見直す際は、感情的にならず、具体的なタスクを洗い出すことから始めましょう。
現状の課題を共有し、お互いの得意なことや苦手なことを考慮しながら、無理のない範囲で役割を再構築することが大切です。
項目 | 担当者 (例:夫) | 担当者 (例:妻) | 備考 |
|---|---|---|---|
朝食準備 | 〇 | 前日の夜に準備 できるものはしておく | |
保育園・幼稚園送迎 | 〇(行き) | 〇(帰り) | 週ごとに交代制も検討 |
夕食準備 | 〇 | ミールキットや 作り置きも活用 | |
お風呂 | 〇 | 子どもと一緒に入る | |
寝かしつけ | 〇 | 絵本読み聞かせなど | |
洗濯 | 〇 | 畳むのは週末にまとめて | |
ゴミ出し | 〇 | 朝の出勤時に | |
買い物 | 〇 | ネットスーパーも活用 | |
週末の掃除 | 〇 | 〇 | 役割分担して 手早く終わらせる |
上記のように、家事・育児のタスクを具体的にリストアップし、誰が何を担当するかを明確にすることで、負担の偏りが見えやすくなります。
また、一度決めたら終わりではなく、子どもの成長やライフステージの変化に合わせて、定期的に見直す機会を設けることも重要です。
➁「ありがとう」を伝え合う習慣

役割分担をしても、お互いの努力が報われないと感じると、不満が募りやすくなります。
些細なことでも「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え合う習慣は、夫婦関係の潤滑油となり、お互いのモチベーションを高める効果があります。
「洗濯ありがとう」「子どもを寝かしつけてくれて助かったよ」など、具体的に感謝を伝えることで、相手は「自分の貢献が認められている」と感じ、次への協力意欲へと繋がります。
〇頼れるものは頼る 外部サービスを賢く利用する
「お金をかけるのはもったいない」と感じるかもしれませんが、外部サービスは時間と心のゆとりを買うための有効な投資です。
上手に活用することで、あなたの負担を大幅に軽減し、家族との時間や自分のための時間を確保できるようになります。
①家事代行や宅配サービスで時短を叶える
日々の家事や食事の準備は、ワーママにとって大きな負担です。
これらのタスクを外部サービスに任せることで、貴重な時間を生み出し、精神的な負担も軽減できます。
- 家事代行サービス: 掃除、洗濯、料理、買い物、整理収納など、多岐にわたる家事をプロに任せることができます。週に一度や月に数回など、利用頻度や内容をライフスタイルに合わせて選べます。特に、水回りの掃除や普段手が回らない場所の清掃など、労力のかかる家事を依頼すると、効果を実感しやすいでしょう。
- 食材宅配サービス・ミールキット: 買い物に行く手間を省き、献立を考える負担も軽減できます。新鮮な食材が自宅に届くサービスや、下ごしらえ済みの食材とレシピがセットになったミールキットを利用すれば、調理時間を大幅に短縮できます。
- ネットスーパー: 重い飲み物やかさばる日用品も自宅まで届けてくれるため、子連れでの買い物の負担がなくなります。計画的に利用することで、無駄な買い物を減らす効果も期待できます。
➁保育園や学童 病児保育を上手に活用する

子どもの預け先は、ワーママが安心して働くための基盤です。既存のサービスを最大限に活用し、いざという時の備えも万全にしておきましょう。
- 保育園・幼稚園の延長保育や一時保育: 通常の保育時間では間に合わない場合や、急な残業、リフレッシュしたい時などに活用できます。事前に登録や予約が必要な場合が多いため、早めに情報を集めておきましょう。
- 学童保育: 小学校入学後も、放課後の子どもの居場所として学童保育を利用できます。共働き家庭の強い味方となるでしょう。
- 病児保育・病後児保育: 子どもが病気で保育園や学校に行けない時、仕事が休めない場合に利用できる施設です。事前の登録が必要な場合が多く、利用条件や料金は施設によって異なりますが、急な発熱時などには非常に心強い存在となります。自宅での訪問型病児保育サービスも増えてきています。
〇実家や友人との関係を良好に保つコツ

家族や外部サービスだけでなく、実家や友人といった身近な存在も、ワーママの強力なサポートになり得ます。
精神的な支えや、いざという時の助けを求めるためにも、日頃から良好な関係を築いておくことが大切です。
- 実家との連携: 頼れる距離に実家がある場合、子どもの送迎や短時間の預かり、食事の差し入れなど、様々な面で助けてもらえる可能性があります。ただし、頼りすぎは禁物です。感謝の気持ちを常に伝え、無理のない範囲でお願いすることが重要です。定期的に顔を見せたり、お礼の品を贈ったりと、日頃からのコミュニケーションを大切にしましょう。
- 友人との情報交換と助け合い: 同じ子育て中の友人やママ友は、共感し合える貴重な存在です。子育ての悩みや仕事の愚痴を聞いてもらったり、情報交換をしたりすることで、精神的な負担が軽くなります。また、お互い様精神で、急なピンチの時に助け合える関係性を築いておくと、いざという時に心強いでしょう。
子育てと仕事の両立で疲れた心を癒やす セルフケアの重要性
子育てと仕事の両立に日々奮闘するワーママのあなたは、知らず知らずのうちに自分の心と体を後回しにしてしまいがちです。
しかし、疲れ切った状態では、家族に笑顔で接することも、仕事でパフォーマンスを発揮することも難しくなってしまいます。
セルフケアは、決して贅沢なことではなく、ワーママが笑顔で持続的に両立していくために不可欠な投資なのです。
まずは、自分自身を大切にする時間を意識的に作り、心のゆとりを取り戻すことから始めましょう。
〇短時間でもOK ワーママのリフレッシュ術
「時間がない」と感じるワーママでも、ほんの数分、数十分のスキマ時間でも実践できるリフレッシュ術はたくさんあります。
大切なのは、完璧を目指さず、今の自分にできることから始めることです。
①心のゆとりを取り戻すマインドフルネス

心がざわついたり、イライラしたりする時は、意識的に「今、ここ」に集中するマインドフルネスを取り入れてみましょう。
数分間の実践でも、心の状態を落ち着かせ、ゆとりを取り戻す助けになります。
実践方法 | 具体的な内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
呼吸に意識を向ける | 椅子に座り、目を閉じて、 自分の呼吸の音や感覚に集中します。 吸う息、吐く息を数えたり、 お腹の動きを感じたり するだけでもOKです。 | 心を落ち着かせ、 集中力を高める |
五感を使う | 温かい飲み物をゆっくり味わう、 好きなアロマを焚く、 お気に入りの音楽を聴く、 自然の音に耳を傾けるなど、 一つの感覚に集中します。 | 気分転換になり、 リラックスを促す |
ボディスキャン | 仰向けになり、 足のつま先から 頭のてっぺんまで、 体の各部位の感覚に 意識を向けます。 痛みや緊張があれば、 呼吸とともに手放す イメージを持ちます。 | 体の緊張をほぐし、 疲労感を軽減する |
これらの方法は、通勤電車の中や、子どもが寝た後の数分間でも実践可能です。
継続することで、ストレス耐性が高まり、心の回復力が向上します。
➁質の良い睡眠を確保する工夫

睡眠は、心身の疲労回復に最も重要な要素です。
睡眠時間が十分に取れない日でも、質の良い睡眠を意識することで、翌日のパフォーマンスは大きく変わります。
実践方法 | 具体的な内容 | ポイント |
|---|---|---|
寝る前の環境 を整える | 寝室を暗くし、適度な室温 (20℃前後)に保ちます。 寝る1時間前からは、 スマートフォンや パソコンの使用を控え、 ブルーライトを避けます。 | リラックスできる 空間作りが重要 |
入浴で 体を温める | 寝る90分~2時間前を 目安に、38~40℃程度 のぬるめのお湯に ゆっくり浸かります。 体の深部体温が上がり、 その後下がることで 自然な眠気を誘います。 | 体温の変動を 利用して入眠を スムーズに |
カフェインや アルコールを 控える | 夕食後や寝る前は、 カフェインを含む飲み物 (コーヒー、紅茶、 エナジードリンクなど)や アルコールの 摂取を避けます。 | 睡眠の質を 低下させる 原因を排除 |
軽いストレッチや 深呼吸 | 寝る前に、ベッドの上で できる簡単なストレッチや、 腹式呼吸を数回行うことで、 心身をリラックスさせ、 入眠しやすくします。 | 心身の緊張を 解き放つ |
完璧な睡眠を目指すのではなく、今の状況でできる最善を尽くすという意識が大切です。
➂「まあいっか」の精神で自分を許す
子育てと仕事の両立で疲れてしまう大きな原因の一つに、「完璧主義」があります。
家事も育児も仕事も、すべてにおいて完璧であろうとすることで、自分自身を追い詰めていませんか?
「まあいっか」という言葉には、自分を許し、不完全さを受け入れる大きな力があります。
食器が洗い残っていても、部屋が少し散らかっていても、子どもの宿題を完璧に見てあげられなくても、「今日はここまででOK」「また明日頑張ればいい」と自分に言い聞かせてみましょう。
この心のゆとりが、無駄なストレスを減らし、心に平穏をもたらします。
「完璧な母親」や「完璧なワーママ」は存在しません。
時には手抜きをしたり、誰かに頼ったりすることも、両立を続ける上で必要なスキルです。
自分自身に優しくなることで、心に余裕が生まれ、家族にも自然と笑顔で接することができるようになります。
④自分を褒める習慣で自己肯定感を高める
忙しい日々の中で、私たちはつい自分の至らなかった点ばかりに目を向けがちです。
しかし、子育てと仕事を両立しているあなたは、それだけで十分に素晴らしい存在です。
どんな小さなことでもいいので、毎日自分を褒める習慣を取り入れてみましょう。
- 朝、時間通りに起きられた。
- 子どもの話に耳を傾けられた。
- 疲れていても、夕食を作った。
- 職場で一つ仕事をやり遂げた。
- お風呂に入れた。
このように、当たり前だと思っていることでも、一つ一つを意識して「よく頑張ったね」「えらいね」と自分に語りかけることで、自己肯定感は少しずつ高まっていきます。
自己肯定感が高まると、ネガティブな感情に囚われにくくなり、困難な状況にも前向きに対処できるようになります。
寝る前に、今日一日で自分が頑張ったことや、良かったことを3つ書き出す「感謝日記」や「褒め日記」もおすすめです。
自分自身の価値を認め、大切にする習慣が、疲れた心を癒やし、明日への活力を生み出します。
子育てと仕事の両立はマラソン 長期的な視点を持つ
子育てと仕事の両立は、時に息切れしそうになるほどの長距離走に例えられます。
目の前のタスクをこなすことに精一杯で、ゴールが見えなくなることもあるでしょう。
しかし、これは一時的なものではなく、子どもの成長や自身のキャリアパスに合わせて、常に形を変えながら続いていく道のりです。
今、あなたが感じている疲労や限界は、決してあなただけのものではありません。
このマラソンを走り抜くためには、短期的な視点だけでなく、長期的な視点を持ってペース配分を考え、自分を労わる時間を作ることが不可欠です。
完璧を目指すのではなく、しなやかに、そして柔軟に対応していく心の準備が、この長い道のりを乗り越える鍵となります。
①完璧なワーママはいない 諦める勇気も大切

「子育ても仕事も完璧にこなしたい」「家事も手抜きなくやりたい」そう考えるあなたは、とても真面目で責任感が強い方でしょう。
しかし、その完璧主義が、知らず知らずのうちにあなた自身を追い詰めている可能性もあります。
子育てと仕事の両立において、完璧なワーママは存在しません。
時には、「まあいっか」と割り切る勇気や、諦める勇気を持つことが、あなたの心と体を守る上で非常に重要です。
例えば、以下のようなことは、決して手を抜いているわけではなく、長期的な視点でより良いバランスを見つけるための「戦略」だと捉えてみましょう。
- 手作りにこだわりすぎず、レトルト食品や惣菜、冷凍食品を上手に活用する。
- 掃除は毎日完璧にせず、気になった時にサッと済ませる程度にする。
- 子どもの持ち物や洋服は、最低限で済ませ、完璧に揃えようとしない。
- 趣味や習い事を一旦お休みする期間を作る。
- 仕事で無理な残業を断る勇気を持つ。
大切なのは、自分自身が笑顔でいられること。
あなたの笑顔は、家族にとって何よりの栄養です。
すべてを抱え込もうとせず、時には「これは諦める」と決断することで、本当に大切なことにエネルギーを注ぐことができるようになります。
➁子どもの成長に合わせて変化する両立の形
子育てと仕事の両立の形は、子どもの成長段階によって大きく変化します。
乳幼児期は身体的なケアの負担が大きく、手がかかる時期ですが、小学校に上がると学童保育や習い事など、外部サービスとの連携が重要になります。
思春期には精神的なサポートが求められるようになるでしょう。
それぞれのステージで求められる親の役割や、両立のポイントは異なります。
常に同じやり方で乗り切ろうとするのではなく、子どもの成長に合わせて柔軟に、両立の形をアップデートしていく視点が大切です。
子どもの成長段階 | 両立で求められること(一例) | 両立のポイント |
|---|---|---|
乳幼児期 (0~2歳) | 授乳・離乳食、 おむつ交換、夜泣き対応 など身体的ケアの負担大 |
|
幼児期 (3~6歳) | 集団生活への適応、 遊びを通じた学び、 病気の頻発 |
|
小学校低学年 (7~9歳) | 学童保育、宿題、 習い事、友達関係 |
|
小学校 高学年~ 中学生 (10~15歳) | 学習習慣の確立、 思春期の心のケア、 部活動・塾 |
|
上記はあくまで一例であり、子どもの個性や家庭の状況によって最適な形は異なります。大切なのは、「今」の子どもと自分にとって何が最善かを常に考え、柔軟に対応していくことです。
➂未来の自分を想像してポジティブに

今、あなたが感じている「疲れた」という気持ちは、決してネガティブなものではありません。
それは、あなたがそれだけ頑張っている証拠であり、「このままではいけない」という心からのSOSでもあります。
両立に疲れた時こそ、少し立ち止まって、未来の自分を想像してみてください。
子どもが成長し、手がかからなくなった時、あなたはどんな自分になっていたいでしょうか。
仕事でどんな目標を達成したいでしょうか。そして、家族とどんな時間を過ごしたいでしょうか。
具体的な未来を想像することで、今の困難が永遠に続くわけではないこと、そしてこの経験が未来の自分を強くしてくれることを実感できるはずです。
疲れた時は、頑張りすぎた自分を認め、「よく頑張ったね」と褒めてあげましょう。
そして、「この状況は一時的なもの」、「きっと乗り越えられる」と、ポジティブな言葉を自分に語りかける習慣を持つことが大切です。
子育てと仕事の両立は、確かに大変な道のりです。
しかし、この経験を通して得られる学びや成長、そして家族との絆は、何物にも代えがたい宝物となるでしょう。
未来の自分を信じ、「今の頑張りは、きっと報われる」という希望を胸に、あなたらしいペースでこのマラソンを走り続けてください。
まとめ
子育てと仕事の両立で疲れてしまうのは、時間不足だけでなく、完璧主義や頼れない環境が背景にあることが多いです。
一人で抱え込まず、タスクの見える化や「やらないこと」を決める時間管理術、夫や外部サービスとの連携、そして何よりも自分を癒やすセルフケアが重要です。
完璧を目指す必要はありません。
「まあいっか」の精神で自分を許し、少しずつできることから始めてみましょう。
あなたの笑顔が、家族の笑顔に繋がります。





