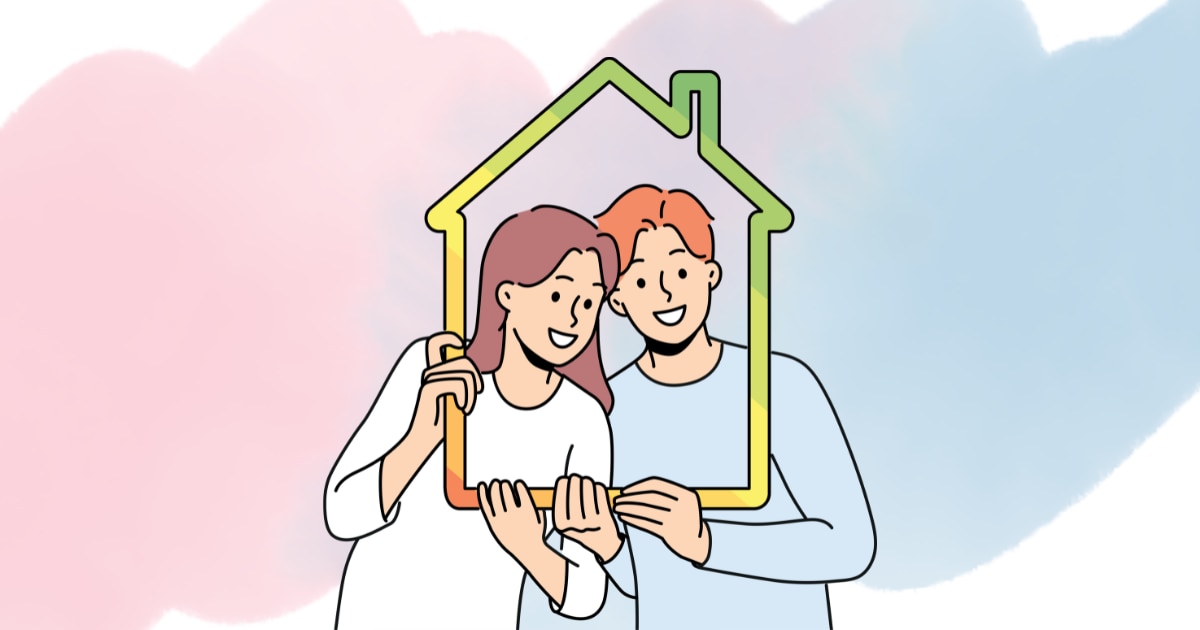震災に備える!こどもを守るための防災対策チェックリスト&マニュアル
いつ起こるかわからない震災。大切なこどもたちの命と心を守るために、今すぐできる対策を知りたいと思っていませんか?
この記事では、震災からこどもを守るための具体的な防災計画から、年齢別の対策、緊急時の行動マニュアル、必要な備蓄品リスト、さらには心のケアまで、網羅的に解説します。
ご家族で実践できる具体的な方法がわかり、震災への不安を安心に変えるための第一歩を踏み出せます。
目次[非表示]
- 1.はじめに 震災からこどもを守る重要性
- 1.1.なぜ今、こどもの防災対策が必要なのか…?
- 1.2.
- 2.震災対策の第一歩 家族で話し合う防災計画
- 3.こどもの年齢別 震災対策のポイント
- 3.1.①乳幼児と保護者のための震災対策
- 3.1.1.〇乳幼児に必要な防災グッズと備蓄
- 3.1.2.〇避難時の抱っこやおんぶの工夫
- 3.2.➁学童期こどもと取り組む震災対策
- 3.2.1.〇こども自身が身につけるべき防災行動
- 3.2.2.〇学校や地域の避難訓練への参加
- 3.3.➂思春期こどもとの震災対策 コミュニケーションの重要性
- 3.3.1.〇SNS利用と情報収集のルール
- 3.3.2.〇こどもの意見を取り入れた防災計画
- 4.震災発生時 こどもを守るための行動マニュアル
- 5.備蓄と非常持ち出し袋 こども用品の準備リスト
- 5.1.①こども用非常持ち出し袋のチェックリスト
- 5.1.1.〇乳幼児向けのおむつ・ミルク・離乳食
- 5.1.2.〇学童期・思春期向けの水・食料・衛生用品
- 5.2.➁自宅での備蓄品リスト こどもと家族のために
- 5.2.1.〇最低3日分 理想は1週間分の備蓄
- 5.2.2.〇季節に応じた衣類や防寒具の準備
- 6.震災後のこどもの心のケアとサポート
- 6.1.①震災がこどもに与える心理的影響
- 6.2.➁こどもの不安を和らげる接し方
- 6.3.➂専門機関への相談とサポート体制
- 7.日常からできる震災対策 こどもとの防災訓練
- 7.1.①家庭でできる簡単な防災訓練
- 7.2.➁地域の防災訓練への積極的な参加
- 7.3.➂こども向け防災教育の活用
- 8.まとめ
はじめに 震災からこどもを守る重要性
なぜ今、こどもの防災対策が必要なのか…?

日本は世界有数の地震多発国であり、いつどこで大規模な地震が発生してもおかしくない状況にあります。
特に、近年では南海トラフ地震や首都直下地震など、広範囲に甚大な被害をもたらす可能性のある巨大地震の発生が懸念されています。
このような状況下で、最も守るべき存在であるこどもたちの安全を確保することは、私たち親にとって喫緊の課題です。
こどもたちは、大人に比べて身体が小さく、判断力や情報収集能力も未熟であるため、災害時には特に脆弱な立場に置かれます。
例えば、突然の揺れにパニックになったり、避難経路を理解できなかったり、避難所での生活環境に適応することが難しかったりする場合があります。東日本大震災や熊本地震など、過去の震災を振り返ると、事前の備えがいかに重要であったかが浮き彫りになります。
「まさか」はいつか「もしも」に変わります。
震災は「いつか来るもの」ではなく、「いつ来てもおかしくないもの」として捉え、今すぐにでも具体的な対策を講じることが、こどもたちの命と未来を守るための第一歩となるのです。
こどもたちの安全を確保し、震災を乗り越えるための具体的なステップを、ぜひ本記事で見つけてください。
震災対策の第一歩 家族で話し合う防災計画

震災はいつ、どこで発生するか予測できません。
特にこどもを持つご家庭では、日頃からの備えと家族での話し合いが、いざという時にこどもを守るための最も重要な第一歩となります。
この章では、家族全員で取り組むべき防災計画の策定について詳しく解説します。
①ハザードマップで自宅周辺のリスクを知る
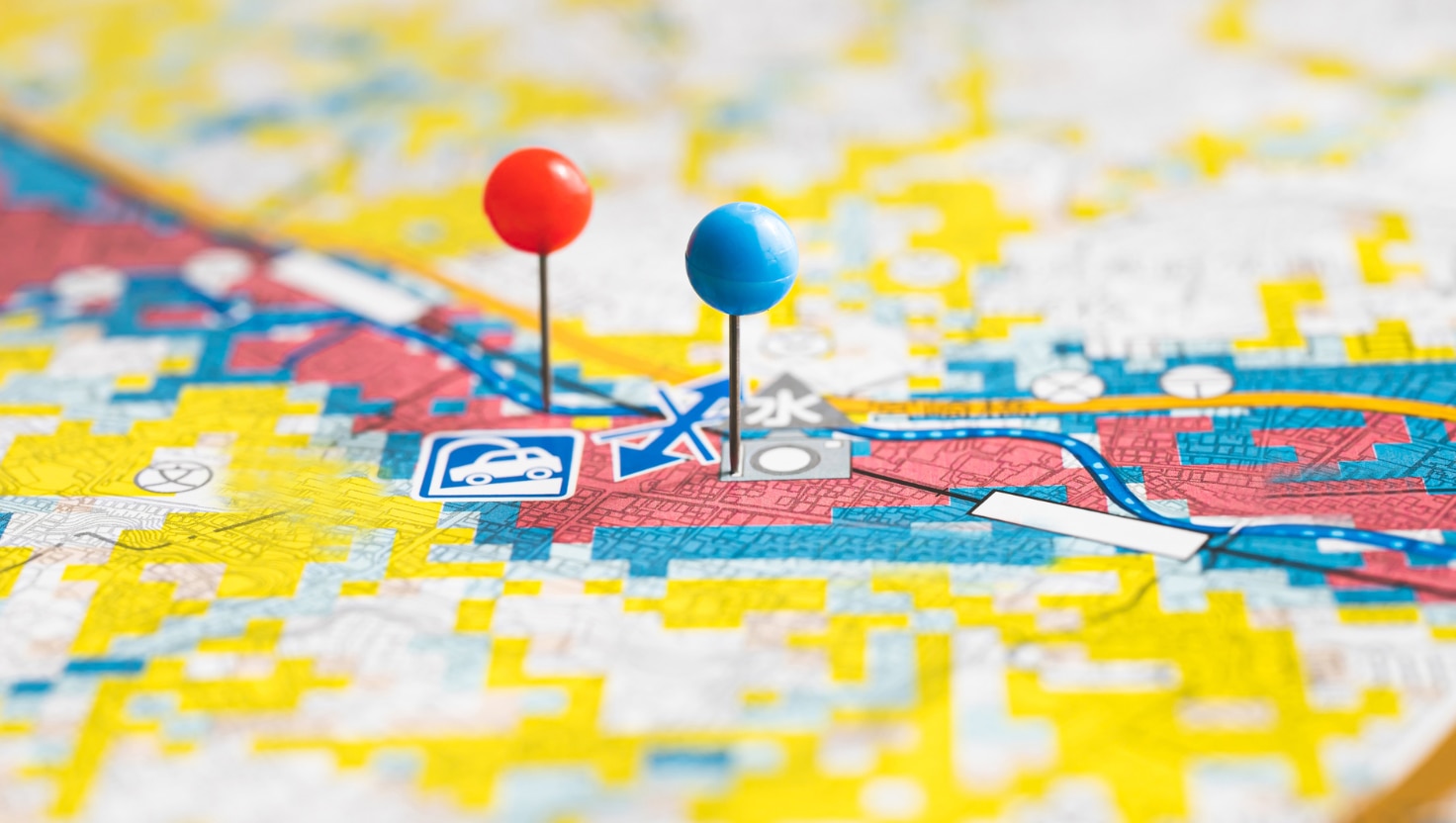
家族の防災計画を立てる上で、まず自宅や生活圏にどのような災害リスクがあるのかを正確に把握することが不可欠です。そのために活用すべきが「ハザードマップ」です。
ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害範囲や避難場所、避難経路などを地図上に示したものです。
お住まいの市区町村の役所や役場の窓口、または各自治体のウェブサイトで入手できます。国土交通省のハザードマップポータルサイトでも全国の情報を確認できます。
自宅周辺だけでなく、こどもが通う学校や保育園、よく遊びに行く公園、通勤・通学経路など、家族が普段過ごす様々な場所のリスクも確認しましょう。
特に、洪水、土砂災害、津波、地震による揺れやすさ、液状化の可能性など、地域によって異なる災害の種類を把握することが重要です。
ハザードマップの 種類 | 確認すべき リスク |
|---|---|
洪水 ハザードマップ | 河川の氾濫による 浸水想定区域、 浸水の深さ |
内水 ハザードマップ | 下水道の排水能力を 超えた際の 浸水想定区域、 浸水の深さ |
土砂災害 ハザードマップ | 土石流、 急傾斜地の崩壊、 地すべりの危険箇所 |
津波 ハザードマップ | 津波の浸水想定区域、 津波到達時間 |
地震 ハザードマップ | 地震による揺れやすさ、 液状化の可能性、 建物の倒壊リスク |
こどもと一緒にハザードマップを見ることで、災害への意識を高め、避難の必要性を理解させる良い機会にもなります。
➁家族の安否確認方法と集合場所を決める

震災発生時、家族が離れ離れになる可能性は十分にあります。
そのような状況で、家族の安否を確認し、安全を確保するための具体的な方法を事前に決めておくことが非常に重要です。
まず、連絡手段について話し合いましょう。
携帯電話が不通になることを想定し、公衆電話の場所や、NTTが提供する「災害用伝言ダイヤル171」や「災害用伝言板web」の利用方法を家族全員で確認しておくべきです。
また、SNSやメッセージアプリが災害時に有効な情報伝達手段となる場合もありますが、通信状況によっては利用できない可能性も考慮し、複数の方法を検討しておくことが賢明です。
安否確認方法の例 | ポイント |
|---|---|
災害用伝言 ダイヤル171 | 電話番号と メッセージを 録音・再生。 公衆電話からも 利用可能。 |
災害用伝言板 web | インターネット上で 安否情報を 登録・確認。 スマートフォンからも 利用可能。 |
SNS メッセージアプリ | 災害時モードや 安否確認機能の活用。 通信状況に注意。 |
親戚宅など 遠方の連絡先 | 被災地外の親戚を 中継点として 安否を連絡する 「集合場所外」の連絡先。 |
次に、家族が合流するための集合場所を複数決めておきましょう。
自宅が無事な場合は自宅を一時集合場所としますが、自宅が倒壊したり火災の危険がある場合は、近所の公園や広場など、安全な場所を「一時集合場所」として定めます。
さらに、そこも危険な場合は、指定避難所や広域避難場所など、より遠くの安全な場所を「二次集合場所」として決めておくと良いでしょう。
こどもが学校や学童、習い事などで一人でいる場合の行動についても話し合っておく必要があります。
学校では引き渡し訓練などが行われますが、万が一の場合に備え、誰が迎えに行くのか、またはこどもがどこで待機するのかを明確にしておくことが、こどもの不安を軽減し、安全を守る上で非常に重要です。
➂こどもにもわかる防災ルールと役割分担

家族の防災計画は、大人だけで決めるものではありません。
こどもにも理解できる言葉で、震災時のルールやそれぞれの役割を伝え、一緒に考えることが大切です。
これにより、こどもは「自分も家族の一員として防災に関わっている」という意識を持ち、主体的に行動できるようになります。
まず、震災発生時にとるべき基本的な行動を、こどもにも分かりやすい言葉で教えましょう。
例えば、「地震が起きたら、まず頭を守って机の下に隠れる」「火事の時は姿勢を低くして避難する」といった具体的な行動です。
学校で習う「おかしも(押さない、駆けない、喋らない、戻らない)」などのルールも、家庭で繰り返し確認しましょう。
次に、家族それぞれの役割分担を決めます。
これは、家族構成やこどもの年齢に応じて柔軟に設定します。
例えば、小さなこどもがいる家庭では、保護者がこどもの安全確保を最優先とし、別の家族が避難経路の確認や備蓄品の持ち出しを担当するなどです。
思春期のお子さんには、情報収集や高齢の家族のサポートなど、より責任のある役割を与えることも可能です。
家族の役割分担例 | 具体的な行動 |
|---|---|
保護者A (主担当) | こどもの安全確保、 避難経路の確認、 緊急連絡先への連絡 |
保護者B (副担当) | 非常持ち出し袋の準備、 火元の確認、 ペットの保護 |
学童期こども | 自分の身を守る行動 (机の下に隠れるなど)、 家族への声かけ、 避難経路の確認を手伝う |
思春期こども | 家族の安否確認 (災害用伝言ダイヤルなど)、 情報収集、 高齢者や乳幼児のサポート |
これらのルールや役割分担は、一度決めたら終わりではありません。
定期的に家族会議を開き、見直しや訓練を行うことで、いざという時にスムーズに行動できるようになります。
こどもが成長するにつれて、役割も変化させていくことが望ましいです。
こどもの年齢別 震災対策のポイント
震災対策は、こどもの年齢や発達段階に応じて、その内容やアプローチを変える必要があります。
それぞれの年齢層に合わせた具体的な対策を講じることで、より効果的にこどもたちの安全を守り、精神的な安定を保つことができます。
①乳幼児と保護者のための震災対策
乳幼児は自ら身を守ることができないため、保護者による事前の準備と、発生時の迅速な対応が不可欠です。
乳幼児の特性を理解した上で、きめ細やかな対策を立てることが重要になります。
〇乳幼児に必要な防災グッズと備蓄

乳幼児は、おむつやミルク、離乳食など、特定の消耗品が不可欠です。これらは災害時に入手困難になる可能性が高いため、普段から多めに備蓄しておくことが命を守る上で非常に大切です。
アレルギーがある場合は、必ず代替品や対応食を準備しておきましょう。
以下に、乳幼児のための防災グッズと備蓄品リストをまとめました。
カテゴリ | 具体的な品目 | ポイント・備考 |
|---|---|---|
食料・飲料 | 液体ミルク、粉ミルク、 哺乳瓶、離乳食 (レトルト・フリーズドライ)、 ベビーフード、おやつ、 水(調乳用・飲用) | 最低3日分、 理想は1週間分。 アレルギー対応品を 忘れずに。 |
衛生用品 | 紙おむつ、おしりふき、 おむつ処理袋、 ウェットティッシュ、 手口ふき、固形石鹸、 ベビー用保湿剤 | 多めに準備。 衛生環境が 悪化しやすいため、 清潔保持が重要。 |
衣類・寝具 | 着替え(複数枚)、 肌着、靴下、防寒具 (ブランケット、おくるみ)、 タオル | 季節に応じたもの。 汚れたり濡れたり することを 想定して多めに。 |
医薬品・ケア用品 | かかりつけ医からの処方薬、 体温計、冷却シート、 爪切り、綿棒、 絆創膏、消毒液 | 常備薬は 多めに準備し、 使用期限を確認。 |
その他 | 抱っこひも、おんぶひも、 母子手帳、保険証のコピー、 お気に入りのおもちゃ、 絵本、ビニール袋、 筆記用具 | 抱っこひもは 避難時の移動に必須。 母子手帳は 医療情報として重要。 |
〇避難時の抱っこやおんぶの工夫
乳幼児を連れて避難する際は、両手が自由に使える抱っこひもやおんぶひもを必ず使用しましょう。
これにより、転倒を防ぎ、荷物を持つことができ、周囲の状況にも対応しやすくなります。避難経路は瓦礫や段差が多い可能性があるため、足元に十分注意し、常にこどもの安全を最優先に考えて行動してください。
冬場は防寒対策として、ブランケットやケープでしっかりと覆い、体温低下を防ぐ工夫も必要です。
➁学童期こどもと取り組む震災対策
学童期になると、こどもたちは自分の身を守るための基本的な行動を理解し、実践できるようになります。この時期は、こども自身が防災に関する知識を身につけ、積極的に訓練に参加することが大切です。
〇こども自身が身につけるべき防災行動

小学校に通うこどもたちには、自宅や学校で地震が起きた際の基本的な行動を繰り返し教え、身につけさせることが重要です。
「まず低く、頭を守り、動かない」というシェイクアウト訓練の原則を理解させ、実践できるよう訓練しましょう。
また、家族との連絡方法(災害用伝言ダイヤル171の利用方法など)や、万が一離れ離れになった場合の集合場所を明確に決めておくことも必要です。
自宅の非常持ち出し袋の場所や、中身の確認を一緒に行い、いざという時に自分で持ち出せるようにしておきましょう。
〇学校や地域の避難訓練への参加
学校では定期的に避難訓練が行われますが、家庭でも学校の訓練内容について話し合い、自宅での行動と関連付けることが大切です。
地域の防災訓練には、親子で積極的に参加しましょう。
地域住民との連携や、避難所の場所、運営方法などを知る良い機会となります。
訓練を通じて、実際に避難する際の課題や危険箇所を発見し、家族の防災計画に反映させることができます。
こどもが地域の一員として防災活動に参加することで、防災意識を高めることにも繋がります。
➂思春期こどもとの震災対策 コミュニケーションの重要性
思春期のこどもたちは、自立心が芽生え、友人とのつながりやSNSの利用が増える時期です。
彼らの特性を理解し、意見を尊重しながら、防災対策を進めることが円滑なコミュニケーションに繋がります。
〇SNS利用と情報収集のルール

災害時、思春期世代はSNSを通じて情報を収集したり、安否確認を行ったりすることが多いでしょう。
しかし、SNSにはデマや誤情報も拡散されやすいというリスクがあります。
家族で事前に「信頼できる情報源(例:気象庁、自治体の公式発表、主要な報道機関など)を確認する」「不確かな情報は安易に拡散しない」「バッテリー消費を抑える工夫をする」といったルールを決めておくことが重要です。
SNSを有効活用しつつ、その危険性も理解させることで、冷静な判断力を養うことができます。
〇こどもの意見を取り入れた防災計画
思春期のこどもたちは、大人と同じように考える力を持っています。
防災計画を立てる際には、彼らの意見やアイデアを積極的に取り入れましょう。
例えば、非常持ち出し袋に入れるもの、避難経路の確認、家族の役割分担などについて話し合うことで、当事者意識を高め、より実効性のある計画になります。
体力がある場合は、避難所での物資運搬や、幼いこどもたちのケアなど、具体的な役割を任せることも検討できます。
こどもたちの自立心や責任感を育む良い機会となり、災害時に主体的に行動できる力を養うことにも繋がります。
震災発生時 こどもを守るための行動マニュアル
①地震発生直後 こどもと一緒に身を守る行動

震災発生直後の数秒から数分間は、こどもの命を守るための最も重要な時間です。
大きな揺れを感じたら、まずは落ち着いて身の安全を確保しましょう。
こどもと一緒に、以下の行動を迅速に実行してください。
- 姿勢を低くする(DROP):頭や体を守るために、すぐに姿勢を低くします。
- 頭を守る(COVER):テーブルの下や頑丈な家具の陰に隠れ、頭を抱えるなどして頭部を保護します。近くに隠れる場所がない場合は、クッションや座布団などで頭を守りましょう。
- 揺れが収まるまで動かない(HOLD ON):揺れが収まるまで、その場でじっと身を守り続けます。こどもがパニックにならないよう、落ち着いた声で「大丈夫だよ、ママ(パパ)がそばにいるよ」と声をかけ続けましょう。
また、揺れが収まったら、火の元を確認し、可能であればガスの元栓を閉め、ブレーカーを落としましょう。
避難経路を確保するためにドアや窓を開けることも重要ですが、その際はガラスの飛散に注意してください。こどもを抱きかかえるか、手をつないで安全な場所へ移動する準備を始めます。
➁避難時の注意点 こどもとの安全な移動方法

揺れが収まり、自宅での安全確保が難しいと判断した場合は、指定された避難所への移動を検討します。
避難する際は、こどもの安全を最優先に、以下の点に注意して行動しましょう。
項目 | こどもとの避難時のポイント |
|---|---|
服装と靴 | 動きやすく、 肌の露出が少ない 長袖・長ズボンを 着用させましょう。 足元はスニーカーなど、 底が厚く歩きやすい靴を選び、 ガラスの破片などから 足を保護します。 乳幼児は抱っこ紐や おんぶ紐を活用し、 保護者の体が自由に 動かせるようにします。 |
非常持ち出し袋 | 事前に準備したこども用の 非常持ち出し袋 (おむつ、ミルク、離乳食、 お気に入りのおもちゃなど) を忘れずに持ち出します。 必要最低限のものを 厳選し、両手が空くように リュックサックで 背負うのが理想です。 |
移動経路 | 事前に確認しておいた 安全な避難経路を通行します。 倒壊した建物やブロック塀、 電線、ガラスの破片など、 危険な場所には 絶対に近づかない ようにしましょう。 こどもから目を離さず、 必ず手をつないで移動します。 |
周囲との連携 | 近隣住民や他の避難者と協力し、 助け合いながら移動することも大切です。 特に小さなこどもを連れている場合は、 周囲のサポートが大きな助けとなります。 |
情報収集 | ラジオや防災アプリなどで、 常に正確な情報を収集し、 冷静に行動することが重要です。 デマに惑わされないよう注意しましょう。 |
避難経路の途中で、こどもが不安を感じたり、疲れて歩けなくなったりすることもあります。
その際は、無理をさせず、休憩を取りながら励まし、安心感を与えるように心がけてください。
➂避難所での生活 こどもへの配慮と対策

避難所での生活は、プライバシーの確保が難しく、不慣れな環境からこどもに大きなストレスを与える可能性があります。
こどもたちが心身ともに健やかに過ごせるよう、以下の点に配慮し、対策を講じましょう。
- プライベート空間の確保:可能であれば、段ボールや簡易テントなどで、家族が落ち着ける小さな空間を作りましょう。こどもが安心できる場所があることで、精神的な負担を軽減できます。
- 衛生管理の徹底:手洗いやうがいを励行し、感染症の予防に努めます。おむつ交換や授乳スペースの確保、簡易トイレの利用方法など、こども特有の衛生ニーズに対応できるよう準備しておきましょう。
- 食事と水分補給:アレルギーを持つこどもや乳幼児のために、事前に備蓄した非常食やアレルギー対応食品、粉ミルクなどを活用します。水分補給はこまめに行い、脱水症状を防ぎましょう。
- ストレス軽減と遊び:避難所生活はこどもにとって退屈で不安なものです。お気に入りのおもちゃや絵本、簡単な遊び道具を持参し、こどもが遊びを通じてストレスを発散できる時間を作りましょう。他のこどもたちとの交流も大切です。
- 体調管理と医療:こどもの体調に変化がないか常に注意し、発熱や下痢などの症状が見られた場合は、速やかに避難所の医療担当者や救護所へ相談しましょう。常備薬がある場合は、忘れずに携帯し、服用を継続させます。
- 情報収集と共有:避難所内の掲示板や放送、配布される情報紙などで、最新の情報を確認し、こどもにも分かりやすく説明してあげましょう。不安を煽るような情報は避け、正確な情報のみを伝えるように心がけます。
避難所での生活は長期化する可能性もあります。
こどもの様子をよく観察し、精神的なケアが必要な場合は、専門機関への相談も視野に入れるなど、柔軟に対応していくことが大切です。
備蓄と非常持ち出し袋 こども用品の準備リスト
震災発生時、こどもたちの安全と健康を守るためには、事前の備蓄と非常持ち出し袋の準備が不可欠です。
特にこどもは大人と異なり、年齢に応じた特別なケアや物資が必要となるため、きめ細やかな準備が求められます。
ここでは、こどもと家族が安心して過ごせるための備蓄品と非常持ち出し袋の具体的なリストをご紹介します。
①こども用非常持ち出し袋のチェックリスト

非常持ち出し袋は、地震発生直後や避難時にすぐに持ち出せるよう、玄関や寝室など、取り出しやすい場所に保管しておくことが重要です。
こども用は、年齢や成長段階に合わせた内容を準備しましょう。
〇乳幼児向けのおむつ・ミルク・離乳食
乳幼児は特に、日常使い慣れたものを用意しておくことが大切です。
ストレスを最小限に抑えるためにも、種類やサイズを考慮しましょう。
項目 | 具体的な内容 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
飲料水 | 乳幼児用ミネラルウォーター (加熱不要タイプ)、 または煮沸済みの水 | 少量パックで 持ち運びやすいものを。 |
ミルク・離乳食 | 液体ミルク (開封後すぐに飲めるもの)、 キューブ型粉ミルク、 使い捨て哺乳瓶、 レトルト離乳食、 フリーズドライ食品、 ベビーフード | アレルギー対応品も考慮。 スプーンやウェットティッシュも 忘れずに。 |
おむつ・おしりふき | 数日分のおむつ、 おしりふき、 おむつ用ゴミ袋 | 圧縮袋に入れると コンパクトに。 |
衣類 | 着替え(肌着、ロンパースなど)数枚、 防寒着、靴下、帽子 | 季節や気温に 応じたものを。 |
衛生用品 | 除菌シート、手洗い用石鹸、 爪切り、体温計、 お薬手帳、常備薬 | かかりつけ医の連絡先も 控えておく。 |
その他 | 抱っこ紐、バスタオル、 ビニールシート、 お気に入りのおもちゃ、絵本 | 精神的な安定を 促すアイテムも重要。 |
〇学童期・思春期向けの水・食料・衛生用品

学童期・思春期のこどもは、自分で自分の身を守る意識を高めるためにも、一緒に非常持ち出し袋の中身を確認し、準備に参加させることが大切です。
個人で管理できる範囲のものを準備しましょう。
項目 | 具体的な内容 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
飲料水 | ペットボトル飲料水 (500ml程度)数本 | 1人1日3リットルを 目安に。 |
食料 | 栄養補助食品 (カロリーメイトなど)、 乾パン、チョコレート、 ゼリー飲料、アメ | 手軽に食べられ、 高カロリーなものを。 |
衛生用品 | ウェットティッシュ、 生理用品(女子の場合)、 マスク、携帯用歯ブラシセット | 個人に必要なものを優先。 |
衣類 | 着替え(下着、Tシャツ、長ズボン)、 防寒具、靴下 | 体温調節しやすい 重ね着できるものが便利。 |
その他 | 携帯電話充電器 (モバイルバッテリー)、 懐中電灯、笛(防犯・救助用)、 筆記用具、絆創膏、常備薬、 現金(小銭含む) | こども自身が 管理しやすいポーチ などにまとめる。 |
➁自宅での備蓄品リスト こどもと家族のために
自宅での備蓄は、避難所へ移動できない場合や、ライフラインが復旧するまでの期間を自宅で過ごすために非常に重要です。
ローリングストック法を活用し、日常的に消費しながら補充していくことで、常に新鮮な備蓄品を保つことができます。
〇最低3日分 理想は1週間分の備蓄
政府推奨の最低3日分、できれば1週間分の備蓄を目指しましょう。
こどもがいる家庭では、特に水と食料、衛生用品の確保が優先されます。
項目 | 具体的な内容 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
飲料水 | 1人1日3リットルを目安に、 ペットボトル水や ポリタンクに詰めた水 | こどもの年齢に 応じて必要量を調整。 |
非常食 | レトルトご飯、 缶詰(肉・魚・野菜)、 フリーズドライ食品、 アルファ米、カップ麺、 栄養補助食品、 ビスケット、乾パン | 加熱不要なものや、 カセットコンロで 調理できるものも。 |
簡易トイレ ・衛生用品 | 簡易トイレ、凝固剤、 トイレットペーパー、 ティッシュペーパー、 生理用品、大人用おむつ、 ウェットティッシュ、 除菌スプレー、石鹸 | 断水時に備え、 水を使わない タイプを多めに。 |
生活用品 | カセットコンロ、 カセットボンベ、 懐中電灯、ランタン、 電池、モバイルバッテリー、 携帯ラジオ、 予備のメガネ・ コンタクトレンズ、 常備薬 | 電池は多めに、 使用期限を確認。 |
寝具 ・防寒具 | 毛布、寝袋、カイロ、アルミブランケット、厚手の靴下、軍手 | 特に冬場の震災に備え、 防寒対策を重視。 |
〇季節に応じた衣類や防寒具の準備

備蓄する衣類は、季節や気温の変化に対応できるよう、重ね着できるものや防寒・防暑対策ができるものを選びましょう。
こどもの成長に合わせて、定期的にサイズを見直すことも忘れてはいけません。
- 春・秋:長袖Tシャツ、パーカー、薄手のジャンパー、長ズボン
- 夏:半袖Tシャツ、短パン、帽子、薄手のタオルケット
- 冬:フリース、ダウンジャケット、厚手のセーター、手袋、マフラー、カイロ、毛布、寝袋
- 共通:下着、靴下、雨具(レインコート)、スニーカー(歩きやすいもの)
これらを圧縮袋に入れて保管すると、スペースを節約できます。また、こどもが成長してサイズが合わなくなった衣類は、すぐに新しいものと入れ替えるようにしましょう。
震災後のこどもの心のケアとサポート
震災は、こどもの心に大きな影響を与える可能性があります。
物理的な安全が確保された後も、こどもの心のケアは長期にわたる重要な課題です。
こどもの心の状態を理解し、適切なサポートを提供することが、健やかな成長を支える上で不可欠です。
①震災がこどもに与える心理的影響
震災はこどもたちに、年齢や個々の性格、被災状況によって異なる心理的な影響をもたらします。一時的な反応だけでなく、長期にわたる影響に注意が必要です。
- 乳幼児(0~3歳)言葉での表現が難しいため、夜泣き、後追い、食欲不振、おねしょの増加、指しゃぶりなどの退行現象が見られることがあります。親の不安を敏感に感じ取り、ぐずりや癇癪が増えることもあります。
- 学童期(4~12歳)悪夢、不眠、集中力の低下、学習意欲の低下、頭痛や腹痛などの身体症状、情緒不安定、攻撃的な行動、友達とのトラブルなどが現れることがあります。災害の記憶がフラッシュバックすることもあります。
- 思春期(13歳~)抑うつ、不安、無気力、引きこもり、自傷行為、反抗的な態度、飲酒や喫煙などの問題行動、将来への絶望感などが現れることがあります。友人関係や社会とのつながりを避ける傾向が見られることもあります。大人と同じようにストレスを感じつつも、それを表現することが難しい場合があります。
これらの症状は、被災直後から数週間で現れることが一般的ですが、数ヶ月、あるいは数年後に遅れて現れることもあります。
症状が長引いたり、日常生活に支障が出たりする場合は、専門家のサポートを検討することが重要です。
➁こどもの不安を和らげる接し方

こどもの心のケアにおいて、最も重要なのは、親や周囲の大人が安心感を与え、寄り添うことです。以下の点を心がけて接しましょう。
心構え | 具体的な接し方 |
|---|---|
安心感を 与える |
|
感情を 受け止める |
|
情報との向き合い方 |
|
親自身のケア |
|
こどもが示す変化は、ストレスへの正常な反応である場合も多いです。
焦らず、長い目で見て寄り添い続ける姿勢が大切です。
➂専門機関への相談とサポート体制
こどもの心理的な反応が長引いたり、日常生活に支障をきたしたりする場合、あるいは親だけでは対応が難しいと感じる場合は、専門機関への相談をためらわないでください。早期のサポートが、こどもの心の回復を助けます。
- 児童相談所こどもに関するあらゆる相談を受け付けています。心理士によるカウンセリングや、必要に応じて医療機関への紹介も行われます。
- 精神科・心療内科こども専門の精神科医や児童精神科医がいる医療機関では、より専門的な診断と治療(カウンセリング、プレイセラピー、薬物療法など)が受けられます。
- スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー学校に配置されている場合、こどもや保護者からの相談に応じ、学校生活における心のケアや、必要に応じて外部機関との連携をサポートします。
- 各自治体の相談窓口・保健センター市区町村の保健センターや健康福祉課などで、精神保健福祉に関する相談窓口が設けられていることがあります。地域のサポート情報も得られます。
- NPO法人・民間団体被災地のこどもたちの心のケアを専門とするNPO法人や民間団体もあります。独自のプログラムや活動を通じて、こどもたちの回復を支援しています。
相談の目安としては、以下のような状態が続く場合です。
- 症状が数週間以上続き、改善の兆しが見られない。
- 食欲不振や不眠がひどく、身体的な健康に影響が出ている。
- 学校に行けない、友達と遊べないなど、日常生活に大きな支障が出ている。
- 自傷行為や他害行為が見られる。
これらの専門機関は、こどもだけでなく、保護者自身の心のケアや、こどもへの接し方に関するアドバイスも提供しています。
一人で抱え込まず、積極的にサポートを求めましょう。
日常からできる震災対策 こどもとの防災訓練
震災への備えは、特別な日に行うものではなく、日々の生活の中に溶け込ませることが重要です。特にこどもにとっては、遊びや学びを通して自然と防災意識を高めることが、いざという時の冷静な判断と行動につながります。
①家庭でできる簡単な防災訓練

自宅での防災訓練は、家族全員が参加し、具体的な行動をイメージする絶好の機会です。
ゲーム感覚で楽しみながら、いざという時にどう動くかを体に覚えさせましょう。
家庭でできる 防災訓練の例 | こどもとの取り組み方 |
|---|---|
シェイクアウト 訓練 | 地震発生時に 「まず低く、頭を守り、動かない」 の3つの安全行動を、 合図に合わせて実践します。 家具の下やテーブルの下など、 安全な場所を一緒に確認しましょう。 |
避難経路の 確認 | 自宅から安全な場所 (庭、公園など)までの経路を 家族で歩いて確認します。 夜間や停電時を想定し、 懐中電灯を使って 歩く練習も効果的です。 |
非常持ち出し袋の 点検 | 定期的に 非常持ち出し袋の中身を 一緒に確認し、 賞味期限切れの食品や 使えなくなったものがないか チェックします。 こども用のアイテム (おもちゃ、絵本など)も 忘れずに入れましょう。 |
防災グッズの 置き場所確認 | 懐中電灯、携帯ラジオ、 笛などの防災グッズが どこにあるかを こどもにも教え、 いざという時に 自分で取り出せるようにします。 |
家族会議と 役割分担 | 防災について 定期的に話し合う機会を 設け、こどもにもできる役割 (ペットの世話、貴重品を 集めるなど)を与え、 「自分も家族の一員として 備える」意識を育みます。 |
これらの訓練は、一度きりではなく、季節の変わり目や長期休暇前など、定期的に行うことが大切です。
➁地域の防災訓練への積極的な参加

地域で行われる防災訓練は、家庭内だけでは得られない実践的な知識と、地域住民との連携を学ぶ貴重な機会です。
積極的に参加し、地域全体の防災力を高めましょう。
地域の防災訓練の種類 | 参加のメリット |
|---|---|
自治体主催 の総合防災訓練 | 避難所の開設・ 運営訓練、 初期消火訓練、 応急手当訓練など、 多岐にわたる訓練が 体験できます。 専門家からの指導を 受けられることも多く、 実践的な知識が身につきます。 |
自主防災組織 の活動 | 町内会やマンション単位で 組織される 自主防災組織の活動に 参加することで、 地域ごとの特性に応じた 具体的な対策や、 共助の仕組みを 学ぶことができます。 |
避難所運営 ゲーム(HUG) | 避難所の運営を シミュレーションする ゲーム形式の訓練です。 こどもから大人まで、 避難所で起こりうる 様々な課題を疑似体験し、 助け合いの重要性を 理解できます。 |
こどもと一緒に参加することで、地域の避難所や避難経路を実際に確認でき、いざという時に安心して行動できるようになります。
また、地域住民との顔の見える関係を築くことは、災害時の相互支援にもつながります。
➂こども向け防災教育の活用

こどもが防災を楽しく、かつ効果的に学ぶための教材や機会は多岐にわたります。
こどもの興味や発達段階に合わせて、最適な方法を選びましょう。
防災教育の 活用例 | こどもへの効果 |
|---|---|
防災絵本・ アニメ・動画 | 幼いこどもでも 理解しやすいストーリーや キャラクターを通じて、 地震や津波、 火災などの危険性や、 身を守るための行動を 自然に学ぶことができます。 |
防災イベント・ 体験施設 | 全国各地の防災科学館や 消防署、防災センターなどでは、 地震体験、煙体験、消火体験など、 五感を使いながら 防災を学べるプログラムが 用意されています。 実際に体を動かすことで、 記憶に残りやすくなります。 |
学校や保育園・ 幼稚園での 防災教育 | 定期的な避難訓練や 防災学習を通じて、 集団での行動や、 先生の指示に従うことの 重要性を学びます。 家庭でも、学校での学びについて 話を聞く機会を設けましょう。 |
防災ゲーム・アプリ | スマートフォンや タブレットで 楽しめる防災ゲームや アプリは、クイズ形式や シミュレーション形式で、 防災知識を楽しく習得できます。 家族で一緒に プレイするのも良いでしょう。 |
これらの教育を通じて、こどもは「自分の命は自分で守る」という自助の意識と、「困っている人を助ける」共助の精神を育むことができます。
親は、こどもの疑問に丁寧に答え、防災への関心を深めるサポートをすることが大切です。
まとめ
震災からこどもを守るためには、日頃からの備えと継続的な取り組みが不可欠です。
この記事では、家族での防災計画から年齢別の対策、緊急時の行動マニュアル、備蓄品の準備、そして心のケアに至るまで、多角的な視点から具体的な対策を解説しました。
予測不可能な震災から大切なこどもたちの命と未来を守るため、今日からできる一歩を踏み出し、家庭で防災力を高めていきましょう。
定期的な見直しと訓練を通じて、災害に強い社会を共に築くことが何よりも重要です。