
ゲーム感覚で楽しく学ぶ!小学生のおこづかい管理で身につく金銭感覚と貯める習慣
「小学生のおこづかい管理、どうすればいい?」と悩む保護者の方へ。
この記事では、お子さんがゲーム感覚で楽しく金銭感覚と貯める習慣を身につけられる具体的な方法を解説します。
いつから、いくら、どう渡すかといった基本ルールから、おこづかい帳やアプリを使った管理術、貯蓄目標の立て方、失敗を学びにする親の対応まで、未来につながるお金の教育を始めましょう。
目次[非表示]
- 1.小学生のおこづかい管理はなぜ必要?未来につながる大切な学び
- 2.小学生のおこづかい管理を始める前に!親が知っておくべきルールと心構え
- 2.1.いつから始める?小学生のおこづかい開始の目安
- 2.2.いくらが適切?小学生のおこづかい金額の決め方
- 2.3.お手伝いと連動させる?おこづかいの渡し方ルール
- 2.4.使い道は自由?小学生のおこづかいルール設定のポイント
- 3.ゲーム感覚で楽しく続く!小学生のおこづかい管理をサポートするアイデア
- 4.金銭感覚と貯める習慣を育む!小学生のおこづかい管理で大切なこと
- 4.1.「使う」「貯める」のバランスを学ぶ!計画的なおこづかいの使い方
- 4.2.失敗は学びのチャンス!小学生がおこづかいで困った時の親の対応
- 4.3.親ができるサポート!小学生のおこづかい管理を見守るヒント
- 5.まとめ
小学生のおこづかい管理はなぜ必要?未来につながる大切な学び
小学生のうちからおこづかいの管理を始めることは、単にお金の計算ができるようになるだけでなく、将来社会で自立して生きていくために不可欠な金銭感覚と生活スキルを育む、大切な学びの機会となります。
現代社会はキャッシュレス化が進み、お金の形が見えにくくなっています。
だからこそ、子どもたちが実体験を通して「お金とは何か」「どう使うべきか」を学ぶ重要性が増しているのです。
この章では、なぜ今、小学生のおこづかい管理が必要なのか、そしてそれが子どもたちの未来にどのようなポジティブな影響をもたらすのかを詳しく解説します。
お金の教育はなぜ今、必要なのか?変化する社会と子どもの未来
 かつては現金でのやり取りが主流でしたが、現代ではクレジットカードや電子マネー、QRコード決済など、目に見えない形でお金が動くことが増えました。
かつては現金でのやり取りが主流でしたが、現代ではクレジットカードや電子マネー、QRコード決済など、目に見えない形でお金が動くことが増えました。
これにより、子どもたちは「お金を使う」という行為を実感しにくくなっています。
コンビニエンスストアでの買い物も、親のスマートフォンをかざすだけで完了してしまうため、お金の価値や有限性を意識する機会が減っているのが現状です。
このような社会の変化の中で、家庭でのおこづかい管理を通じた金銭教育は、子どもが「見えないお金」を正しく理解し、賢く付き合うための基礎を築く上で非常に重要です。
将来、社会に出たときに必要となる金融リテラシーの第一歩として、小学生のうちからお金に関する具体的な経験を積ませることが、子どもたちの明るい未来につながるのです。
おこづかい管理で身につく!子どもの成長に不可欠な5つのスキル
 /おこづかい管理は、子どもたちに以下のような多岐にわたるスキルを身につけさせます。
/おこづかい管理は、子どもたちに以下のような多岐にわたるスキルを身につけさせます。
これらは学力とは異なる、実社会で役立つ「生きる力」として、子どもの成長に不可欠なものです。
身につくスキル | 具体的な学び |
|---|---|
金銭感覚と 価値理解 | 「〇〇円で何が買えるか」 「このおもちゃはどれくらいの価値があるか」 といった、 お金の具体的な価値や有限性を肌で感じます。 また、物を買うためにはお金が必要であり、 そのお金は親が働いて得ているという、 労働と対価の関係を 理解するきっかけにもなります。 |
計画性と 予算管理 | 限られたおこづかいの中で 「今月は何に使うか」 「欲しいものを買うためにどう貯めるか」 といった計画を立てる力が養われます。 予算内でやりくりする経験は、 将来の家計管理や ライフプランニングの基礎となります。 |
選択と 意思決定 | 「お菓子を買うか、 それとも貯めてゲームを買うか」など、 優先順位をつけ、自分で選択し、 決定する経験を重ねます。 このプロセスで、 衝動買いを抑える自制心や、 選択の結果に対する責任感が育まれます。 |
自己管理能力と 責任感 | おこづかい帳をつけたり、 貯金をしたりすることで、 自分のお金の流れを把握し、 自己を管理する能力が向上します。 お金を計画的に使うことで、 「自分で決めたことは自分で責任を持つ」 という自立心が育ちます。 |
問題解決能力 | 「おこづかいが足りなくなった」 「予定外の出費があった」 といった金銭的な問題に直面した際、 「どうすれば解決できるか」を 自分で考え、親と相談しながら 解決策を見つける力が養われます。 これは、実社会で遭遇する 様々な問題への対処能力につながります。 |
「貯める」から始まる!未来を切り拓く貯蓄習慣の重要性

おこづかい管理の中で特に重要なのが「貯める」という習慣です。
欲しいものをすぐに買うのではなく、目標を設定し、それに向かってコツコツとお金を貯める経験は、子どもにとって大きな達成感と自信を与えます。
この「目標のために努力し、達成する」というプロセスは、金銭面だけでなく、将来の学習やキャリア形成においても非常に価値のある経験となります。
また、貯蓄を通じて、お金には「使う」だけでなく「貯めて増やす」という側面があることを学び始めます。
すぐに成果が見えなくても、継続することで大きな目標が達成できることを知ることは、将来の資産形成や長期的な視点を持つ上で不可欠な基礎となります。
小さいうちから貯蓄の楽しさや重要性を知ることで、子どもたちは未来を見据えた賢いお金の使い方を身につけていくことができるのです。
小学生のおこづかい管理を始める前に!親が知っておくべきルールと心構え
小学生のおこづかい管理は、子どもが社会で生きていく上で不可欠な金銭感覚と自立心を育む大切なステップです。
しかし、ただお金を渡せば良いというものではありません。
始める前に親がしっかりとルールや心構えを整えることで、子どもは安心して学び、より効果的な金銭教育へとつながります。
いつから始める?小学生のおこづかい開始の目安
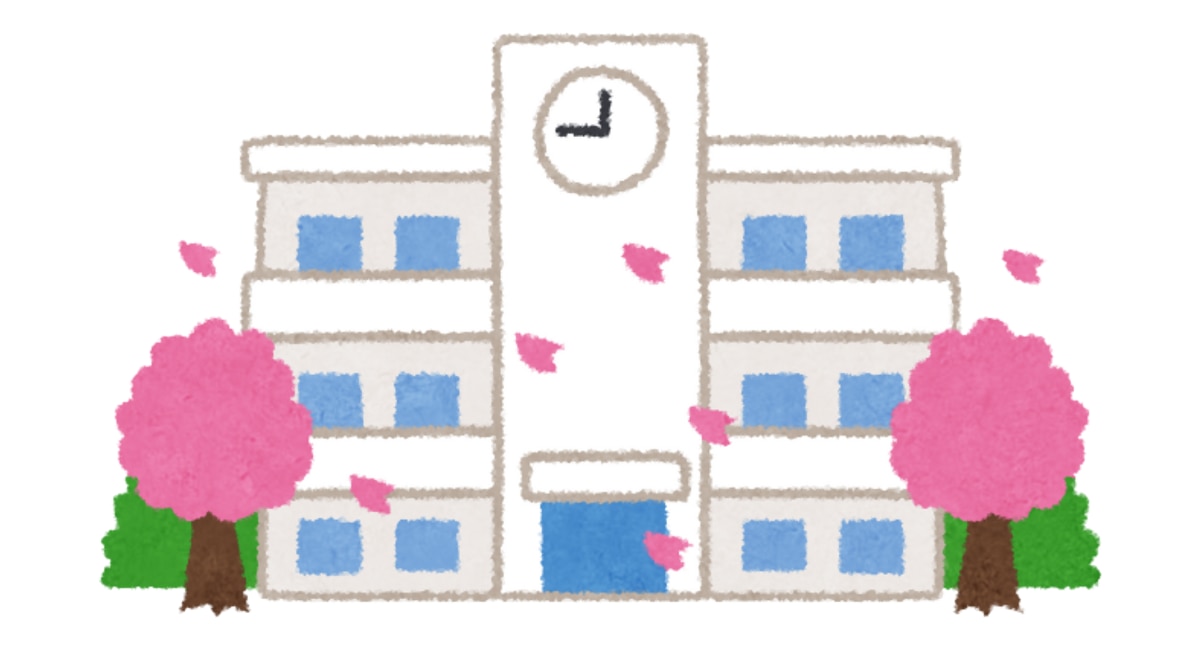
おこづかいを始める時期に「正解」はありませんが、一般的には小学校に入学する頃から低学年で始める家庭が多いようです。
大切なのは、子どもの発達段階を見極めることです。
- お金への興味:お金について質問したり、お店での支払いに興味を示したりするようになったら、始める良い機会かもしれません。
- 簡単な計算能力:足し算や引き算など、簡単な計算ができるようになると、おこづかいの管理がしやすくなります。
- 自己管理能力の兆し:自分の持ち物を整理したり、簡単な約束を守ったりできるようになっていれば、お金の管理も任せられる可能性が高まります。
焦る必要はありません。
子どもが「自分のお金が欲しい」「自分で買い物をしたい」という気持ちを持つようになった時が、おこづかいを始める最適なタイミングと言えるでしょう。
親子で話し合い、子どもの準備ができたと感じた時にスタートするのが理想的です。
いくらが適切?小学生のおこづかい金額の決め方
 おこづかいの金額は、家庭の経済状況や子どもの年齢、そして何をおこづかいで賄うかによって大きく異なります。
おこづかいの金額は、家庭の経済状況や子どもの年齢、そして何をおこづかいで賄うかによって大きく異なります。
「いくらが適切か」という明確な答えはありませんが、いくつかの目安や考え方があります。
一般的には、学年×100円〜500円程度を月額とする家庭が多いようです。
例えば、小学1年生なら月100円〜500円、小学6年生なら月600円〜3,000円といった具合です。
ただし、これはあくまで目安であり、重要なのは親子で納得して金額を決めることです。
金額を決める際のポイント:
- 家庭の経済状況:無理のない範囲で設定しましょう。
- 子どもの年齢と学年:年齢が上がるにつれて、必要なものや興味の対象も広がるため、金額を段階的に上げていくのが一般的です。
- おこづかいで賄う範囲:お菓子、文房具、おもちゃ、友達との遊び代など、何をおこづかいから出すのかを具体的に決めると、必要な金額が見えてきます。
- 周囲の状況:クラスの友達がどれくらいもらっているかを知るのも参考になりますが、他家庭と比較しすぎないことが大切です。
以下の表は、一般的なおこづかいの目安をまとめたものです。
学年 | 月額の目安 (一般的な範囲) | おこづかいで 賄う主なもの |
|---|---|---|
小学1〜2年生 | 100円〜500円 | ・お菓子 ・消しゴムなどの 小さな文房具 |
小学3〜4年生 | 500円〜1,500円 | ・お菓子 ・文房具 ・ガチャガチャ ・ちょっとしたおもちゃ |
小学5〜6年生 | 1,000円〜3,000円 | ・お菓子 ・文房具 ・漫画 ・雑誌 ・友達との遊び代 ・趣味の小物 |
金額は一度決めたら終わりではありません。
子どもの成長や必要に応じて、定期的に見直しの機会を設けるようにしましょう。
お手伝いと連動させる?おこづかいの渡し方ルール
 おこづかいをお手伝いと連動させるかどうかは、家庭によって意見が分かれるポイントです。
おこづかいをお手伝いと連動させるかどうかは、家庭によって意見が分かれるポイントです。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、家庭の教育方針に合った方法を選ぶことが重要です。
連動させる場合 (報酬型) | 連動させない場合 (定額型) | |
|---|---|---|
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
どちらの方式を選ぶにしても、「なぜおこづかいを渡すのか」という目的を明確にし、子どもに伝えることが大切です。
- 報酬型:「このお手伝いをしたら〇円」と具体的に決め、労働の対価としてお金を得る経験をさせます。
- 定額型:家族の一員としての家事とは別に、金銭管理の練習として定期的におこづかいを渡します。必要に応じて、特別なお手伝いや頑張りに対して臨時収入を与えることも検討できます。
お手伝いは家族の一員としての協力であり、おこづかいは金銭管理を学ぶためのツール、という考え方で区別する家庭も増えています。
親子のコミュニケーションを通じて、最も納得のいく方法を見つけましょう。
使い道は自由?小学生のおこづかいルール設定のポイント

おこづかいの使い道は、基本的には子どもに任せるのが金銭感覚を育む上で重要です。
自分で考えてお金を使う経験こそが、生きる力を養います。しかし、完全に自由にしてしまうと、困った事態に陥る可能性もあります。
ルール設定のポイントは、「自由」と「責任」のバランスです。
- 基本は自由:子どもが自分の判断でお金を使うことで、何にどれくらいお金がかかるのか、何を買えば満足できるのかといったことを肌で感じられます。
- 最低限の制限:安全に関わるもの(危険なもの、不適切なもの)や、教育上好ましくないもの(ギャンブル性の高いもの、他人に迷惑をかけるもの)については、事前に購入を禁止するルールを設けておきましょう。
- 親子での話し合い:ルールは親が一方的に決めるのではなく、子どもと一緒に話し合って決めることが大切です。なぜそのルールが必要なのかを説明し、子どもが納得できるように導きましょう。
- 貯蓄・寄付の推奨:「使う」だけでなく、「貯める」ことの重要性も教えるために、おこづかいの一部を貯蓄に回すことを推奨したり、寄付という選択肢を教えたりするのも良いでしょう。
- ルール違反への対応:もしルールを破ってしまった場合の対応も、事前に話し合っておくと安心です。例えば、「次のおこづかいを減らす」「一時的にストップする」など、具体的なペナルティを決めておきます。
「失敗は学びのチャンス」と捉え、たとえ使いすぎてしまっても、頭ごなしに叱るのではなく、なぜそうなったのか、次からはどうすれば良いのかを一緒に考える姿勢が、子どもの成長を促します。
ゲーム感覚で楽しく続く!小学生のおこづかい管理をサポートするアイデア
小学生のおこづかい管理は、ただお金の計算をするだけでなく、「楽しい」と感じることが継続の鍵です。
ここでは、子どもが自ら進んでお金と向き合えるようになる、ゲーム感覚を取り入れた具体的なアイデアをご紹介します。
親子で協力しながら、金銭感覚を育む貴重な体験を積み重ねていきましょう。
おこづかい帳は最強ツール!小学生向けおこづかい帳の選び方と書き方
 おこづかい帳は、お金の流れを「見える化」し、計画的なお金の使い方や貯める習慣を身につけるための最強ツールです。
おこづかい帳は、お金の流れを「見える化」し、計画的なお金の使い方や貯める習慣を身につけるための最強ツールです。
記録をつけることで、自分が何にどれくらい使ったのか、あといくら使えるのかが明確になり、自然と金銭感覚が養われます。
子どもが飽きずに続けられるよう、それぞれのタイプに合ったおこづかい帳を選び、書き方を工夫することが大切です。
おこづかい帳の基本的な項目は以下の通りです。
親子で一緒に確認しながら、丁寧に記録する習慣をつけましょう。
項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
日付 | お金を使った日 もらった日 | いつお金が動いたかを 記録します。 |
項目(内容) | 何を買ったか 何に使ったか どこからもらったか | 具体的な品名や 目的を記録することで、 お金の使い道を 振り返りやすくなります。 |
収入 | おこづかい お年玉 お手伝いの報酬など | もらった金額を 記入します。 |
支出 | 使った金額 | 購入したものの金額を 記入します。 |
残高 | 現在の手持ちのお金 | 「前の日の残高+収入-支出」で 計算します。計算力を養う 良い機会にもなります。 |
手書き派におすすめ!市販のおこづかい帳・自作ワークシート
 手書きのおこづかい帳は、実際にペンを動かすことで、お金の流れをより深く意識できるというメリットがあります。
手書きのおこづかい帳は、実際にペンを動かすことで、お金の流れをより深く意識できるというメリットがあります。
市販のおこづかい帳には、キャラクターデザインのものから、シンプルなデザイン、費目ごとに分けられるものまで様々な種類があります。
選ぶ際は、子どもの興味を引くデザインであること、記入欄が大きくて書きやすいこと、そして計算スペースが十分にあるかを確認しましょう。
また、シールやスタンプを使って、記録を楽しくデコレーションするのもおすすめです。
市販品以外にも、ノートやルーズリーフを使って自作したり、インターネットで無料のワークシートをダウンロードして活用する方法もあります。
自作の最大のメリットは、子どもの成長や興味に合わせて自由にカスタマイズできる点です。
例えば、目標貯金額を記入する欄を設けたり、達成度をグラフで示したりするのも良いでしょう。
親子で一緒にデザインを考える時間も、金銭教育の一環となります。
スマホ派におすすめ!小学生向けおこづかい管理アプリ
 スマートフォンやタブレットに慣れている子どもには、おこづかい管理アプリも有効な選択肢です。
スマートフォンやタブレットに慣れている子どもには、おこづかい管理アプリも有効な選択肢です。
アプリの最大の魅力は、自動計算機能やグラフ化機能により、手軽に正確な記録ができる点にあります。
視覚的に分かりやすく、お金の増減や使い道の割合を一目で把握できるため、子どもが飽きずに続けやすいでしょう。
アプリを選ぶ際は、子どもの年齢に合った操作のしやすさ、視覚的な分かりやすさ、そして広告の有無などを確認することが重要です。
また、親子で記録を共有できる機能があるアプリを選べば、親が子どものお金の管理状況を把握しやすくなり、適切なアドバイスを与える助けにもなります。
ただし、スマートフォン利用には時間管理やセキュリティ面での注意も必要です。
アプリを使う際は、使用時間やパスワードの管理について親子でルールを決め、あくまでお金の管理をサポートするツールとして活用するようにしましょう。
貯める習慣を身につける!目標設定と見える化の工夫
 おこづかい管理で最も大切なことの一つは、「貯める」という習慣を身につけることです。
おこづかい管理で最も大切なことの一つは、「貯める」という習慣を身につけることです。
そのためには、具体的な目標を設定し、その達成状況を「見える化」する工夫が効果的です。
まずは、子ども自身に「何のために貯めたいのか」を考えさせましょう。
欲しいゲームソフト、憧れのおもちゃ、家族旅行の費用、習い事の道具など、具体的な目標があることで、貯めるモチベーションが格段に上がります。
目標金額と期限を明確に設定し、それを達成するための計画を親子で話し合います。
目標の「見える化」には様々な方法があります。
例えば、透明な貯金箱を用意し、お金が貯まっていく様子を毎日確認できるようにする、目標金額までの道のりをグラフや絵で表した「貯金マップ」を作成し、貯金するたびに色を塗ったりシールを貼ったりする、といった方法が考えられます。
貯金箱に「〇〇(目標物)貯金」と書いたり、目標物の写真を貼ったりするのも良いでしょう。
目標を達成した際には、親子でその喜びを分かち合い、頑張りを心から褒めてあげることが重要です。
達成感は次の目標への意欲につながり、より一層貯める習慣を定着させます。
お金の価値を学ぶ!親子でできる金銭教育アクティビティ
 おこづかい管理は、単なる計算練習ではありません。
おこづかい管理は、単なる計算練習ではありません。
お金がどのように稼がれ、どのように使われ、どのような価値を持つのかを理解するための大切な金銭教育の機会です。
日常生活や遊びの中に、お金の価値を学ぶアクティビティを取り入れてみましょう。
- 買い物体験:スーパーやコンビニエンスストアへ一緒に買い物に行き、商品の値段を比較させたり、予算内で必要なものを選ばせたりする体験は、お金の価値を肌で感じる良い機会です。レジでの支払いやおつりの確認も、計算力と金銭感覚を養います。
- お店屋さんごっこ:自宅で「お店屋さんごっこ」をするのも効果的です。子どもが店員役と客役を交代で体験することで、商品を売る側の気持ちや、お金を払って物を手に入れるという行為を遊びながら学ぶことができます。値段設定や商品の陳列なども任せてみましょう。
- 公共料金や税金の話:家庭で電気やガス、水道の料金明細を見せながら、「これだけのお金で、私たちの生活が成り立っているんだよ」と話すことで、お金が社会を支えていることを具体的に伝えることができます。税金についても、身近な例を挙げて説明してみましょう。
- ボードゲーム:「人生ゲーム」や「モノポリー」など、お金を扱うボードゲームは、楽しみながらお金の管理や投資の概念を学ぶのに最適です。ゲームを通じて、お金が増えたり減ったりする仕組み、計画的な支出の重要性を体験できます。
- お金に関する絵本や漫画:お金の歴史や役割、働き方と対価の関係などを分かりやすく解説した絵本や漫画を一緒に読むのもおすすめです。視覚的に理解を深めることができます。
これらのアクティビティを通じて、子どもはお金が「限りある資源」であり、大切に使うべきものであるという認識を深めていくでしょう。
親は、子どもの疑問に丁寧に答え、共に考える姿勢を示すことが大切です。
金銭感覚と貯める習慣を育む!小学生のおこづかい管理で大切なこと
「使う」「貯める」のバランスを学ぶ!計画的なおこづかいの使い方
子どもたちは、自分のお金で欲しいものを買う喜びを知る一方で、計画的にお金を使うことの重要性や、目標のために貯蓄する大切さを学びます。
まず、おこづかいをもらったら、何に使うか、どれくらい貯めるかを親子で話し合う時間を持つことをおすすめします。
例えば、「今すぐ使いたいもの」「将来のために貯めておきたいもの」の二つのカテゴリに分けて考えさせることで、自然と計画性が育まれます。
貯蓄を促すためには、具体的な目標設定が有効です。
例えば、「誕生日プレゼントとして欲しいゲームを買うために貯める」「家族旅行で使うおやつ代を貯める」など、子どもがワクワクするような目標を設定し、その目標達成に向けてどれくらい貯める必要があるかを一緒に計算してみましょう。
目標を達成した時の喜びは、その後の貯蓄習慣に大きく影響します。
また、衝動買いをしておこづかいがすぐになくなってしまう経験も、学びの機会です。
なぜすぐに使い切ってしまったのか、次からはどうすればいいかを振り返ることで、より賢いお金の使い方を身につけることができます。
「消費」「浪費」「投資」といった概念を簡単な言葉で伝え、お金の使い道について親子で対話することも、金銭感覚を育む上で非常に有効です。
失敗は学びのチャンス!小学生がおこづかいで困った時の親の対応
 小学生のおこづかい管理において、子どもが失敗することは避けられません。
小学生のおこづかい管理において、子どもが失敗することは避けられません。
しかし、その失敗こそが、金銭感覚を磨くための貴重な学びの機会となります。
親は、子どもが困った時にどのように対応するかが非常に重要です。
よくある失敗としては、「おこづかいを使いすぎてしまい、次のおこづかい日まで何も買えない」「衝動買いをして後で後悔する」「おこづかい帳をつけずにお金がどこへ行ったかわからなくなる」などが挙げられます。
このような時、親がまずすべきことは、子どもを叱るのではなく、まずは子どもの話に耳を傾け、困っている気持ちに寄り添うことです。
「どうして困っているの?」「何があったのか教えてくれる?」と優しく問いかけ、子どもの状況を理解することから始めましょう。
その後、なぜそうなってしまったのか、原因を一緒に考えます。
例えば、「計画を立てなかったからかな?」「本当に必要だったものだったかな?」など、具体的な問いかけで気づきを促します。
そして、最も大切なのは、子ども自身に解決策を考えさせることです。
親が安易に前借りさせたり、追加のおこづかいを与えたりすることは、自立心を育む機会を奪ってしまいます。
「次のおこづかいまで我慢する」「本当に必要なものだけ買うようにする」といった解決策を子ども自身が見つけられるよう、サポートしましょう。
失敗から学んだことを確認し、「次はこうしてみようね」と前向きなアドバイスを送ることで、子どもは失敗を恐れずに挑戦し、成長していくことができます。
「失敗しても大丈夫、そこから学べばいい」というメッセージを伝え続けることが、子どもの金銭感覚を育む上で非常に大切です。
親ができるサポート!小学生のおこづかい管理を見守るヒント
 小学生のおこづかい管理は、親が一方的に教え込むものではなく、子どもが自ら学び、成長していくプロセスを親が適切に見守り、サポートすることが成功の鍵となります。
小学生のおこづかい管理は、親が一方的に教え込むものではなく、子どもが自ら学び、成長していくプロセスを親が適切に見守り、サポートすることが成功の鍵となります。
過干渉にならず、かといって放置もしない、絶妙なバランスが求められます。
以下に、親ができる具体的なサポートのヒントをまとめました。
サポートのポイント | 具体的な行動・声かけ |
|---|---|
定期的な 対話の場を 設ける | 「今週は何に使ったの?」 「何か欲しいものはある?」など、 定期的におこづかいについて 話す時間を作りましょう。 おこづかい帳を一緒に見ながら、 使途を振り返るのも良い機会です。 「なぜそれを買いたかったの?」 「使ってみてどうだった?」など、 子どもの選択の背景や 感想を聞くことで、 お金の価値や満足度について 考えさせることができます。 |
親自身の 金銭感覚 を示す | 親が計画的に お金を使う姿を見せることは、 子どもにとって何よりの教育です。 スーパーでの買い物時に 「これは必要だから買うね」 「これは今すぐ必要じゃないから、 また今度にしよう」など、 考えるプロセスを 言葉にして伝えましょう。 家計の話を簡単な言葉で共有し、 お金が無限ではないこと、 働いて得られるものであることを 理解させましょう。 |
自立を促す 見守り方 | 子どもがおこづかいを 使い切ってしまっても、 すぐに助け舟を出さず、 次のおこづかいまで待たせるなど、 「自分で何とかする」 経験をさせることが重要です。 ただし、困っている時には共感し、 一緒に解決策を考える姿勢を忘れずに。 最終的な判断は子どもに委ね、 その結果を受け入れることも 学びの一部です。 |
お金以外の 価値を 伝える | お金で買えない価値 (友情、健康、経験など)が あることを伝えましょう。 お金はあくまで道具であり、 人生を豊かにするための 手段であることを 教えることが大切です。 寄付や募金を通じて、 お金が社会貢献にもつながることを 教えるのも良い経験になります。 |
親が見守り、適切なタイミングでアドバイスを送ることで、子どもは金銭管理能力だけでなく、自己管理能力や問題解決能力も高めていくことができます。
信頼関係を築きながら、子どもの成長を温かくサポートしていきましょう。
まとめ
小学生のおこづかい管理は、単にお金を渡すだけでなく、お子さんが将来にわたって役立つ金銭感覚や貯める習慣を育む大切な機会です。
ゲーム感覚で楽しみながら、おこづかい帳の活用や目標設定を通じて、お金の価値や計画的な使い方を親子で学んでいきましょう。
失敗を恐れず、親が見守り、適切にサポートすることで、お子さんはお金との健全な付き合い方を身につけ、自立心を育んでいけます。
今日からぜひ、親子で楽しくおこづかい管理を始めてみませんか。






