
【保存版】赤ちゃん行事のやること完全ガイド!生後すぐ~1歳までを徹底解説
赤ちゃんが生まれて初めての行事、何から手をつけていいか迷っていませんか?
お七夜、お宮参り、お食い初め、初誕生など、大切なイベントが目白押しで「やること」が多くて不安に感じる方もいるでしょう。
この記事では、生後すぐから1歳までの主要な赤ちゃん行事について、目的から具体的な準備、当日の流れ、費用、誰を呼ぶかまで、知りたい情報を網羅的に解説します。
この完全ガイドを読めば、各行事を自信を持って迎えられ、大切な思い出をスムーズに作ることができます。
不安を解消し、赤ちゃんとの特別な時間を存分に楽しむための「やることリスト」としてご活用ください。
目次[非表示]
- 1.はじめに 赤ちゃん行事のやることリストで不安を解消しよう
- 2.赤ちゃん行事の基本 目的と一般的な流れ
- 2.1.赤ちゃん行事を行う意味とは
- 2.2.行事の準備で押さえておきたいポイント
- 3.生後すぐに行う赤ちゃん行事のやること
- 3.1.お七夜 命名式のやること
- 3.1.1.①お七夜・命名式でやることリスト
- 3.1.2.➁命名書の書き方
- 3.2.出産祝いのお返し 内祝いのやること
- 3.2.1.①内祝いを贈る時期
- 3.2.2.➁内祝いの品物選びと準備
- 4.生後100日前後に行う赤ちゃん行事のやること
- 4.1.お宮参りのやること 完全ガイド
- 4.1.1.①お宮参りの時期と目的
- 4.1.2.➁お宮参りの準備リスト
- 4.1.3.③お宮参り当日の流れと注意点
- 4.1.4.④お宮参りの費用の目安
- 4.2.お食い初めのやること 完全ガイド
- 4.2.1.①お食い初めの時期と目的
- 4.2.2.➁お食い初めの準備リスト
- 4.2.3.③お食い初めの献立と食器
- 4.2.4.④お食い初め当日の流れと儀式
- 4.2.5.⑤お食い初めの費用の目安
- 5.生後半年頃に行う赤ちゃん行事のやること
- 5.1.ハーフバースデーのやること
- 5.2.初節句(桃の節句・端午の節句)のやること
- 5.2.1.桃の節句(ひな祭り)のやること
- 5.2.2.端午の節句(こどもの日)のやること
- 6.1歳頃に行う赤ちゃん行事のやること
- 6.1.初誕生祝いのやること 一升餅・選び取り
- 6.1.1.①初誕生祝いの準備と流れ
- 6.1.2.➁一升餅のやること
- 6.1.3.③選び取りのやること
- 6.1.3.1.選び取りの準備
- 6.1.3.2.選び取りの品物例と意味
- 7.赤ちゃん行事のやること よくある質問
- 7.1.Q1,行事はすべてやらなきゃダメ?
- 7.2.Q2,費用はどのくらいかかる?
- 7.3.Q3,誰を呼ぶべき?
- 8.まとめ
はじめに 赤ちゃん行事のやることリストで不安を解消しよう
赤ちゃんが生まれて、喜びとともに
「これからどんな行事があるんだろう?」
「何を準備すればいいの?」
と、少し不安を感じていませんか?
初めての育児では、お七夜やお宮参り、お食い初めなど、様々な伝統的な赤ちゃん行事が控えています。
これらの行事は、赤ちゃんの健やかな成長を願う大切な機会ですが、慣れないことばかりで
「やることが多すぎて大変そう」
「どこから手をつけていいか分からない」
と感じるパパママも少なくありません。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するため、生後すぐから1歳までに行う主要な赤ちゃん行事について、それぞれの「やること」を完全ガイドとしてまとめました。
準備から当日の流れ、必要なものまで、具体的なやることリストとして分かりやすく解説します。
このガイドを読めば、赤ちゃん行事の全体像を把握し、安心して大切な記念日を迎えられるでしょう。ぜひ、赤ちゃんの成長を祝うかけがえのない時間を、心ゆくまで楽しんでください。
赤ちゃん行事の基本 目的と一般的な流れ
 赤ちゃんが生まれてから1歳になるまでの間には、様々な伝統的な行事があります。
赤ちゃんが生まれてから1歳になるまでの間には、様々な伝統的な行事があります。
これらの行事は、単なる形式ではなく、赤ちゃんの健やかな成長を願い、家族の絆を深める大切な機会となります。
まずは、赤ちゃん行事を行う意味と、準備の際に押さえておきたい基本的なポイントを見ていきましょう。
赤ちゃん行事を行う意味とは
赤ちゃん行事には、古くからの伝統に基づいた深い意味が込められています。主な目的は以下の通りです。
主な目的 | 具体的な内容 |
|---|---|
健やかな成長 | 神様への感謝と祈願 |
家族の絆 | 喜びを分かち合う |
伝統継承 | 日本の文化に触れる |
成長の節目 | 記録を残し振り返る |
社会へのお披露目 | 親戚や友人に紹介 |
これらの行事を通じて、親として改めて赤ちゃんへの愛情を確認し、家族や親戚と共に喜びを分かち合うことができます。
また、日本の文化や伝統に触れる貴重な機会でもあります。
行事の準備で押さえておきたいポイント
赤ちゃん行事をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
特に重要な準備項目は以下の通りです。
準備項目 | 確認事項 |
|---|---|
スケジュール | 赤ちゃんの体調優先 |
スケジュール | 参加者の都合調整 |
場所の選定 | 自宅か外部施設か |
衣装の準備 | セレモニードレス等 |
費用の目安 | 大まかな予算設定 |
参加者の範囲 | 誰を招待するか |
記念撮影 | プロに依頼するか |
情報収集 | 地域の習慣を確認 |
これらの準備を始める際は、無理のない計画を立てることが最も重要です。
赤ちゃんの体調を最優先し、家族とよく相談しながら進めましょう。
焦らず、準備の過程も楽しむ気持ちで臨むことが大切です。
生後すぐに行う赤ちゃん行事のやること
赤ちゃんが生まれてすぐに行う行事は、新しい家族を迎え入れた喜びを分かち合い、今後の健やかな成長を願う大切な機会です。
ここでは、生後間もなく行う「お七夜・命名式」と、出産祝いへのお礼である「内祝い」について、それぞれやるべきことを詳しく解説します。
お七夜 命名式のやること
赤ちゃんが生まれて初めて迎えるお祝いが「お七夜」です。
これは、赤ちゃんの誕生から7日目の夜に行う伝統的な行事で、無事に生まれたことを喜び、健やかな成長を願うとともに、社会の一員として迎え入れる意味合いがあります。
お七夜と合わせて行われることが多いのが「命名式」です。
これは、赤ちゃんの名前を正式に発表し、命名書を作成して神棚や床の間、ベビーベッドの近くなどに飾る儀式です。
家族の絆を深める大切な時間となります。
①お七夜・命名式でやることリスト
お七夜・命名式は、自宅で家族のみで行うのが一般的です。
特別な準備は不要ですが、以下のことを準備しておくとスムーズに進められます。
やること | 詳細 |
|---|---|
命名書作成 | 赤ちゃんの名前を記入 |
お祝い膳 | 家族でごちそうを囲む |
記念撮影 | 赤ちゃんと命名書で |
赤ちゃんの紹介 | 家族や親戚へ |
➁命名書の書き方
 命名書は、市販のものや手書きのものでも構いません。
命名書は、市販のものや手書きのものでも構いません。
以下の項目を正確に記入しましょう。
項目 | 内容 |
|---|---|
氏名 | 赤ちゃんのフルネーム |
生年月日 | 和暦で記入 |
名付け親 | 父母の名前など |
続柄 | 長男、長女など |
日付 | 命名日 |
命名書は、赤ちゃんの名前を家族や親戚に披露する大切なものです。
心を込めて丁寧に書きましょう。
出産祝いのお返し 内祝いのやること

出産祝いをいただいた方へのお礼として贈るのが「内祝い」です。
本来は「身内でのお祝いごと」を分かち合う意味合いがありましたが、現代ではお祝いへのお礼として定着しています。
感謝の気持ちを伝える大切な機会ですので、失礼のないように準備しましょう。
①内祝いを贈る時期
内祝いを贈る時期は、赤ちゃんが生後1ヶ月頃、お宮参りの時期を目安にするのが一般的です。
遅くとも生後2ヶ月以内には贈るようにしましょう。
出産直後は体調が優れないこともありますので、無理のない範囲で準備を進めることが大切です。
➁内祝いの品物選びと準備
内祝いの品物選びや準備でやることのポイントは以下の通りです。
項目 | 詳細 |
|---|---|
相場 | いただいた金額の1/3~半額 |
品物 | タオル、お菓子、カタログギフトなど |
のし | 「内祝」と赤ちゃんの名前 |
メッセージ | お礼と赤ちゃんの報告 |
品物は、相手の好みを考慮しつつ、日持ちするものや実用的なものを選ぶと喜ばれます。
また、赤ちゃんの名前を記した「のし」をつけ、出産報告と感謝の気持ちを伝えるメッセージカードを添えると、より丁寧な印象になります。
生後100日前後に行う赤ちゃん行事のやること
生後100日前後は、赤ちゃんの成長を祝い、今後の健やかな成長を願う大切な行事が集中する時期です。
代表的な行事である「お宮参り」と「お食い初め」について、それぞれ具体的な「やること」を解説します。
お宮参りのやること 完全ガイド

お宮参りは、赤ちゃんが無事に生まれたことを氏神様に報告し、今後の健やかな成長を願う伝統的な行事です。
一般的には生後1ヶ月頃に行われますが、赤ちゃんの体調や気候を最優先し、無理のない時期を選びましょう。
①お宮参りの時期と目的
男の子は生後31日目、女の子は生後32日目頃に行うのが一般的とされています。
しかし、あくまで目安であり、真夏や真冬、雨の日などは避け、赤ちゃんとママの体調が落ち着いてから行うのが賢明です。
この行事の目的は、氏神様(その土地を守る神様)に赤ちゃんの誕生を報告し、健やかな成長を見守っていただくことです。
➁お宮参りの準備リスト
お宮参りを行うにあたり、事前に準備すべきことをまとめました。
項目 | やること |
|---|---|
参拝先の決定 | 氏神様や 有名な神社を選ぶ |
ご祈祷の予約 | 事前に電話で 確認・予約 |
初穂料の準備 | のし袋に入れ、 金額を確認 |
赤ちゃんの衣装 | 祝い着(産着)を準備 |
両親・参列者の服装 | フォーマルな服装を用意 |
写真撮影の手配 | スタジオ撮影や 出張撮影の検討 |
会食場所の検討 | 自宅かお店か、 予約が必要か確認 |
移動手段の確保 | ベビーカー、 抱っこ紐など |
③お宮参り当日の流れと注意点
当日は、まず神社へ向かい、ご祈祷を受ける場合は受付を済ませます。
ご祈祷中は赤ちゃんが泣き出すこともあるため、授乳やおむつ替えの準備をしておきましょう。
ご祈祷後は、境内で記念撮影をしたり、家族で会食をしたりして過ごします。
長時間の外出は赤ちゃんに負担がかかるため、休憩を挟みながら無理なく進めることが大切です。
④お宮参りの費用の目安
お宮参りにかかる費用は、ご祈祷料、衣装代、写真代、会食代などによって大きく変動します。
費用の内訳 | 目安 |
|---|---|
ご祈祷料(初穂料) | 5,000円~10,000円 |
赤ちゃんの衣装代 | レンタル:5,000円~ 購入:20,000円~ |
写真撮影代 | 10,000円~50,000円 |
会食代 | 人数や場所による |
これらはあくまで目安であり、ご家庭の状況に合わせて計画しましょう。
お食い初めのやること 完全ガイド
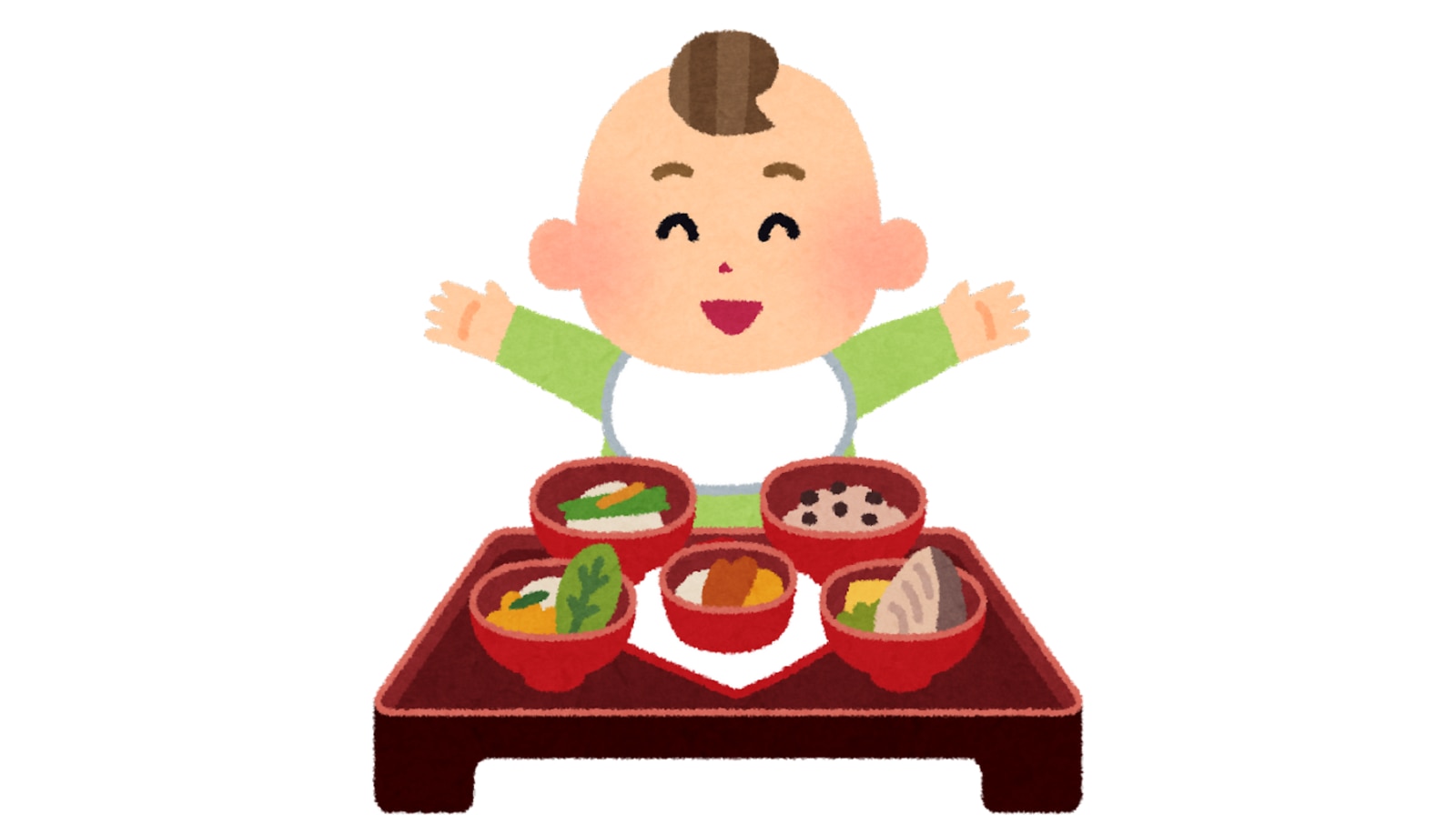
お食い初めは、赤ちゃんが「一生涯、食べることに困らないように」という願いを込めて行う伝統的なお祝いです。
生後100日~120日目頃に行うのが一般的で、「百日祝い(ももかいわい)」とも呼ばれます。
①お食い初めの時期と目的
生後100日目頃に行うのが一般的ですが、この日ちょうどに行う必要はありません。
赤ちゃんの体調やご家族の都合に合わせて、生後100日~120日頃の間で吉日を選んで行いましょう。
この行事の目的は、赤ちゃんに初めてお膳を用意し、食べさせる真似をすることで、食の神様へ感謝し、健やかな成長と食に困らない人生を願うことです。
➁お食い初めの準備リスト
お食い初めをスムーズに進めるための準備リストです。
項目 | やること |
|---|---|
献立の決定 | 祝い膳のメニューを決める |
食材の準備 | 鯛、赤飯、吸い物など |
食器の準備 | お祝い膳(漆器など)を用意 |
歯固めの石 | 神社で借りるか、通販で購入 |
祝い箸 | 新しい箸を用意する |
「養い親」の選定 | 儀式で食べさせる役の人 |
写真撮影の準備 | 記念撮影の場所や道具 |
③お食い初めの献立と食器
お食い初めの献立は、一般的に「一汁三菜」が基本です。
縁起の良い食材が使われます。
献立例 | 意味合い |
|---|---|
鯛の塩焼き | 「めでたい」に通じる |
赤飯 | 邪気を払う、魔除け |
吸い物 | 吸う力が強くなるように |
煮物 | 根菜で根気強く育つように |
香の物(漬物) | 長寿を願う |
歯固めの石 | 丈夫な歯が生えるように |
食器は、男の子は朱色、女の子は黒色の漆器を用いるのが一般的ですが、最近ではベビー食器セットなど、可愛らしいものも多く販売されています。
自宅にある食器で代用しても問題ありません。
④お食い初め当日の流れと儀式
お食い初めは、家族が集まって行われることが多いでしょう。
儀式では、「養い親」と呼ばれる長寿の親族(祖父母など)が赤ちゃんを抱き、箸で食べ物を赤ちゃんの口元に運び、食べさせる真似をします。
この際、以下の順番で食べさせるのが一般的です。
- ご飯
- 吸い物
- ご飯
- 魚
- ご飯
- 吸い物
これを3回繰り返します。
最後に「歯固めの儀式」として、歯固めの石に箸を軽く触れさせ、その箸を赤ちゃんの歯茎に優しく当てて、「丈夫な歯が生えますように」と願います。
⑤お食い初めの費用の目安
お食い初めにかかる費用は、手作りするか、仕出しを頼むか、外食するかで大きく変わります。
費用の内訳 | 目安 |
|---|---|
食材費(手作り) | 5,000円~10,000円 |
仕出し・宅配 | 5,000円~15,000円 |
外食(お店) | 10,000円~30,000円 |
食器レンタル | 3,000円~5,000円 |
自宅で行う場合は食材費が中心となり、外食や仕出しを利用する場合は、その費用が加算されます。
ご家庭のスタイルに合わせて選びましょう。
生後半年頃に行う赤ちゃん行事のやること
赤ちゃんが生まれて半年が経つ頃には、生活リズムも整い、表情も豊かになります。
この時期に行う行事として、ハーフバースデーと初節句があります。
どちらも赤ちゃんの健やかな成長を祝う大切な節目です。
ハーフバースデーのやること
 ハーフバースデーとは、生後6ヶ月を迎えた赤ちゃんを祝う行事です。
ハーフバースデーとは、生後6ヶ月を迎えた赤ちゃんを祝う行事です。
半年間の成長を振り返り、記念に残すことが目的です。
特別な儀式があるわけではなく、家族でお祝いするのが一般的です。
ハーフバースデーの主なやることリストは以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
時期 | 生後6ヶ月頃 |
目的 | 半年の成長を祝う |
記念撮影 | 寝相アート 飾り付け |
食事 | 離乳食ケーキ 家族での食事 |
プレゼント | 記念品を選ぶ |
準備 | 飾り付け用意 衣装準備 |
寝相アートや飾り付けで写真を撮ったり、離乳食が始まっていれば離乳食ケーキを作ってあげるのも良い思い出になります。
家族みんなで赤ちゃんの成長を喜びましょう。
初節句(桃の節句・端午の節句)のやること
初節句は、赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句のことです。
女の子は桃の節句(ひな祭り)、男の子は端午の節句(こどもの日)として、子どもの健やかな成長と幸福を願う大切な行事です。
桃の節句(ひな祭り)のやること
 桃の節句は、3月3日に女の子の健やかな成長を願う行事です。
桃の節句は、3月3日に女の子の健やかな成長を願う行事です。
主に雛人形を飾り、お祝いの食事をします。
桃の節句の主なやることリストは以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
時期 | 3月3日 |
対象 | 女の子 |
飾り付け | 雛人形を飾る |
食事 | ちらし寿司 はまぐり汁 |
食事 | ひなあられ 菱餅 |
お祝い | 家族や親戚と |
雛人形は、2月中旬頃から飾り始め、節句が終わったらすぐに片付けるのが良いとされています。
お祝いの食事には、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物、ひなあられなどが定番です。
端午の節句(こどもの日)のやること
 端午の節句は、5月5日に男の子の健やかな成長と立身出世を願う行事です。
端午の節句は、5月5日に男の子の健やかな成長と立身出世を願う行事です。
五月人形や鯉のぼりを飾り、お祝いの食事をします。
端午の節句の主なやることリストは以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
時期 | 5月5日 |
対象 | 男の子 |
飾り付け | 五月人形 鯉のぼり |
食事 | ちまき |
食事 | 柏餅 |
風習 | 菖蒲湯に入る |
お祝い | 家族や親戚と |
五月人形や鯉のぼりは、4月中旬頃から飾り始めます。
お祝いの食事には、ちまきや柏餅が定番です。
また、菖蒲湯に入ることで、無病息災を願う風習もあります。
1歳頃に行う赤ちゃん行事のやること
赤ちゃんが生まれてから初めて迎える誕生日、「初誕生祝い」は特別な節目です。
1歳まで無事に成長したことへの感謝と、これからの健やかな成長を願う大切な行事。
この章では、初誕生祝いの中でも特に人気の高い「一升餅」と「選び取り」を中心に、具体的なやることや準備について解説します。
初誕生祝いのやること 一升餅・選び取り
 初誕生祝いは、地域や家庭によって様々な祝い方がありますが、多くの場合、家族や親しい親族が集まって行われます。
初誕生祝いは、地域や家庭によって様々な祝い方がありますが、多くの場合、家族や親しい親族が集まって行われます。
ここでは、一般的な流れと、メインとなる一升餅・選び取りについて詳しく見ていきましょう。
①初誕生祝いの準備と流れ
まずは、初誕生祝いを行う上での基本的な準備と当日の流れを把握しましょう。
- 日時と場所の決定:家族や親族の都合を考慮し、自宅やレストランなどを選びます。
- 招待客の選定と連絡:誰を招待するかを決め、早めに連絡します。
- 食事の手配:自宅で手作りするか、仕出し料理やケータリングを利用するか検討します。
- バースデーケーキの準備:赤ちゃんが食べられる素材を使ったケーキを選ぶ家庭も増えています。
- 記念撮影の準備:写真や動画で思い出を残しましょう。
➁一升餅のやること
 一升餅は、「一生食べ物に困らないように」「一生健康に過ごせるように」という願いを込めて、1歳になった赤ちゃんに約1.8kg(一升)のお餅を背負わせる伝統的な行事です。
一升餅は、「一生食べ物に困らないように」「一生健康に過ごせるように」という願いを込めて、1歳になった赤ちゃんに約1.8kg(一升)のお餅を背負わせる伝統的な行事です。
地域によっては「踏み餅」として、お餅を踏ませる場合もあります。
一升餅の準備
- お餅の手配:和菓子店や餅専門店、インターネット通販などで購入できます。名前入りのものや小分けにされたものもあります。
- 風呂敷またはリュックの準備:お餅を背負わせるためのものです。赤ちゃん用の可愛いリュックも人気です。
一升餅のやり方
一般的な一升餅のやり方は以下の通りです。
- お餅を風呂敷で包むか、リュックに入れます。
- 赤ちゃんに背負わせます。
- 赤ちゃんが立ち上がろうとしたり、歩こうとしたりする姿を見守ります。
赤ちゃんにとって重いお餅を背負うことは大変なことです。
無理強いせず、赤ちゃんのペースに合わせて行いましょう。
転んでも大丈夫なように、周囲にクッションなどを置くと安心です。
③選び取りのやること
選び取りは、赤ちゃんの前に様々な品物を並べ、どれを手に取るかで将来の職業や才能を占う楽しい行事です。
赤ちゃんが何に興味を持つか、家族みんなで盛り上がります。
選び取りの準備
- 品物の選定:赤ちゃんの興味を引きそうな、安全な品物を選びましょう。
- スペースの確保:赤ちゃんが自由に動き回れるよう、広い場所で行います。
選び取りの品物例と意味
選び取りでよく使われる品物とその意味をまとめました。

品物 | 意味 |
|---|---|
お金(財布) | お金に困らない |
筆・ペン | 学者・物書き |
そろばん・電卓 | 商売上手・計算に強い |
ハサミ | 手先が器用・美容師 |
ボール | スポーツ選手 |
定規 | 建築家・几帳面 |
辞書 | 知識豊富・研究者 |
おもちゃ | 楽しい人生 |
楽器 | 音楽の才能 |
スプーン | 料理人・食べ物に困らない |
これらの品物以外にも、家庭ならではの品物を取り入れるのも良いでしょう。
例えば、赤ちゃんが好きな絵本や、親の職業に関連する小物などもおすすめです。
選び取りはあくまでお祝いのイベントです。
結果にとらわれすぎず、赤ちゃんの成長を喜び、家族の楽しい思い出として残しましょう。
赤ちゃん行事のやること よくある質問
赤ちゃんとの生活では、たくさんの「初めて」があり、行事についても疑問や不安を感じる方もいるでしょう。
ここでは、赤ちゃん行事に関するよくある質問にお答えします。
Q1,行事はすべてやらなきゃダメ?
赤ちゃん行事は、すべてを義務的に行う必要はありません。
古くからの伝統的な意味合いを持つものが多いですが、現代においてはご家庭の状況や考え方に合わせて、無理なく行うことが大切です。
例えば、遠方に住む祖父母が参加できない場合は、日を改めて家族だけでお祝いしたり、写真撮影のみにしたりと、柔軟に対応しても問題ありません。
大切なのは、赤ちゃんの健やかな成長を願う気持ちです。
ご家族で話し合い、どの行事をどのように行うか決めましょう。
Q2,費用はどのくらいかかる?
赤ちゃん行事にかかる費用は、行事の種類や規模、内容によって大きく異なります。
主な費用の内訳としては、衣装代、写真撮影代、食事代、初穂料(お宮参りなど)などが挙げられます。
一般的な目安を以下の表にまとめました。
これはあくまで一例であり、ご家庭の予算に合わせて調整することが可能です。
行事名 | 費用目安 | 主な内訳 |
|---|---|---|
お七夜 | 5千円~3万円 | 食事 記念品 |
お宮参り | 3万円~10万円 | 初穂料 衣装 写真 食事 |
お食い初め | 1万円~5万円 | 食材 食器 食事 |
ハーフバースデー | 5千円~3万円 | 飾り付け ケーキ |
初節句 | 数千円~数十万円 | 飾り 食事 衣装 |
初誕生祝い | 2万円~8万円 | 一升餅 選び取り 食事 |
無理のない範囲で、思い出に残るお祝いを計画しましょう。
レンタル衣装や自宅での食事会などを活用すれば、費用を抑えることも可能です。
Q3,誰を呼ぶべき?
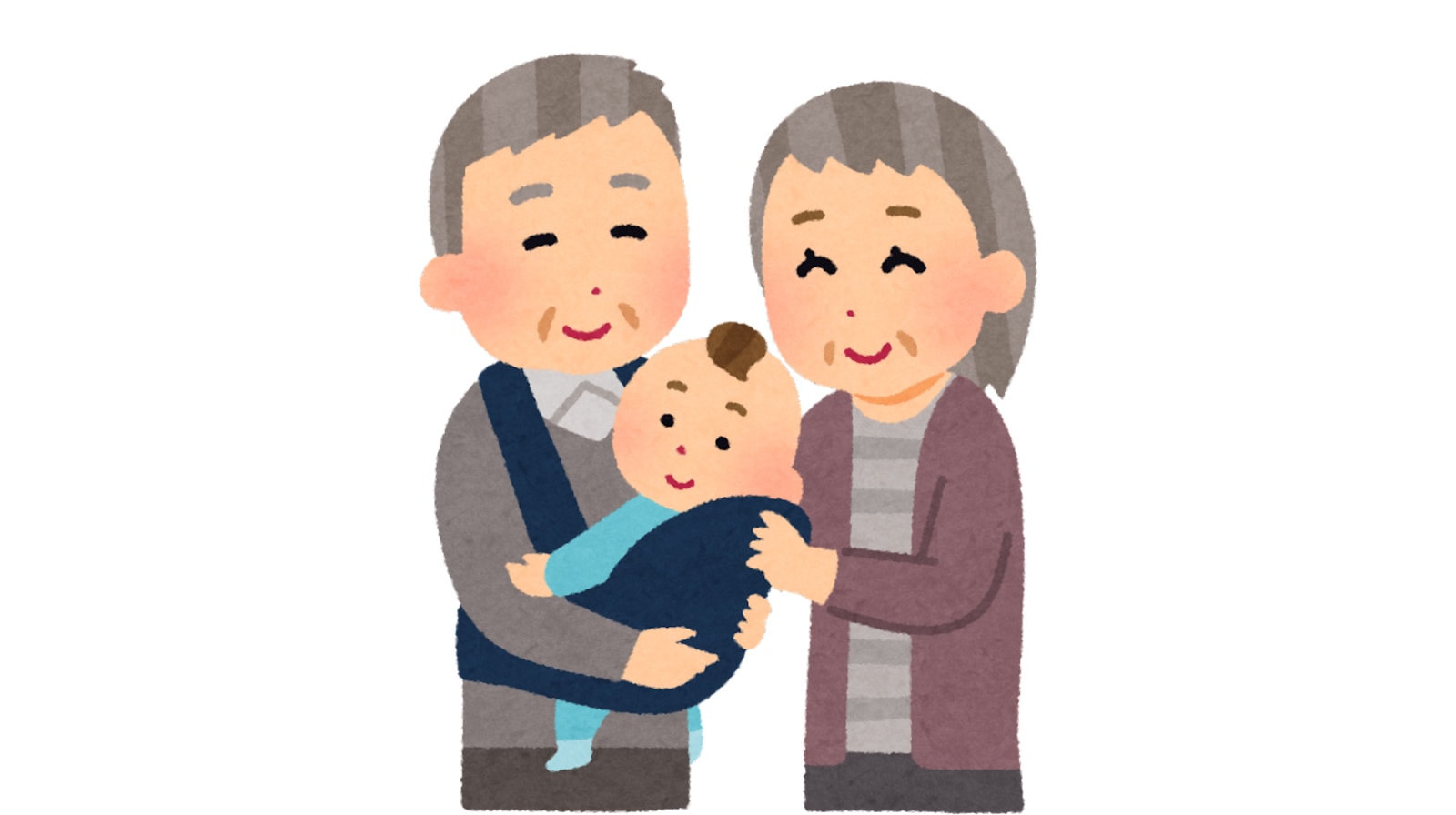 赤ちゃん行事に誰を呼ぶかは、行事の種類やご家庭の考え方によって異なりますが、基本的には両家の祖父母を招待することが多いです。
赤ちゃん行事に誰を呼ぶかは、行事の種類やご家庭の考え方によって異なりますが、基本的には両家の祖父母を招待することが多いです。
以下に、一般的な参加者の例を挙げます。
- お七夜:赤ちゃんと両親のみ、または祖父母を招くことも。
- お宮参り:赤ちゃんと両親、両家の祖父母。
- お食い初め:赤ちゃんと両親、両家の祖父母。
- ハーフバースデー:赤ちゃんと両親のみ、または親しい友人を招くことも。
- 初節句:赤ちゃんと両親、両家の祖父母。
- 初誕生祝い:赤ちゃんと両親、両家の祖父母。親しい親戚や友人を招くことも。
誰を呼ぶかは、ご家族の意向と、招待する方の都合を考慮して決めましょう。
招待客が多い場合は、会場の広さや費用なども考慮に入れる必要があります。
事前に両家と相談し、納得のいく形で進めることが大切です。
まとめ
赤ちゃんとの行事は、お子様の健やかな成長を祝い、家族の絆を深める貴重な機会です。
お七夜からお宮参り、お食い初め、ハーフバースデー、初節句、そして初誕生まで、それぞれの行事には大切な意味と具体的なやることがあります。
この記事が、忙しい日々の中で行事の準備を進める皆様の一助となり、不安なく、お子様との思い出を心ゆくまで楽しめるよう願っています。
完璧を目指すのではなく、家族のペースで、笑顔あふれる一日を過ごしてください。




