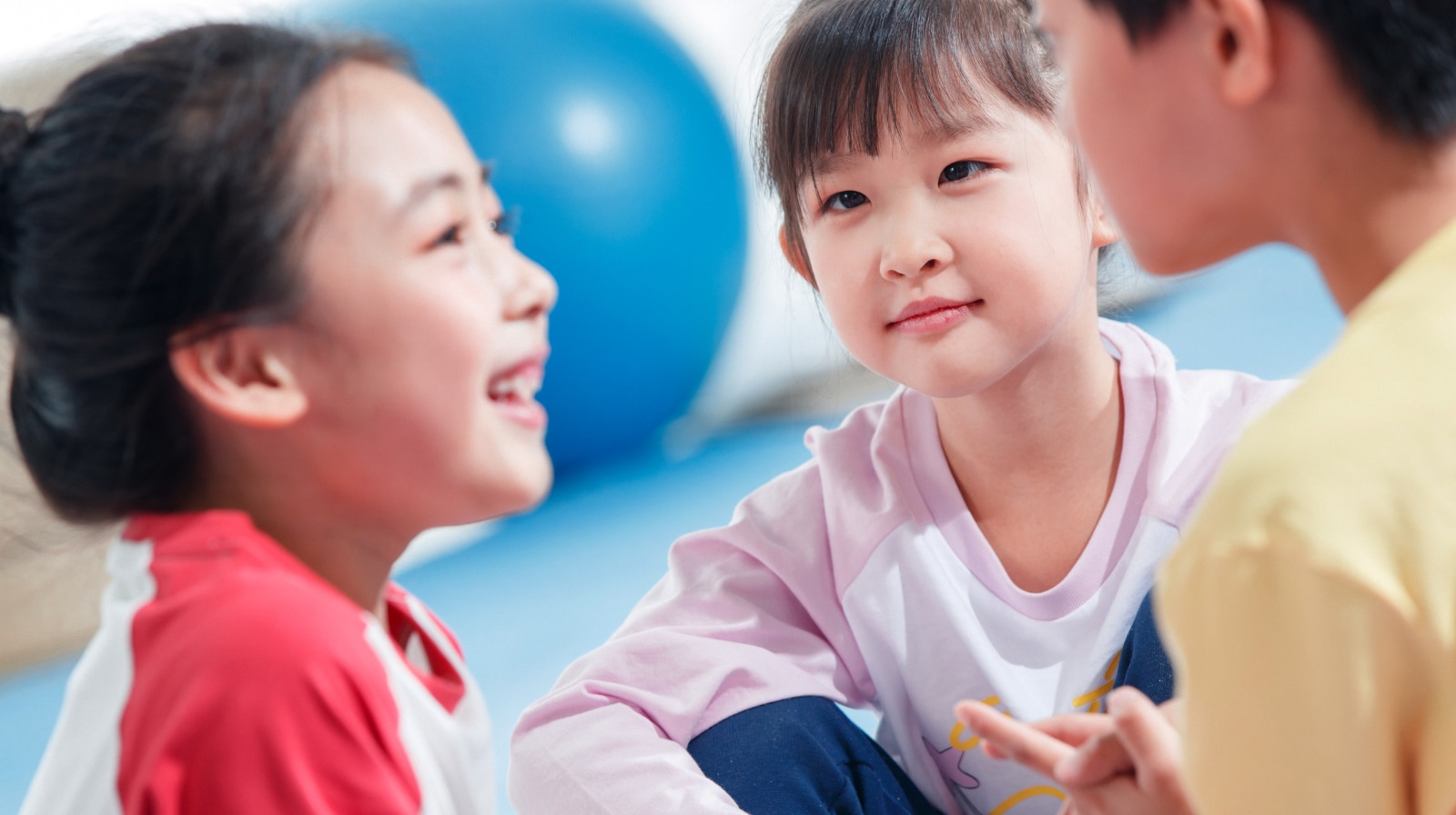将来に差がつく!小学生のコミュニケーション能力を育む家庭でできる簡単トレーニング
「うちの子、友達と上手に話せない」
「学校で意見を言えない」と悩んでいませんか?
小学生のコミュニケーション能力は、将来の人間関係や社会性を築く上で非常に重要です。
この記事では、なぜ今コミュニケーション能力が重要なのかを解説し、お子さんの現状がわかるチェックリスト、そして家庭で今日から実践できる簡単なトレーニング方法を具体的にご紹介します。
親の心構えも合わせて知ることで、お子様のコミュニケーション能力をぐんぐん伸ばし、自信を持って社会で活躍できる力を育むことができます。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、小学生のコミュニケーション能力が重要なのか
- 2.小学生のコミュニケーション能力 チェックリスト
- 3.家庭でできる!小学生のコミュニケーション能力を育む簡単トレーニング
- 3.1.会話力を高める日常の工夫
- 3.1.1.①質問で子どもの考えを引き出す
- 3.1.2.➁相槌と共感で聞く力を育む
- 3.1.3.➂家族会議で意見交換の場を作る
- 3.2.表現力を豊かにする遊びと学び
- 3.2.1.①絵本の読み聞かせと感想の共有
- 3.2.2.➁役割遊びやごっこ遊びで多様な視点を体験
- 3.2.3.➂ボードゲームやカードゲームで戦略的思考と交渉力を養う
- 3.3.自己肯定感を育み自信につなげる
- 3.3.1.①ポジティブな声かけで挑戦を応援する
- 3.3.2.➁お手伝いを通して役割と責任を学ぶ
- 3.3.3.➂感謝の気持ちを言葉で伝える習慣
- 4.小学生のコミュニケーション能力を伸ばす親の心構え
- 5.まとめ
なぜ今、小学生のコミュニケーション能力が重要なのか
将来を左右する非認知能力としてのコミュニケーション力

現代社会において、学力だけでなく、非認知能力の重要性がますます高まっています。
非認知能力とは、数値で測ることが難しい、意欲、協調性、忍耐力、自制心、そしてコミュニケーション能力といった、人間が社会で生きていく上で不可欠なスキルのことです。
特にコミュニケーション能力は、学業成績や将来のキャリア、さらには幸福な人間関係を築く上で、その基盤となる重要な要素とされています。
文部科学省が提唱する「生きる力」の概念や、OECD(経済協力開発機構)が提唱する「Education 2030」の学習の枠組みにおいても、知識の習得だけでなく、変化の激しい時代を生き抜くための「資質・能力」の育成が重視されています。
コミュニケーション能力は、まさにその核となる力であり、具体的には以下のような場面でその真価を発揮します。
- 仕事でチームメンバーと協力してプロジェクトを進める際
- 多様な価値観を持つ人々と円滑な人間関係を築く際
- 困難な問題に直面した際に、周囲と協力して解決策を見出す際
- 自分の意見を明確に伝え、相手の意見を理解し、合意形成を行う際
AI技術が進化し、多くの定型業務が自動化される未来において、人間ならではの創造性や共感力、そして他者と協働するコミュニケーション能力は、より一層価値あるものとなるでしょう。
小学生のうちからこれらの非認知能力、特にコミュニケーション能力を育むことは、子どもたちが将来、どのような社会に進んでも自らの可能性を最大限に引き出し、豊かな人生を送るための土台となります。
小学生期に育むべき社会性とは

小学生期は、子どもたちが家庭という小さな世界から一歩踏み出し、学校という集団生活の中で社会性を本格的に育んでいく非常に重要な時期です。
この時期に培われる社会性は、将来の人間関係や社会への適応能力に大きく影響します。
社会性とは、他者と関わりながら集団の中で適切に行動し、共に生活していくための能力全般を指します。
具体的には、以下のような要素が小学生期に育むべき社会性の核となります。
- 他者の気持ちを理解し、共感する力(共感力)
- 自分の意見や感情を適切に表現する力(自己表現力)
- 相手の話を注意深く聞き、理解する力(傾聴力)
- 集団のルールや規範を理解し、守る力
- 異なる意見を持つ人々と協力し、合意形成する力(協調性・交渉力)
- 困ったときに助けを求めたり、逆に助けたりする力
学校生活では、クラスメイトとの共同学習、休み時間の遊び、係活動、運動会や学芸会といった行事など、様々な場面で他者との関わりが生まれます。
これらの経験を通じて、子どもたちは自分の役割を認識し、責任感を持ち、多様な価値観を持つ仲間と共に目標を達成する喜びや難しさを学びます。
この時期に培われた社会性は、中学校、高校、そして大人になってからの社会生活の基盤となり、より豊かな人間関係を築き、社会の一員として貢献していく上で不可欠な能力となるのです。
友達関係や学校生活でのコミュニケーションの重要性

小学生にとって、友達関係や学校生活は日々の大半を占める重要な活動の場です。
この環境において、コミュニケーション能力は、子どもたちの精神的な安定、学習意欲、そして自己肯定感に直接的に影響を与えます。
円滑なコミュニケーションは、良好な友達関係を築き、学校生活を充実させるための鍵となります。
例えば、友達を遊びに誘う、自分の意見を伝える、相手の気持ちを察する、トラブルが起きた時に話し合って解決するなど、日常のあらゆる場面でコミュニケーション能力が求められます。
これが不足すると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
コミュニケーション 能力の有無 | 友達関係 学校生活への影響 |
|---|---|
不足している 場合 |
|
備わっている 場合 |
|
このように、コミュニケーション能力は、単なる会話のスキルに留まらず、子どもたちが社会で生きていく上での基盤となる「心の健康」と「学習の質」に深く関わっています。
小学生のうちにこの能力を育むことは、子どもたちが学校生活を楽しく送り、健やかに成長するための最も重要な投資の一つと言えるでしょう。
小学生のコミュニケーション能力 チェックリスト

小学生のコミュニケーション能力は、社会性を育み、健全な人間関係を築く上で不可欠な要素です。
このチェックリストは、お子様のコミュニケーション能力を理解し、成長をサポートするための指標としてご活用ください。
項目 | 具体的な行動例 |
|---|---|
自分の気持ちを 表現できるか |
|
| |
【お子様の様子】 お子様が、自分の内面にある感情や考えを、 言葉や態度で相手に伝えようとしているかを 確認しましょう。 言葉に詰まることがあっても 伝えようとする意欲があるか どうかが重要です。 自己表現の機会を多く与えることで、 伝える力は伸びていきます。 | |
相手の話を 最後まで 聞くことが できるか |
|
| |
【お子様の様子】 「聞く力」はコミュニケーションの土台です。 お子様が、相手の言葉だけでなく、 その背景にある意図や感情を 理解しようと努めているか を観察しましょう。 集中して聞く姿勢があるかどうかも 大切なポイントです。 傾聴の姿勢は、良好な人間関係を 築く上で不可欠な能力です。 | |
友達と 協力して 遊べるか |
|
| |
【お子様の様子】 友達との遊びを通して、 お子様が協調性や問題解決能力を 育んでいるかを確認します。 集団の中で自分の立ち位置を理解し、 他者と協調しながら行動できるかは、 社会性を測る重要な指標です。 共同作業を通じて、 譲り合いや役割分担の重要性を学びます。 | |
困ったときに 助けを 求められるか |
|
| |
【お子様の様子】 「助けて」と言えることは、自己肯定感の現れです。 お子様が困難な状況に直面した際、 適切に援助を求めることができるかを確認しましょう。 これは、将来的に困難を 乗り越える力にもつながります。 信頼できる大人や友達に頼ることは、 健全な成長に不可欠なスキルです。 | |
このチェックリストは、お子様のコミュニケーション能力の現状を把握し、今後の成長を促すための手がかりとなります。
もし気になる点があれば、次の章でご紹介する家庭でできるトレーニングを試してみてください。
小学生のコミュニケーション能力は、日々の生活の中での親子の関わりや、友達との遊びを通じて自然と育まれるものです。
焦らず、お子様のペースに合わせてサポートしていきましょう。
家庭でできる!小学生のコミュニケーション能力を育む簡単トレーニング
小学生のお子さんのコミュニケーション能力は、日々の家庭生活の中で自然に育まれるものです。
特別な習い事や教材に頼らなくても、親子の日常的な関わり方やちょっとした工夫で、その土台をしっかりと築くことができます。
ここでは、家庭で無理なく実践できるトレーニング方法を具体的にご紹介します。
会話力を高める日常の工夫
コミュニケーションの基本は「話す」と「聞く」です。
まずは、お子さんが安心して自分の気持ちを表現できるような会話の環境を整えましょう。
①質問で子どもの考えを引き出す

子どもとの会話では、単に「はい」「いいえ」で終わるような質問ではなく、お子さんの考えや気持ちを深掘りするオープンな質問を心がけましょう。
- 「今日の学校で、一番楽しかったことは何だった?」
- 「その時、〇〇ちゃんはどう思ったのかな?」
- 「もし、あなたが主人公だったら、どうする?」
このように具体的な質問をすることで、お子さんは自分の意見を整理し、言葉にする練習ができます。
親は焦らず、お子さんが言葉を探す時間を待ってあげることが大切です。
➁相槌と共感で聞く力を育む
お子さんが話しているときは、最後まで話を遮らずに聞く姿勢が何よりも重要です。「うんうん」「なるほど」「それでどうなったの?」といった相槌を適度に挟み、お子さんの話に耳を傾けていることを示しましょう。
また、お子さんの感情に寄り添う共感の言葉を添えることで、お子さんは「自分の話を聞いてもらえている」「理解してもらえている」と感じ、安心して話すことができるようになります。
例えば、「それは嬉しかったね」「大変だったね」など、お子さんの感情を言葉にして返すことで、感情の理解と表現にもつながります。
➂家族会議で意見交換の場を作る

週末の過ごし方、夕食のメニュー、家庭のルールなど、家族みんなで話し合う機会を定期的に設けましょう。
家族会議では、全員が平等に意見を出し、互いの意見を尊重しながら合意形成を目指す練習ができます。
例えば、「次の休日はどこに行きたい?」「その理由は何?」といったテーマで話し合い、多数決だけでなく、全員が納得できる解決策を探るプロセスを経験させましょう。
これにより、お子さんは自分の意見を論理的に伝える力や、他者の意見を聞き入れる柔軟性を養うことができます。
表現力を豊かにする遊びと学び
言葉だけでなく、表情や態度、行動を通して自分の気持ちを伝える「表現力」も、コミュニケーションには欠かせません。
遊びを通して自然に表現力を高める方法を取り入れましょう。
①絵本の読み聞かせと感想の共有

絵本の読み聞かせは、語彙力や想像力を育むだけでなく、登場人物の気持ちを想像する共感力を養う絶好の機会です。
読み聞かせの後には、「この子、どんな気持ちだったと思う?」「もしあなたがこの子だったら、どうする?」といった質問を投げかけ、お子さんの感想や考えを引き出しましょう。
様々な感情や状況が描かれた絵本に触れることで、お子さんは多様な表現方法を学び、言葉では言い表しにくい感情も理解できるようになります。
➁役割遊びやごっこ遊びで多様な視点を体験

お医者さんごっこ、お店屋さんごっこ、ヒーローごっこなど、役割を決めて遊ぶことは、お子さんのコミュニケーション能力を大きく伸ばします。
異なる役割になりきることで、相手の立場や気持ちを想像する力が育ちます。
例えば、お店屋さんごっこでは「いらっしゃいませ」「これください」といった定型的な会話を学び、お医者さんごっこでは「どこが痛いですか?」「大丈夫ですよ」といった相手を気遣う言葉を覚えます。
これにより、社会性や協調性が自然と身につきます。
➂ボードゲームやカードゲームで戦略的思考と交渉力を養う

ボードゲームやカードゲームは、ルールを理解し、戦略を立て、時には交渉しながら進めるため、論理的思考力や問題解決能力、そして交渉力を養うのに非常に効果的です。
勝敗があるゲームを通して、感情をコントロールする力も育まれます。
家族で一緒に楽しめる代表的なゲームと、そこから得られるコミュニケーション能力の要素を以下にまとめました。
ゲームの種類 | 得られる コミュニケーション 能力の要素 |
|---|---|
人生ゲーム モノポリー | 交渉力 金銭感覚 計画性 勝敗を受け入れる姿勢 |
UNO トランプ (ババ抜き、七並べなど) | ルール理解 相手の状況を読む力 感情コントロール |
オセロ 将棋 チェス | 論理的思考力 先を読む力 集中力 負けを受け入れる姿勢 |
カタンの開拓者たち ドミニオン | 交渉力 戦略的思考 協力と競争のバランス |
ゲーム中は、単に勝ち負けにこだわるだけでなく、「なぜその手を選んだの?」「次はどうする?」といった問いかけを通して、お子さんの思考プロセスを言語化させる機会を作りましょう。
自己肯定感を育み自信につなげる
コミュニケーション能力は、「自分は認められている」「自分にはできる」という自己肯定感に裏打ちされて初めて、自信を持って発揮されます。
お子さんの自己肯定感を高めるための関わり方を意識しましょう。
①ポジティブな声かけで挑戦を応援する

お子さんが何か新しいことに挑戦しようとするとき、結果がどうであれ、その挑戦する姿勢自体を褒め、応援する声かけをしましょう。
「よく頑張ったね!」「〇〇ができてすごいね!」「失敗しても大丈夫、また挑戦しよう!」といったポジティブな言葉は、お子さんの意欲と自信を育みます。
具体的な行動を褒めることで、お子さんは「自分は何ができて、どうすればもっと良くなるのか」を理解し、次の行動につなげることができます。
「努力は報われる」という経験は、自己肯定感を高める上で非常に重要です。
➁お手伝いを通して役割と責任を学ぶ

家庭の中で、お子さんに年齢に応じたお手伝いを任せましょう。
食卓の準備、洗濯物をたたむ、ゴミ出しなど、どんなに小さなことでも構いません。
お手伝いを通して、お子さんは家族の一員としての役割を自覚し、責任感を育みます。
お手伝いができたときには、「ありがとう、助かったよ!」と具体的に感謝の気持ちを伝えることで、お子さんは自分の行動が誰かの役に立っているという自己有用感を得ることができます。
この「貢献感」は、自己肯定感を高め、積極的に他者と関わろうとする意欲につながります。
➂感謝の気持ちを言葉で伝える習慣

日頃から家族間で「ありがとう」と感謝の気持ちを言葉で伝え合う習慣をつけましょう。
例えば、お子さんが何かをしてくれた時だけでなく、親が食事を作った時、送迎をした時など、日常の些細なことにも感謝を表現します。
感謝の言葉は、相手への敬意と承認を示し、良好な人間関係を築く上で不可欠です。
お子さんが感謝の気持ちを自然に表現できるようになれば、学校や社会生活においても、円滑な人間関係を築くことができるようになります。
小学生のコミュニケーション能力を伸ばす親の心構え
小学生のコミュニケーション能力を育む上で、日々のトレーニングはもちろん大切ですが、それ以上に重要なのが親の心構えです。
親がどのような態度で子どもと向き合い、どのような環境を提供するかが、子どもの社会性や自己表現力を大きく左右します。
ここでは、親が意識すべき3つの心構えについて詳しく解説します。
子どもの個性と成長ペースを尊重する

子どもたちのコミュニケーション能力は、一人ひとり異なるペースで育まれます。
社交的な子もいれば、じっくりと人間関係を築く内向的な子もいます。
親はまず、子どもの個性と生まれ持った気質を深く理解し、尊重することが大切です。
他の子と比べることは避け、その子自身の成長を見守る姿勢を持ちましょう。
無理に社交性を押し付けたり、苦手なことを克服させようと焦ったりすると、かえって子どもの自己肯定感を損ね、コミュニケーションへの意欲を失わせてしまう可能性があります。
子どもが安心して自分らしさを発揮できる環境を整えることが、結果的に健全なコミュニケーション能力の発展につながります。
親の心構え | 具体的な行動例 |
|---|---|
個性を認め、 比較しない |
|
成長ペースを 見守る |
|
失敗を恐れず挑戦できる環境を作る

コミュニケーションは、試行錯誤の連続です。
自分の気持ちをうまく伝えられなかったり、相手の意図を誤解してしまったりと、小学生の間には様々な「失敗」を経験するでしょう。
しかし、これらの失敗こそが、コミュニケーション能力を磨くための貴重な学びの機会となります。
親は、子どもが失敗を恐れずに新しい挑戦ができるような、心理的に安全な環境を提供することが重要です。
「間違えても大丈夫」「次はもっとうまくいくよ」といった肯定的なメッセージを伝え、挑戦したこと自体を評価しましょう。
失敗したときには、責めるのではなく、一緒に原因を考え、次への改善策を話し合う姿勢が、子どもの挑戦意欲と問題解決能力を育みます。
親の心構え | 具体的な行動例 |
|---|---|
失敗を肯定的に 捉える |
|
心理的安全性を 確保する |
|
親自身がコミュニケーションの良い手本となる

子どもは、親の姿を見て学び、育ちます。
コミュニケーション能力も例外ではありません。
親が日々の生活の中で、どのようなコミュニケーションを取っているかが、子どもにとって何よりもの生きた教材となります。
夫婦間での丁寧な言葉遣い、子どもへの能動的な傾聴、感謝や謝罪の気持ちを素直に伝える姿など、親自身が良好なコミュニケーションの模範となることが大切です。
また、感情的にならず、冷静に自分の気持ちを伝える練習を親自身も心がけましょう。
親がコミュニケーションを大切にする姿勢を見せることで、子どもは自然と、言葉の力や人との関わりの大切さを学んでいきます。
親の心構え | 具体的な行動例 |
|---|---|
模範的な 対話を示す |
|
感情表現と 共感の習慣 |
|
まとめ
小学生のコミュニケーション能力は、学力だけでなく、将来の人間関係や社会で生き抜く力を育む上で不可欠です。
家庭での日々の関わりが、子どもが自信を持って自分の意見を伝え、他者を理解し、協力する力を伸ばす土台となります。
ご紹介した簡単なトレーニングや親の心構えを実践することで、お子様は多様な価値観の中でしなやかに生きる力を身につけ、将来の可能性を大きく広げることができるでしょう。