
水慣れはいつから?子ども 水泳教室 いつから通うべき?発達段階別で徹底解説
「子どもを水泳教室にいつから通わせるべき?」
そんな疑問をお持ちの保護者の方へ。
この記事では、0歳からの水慣れの始め方から、ベビー・幼児・学童期といった発達段階ごとの最適な水泳教室の開始時期を徹底解説します。
心肺機能向上や安全対策、精神面での成長といった水泳のメリットはもちろん、費用や持ち物、失敗しない教室選びのポイントまで網羅。
お子様の成長に合わせた最適な水泳の始め方がきっと見つかります。
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.水慣れはいつから始めるべき?水への抵抗をなくす第一歩
- 2.1.家庭でできる水慣れの方法
- 2.2.プールデビューの目安と注意点
- 3.子ども 水泳教室 いつから通うべき?発達段階別の最適な時期を解説
- 3.1.0歳から2歳頃 ベビー水泳の時期
- 3.1.1.ベビー水泳で得られる効果と注意点
- 3.2.3歳から5歳頃 幼児水泳の時期
- 3.3.6歳から小学校高学年 学童水泳の時期
- 3.3.1.学童期に目指せる泳ぎの習得と体力向上
- 4.水泳教室に通うメリットと知っておきたいこと
- 4.1.身体能力と心肺機能の向上
- 4.2.精神面での成長 自立心と協調性
- 4.3.万が一の安全対策 溺水事故の防止
- 4.4.水泳教室に通う際のデメリットや注意点
- 5.失敗しない子ども向け水泳教室の選び方
- 5.1.カリキュラムと指導方針の確認
- 5.2.コーチの質と安全性
- 5.3.施設の環境と通いやすさ
- 5.4.体験レッスンや見学の活用
- 6.子どもを水泳教室に通わせる前のよくある質問
- 6.1.水泳教室の費用相場はどのくらい?
- 6.2.水泳教室の持ち物は何が必要?
- 6.3.水泳が苦手な子でも大丈夫?
- 7.まとめ
はじめに
 「子どもに水泳を習わせたいけれど、いつから始めるのがベストなの?」
「子どもに水泳を習わせたいけれど、いつから始めるのがベストなの?」
「水慣れは必要?」
「どんなメリットがあるの?」
多くのお父さん、お母さんが、お子さんの水泳についてこのような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
水泳は、単に泳ぎのスキルを習得するだけでなく、心肺機能の向上、全身運動による身体能力の発達、そして万が一の際の安全確保にも繋がる、子どもの成長に多くのポジティブな影響をもたらす素晴らしい運動です。
このページでは、水慣れの最初のステップから、お子さんの発達段階に応じた水泳教室に通う最適な時期、さらには水泳がもたらす心身の成長、そして水泳教室に通う際のメリット・デメリット、失敗しない教室選びのポイントまで、親御さんが知りたい情報を網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、お子さんの水泳に関する疑問や不安が解消され、自信を持って水泳を始めるための一歩を踏み出せることでしょう。
水慣れはいつから始めるべき?水への抵抗をなくす第一歩
お子さんが水泳教室に通う前に、まずは水に慣れることから始めましょう。
水慣れは、水への恐怖心を取り除き、水に親しみを感じさせるための非常に重要なステップです。
無理なく楽しく水に触れる経験を積むことで、その後の水泳学習がスムーズに進みます。
家庭でできる水慣れの方法
 特別な道具がなくても、ご家庭のお風呂で簡単に水慣れを始めることができます。
特別な道具がなくても、ご家庭のお風呂で簡単に水慣れを始めることができます。
生後間もない頃から、お風呂の時間を利用して少しずつ水に触れさせてあげましょう。
- お風呂での水遊び毎日のお風呂の時間を、水遊びの機会に変えましょう。湯船に浸かるだけでなく、おもちゃを使って水をすくったり、パシャパシャと水面を叩いたりすることで、水との触れ合いを楽しみます。まずは顔に水がかかることに抵抗がないよう、優しくお湯をかけてあげましょう。
- 顔に水をかける練習:お子さんの目を見て「お顔にジャーだよ」などと声をかけながら、手で優しく顔に水をかけたり、タオルを絞った水で顔を拭いてあげたりします。徐々にコップやシャワーで頭から水をかける練習へとステップアップしていきます。
- 潜る練習の導入:顔に水がかかることに慣れてきたら、親が先に潜って見せたり、鼻をつまんで息を止める練習をしたりと、遊び感覚で水に潜る準備を始めます。無理強いはせず、お子さんのペースに合わせて進めることが大切です。
- シャワーの活用シャワーも水慣れに有効なツールです。最初は足元から、徐々に体全体にシャワーをかけて慣らしていきましょう。水圧を弱め、ぬるめの温度に設定することで、お子さんの不快感を減らせます。頭からシャワーを浴びることに抵抗がある場合は、親が抱っこして一緒に浴びるなど、安心できる環境で試してみましょう。
- 親子でのスキンシップ水慣れの時間は、親子のスキンシップを深める絶好の機会でもあります。お子さんを抱っこして湯船に浸かったり、一緒に歌を歌いながら体を洗ったりすることで、水に対するポジティブな感情を育むことができます。親が楽しそうにしている姿を見せることも、お子さんが水に親しむための大切な要素です。
大切なのは、「楽しい」という気持ちを最優先にすることです。
決して無理強いはせず、お子さんが水に触れることを嫌がらないように、少しずつ、遊びの延長として取り組んでいきましょう。
プールデビューの目安と注意点
 家庭での水慣れが進んだら、いよいよプールデビューを検討する時期です。
家庭での水慣れが進んだら、いよいよプールデビューを検討する時期です。
プールは家庭のお風呂とは異なる環境のため、いくつかの注意点を守りながら安全に楽しみましょう。
- プールデビューの一般的な目安多くのベビー向けプールや水泳教室では、首が完全に座っていること(一般的に生後4ヶ月頃から)をプールデビューの目安としています。これは、お子さんの体温調節機能や免疫機能が未発達であること、そして安全面を考慮しての基準です。自治体の施設や民間のスイミングスクールによって基準が異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
- プールデビュー時の注意点初めてのプールは、お子さんにとって刺激が多く、疲労しやすい環境です。以下の点に注意して、安全で楽しいプールデビューにしましょう。
項目 | 注意点 |
|---|---|
体調管理 | 発熱、下痢、咳、湿疹などの症状がある場合は、 プール利用を控えましょう。 体調が万全な日を選び、 プールに入る前には必ず検温を行いましょう。 |
水温の確認 | ベビー向けプールは一般的に 30℃~33℃程度の温水に設定されていますが、 事前に水温を確認し、 お子さんにとって快適な温度であるか確認しましょう。 冷たい水は体調を崩す原因になります。 |
利用時間 | 最初は10分~15分程度の短時間から始め、 お子さんの様子を見ながら 徐々に時間を延ばしていきましょう。 無理は禁物です。 |
安全対策 | 保護者は常に目を離さず、 お子さんのすぐそばで行動しましょう。 ベビー用の浮き輪や アームヘルパーを使用する場合でも、 過信せず必ず保護者が支えるようにしてください。 |
持ち物 | 水着(ベビー用スイムパンツ)、 タオル、水遊び用おむつ(必要な場合)、 着替え、飲み物など、 必要なものは事前に準備しておきましょう。 |
プール後のケア | プールから上がったら、 体を冷やさないようにすぐにタオルで拭き、 温かいシャワーを浴びましょう。 水分補給も忘れずに行い、 疲れていないかお子さんの様子を よく観察してください。 |
これらの注意点を守ることで、お子さんは水に慣れ親しみ、水泳学習への良いスタートを切ることができるでしょう。
子ども 水泳教室 いつから通うべき?発達段階別の最適な時期を解説
子どもの水泳教室は、いつから始めるのが最適なのでしょうか。
お子様の成長には個人差がありますが、一般的には発達段階に合わせた適切な時期があります。
ここでは、0歳から小学校高学年まで、それぞれの時期に水泳教室で得られる効果や、身につくスキルについて詳しく解説します。
0歳から2歳頃 ベビー水泳の時期

ベビー水泳は、生後6ヶ月頃から2歳頃までの赤ちゃんを対象とした水泳教室です。
この時期の赤ちゃんは、まだ水への恐怖心が少なく、本能的に水に親しみやすい特性があります。
保護者の方と一緒にプールに入り、水中でスキンシップを図りながら水慣れを進めていきます。
ベビー水泳の主な目的は、泳ぎを習得することよりも、水に慣れ親しみ、水中で安全に過ごすための基礎感覚を養うことにあります。
水中で体を動かすことで、バランス感覚や全身運動能力が自然と育まれます。
ベビー水泳で得られる効果と注意点
ベビー水泳には、お子様の心身の成長に多くの良い効果が期待できます。
しかし、注意すべき点もいくつかあります。
項目 | 得られる効果 | 注意点 |
|---|---|---|
身体能力 | 全身運動による筋力や バランス感覚の発達、 心肺機能の向上 | 体調が優れない時は 無理をさせない、 水温が適切か確認する |
精神面 | 水への抵抗感をなくし、 好奇心や探求心を育む | お子様が嫌がる場合は 無理強いせず、 まずは水遊びから始める |
親子関係 | 親子のスキンシップを深め、 信頼関係を築く | 保護者も体調管理を徹底し、 安全に配慮する |
安全対策 | 水への抵抗が減り、 万が一の際の 冷静な対応に繋がる | 水から目を離さず、 常に手の届く範囲で サポートする |
ベビー水泳は、親子の絆を深めながら、お子様が水と楽しく触れ合うための貴重な機会となります。
無理なく、お子様のペースに合わせて進めることが最も重要です。
3歳から5歳頃 幼児水泳の時期

3歳から5歳頃の幼児期は、身体能力が著しく発達し、指示を理解して行動できるようになる時期です。
この時期から水泳教室に通い始めるお子様が多く、本格的な水慣れから基本的な泳ぎのスキル習得を目指します。
遊びの要素を取り入れながら、集団での活動を通して水への適応力を高めていきます。
この時期の水泳教室では、「顔つけ」「息継ぎ」「バタ足」「けのび」といった、泳ぎの基礎となる動作を身につけることが主な目標となります。
また、コーチや友達との関わりの中で、社会性や協調性も育まれます。
項目 | 身につく水泳スキル | 期待できる成長 |
|---|---|---|
水慣れ 呼吸 | ・顔つけ ・水中で目を開ける ・鼻から息を吐く ・潜る | 水への恐怖心の克服、 自信の獲得 |
浮く 進む | ・浮き身 (だるま浮き、伏し浮き) ・バタ足 ・けのび | バランス感覚の向上、 全身運動能力の発達 |
社会性 | ・コーチや友達との コミュニケーション ・順番を守る | 協調性、自立心、 集団行動のルール理解 |
体力 | ・心肺機能の向上 ・持久力の基礎作り | 風邪をひきにくい丈夫な体、 運動能力の全体的な底上げ |
幼児期に水泳を始めることで、運動能力だけでなく、精神面でも大きな成長を促すことができます。
水泳を通じて得られる達成感は、お子様の自己肯定感を高めることにも繋がります。
6歳から小学校高学年 学童水泳の時期
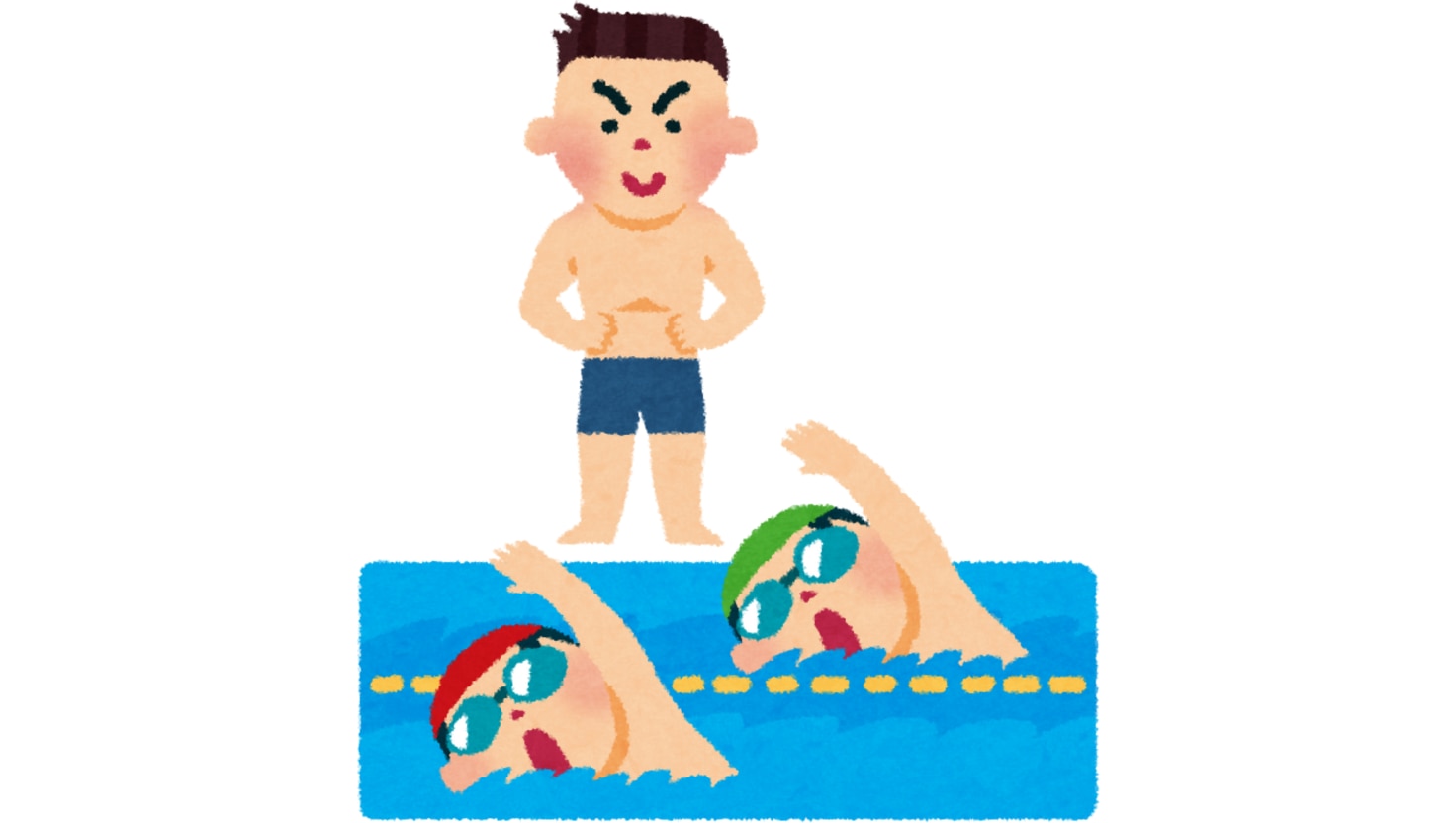
小学校に入学する6歳頃から小学校高学年にかけては、水泳のスキルを本格的に習得し、泳ぎの完成を目指す時期です。
この時期になると、運動能力がさらに向上し、複雑な動きも習得できるようになります。
水泳教室では、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライといった四泳法の習得を目指し、個々の泳力に応じた指導が行われます。
学童水泳では、技術の向上だけでなく、タイムを意識した練習や、より長い距離を泳ぐことで持久力を高めることも目標となります。
また、級や段の認定制度がある教室も多く、目標を設定して達成していくことで、お子様のモチベーション維持にも繋がります。
学童期に目指せる泳ぎの習得と体力向上
学童期の水泳は、技術的な向上と体力向上に大きく貢献します。
項目 | 習得できる泳ぎ・スキル | 期待できる体力・精神面での成長 |
|---|---|---|
四泳法 | クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライの習得と フォーム改善 | 全身の筋力、 柔軟性、 バランス感覚の向上 |
持久力 | 長距離を安定して泳ぐ能力、 ターンやスタートの技術 | 心肺機能の飛躍的な向上、 疲れにくい体作り |
目標達成 | 級・段位取得、 タイム測定、 大会参加 | 目標設定と達成の喜び、 自己肯定感の向上 |
精神面 | 集中力、 忍耐力、 課題解決能力の向上 | 自己管理能力、 規律を守る意識、 健全な競争心 |
学童期に水泳を続けることで、お子様は高い運動能力と健全な精神を育むことができます。
水泳は全身運動であり、生涯にわたって楽しめるスポーツとなるでしょう。
水泳教室に通うメリットと知っておきたいこと
 子どもが水泳教室に通うことは、単に泳ぎ方を学ぶだけでなく、その成長に多岐にわたる良い影響をもたらします。
子どもが水泳教室に通うことは、単に泳ぎ方を学ぶだけでなく、その成長に多岐にわたる良い影響をもたらします。
身体的な発達はもちろん、精神面や社会性の向上、さらには万が一の事態に備える安全対策としても非常に有効です。
しかし、通わせる上で知っておくべき注意点やデメリットも存在します。
ここでは、それらを詳しく解説します。
身体能力と心肺機能の向上
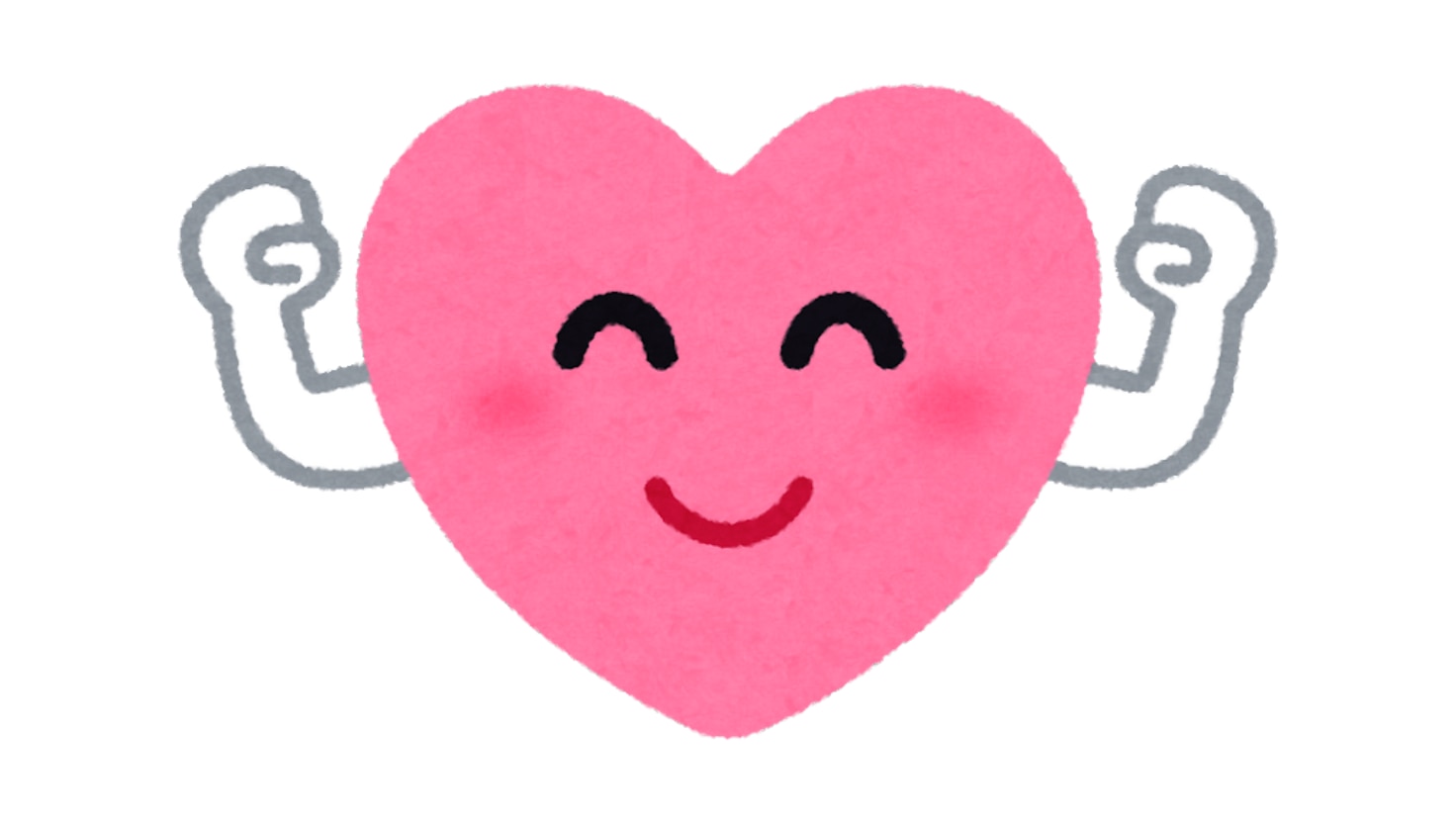 水泳は、全身の筋肉をバランス良く使う運動であり、陸上では得られない独特の負荷が身体にかかります。
水泳は、全身の筋肉をバランス良く使う運動であり、陸上では得られない独特の負荷が身体にかかります。
水中で体を動かすことで、以下のような身体能力の向上が期待できます。
- 全身の筋力アップ: 水の抵抗を利用して、手足だけでなく体幹の筋肉も効率的に鍛えられます。特に、体幹が鍛えられることで姿勢の改善にもつながります。
- 心肺機能の強化: 水中で呼吸をコントロールすることで、心臓や肺の機能が向上し、持久力が高まります。これは、風邪をひきにくい丈夫な体を作る基盤となります。
- 柔軟性の向上: 水の浮力によって関節への負担が軽減されるため、無理なく体を大きく動かすことができ、柔軟性が高まります。
- バランス感覚の育成: 水中でバランスを取りながら進むことで、平衡感覚や協応性が養われます。
- 肥満の予防と解消: 消費カロリーが高いため、子どもの肥満予防や健康的な体づくりに役立ちます。
精神面での成長 自立心と協調性
 水泳教室は、子どもたちの精神的な成長にも大きく貢献します。
水泳教室は、子どもたちの精神的な成長にも大きく貢献します。
泳ぎの習得過程や集団行動の中で、様々な学びがあります。
- 目標達成による自信: 級の取得や目標タイムの達成など、具体的な目標に向かって努力し、それを達成する喜びは、子どもの自信を育み、次の挑戦への意欲につながります。
- 集中力と忍耐力の向上: 練習を通じて、コーチの指示に集中し、繰り返し練習する中で忍耐力が養われます。
- 規律性と社会性の習得: 教室のルールを守り、時間を守るといった規律性が身につきます。また、コーチや他の生徒とのコミュニケーションを通じて、協調性や社会性が育まれます。
- 自立心の芽生え: 自分の持ち物の管理や、レッスン中の着替えなど、自分でできることが増えることで、自立心が芽生えます。
万が一の安全対策 溺水事故の防止

水泳スキルは、単なるスポーツの習得に留まらず、万が一の溺水事故から身を守るための重要な手段となります。
水泳教室で学ぶことは、子どもの安全を守る上で不可欠な知識と技術です。
- 水の危険性の理解: 水の特性や危険性を学び、水辺での安全な行動を身につけます。
- 自己保全能力の習得: 浮く、泳ぐといった基本的なスキルを習得することで、万が一水に落ちた際に慌てず、自分の命を守る行動が取れるようになります。
- 冷静な判断力の育成: 予期せぬ事態に直面した際にも、パニックにならず冷静に対応するための判断力が養われます。
水泳教室に通う際のデメリットや注意点
 水泳教室には多くのメリットがありますが、通わせる親御さんにとって、費用面や送迎の手間、体調管理など、いくつか注意すべき点があります。
水泳教室には多くのメリットがありますが、通わせる親御さんにとって、費用面や送迎の手間、体調管理など、いくつか注意すべき点があります。
これらを事前に把握し、対策を講じることで、よりスムーズに教室に通わせることができます。
懸念される点(デメリット) | 対策・注意点 |
|---|---|
費用負担 | 月謝だけでなく、 入会金、 水着やゴーグルなどの初期費用、 交通費なども考慮し、 総額を事前に確認して 無理のない範囲で検討しましょう。 キャンペーンなどを 利用するのも良い方法です。 |
送迎の手間と 時間 | 自宅からの距離、 公共交通機関の便、 スクールバスの有無などを考慮し、 保護者の負担が少ない、 無理なく通える教室を選びましょう。 兄弟で通う場合は、 時間帯が合うかどうかも 確認が必要です。 |
体調不良の リスク | 塩素による肌荒れや目の充血、 耳鼻科系のトラブル、 風邪など。 レッスン後のシャワーや保湿、 耳栓の使用、 体調が優れない日の 無理な参加は控えましょう。 乾燥肌やアレルギーがある場合は、 事前に医師に相談することも大切です。 |
モチベーションの 維持 | 子どもが水泳を嫌がったり、 上達に伸び悩んだりする時期もあります。 無理強いせず、 子どもの気持ちに寄り添い、 時には休憩も大切です。 小さな成長でも褒めることで、 モチベーションを維持しやすくなります。 |
指導内容や コーチとの相性 | 教室のカリキュラムや指導方針、 コーチとの相性は 子どもの上達や楽しさに大きく影響します。 体験レッスンや見学で実際に確認し、 子どもに合った環境を選びましょう。 |
失敗しない子ども向け水泳教室の選び方
 お子様が水泳を始めるにあたり、どの水泳教室を選べば良いか迷う保護者の方は少なくありません。
お子様が水泳を始めるにあたり、どの水泳教室を選べば良いか迷う保護者の方は少なくありません。
水泳教室選びは、お子様の成長や水泳への興味に大きく影響するため、慎重に行うことが重要です。
ここでは、失敗しないための具体的なポイントを解説します。
カリキュラムと指導方針の確認
水泳教室のカリキュラムと指導方針は、お子様の成長に直結する最も重要な要素です。
年齢や泳力に応じた適切なプログラムが組まれているか、事前にしっかりと確認しましょう。
確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
カリキュラム内容 | 年齢別・泳力別の クラス分けが明確か、 段階的な進級制度があるか |
指導方針 | 技術習得と楽しさのバランス、 個別指導の有無、 少人数制か |
進級基準 | 目標とする泳ぎの基準が 明確に示されているか、 進級テストの頻度 |
特に、お子様の発達段階に合わせたカリキュラムが用意されているかは重要です。
例えば、ベビー水泳では水慣れや親子のスキンシップを重視し、幼児水泳では遊びを通して水に親しみ、学童水泳では基礎的な泳ぎの習得を目指すなど、それぞれの時期に最適な内容であるべきです。
また、進級制度が明確であれば、お子様も目標を持って取り組むことができます。
指導方針については、技術習得を重視するのか、まずは水に慣れて楽しむことを優先するのか、教室によって異なります。
お子様の性格や目的、保護者の方の考え方に合った教室を選ぶことが大切です。
少人数制であれば、コーチの目が行き届きやすく、きめ細やかな指導が期待できます。
コーチの質と安全性
 水泳教室において、コーチの質は指導の成果と安全に大きく影響します。
水泳教室において、コーチの質は指導の成果と安全に大きく影響します。
お子様を安心して任せられるコーチがいるか、そして安全管理体制が整っているかを確認しましょう。
確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
コーチの資格・経験 | 水泳指導に関する資格保有の有無、 指導経験年数、 専門知識 |
子どもへの接し方 | 明るく、 親身な対応か、 褒めて伸ばす指導か、 コミュニケーション能力 |
安全管理体制 | 監視員の配置、 緊急時の対応マニュアル、 AEDの設置場所と使用訓練 |
コーチが水泳指導に関する適切な資格(例:日本水泳連盟公認指導員など)を保有しているか、また指導経験が豊富であるかは重要な判断基準です。
何よりも、お子様が安心して水に親しめるよう、コーチが明るく、親身になって接してくれるか、そしてお子様の性格やレベルに合わせた声かけや指導ができるかを見極めましょう。
体験レッスンや見学時に、実際の指導風景を観察し、コーチと子どものコミュニケーションの様子を確認することをおすすめします。
さらに、万が一の事故に備えた安全管理体制が徹底されているかも非常に重要です。
常に監視員が配置されているか、緊急時の対応手順が明確か、AEDなどの救命設備が整っているかなど、具体的な安全対策について質問し、確認するようにしましょう。
施設の環境と通いやすさ
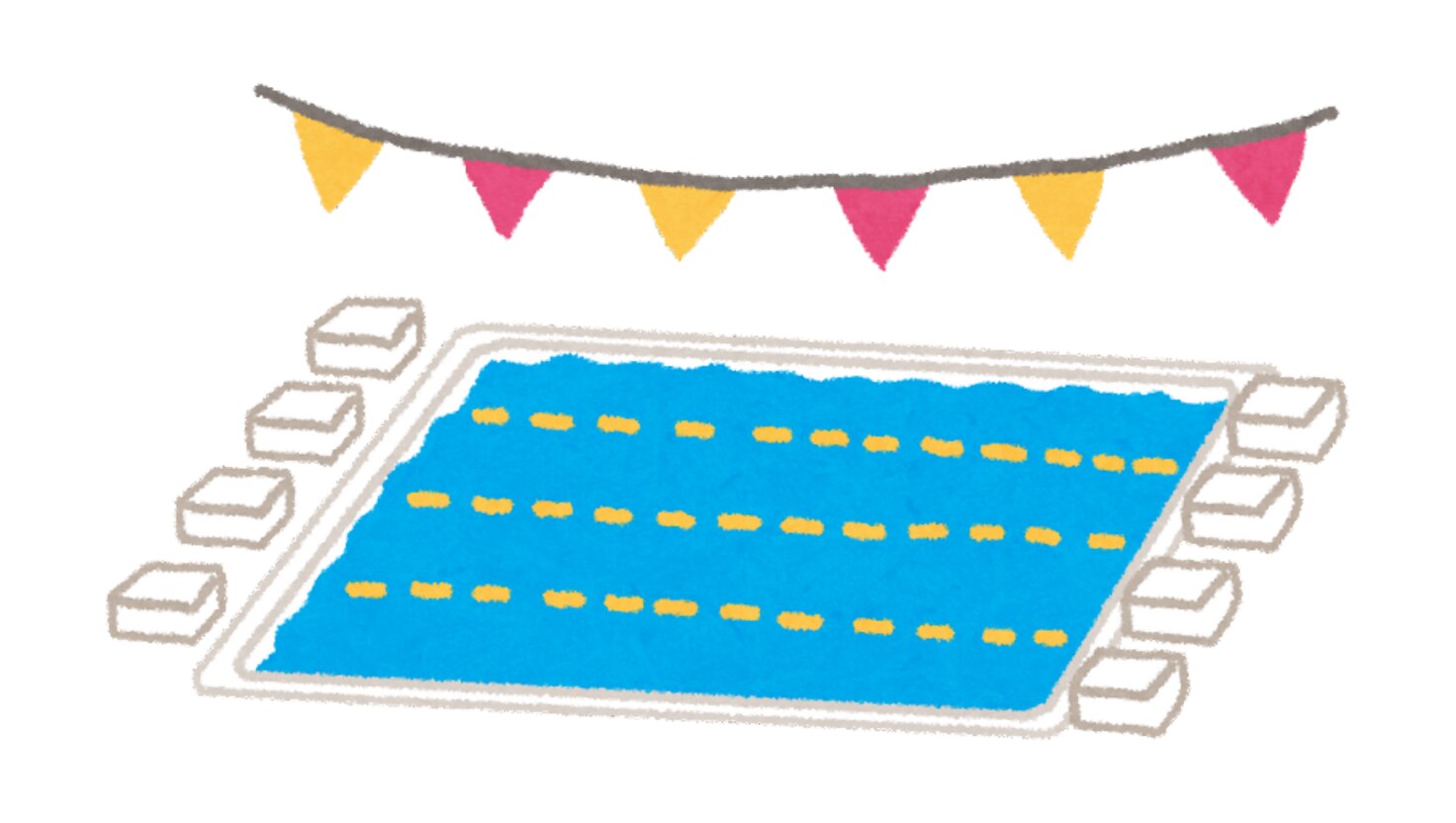 継続して通うためには、施設の環境と通いやすさも重要な選定ポイントです。
継続して通うためには、施設の環境と通いやすさも重要な選定ポイントです。
清潔さ、快適性、そして自宅からのアクセスなどを考慮して選びましょう。
確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
プールの環境 | 水質管理(透明度、塩素濃度)、 水温、清潔さ、 採暖室の有無 |
付帯施設 | 更衣室、シャワー、 トイレの清潔さ、 使いやすさ、 ロッカーの安全性 |
通いやすさ | 自宅からの距離、 送迎バスの有無、 駐車場、 公共交通機関の利便性 |
その他制度 | 振替制度の有無と柔軟性、 保護者の見学スペース |
プールは水質が常に清潔に保たれているか、水温は適切か(特にベビー・幼児向けクラスでは高めに設定されていることが多いです)、採暖室があるかなどを確認しましょう。
また、更衣室やシャワー、トイレといった付帯施設も、お子様が利用しやすい清潔な環境であることが大切です。
ロッカーの鍵の有無や、保護者が付き添いやすい広さかどうかも見ておくと良いでしょう。
そして、最も現実的な問題として「通いやすさ」が挙げられます。
自宅からの距離、送迎バスの運行ルートや時間、駐車場の有無、公共交通機関でのアクセスなどを確認し、無理なく継続して通える教室を選ぶことが肝心です。
急な体調不良や用事などでレッスンを休む場合に備え、振替制度の有無やその柔軟性も確認しておくと安心です。
体験レッスンや見学の活用
最終的な判断を下す前に、体験レッスンや見学を積極的に活用することを強くおすすめします。
実際に教室の雰囲気を感じ、お子様の反応を見ることで、最適な選択ができるようになります。
確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
体験レッスンの内容 | 実際のクラスに参加できるか、 コーチとの相性はどうか |
お子様の反応 | 楽しんでいるか、 水に慣れているか、 コーチの指示に従えているか |
見学時の観察点 | 教室全体の雰囲気、 他の生徒の様子、 安全管理の状況 |
複数教室の比較 | 複数の教室を体験・見学し、 比較検討する |
多くの水泳教室では、無料または有料の体験レッスンを提供しています。
この機会に、お子様が実際にプールに入り、コーチの指導を体験してみましょう。
お子様がレッスンを楽しめているか、コーチとの相性はどうか、水に抵抗なく取り組めているかなどを確認できます。
また、保護者の方は見学を通じて、教室全体の雰囲気や他の生徒たちの様子、コーチの指導方法、そして安全管理がどのように行われているかをじっくり観察することができます。
可能であれば、複数の水泳教室の体験レッスンや見学に参加し、それぞれの特徴を比較検討することをおすすめします。
比較することで、それぞれの教室のメリット・デメリットがより明確になり、お子様にとって最適な環境を見つけ出すことができるでしょう。
子どもを水泳教室に通わせる前のよくある質問
水泳教室の費用相場はどのくらい?
 子どもを水泳教室に通わせる際に気になるのが費用面です。
子どもを水泳教室に通わせる際に気になるのが費用面です。
一般的に、水泳教室の費用は、「入会金」「月謝」「年会費」「指定用品代」の4つで構成されることが多いです。
これらの費用は、教室の規模(大手スイミングスクール、地域の公共施設、個人経営など)や提供されるコース内容、地域によって大きく異なります。
ここでは、一般的な費用相場をまとめた表を示します。
費用項目 | 相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
入会金 | 5,000円~15,000円程度 | 初回のみ支払う費用。 キャンペーンで 無料になる場合もあります。 |
月謝 | 5,000円~10,000円程度 | 週1回のレッスンを想定。 回数が増えたり、 プライベートレッスンだと 高くなります。 |
年会費 | 2,000円~5,000円程度 | 年に一度支払う費用。 月謝に含まれている場合も あります。 |
指定用品代 | 5,000円~15,000円程度 | 水着、スイミングキャップ、 ゴーグルなど。 教室指定品の場合に 必要です。 |
上記以外にも、進級テスト代や短期講習の費用、バス送迎を利用する場合は別途料金が発生することもあります。
複数の水泳教室の料金体系を比較検討し、総額でいくらになるのかを確認することが重要です。
水泳教室の持ち物は何が必要?
 水泳教室に通う際に、忘れ物がないように事前に準備しておきたい持ち物があります。
水泳教室に通う際に、忘れ物がないように事前に準備しておきたい持ち物があります。
基本的には、水着、スイミングキャップ、ゴーグル、タオルの4点が必須アイテムとなります。
その他、あると便利な持ち物や、教室によっては必要となるものもあります。
- 水着:動きやすく、体にフィットするものが良いでしょう。教室によっては指定の水着がある場合もあります。
- スイミングキャップ:髪の毛が水に濡れるのを防ぎ、プールの水質を保つためにも必須です。こちらも指定品の場合があります。
- ゴーグル:目を保護し、水中での視界を確保するために重要です。曇り止め加工がされているものや、子どもの顔にフィットするものを選びましょう。
- タオル:吸水性の良いバスタオルやセームタオルが便利です。
- 水筒:レッスン中の水分補給は非常に重要です。
- 着替え:水泳後に体を冷やさないよう、すぐに着替えられる服を用意しましょう。
- シャンプー・ボディソープ:シャワーを浴びる際に使用します。
- ビニール袋:濡れた水着やタオルを入れるために使います。
- ヘルパー:浮力補助具として、教室によっては持参を求められる場合があります。
入会時に持ち物リストが配布されることがほとんどですので、必ず確認し、不足がないように準備を進めましょう。
水泳が苦手な子でも大丈夫?
 「うちの子は水が苦手だから、水泳教室に通わせるのは難しいかも…」と心配される保護者の方は少なくありません。
「うちの子は水が苦手だから、水泳教室に通わせるのは難しいかも…」と心配される保護者の方は少なくありません。
しかし、多くの水泳教室では、水が苦手な子どもでも安心して始められるよう、段階的な指導カリキュラムが組まれています。
具体的には、以下のようなサポートや配慮がなされます。
- 水慣れからのスタート:いきなり泳ぐ練習をするのではなく、顔を水につける、水に潜る、浮くといった基本的な水慣れから丁寧に指導します。水遊びの要素を取り入れながら、水への恐怖心を和らげていきます。
- 少人数制クラス:コーチの目が届きやすい少人数制のクラスでは、一人ひとりの進捗や苦手な部分に合わせてきめ細やかな指導を受けることができます。
- コーチのサポート:経験豊富なコーチが、子どもの気持ちに寄り添い、励ましながら指導を進めます。無理強いはせず、子どものペースを尊重してくれるでしょう。
- 成功体験の積み重ね:小さな「できた!」を積み重ねることで、子どもは自信を持ち、水泳に対する苦手意識を克服していきます。
水が苦手な子どもにとって、水泳教室は水に親しみ、泳ぎを習得するだけでなく、「苦手なことにも挑戦し、克服できた」という大きな自信と達成感を得る貴重な機会となります。
体験レッスンなどを活用して、教室の雰囲気や指導方法を確認することをおすすめします。
まとめ
子どもが水泳を始める最適な時期は、一概に「何歳から」と決まるものではありません。
水慣れは乳幼児期から家庭で始め、水への抵抗をなくすことが大切です。
水泳教室は、0歳からのベビー水泳、3歳頃からの幼児水泳、小学校入学後の学童水泳と、お子様の成長段階や興味に合わせて選べます。
水泳は、身体能力や心肺機能の向上に加え、自立心や協調性を育み、万が一の際の安全対策にもつながる素晴らしい習い事です。
お子様の個性やペースを尊重し、カリキュラムやコーチの質、施設の環境などを考慮して、最適な水泳教室を選び、心身の健やかな成長を応援しましょう。





